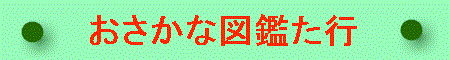 |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
・「あ」から始まる魚 ・「い〜え」から始まる魚 ・「お」から始まる魚 ・「か」から始まる魚 ・「き〜こ」から始まる魚
・さ行の魚 ・な行の魚 ・は行の魚 ・「ま」から始まる魚 ・「み〜も」から始まる魚 ・やらわ行の魚
| 魚の名前 | 特徴 | 関連する仲間の魚 |
| タカベ |
(スズキ目タカベ科) 夏を代表する魚で体色は背側が青緑色、腹側が銀白色、側線の上に黄色い縦縞があるのが特徴である。大きさは20cm前後が一般的だが身に脂が多く、塩焼きにするとジュウジュウと脂が滴るほどである。また、タタキにするのもかなり美味しい食べ方である。専門に狙う事はほとんどないのでイサキ釣などの外道で釣れた時は大切に持ち帰り賞味したい魚だ。また、カンパチやヒラマサを狙う時の餌にする事も多く価値の高い魚だ。 |
ウメイロ |
| タコベラ
|
(スズキ目ベラ科)
カワハギ釣りの外道で釣れた一匹。 岩礁帯や藻場、サンゴ礁など様々な場所に居るが、なかなか出会うチャンスは多くない。珍しい魚(珍しい名前)として覚えておくと良いだろう。 |
オハグロベラ |
| タチウオ
|
(スズキ目タチウオ科) 独特の太刀のような姿、色から命名されたと言う説と、水中で立った状態で泳ぎ上から落ちてくるエサを狙う姿勢からタチウオという名前になったと言う説がある。口や歯を見るとわかるように典型的なフィシュイーターで100m前後の水深の中層から底にかけて群れている。移動が早く縦方向にも横方向にもすばやく反応が変化してしまうので船長泣かせの魚でもある。また、一気に食い込みそうな感じだが、エサ取りも上手く小さなアタリですぐにあわせるとハリ掛りしないことも多い。最近ではルアーで狙うことも多くなりさまざまな釣り方が楽しめる魚だ。鮮度が落ちやすいので刺身を楽しむには自分で釣るしかありません。もちろん塩焼きやから揚げも最高ですが、見逃せないのが潮汁です。中落ちと昆布で丁寧にダシを取り塩と酒、若干の醤油で味を調えた御汁は3本の指に入るとまるかつは思っています。 |
|
| ダツ
|
(ダツ目ダツ科) 磯釣りなどで外道に釣れることがあるらしいが船では滅多にお目にかかることは無い。と言うのも長い吻(くちばし)に鋭い歯が並んでいる為なかなかハリ掛りしないのだ。岸沿いの潮目などを回遊し小魚を狙って捕食するフィッシュイーターである。この魚は夜釣りで明かりに集まってきた小魚を狙って船べりに近づいてきたところを玉網でしとめた物である。中骨が青みがかっておりちょっと気味悪いが、味は最高で椀種、揚げ物、焼き物などに調理すると高級な和食素材として通用する。釣り人冥利に尽きる食材だ。 |
|
| タヌキベラ
|
(スズキ目ベラ科)
体側に3本とと背ビレの黒縦帯が特徴だが、成長と共に腹側の縦帯が不鮮明になる。左の写真は正にその状態だ。 この魚は30mの水深でイシダイ五目釣りの外道で掛かってきたが、潮通しの良い環境を好む様だ。 |
オハグロベラ |
| タマガシラ
|
(スズキ目イトヨリダイ科)
あまり馴染みのある魚ではないと思ったら本州中部以南に多い魚らしい。水深100mくらいまでの岩礁帯に生息し、底物釣りなどの外道で釣れる事が多い。まるかつは西伊豆でカサゴ釣りをしたときに外道で釣った事がある。4〜5本の赤い横じまが特徴できれいな魚だ。味もかなり美味く塩焼きや煮魚、大きい物は刺身でもいける。 |
|
| タマガンゾウビラメ
|
(カレイ目ヒラメ科) ヒラメの仲間なので目は左側にあるが、丸い体型からカレイに見間違えられる事も多い。釣れることが多い。体表に体表に(目玉の様なの丸い斑紋)が5個あるのが特徴で1個あるガンゾウビラメ、6個あるムシガレイと間違えやすい。身も薄く小型なので干物や唐揚げにして食べるがカルシュームの補給には持って来いだ。 |
ヒラメ |
| チカメキントキ
|
(スズキ目キントキダイ科)
大きな目と大きな胸鰭、なんと言っても鮮やかな赤い色が特徴。あまり狙って釣ることは少ないが、コマセしゃくりなどで掛かってくると水圧抵抗も強く、何が掛かったのかどきどきしながら巻き上げてきて水面で「おーっ!」と驚きの声を上げてしまう。水深50〜100m位の底から少し上層に群れていることが多い。ウロコが細かく硬いので下ごしらえが大変だが型の良い物は刺身、煮つけでとても美味しい。白身でクセが無く、誰にで好まれる肉質である。 |
|
| チダイ
|
(スズキ目タイ科) タイの仲間のNO2とも言える魚で「ハナダイ」と言う名前の方が有名かもしれない。マダイと非常に良く似ているが、次の点が違い見分けるポイントになっている。まず、尾びれの縁が黒くない(マダイは黒い)、エラブタの縁が血が滲んだように赤い。この二つ目の特徴が名前の由来となっている。小型のものは小鯛の笹漬けで有名な酢締めにしたりするが、大きなものは刺身、塩焼きでマダイと遜色ない。オスは大きくなるとオデコが出っ張ってくることからデコダイとも呼ばれる。なんと言ってもキュンキュンとくる引き味が身上だ。 |
マダイ |
| ツノザメ |
(ツノザメ目ツノザメ科) 背鰭は2つあり、それぞれの前縁に棘が1本ある。これは毒棘といもいわれるが、はっきりしない。臀鰭はない。深海性で、あまり大きくならないが中深場(200〜400m)で良く掛かってくる。 |
|
| テナガダラ |
(タラ目ソコダラ科) 水深200m以深に住む深海魚。アコウ、キンメ釣りの外道で良く登場するトウジンとよく似ているのだが、ある時「コイツはちょっと違うぞ、トウジンほど頭が尖がっていないで寸詰まりだ。」と気が付いた。後の特徴は殆ど同じだが頭の先端の形状が明らかに違うのである。場所によっては「ニセトウジン」なんて呼ばれているところもあるが、俗称「チョッピ」は共通だ。 専門家の間でもソコダラ科の判別は難しいらしい。 |
トウジン |
| テンス
|
(スズキ目ベラ科) ベラの仲間だが、形はアマダイに似ており良く騙されてガッカリする。同じ仲間にイラがいて、こちらにも良く間違えられるが、背びれの第一棘、第二棘が著しく伸びアンテナ状なので区別が付く。大きさは20〜30cmほどで、砂泥底に住んでおりイソメ類や甲殻類を捕食している。両アゴの先端に2本の強い犬歯があり出っ歯状に見え、釣り上げると体を曲げて噛み付こうとするから要注意だ。肉質はやや水っぽくあまり美味しいとは言えない。 |
イラ |
| テンスモドキ
|
(スズキ目ベラ科) カワハギ釣りの外道で掛かってきたが、見たことのない種類だったので写真だけ撮ってリリース。全長20cm位で淡い赤色の綺麗な魚体でした。歯は本家のテンスと同じく出っ歯でベラ科であることは一目瞭然でした。 ですから、詳しい生態やお味に関しても未知な状態です。 |
イラ |
| ドンコ
|
(タラ目チゴダラ科) チゴダラやイタチウオの総称、俗称だが、底物釣りの好きな人々の間では「ドンコ」として有名な魚だ。姿かたちがグロテスクな為初めての人は敬遠しがちだが、その味を知っている人は大切に持ち帰る魚である。まるかつもその容姿のせいか、味の良さか分からないが仲間に「ドンコの親分」というあだ名を付けられている。トックンなどは一番好きな魚はドンコと公言するほどのドンコファンであるが、確かに肝入りの味噌汁の味はピカ一かもしれない。味噌を入れたタタキも実はかなり美味な食べ方で姿かたちを思わず忘れるほどだ。「魚も人も見た目で判断してはいけない。」という事は思い知らせてくれる愛嬌のある顔の魚だ。 |
イタチウオ |
| トウジン
|
(タラ目ソコダラ科) 水深200m以深に住む深海魚。アコウ、キンメ釣りの外道で良く登場する。初めて釣った時には尖った頭、飛び出した目、細く伸びた尾、こんな奇怪な魚がいたものかとビックリしたものだ。毒のある魚以外は必ず試してみるのがまるかつの信条だが、この魚を食べてみるには勇気が必要だった。捌いて皮を剥ぐときれいな白身で、意外なほど淡白で癖のない味であった。刺身は今ひとつだがムニエル、フライなどは美味しい部類に入る。ナカガワはコブ締めにしたら美味しかったと報告している。但し、家族には捌く前の姿を見せないことが最大のコツと言えるかもしれない。 |
テナガダラ |
| トゴットメバル
|
(スズキ目メバル科メバル属)
オキメバル、アカメバルと呼ばれる魚には3種類いて、ウスメバル、ウケクチメバル、そしてこのトゴットメバルである。これらの中では小型の方で25cmくらいまでである。ウスメバルが福島から茨城、千葉北部に多いのに比べ南房、内房、神奈川、静岡に多い。50〜100m位の根回りに群生していて小さな甲殻類や小魚を主食としている。他のメバル同様、美味しい白身でやや身が柔らかいので煮付けや空揚げで食べるのが一番良い賞味方法だ。 |
ウスメバル |
| ドチザメ
(写真は準備中) |
(メジロザメ目ドチザメ科)
内湾などで普通にみられる大人しい性格のサメで、体調は.1.5m位まで大きくなる。 近い種とされるホシザメと共にクセが無く食用にされることも多いが、持ち帰る人は少ないだろう。 |
|
| トラギス
(トラギス)
(クラカケトラギス) |
(スズキ目トラギス科) トラギスの仲間は日本近海に18種ほどいる。その中で代表的なのが赤みを帯びたトラギスと体側にV字模様のあるクラカケトラギスだろう。共にタイガースファンが好きな縞模様の衣装をまとっている。トラギスは主に根際に生息しカワハギ釣りと外道で掛かることが多いが、それに対してクラカケトラギスは砂地に生息しておりシロギス釣りの外道で釣れる事が多い。模様とキスのような形から命名されたのだろうが、顔がキスよりハゼに似ており、体型もずんぐりしていることからトラハゼと呼んでいる地方も多い。味はクラカケトラギスのほうが上で天ぷらやフライにしたほっこりとした白身はかなり美味しい。
(オキトラギス) |
|
| トラザメ |
(メジロザメ目トラザメ科) 150mダチの砂泥底でオニカサゴを狙っていて釣れたが、この日はどのポイントに行ってもこいつが活発で連発だった。潮が動かず、他の魚が絶不調の時に釣れるところを見ると潮が緩くないとエサを捕食できないのかもしれない。 |
|
| トビウオ
|
(ダツ目トビウオ科) 名前は釣りをしない人にも良く知られている有名な魚だ。伊豆七島ではムロアジと並んで高級クサヤの材料にもなっている。なかなか狙ってつれる魚ではないが、夜釣りの時など明かりに誘われて船に近づいてきたところを玉網でサッと掬う事ができる。失敗すると羽ばたいて飛んで逃げられてしまうので、頭から一発勝負で思い切り良く掬う事だ。地方によってはマグロ釣りの特えさに使われたりしている。味はサッパリとした中にも青魚特有の旨みがあり、高級魚として扱われている。刺身や焼き物で食べると良いだろう。 |
|