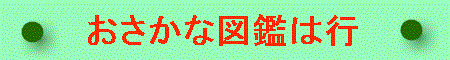 |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
・「あ」から始まる魚 ・「い〜え」から始まる魚 ・「お」から始まる魚 ・「か」から始まる魚 ・「き〜こ」から始まる魚
・さ行の魚 ・た行の魚 ・な行の魚 ・「ま」から始まる魚 ・「み〜も」から始まる魚 ・やらわ行の魚
| 魚の名前 | 特徴 | 関連する仲間の魚 |
| ハガツオ
|
(スズキ目サバ科) 魚屋にも並ばず料理屋でもなかなかお目にかからない釣り人のみが知る超美味なグルメ界の伏兵だ。カツオのような体型で縞もあるが大きな違いがカミソリのような鋭い歯がある事で、名前の由来にもなっている。表層から80mくらいまでの水深で小さな群れを作りイワシやサバ、アジ、イカなどを捕食している。カツオよりも淡い赤身で刺身や寿司が絶品である。身が割れやすい魚なので釣り上げたらはすぐに締めて甲板ではたかせたりしないように注意が必要だ。2〜3日冷蔵庫で寝かせてネギトロ巻きにすると最高だ。 |
カツオ |
| ハシキンメ |
(キンメダイ目ヒウチダイ科) 体は平たく、赤っぽい淡褐色で口から鰓の中は黒い。棘状の突起があり皮もザラザラしているので包丁の刃が当たって捌きにくい。 |
|
| ハチカサゴ
|
(スズキ目フサカサゴ科)
実はこの魚学問的には認知されていないんです。しかし大原の船長たちはカンコ(ウッカリカサゴ)と明確に区別しており、実際に釣って食べてみると違う魚なのかも?と思いました。 身は最低5日、1週間位は寝かせても劣化することなく旨みが増幅され美味しく食べる事ができます。またカンコに比べると脂の乗りが良く、生でも火を入れても美味しく食べられる魚です。 |
カサゴ |
| ハチビキ
|
(スズキ目ハチビキ科) 水深100〜150mのやや深い岩礁帯に生息している。アカサバという別名がある通り体型がサバに似た円筒形で背が濃い赤、腹が銀色がかった赤色である。三浦の漁師は「アバレンボ」と呼ぶが引きが大変強く、大型が数匹同時に掛かるとなかなか上がってこない。身が赤身なのも大きな特徴で味はかなり良い。マグロの値が高い時期には安い旅館などではマグロの化かしに使ったりするそうだ。最大1m近くまで大きくなるが、秋から冬にかけて釣れた物は脂もあり刺身、焼き物、煮物とさまざまな料理で楽しめる。火を入れても身が硬くならないので弁当のおかずにも最適だ。 |
|
| バラムツ
|
(スズキ目クロタチカマス科)
深場釣りをしていて竿先が突然水中へ...なんて事がたまにあります。サメの場合は最初に竿先が叩かれますので「サメの野郎が首振ってやがる!」と分かるのですが、いきなり来た場合は大体こいつの仕業です。初めてのときは丁寧に300mやり取りして、水面で金色の目を見た瞬間体中の力が抜けました。最後まで疲れることなく元気にファイとしてくれるのです。一部好んで食べる人もいるようですが、ワックス成分が多く、食べると下痢を起こすので食品衛生法で販売が禁止されています。鱗が硬いトゲの様に密生しており触ると大怪我をしてしまいます。釣り上げても船上で大暴れしますので注意が必要です。 |
|
| バラメヌケ |
(スズキ目メバル科メバル属) 同じ仲間のアコウダイと良く似ていますが、目の下に棘がありません。また頭部に3本の褐色の帯があり、体にも同色の斑紋があることで見分けがつきます。 味が良く刺身、煮付け、鍋など様々な料理で楽しむ事ができ、味噌漬けなど漬け魚に加工すると日持ちさせる事ができます。 |
アコウダイ |
| ヒイラギ
|
(スズキ目ヒイラギ科) 投げ釣りでは良く顔を見る外道だが、船釣りでは釣れる事が珍しい。この魚はウイリーシャクリで掛かったのだが浅い砂地に群れている。クリスマスでおなじみの柊(ひいらぎ)の葉に似て平たくてトゲがあることから名付けられた。大きくなっても15cm止まりだが3〜5cmの小型のものは乾しておつまみなどに加工される。味は悪くないが骨が多い上に硬く食べにくいので敬遠されるようだ。イシモチ(ニベ)、ホウボウなどと同じく音を出す魚としても知られ、釣り上げるとギーギーと鳴くので可哀想になりすぐにリリースしてしまう魚だ。 |
|
| ヒオドシ
|
(スズキ目フサカサゴ科)
頭部(両目の間)に2本の角があるのが特徴で、中深場のオニカサゴ釣りなどの外道で釣れる事が良くある。鮮やかな緋色、大きな口とカサゴの仲間である事を示す特徴も備えており、40cm位まで大きくなる。英語では、スコーピオン・フィッシュとかユニコーン・フィッシュと呼ばれている。カサゴと同様、煮付けや空揚げが美味しい魚だ。 |
カサゴ |
| ヒガンフグ
|
(フグ目フグ科) ショウサイフグ釣りで良く掛かってくる外道だが、こちらの方が上物だ。左下の写真の下の個体がヒガンフグ、上がショウサイフグである。 |
ゴマフグ |
| ヒメジ
|
(スズキ目ヒメジ科) 沿岸の浅い砂地に住んでいる。全長20cmくらいにしかならないが鮮やかな赤い色と顎にある一対の鮮黄色のヒゲが自己主張している。シロギス釣りの外道などで掛かるが、初心者などは緋鯉と勘違いしてベテランに笑われたりする。それもそのはずで、ヒメジ科には「ウミヒゴイ」という魚もいるのだ。他にもオキナヒメジ、オジサンとユニークな名前の魚がおり、皆ヒゲを持っている。型は小さいが味は良く、天ぷらにして賞味すると良い。 |
|
| ヒメ
|
(ハダカイワシ目ヒメ科)
100m位までの沖の底物釣りの外道で釣れる事が多い。一見ヒメジと良く似ているが、目が大きく下あごのヒゲが無い。小骨が多くあまり美味しくないとされているが、天ぷらやすり身にすると結構食べられる。 |
|
| ヒメコダイ
|
(スズキ目ハタ科) 通称「アカボラ」。比較的暖かい海の水深80〜150m位の砂泥底に生息している。全長20cm程度で全体に鮮赤色で体側中央に黄色い縦じまがある。アマダイ釣りの外道として有名で、この魚が釣れる場所には必ず本命のアマダイもいるといわれている。色が派手で小型なために捨ててしまう釣り人も多いが、味は悪くない為隠れたファンもいる魚だ。白身なので三枚におろして天ぷらにしたり焼いて三杯酢で食べると美味しい。食べたことにない人は一度試してみる価値がある。
|
|
| ヒラメ
|
(カレイ目ヒラメ科) これほど特徴的な形をした魚も珍しい。大きな口に鋭い歯、極端に扁平した体形、強くたくましい尾びれ。典型的なフィッシュイーターで、水深30〜200mの根際の砂地が生活圏である。大きさも1mにもなり、まるかつの記録も98cm、10.2kgである。しかし食べるには2〜3kgくらいが一番良く、浜値も高い。どんな料理でも美味しい高級魚であるが、特にヒレの付け根の「縁側(エンガワ)」はシコシコして旨みが凝縮されており秀逸である。ヒラメ40とも言われ、エサのイワシをなかなか食い込まなかったりするが、一気に飲み込み針ががりすることもよくあるので、一筋縄では行かないところがヒラメ釣りの魅力だろうか。しかし、比較的ビギナーズラックのある釣りでもある。 |
ガンゾウビラメ |
| ヒラソウダ
|
(スズキ目サバ科) 近似種のマルソウダと違い高い評価を受けている。理由はお刺身が大変美味しいことで、中途半端な大きさのホンガツオであれば、文句無しに型の良いヒラソウダの方が上かもしれない。マルとの見分け方は、体が扁平していることと、胸鰭から側線へ続くウロコのある部分(有鱗域)が短いことである。一度生姜醤油で刺身を食べれば、次回から丁寧に血抜きをして大切に持ち帰ることは間違いありません。 |
マルソウダ |
| ヒラマサ
|
(スズキ目アジ科) 鮮やかな背の青色、側面中央に一本通った黄色の縦じまが特徴である。ブリと大変良く似ているが、体がやや薄い(側偏)のと、口元の三角形の部分がヒラマサは丸く、ブリは角張っている事、胸ビレ、腹ビレが黄色味が強い事で区別できる。時速50kmもの猛スピードで泳ぎ回ると言われ、ハリがかりすると猛烈な引きで楽しませてくれる。大きさは1m、30kg以上に達するものもいる。外房のサンマミンチ、サンマエサのカモシ釣りが有名だが、アジなどの活きえさの泳がせ釣りも人気がある。刺身、塩焼き。照り焼き、寿司などどんな食べ方でも美味しい高級魚である。 勝浦川津港の宏昌丸の船長に教えてもらったヒラマサとブリ(ワラサ)の見分け方を紹介します。上の説明よりも分かりやすいと思います。胸ビレが黄色い縦じまに乗るのがヒラマサ、乗らないのがブリ(ワラサ)だそうです。左上の写真を見てもその特徴が良く分かります。ちなみにワラサの項の写真を見て下さい、黄色い縦じまに乗っていないことが良く分かります。 |
ブリ |
| ブリ |
(スズキ目アジ科) ご存知出世魚の代表的存在。 刺身、寿司、焼き物、煮物などどのように料理しても旨く、人気がある魚だ。 |
ワラサ |
| ブリモドキ |
(スズキ目アジ科) 「〜モドキ」とは可哀想な名前だ。ブリには体型こそ似ているが、大きな横縞が入っていて全くイメージが異なる。 大きくなると60cmほどに成長するが、幼魚の時は流れ藻や流木、クラゲなどに着いて暮らしている。ブリは美味しいのにブリモドキは美味しくない...。 |
|
| ホウズキ
|
(スズキ目メバル科ホウズキ属)
アコウダイとそっくりだが、アコウダイはメバル属、ホウズキはホウズキ属である。 アコウダイほど大きくはならず、せいぜい2kg位まで。食べてはアコウダイとほとんど区別がつかない。 |
アコウダイ |
| ホウボウ
|
(カサゴ目ホウボウ科) やや沖合いの砂地が生息域だが夏には浅場、冬は深みに移動する。特徴はなんと言っても良く目立つ青緑色のきれいな胸ビレだ。また、胸ビレの下に3本の軟条が分かれて足のような指のような格好になっている。これを動かしながら海底をエサを求めて動いている様はまるで歩いているように見えるのではないだろうか。虫類や貝類、甲殻類が主食で、全長40〜50cmにもなる。身は透き通った白身で、味も淡白で上品である。頭が大きく骨も硬いが、丁寧に捌けば刺身、椀物、鍋などで美味しく賞味することができる。 |
カナガシラ
カナド |
| ホシザメ
|
(サメ目ドチザメ科) 背から体側にかけて白い点が散在していることからこの名前が付いた。沿岸の浅いところから100m前後の深みの砂泥地に住んでおり小魚や甲殻類を捕食している。大きくても1m未満の小型のサメだが味が良い事から漁師のオカズにされている。特に冬場にはサメ類特有の臭みもほとんどなく大変美味である。フライや煮付けは一般的だが、そぎ身を味噌と酢、味醂、薬味(ネギなど)で合えた水なますは美味しい食べ方のひとつである。また、塩水に漬けてから干した「タレ」もお酒のつまみには最高の食材だ。 |
|
| ホラアナゴ
|
(ウナギ目ホラアナゴ科)
アコウを狙っていると良く掛かってくる。体色が黒く体の大きさに比べて口が異様に大きいのが特徴だ。人が食べるには適さないが、アコウの餌にすると効果がある。日ごろ良く食べているのか、深海でよく光るのか理由は良く分からないが裂いて短冊にすると特エサになる事を覚えていて損はないだろう。 |
オキアナゴ |
| ホンベラ
|
(スズキ目ベラ科) 派手な色合いの多いベラの仲間の中で極めて地味なのがこのホンベラである。オスは褐色が強いがメスは淡い黄緑色である。他のベラの仲間同様、岩礁帯やその回りの砂地に生息している。 |
オハグロベラ |