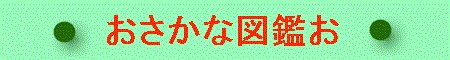 |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
・「あ」から始まる魚 ・「い〜え」から始まる魚 ・「か」から始まる魚 ・「き〜こ」から始まる魚 ・さ行の魚
・た行の魚 ・な行の魚 ・は行の魚 ・「ま」から始まる魚 ・「み〜も」から始まる魚 ・やらわ行の魚
| 魚の名前 | 特徴 | 関連する仲間の魚 |
| オアカムロ
|
(スズキ目アジ科) ムロアジの仲間であるが尾が赤いのが特徴である。ムロアジは泳がせのエサやクサヤでしか人気が無いがオアカは脂が乗りタタキなどにすると本家の味を凌駕する美味さである。従って知る人ぞ知るこの魚は釣れたら丁寧に血抜きしてクーラーに収めることをお勧めする。そんな姿を見かけたら、その人はこの魚の価値を良く知った沖釣りのエキスパートと見て間違いない。 |
アカアジ |
| オウゴンムラソイ
|
(スズキ目メバル科メバル属)
ムラソイの一種と考えられるが、鮮やかな黄色の模様や斑紋が特徴。
|
ムラソイ |
| オキアナゴ
|
(ウナギ目ホラアナゴ科)
口が大きく黒っぽい体色をしている。アコウダイを狙っていると一番下のハリに掛かってくる事がある。引かないし食べられないので面白くはないが、裂いてエサにすると結構アコウの食いが良い。やはり身近な場所にいる魚で脂があるので食べなれているのかしらん。 |
ホラアナゴ |
| オキエソ
|
(ハダカイワシ目エソ科) 砂地に生息し体を少し砂に潜らせて通りがかる小魚を狙っている。他のエソ類と同じく口が大変大きく、口の上に目がついているような風貌である。大きな口には細かく鋭い歯が並んでいて食いつかれた魚は逃げる事ができないようなかなり攻撃的なフィッシュイーターだ。体側に青い帯があるのが特徴で全長30〜40cmになる。この魚はカワハギ釣りの外道で釣れた物だが、小型のルアーにも結構反応するらしい。小骨が多いが淡白な白身で、叩いて団子やサンガにすると美味しく食べられる。 |
|
| オキギス
|
(ニシン目ギス科) 本名は「ギス」。ダボ、ダボギスとかろくな呼ばれ方をしていません。煮ても焼いても美味しくないんですが、すり身にすると最高な食材へ変貌するのです。さつま揚げや団子汁にすると他の魚はかないません。アコウ釣りに行くと良くかかりますが、ハリスに白いネバネバが付きます。キスに似ているのでこのような名前なのでしょうが、良く観察すると口が下についていて、ちょっとトボケた顔をしています。大きさは60cmくらいまで大きくなり、結構引くので初心者は良く勘違いさせられて、上がってからガッカリさせられる、そんな魚です。 |
|
| オキゴンベ |
(スズキ目ゴンベ科) カワハギ釣りの外道で掛かってきたが、最初はオハグロベラの雌かと思った。しかし良く見てみると、体高があり顔つきも違うようなので帰ってから調べてみて「オキゴンベ」と判明しました。 体色は黄色かオレンジ色で、背鰭の第1軟条が長くのびて、背鰭の体側に不明瞭な暗色斑があるのが特徴。 |
|
| オキノテズルモズル
|
(テズルモズル科) ヒトデの仲間、あまりに奇怪な姿なので写真に収めて調べてみると、こりゃまた素っ頓狂な名前だ事。 根魚五目の船で150m位の海底から上がってきました。触手がたくさんあり、船の上でも活発に動かして気持ち悪さNO1です。 |
|
| オニカサゴ(イズカサゴ)
|
(スズキ目フサカサゴ科)
オニカサゴの名前で有名ですが、イズカサゴ、フサカサゴ、ニセフサカサゴの総称です。背ビレに毒があり、刺されると大変痛み釣りどころではなくなってしまう(場合によっては病院へ)らしいです。まるかつはまだ経験はありませんが。口の中に親指をいれ下唇をしっかりと持つ持ち方をマスターすることが大切です。70〜200m位の砂礫帯に生息して50cm2kg位になります。かなり引きが強く、最後の水面まで良くファイトするのが特徴です。水面でも弱りませんのでバラすと海底に戻って行ってしまいます。大型はタモを使うことが必須です。実はまるかつのもっとも好きな釣り物のひとつで、常に仕掛をバックに忍ばせています。いつでもチャンスがあれば....と言うわけです。身が硬く数日寝かせてから食べることが重要ですが、刺身や酒蒸しが絶品です。 |
カサゴ |
| オハグロベラ
|
(スズキ目ベラ科) ベラの仲間では口が大きく体高がある。オスは紫褐色の体色でヒレや鱗の縁が黄緑ががっている。また、背びれの前方2本が糸状に伸びている。メスは赤みががった体色で背びれの前方2本も伸びない。岩礁帯やその回りの砂地に生息している。カワハギ釣りでの外道としてはお馴染みであるが、食べても美味しくないせいか、持ち帰る人もほとんどいない。 |
キュウセン |