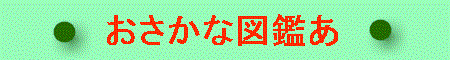 |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
・「い〜え」から始まる魚 ・「お」から始まる魚 ・「か」から始まる魚 ・「き〜こ」から始まる魚 ・さ行の魚
・た行の魚 ・な行の魚 ・は行の魚 ・「ま」から始まる魚 ・「み〜も」から始まる魚 ・やらわ行の魚
| 魚の名前 | 特徴 | 関連する仲間の魚 |
| アイゴ
|
(スズキ目アイゴ科)
沿岸の岩礁帯に生息し、主に海藻類を食べるが雑食性。近年数が増え藻場が枯れてしまう磯焼けの犯人と言う説もある。 背ビレ、腹びれ、尻ビレに毒トゲがあり、刺されるとかなり腫れ痛みが強いので要注意だ。更に目と目の間にも隠されたトゲがあり、これにやられるケースも多い様だ。 |
|
| アイナメ
オスの渡りアイナメ |
(カサゴ目アイナメ科) 岩礁帯やゴロタ石場など根回りに住んでいる。アタリは大型になるほどコツッとかクッと小さいが一呼吸おいてあわせるとグングンと頭を振って抵抗するので特長的な引きが首振りダンスとも言われて有名。イソメ類やエビを良く使うがヒラメ釣りの外道で餌のイワシに飛びついてくる大型は50〜60cmにもなる。ピンクがかった白身は淡白な中にも上品な脂が乗り、大変美味。刺身、塩焼き、煮付けなど色々な料理が楽しめる。小骨があるのでハモのように骨切りした身でしゃぶしゃぶにすると、アイナメの持つ魚の旨みが堪能できる。 |
クジメ ホッケ |
| アオハタ |
(スズキ目ハタ科) ハタの仲間の中では小型の部類で35cm位まで大きくなる。背ビレの後半と尾ビレの縁が鮮やかな黄色なのが特徴だ。マハタのような茶系の横縞に黄色い水玉模様が散りばめられていて、なかなかお洒落な姿だ。青くないのに何故アオハタと名前が付いたのか不思議だ。 |
アカハタ |
| アオメエソ
|
(ヒメ目アオメエソ科)
メヒカリの呼び名でお馴染みの深海魚。 |
|
| アオリイカ
|
(ツツイカ目ヤリイカ科)
イカの王様と呼ばれるほど味が良く、特に刺身が美味い。寿命は1年と言われているが2〜3kgの大きさになるものもいる。まだアオリイカの生態は詳しく解明されている訳ではないが、シロイカ、アカイカ、クァイカの3種があるらしいと考えられている。昔から餌木と呼ばれる和製ルアーで釣る漁が行われていたが、ここ数年船からこの餌木を使って釣る釣り方が定着し人気の釣り物になっている。また防波堤などからキャストして釣る釣り方を「エギング」と呼んで楽しんでいる人たちも多い。形からコウイカの仲間と間違えやすいが、ヤリイカやアカイカと同じ仲間である。 |
アカイカ |
| アカアジ
|
(スズキ目アジ科) この魚は大磯沖でカマスを釣っている時に外道で釣れたものだが最初は尾が赤いのでオアカムロかと思った。しかし、体高があり体型はマアジに似ており尾だけでなく全体に赤身がかっている事から調べてみると別種である事が分かった。大磯沖や二宮沖でアジ釣りをしていると良く混じるらしいが、やや深めのポイントに生息しているようだ。この日はマアジ、オアカムロも釣れたので同じような場所に混棲しているのかもしれない。食べてはマアジと遜色なく美味であった。 |
|
| アカエイ
|
(トビエイ目アカエイ科)
ワラサ釣りの外道で60mのポイントで掛かってきた。一体何が食ったのか?引かないし思いだけで時々生体反応があるだけ。浅い所から深いところまで生息範囲が広いエイである。 尾の付け根付近に太い毒棘があり要注意!!刺されると組織が壊死し、かなり酷い傷になる。 味はすこぶる良い、しかし毒棘が怖くてなかなか船上に引き上げるのが恐ろしい...。釣り船の船長も引き上げずにハリスを切る事を強く推奨するが、首尾良く尾を切って持ち帰ったら、煮付け、唐揚げ、ムニエルなどで賞味してもらいたい。 |
コモンカズベ |
| アカハタ
|
(スズキ目ハタ科)
ハタの仲間では比較的小型の種類で、最大40cm強1.5kgになる。浅めの岩礁帯に生息し、甲殻類や小魚を捕食する。 |
アオハタ |
| アカムツ
|
(スズキ目ホタルジャコ科) 本州中部以南の水深100〜300mに生息している。日本海側ではノドグロと呼ばれ珍重されている。ムツと名前についているが、ムツ科ではなくスズキ科に属している。最近、生息数が少なくなかなか狙って釣ることができない。年に1〜2回お目にかかれば良い方である。味は根魚の中でも最高で、刺身、煮付け、鍋とどんな料理でも美味しい。全長最大50cmほどまで成長する。 |
ムツ |
|
|
(ツツイカ目ヤリイカ科) 正式名称は「ケンサキイカ」である。通称「アカイカ」の方が通りがよい。毎年5〜7月頃に新島などの島周りや外房で乗合船が出る。刺身でも調理しても軟らかくて甘くたいへん美味しいので人気が高い。触腕が長く体色が赤みを帯びているのが特徴である。胴長30〜50cmになるが、小型の同種の個体を「マルイカ」と呼び釣り方も区別されている。ヤリイカやスルメイカと違いアカイカ、マルイカではスッテを使うのが特徴である。 |
アオリイカ |
| アカエソ
|
(ハダカイワシ目エソ科)
内湾や入江の砂地に生息し、良くキス釣などでお目にかかることが多い。大きな口と鋭い歯、赤みがかった体色と体側にある青い帯が特徴である。全長30〜40cmでかなり攻撃的な肉食魚だ。掛かったピンギスに襲い掛かる事がしばしばある。やや小骨が多いが淡白な白身なので、小骨ごとすり身にして椀だねやさつま揚げなどにすると美味しく食べることができる。 |
オキエソ |
| アカタチ
|
(スズキ目アカタチ科) アジ釣りの外道でかかってくることが多い。全長40cmくらいまでで、赤いリボンのような体型である。あまり美味しくない魚なのか、投げてもカモメも咥えて行こうとはしない。何でも食べてみるまるかつもさすがにまだ食べたことはないが、大きなものが釣れたら是非一度チャレンジしてみたいと思っている。実は雑誌に出ていたのだが、これの干物が大好物という記事が掲載されていた。それなりの筆者であったから、まんざらではないのだろう。 |
|
| アカカマス
|
(スズキ目カマス科) 秋から初冬に100m前後の深場に大きな群れを作って回遊する。相模湾の茅ヶ崎〜大磯にかけて乗合船が出て人気の釣物になる。全長60cmにまでなり歯が鋭く、小魚や小型のイカなどを捕食する。見た目と違いカワハギのように上手にエサを取るため、アタリがあってすぐにあわせてもエサだけ取られてしまう。なかなか繊細な集中力を必要とする釣りである。掛かった後は引きも体型の割には強く楽しめる。口は堅いので電動の高速で巻いてもほとんどバレる事はない。早めに巻いて手返しを心がけたい。釣りたての新鮮な魚は極上で、刺身、塩焼き、しゃぶしゃぶ、寿司、天ぷらなど大変美味しい。痛みやすい魚なので大漁のときは干物作りがお勧め。 |
ヤマトカマス |
| アカイサキ
|
(スズキ目ハタ科) やや水深のある岩礁帯に住みオニカサゴや沖メバルの外道でよく掛かってくる。40cmくらいまで大きくなり、オスとメスで体色が異なる。この写真はオスでめすはより赤みがかった色になる。味は賛否が分かれているが、ハタ科に恥じることなく大変美味しい魚である。オニカサゴと同じく身が硬く2、3日寝かすのがコツで、美味しくないという人は多分釣ったその日に食べたと思われる。刺身や煮付けは絶品で、プリプリした食感は病み付きになる。 |
|
| アコウダイ
|
(カサゴ目メバル科メバル属)
水深300〜800mの深海に生息し、岩礁帯のかけ上がりやフラットな砂礫帯に群れを作る。ハダカイワシやイカ類、底生魚類を捕食している。初春から初夏にかけて浅場(300〜400m)に上り産卵(卵胎生)すると考えられている。良く高級なミソ漬、カス漬けなどでは売られているが鮮度の良い物を刺身や鍋で食べることができるのは釣り人の特権である。 おいしい魚の食べ方参照。 |
オオサガ(ベニアコウ)
ベニメヌケ |
| アズマハナダイ
|
(スズキ目ハタ科) これはアマダイ釣りの外道で釣れたもの。沖の中深場で釣れる事が多く、全長15cm位の小型の根魚である。全体がピンク色で鮮やかな赤い横じまが斜めに入っているのが特徴である。また、尾ビレ上端の軟条が糸状に長く伸びている事で見分けがつく。群れている事が多いので掛かる時はバタバタと釣れる。小魚なので身は少ないが煮付けや塩焼きで食べればハタ科の魚なので味は悪くない。 |
サクラダイ |
| アナハゼ
|
(カサゴ目カジカ科) 海草の多い磯や岸よりの浅い岩礁帯に生息している。全長20cmほどで、浅場のイワシメバルの時に良く顔を見せる。カジカの仲間だけあって口が大きく大切なイワシエサをパクリとやってしまう。うろこが無くヌルヌルしており掴むと緑色の生殖器を出したりするので嫌われ者である。味も不味いらしく、食べたという話を聞かない。無益な殺生はしたくないので逃がしてしまうが、同じ魚が何回も掛かってくるかもしれないので不雑な心境だ。 |
|
| アカアマダイ
|
(スズキ目アマダイ科) 水深60〜100mの砂泥地に生息し、底のくぼみや穴にいて上を見あげている。したがって、底から1mくらいのタナを上手にエサを躍らせることが重要な釣り方のポイントになる。針ががりした直後はかなり強く引き、ビックリさせられるが巻きあげの途中おとなしくなり、残り20m位からまた強く引くという特徴がある。関西(特に京都)ではグジと呼ばれ珍重される高級魚である。やや水っぽい肉質なので刺身にする場合はコブ締めが適している。酒蒸しや椀物にすると上品な味が楽しめる。ぬめりを丁寧に取ることが美味しく食べるコツである。 |
シロアマダイ キアマダイ |
| アブラボウズ |
(カサゴ目ギンダラ科) 水深200m以上に居る深海大型魚。大きくなると100kgを越える魚体になるが、この写真の魚は水深500mで釣り上げた6.5kgの幼稚園サイズである。 |
|
| アヤメカサゴ
|
(スズキ目メバル科カサゴ属)
水深50〜150mの岩礁帯に生息し、きわめてカサゴと形態が似ている。しかし、体色を見ると鮮やかな赤橙色の地に黄色の虫食い模様が細かく入る派手な色彩が特徴となり見分けることができる。全長は30cmくらいまでで、なかなか出会うチャンスは少ないがつれた時はじっくりと賞味してみたい。それは、カサゴ類の中でも最も味が良いと言われているからだ。 |
カサゴ |
| アラ |
(スズキ目ハタ科) 水深100〜300mの岩礁混じりの砂泥地に生息している。全長1mにも成長するが普通は40〜50cm位のものが良く釣れる。なかなか狙って釣れる魚ではないが高級魚で相撲の世界ではアラのちゃんこと言えば最高のものである。エラブタに鋭いトゲがあり毒があるので取り扱いには注意が必要である。姿かたちがスズキに似ているので「オキスズキ」などとも呼ばれるが、大きくなるにつれて頭が大きくなりスマートなスズキとは形が異なってくる。刺身は甘味とコクのある上品な味だが釣りたては硬いので1〜2日寝かしてからが良い。焼き物や鍋にしても絶品だ。 |
|