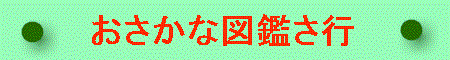 |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
・「あ」から始まる魚 ・「い〜え」から始まる魚 ・「お」から始まる魚 ・「か」から始まる魚 ・「き〜こ」から始まる魚
・た行の魚 ・な行の魚 ・は行の魚 ・「ま」から始まる魚 ・「み〜も」から始まる魚 ・やらわ行の魚
| 魚の名前 | 特徴 | 関連する仲間の魚 |
| サクラダイ
|
(スズキ目ハタ科) タイやアジ、メバルなどを釣っていて「あー、金魚が釣れちゃったよ。」という台詞を言ったり聞いたりした事が誰にもあると思う。その時の主役が赤い色も鮮やかなこの魚の事が多い。全長20cm位までの小魚だが群れをなしているので皆に続けてかかることが多い。性転換する事でも知られており、左の写真でも分かるように体型は同じでも色や模様が全く異なっている。型も小さく身が水っぽいのであまり食べられる事が少なくカモメの餌になる事が多いが塩焼きや煮魚にすると食べられなくはない。 |
アズマハナダイ |
| ササノハベラ
|
(スズキ目ベラ科) さまざまな釣りの外道として登場するベラ科の代表選手。内湾の浅く改装の多い岩礁帯に住むものは小型だが、外洋に面したやや深いところに住むものは赤っぽく大型のものが多い。エビカニなどの甲殻類、イソメ類など何でも食べる。夜は岩陰や藻の間などで眠り、昼間活発に活動する。冬には砂に潜って冬眠もするらしい。ベラの仲間では味の良い方で見た目とは反対にきれいな白身である。 |
オハグロベラ |
| サワラ
|
(スズキ目 サバ科)
パッと見はサバに似ている。銀色の魚体に黒っぽい模様があるので間違いやすいが、1mクラスまで大きくなる魚だ。 |
|
| シイラ
|
(スズキ目シイラ科) スラリとした体型で全長1mを軽く越す大物に成長する。海面近くを活発に泳ぎまわり、流木やパヤオ、漂流物に付く事で知られている。遊泳力は強く、特に大型は引きが大変強いので、最近はルアー釣りの格好のターゲットになっている。力が強いことや群れる事からからマンリキ、マンビキ、クマビキなどの俗称も多い。初夏から夏にかけて黒潮に乗って日本近海に多く姿を見せる。日本ではあまり食味の評価は高くないがハワイでは「マヒマヒ」と呼ばれ白身の高級魚扱いだ。小型はあまりいただけないが、大型はかなり美味く、まるかつも夏のヒラメ釣りで丁寧に餌付けしたイワシを下す時に120cmもの大物に横取りされ、釣り上げた事がある。その腹身の刺身はビックリするほど美味しかった記憶がある。釣り上げた時は金銀青に光ってきれいな魚体だが、死ぬと光が褪せてしまうのも特徴の一つだ。 |
|
| シキシマハナダイ
|
(スズキ目ハタ科) 100mダチでアジを狙っていて底から5m位で飛びついてきたのがこの魚。サクラダイやアズマハナダイで金魚みたいな外道には見慣れていたはずが、「こりゃキレイだわ。」と驚いたほどの極彩色で、特にスミレ色と黄色のコントラストはすごい。ハタ科の魚なので不味い事はないと思うが、カモメに食べてもらった方が喜ばれるでしょう。 |
アズマハナダイ |
| シマアジ
|
(スズキ目アジ科) 押しも押されぬ超高級魚、最大1m、10数キロになる大型のアジの仲間である。特に大型の魚はオオカミと呼ばれ強烈な引きと相反して口が弱く口切れでバラしてしまうため「ガラスの唇」などと例えられる。体中央に走る黄色い縦縞が長めの胸鰭と共にトレードマークである。 |
カイワリ |
| シマガツオ
|
(スズキ目シマガツオ科)
外洋の深場に生息し季節的な回遊をする。日本近海には春から初夏にかけてやってくることが知られている。中層(200〜300m)に群れをなしているので、食う時には単発でなく複数が同時に掛かる傾向がある。大型のものは大変力が強く、柔な竿だと折られてしまうこともある。肉食性でハダカイワシやイカ類を捕食している。釣り上げた直後は銀白色だが、死ぬとすぐに真っ黒に変色し、つけてある水まで黒く染めてしまう。身は白身で淡白、ムニエルやフライでは食べられるが、刺身などでは今ひとつ物足りない。 |
|
| シマフグ
|
(フグ目フグ科)
派手な黄色い鰭と縞々模様が特徴の50〜60cmにもなる大型種。 |
コモンフグ |
| シラコダイ
|
(スズキ目チョウチョウウオ科)
カワハギ釣りの外道で釣れたが、初めて見る魚で家に帰って図鑑で調べるまで名前すら分からなかった。それだけ馴染みは薄いと言う事になるが、有名なチョウチョウウオの仲間だ。この科は南の海に生息するものが多いが、シラコダイはサンゴ礁が住みかではなく温帯の海に良く見られる種類だ。動物性プランクトンが主食でイサキやアジの外道で釣れることも多い。味は悪くないが小型が多く側偏しているので身は少ない。何より食べる機会が極めて少ないだろう。 |
|
| シリヤケイカ
|
(コウイカ目コウイカ科)
スミイカ(コウイカ)と同じく硬い甲羅を持つタイプのイカである。 不味くはないが、スミイカと比べるとちょっと味が落ちるので釣り人の扱いはワンランク下となる。 |
カミナリイカ |
| シロアマダイ
|
(スズキ目 アマダイ科)
アマダイ御三家の中で一番美味とされる超高級魚。 中では一番浅い場所に住むと言われ、最大は2kgを越える大物になる。引きも強烈で、アカのお惚け顔とはちょっと違い、少し悪者の様な顔をしている(気がする)。大きくなるほど悪役面が強くなり、ハリスを引きちぎる態度も悪くなる。 |
アカアマダイ |
| シロムツ
|
(スズキ目ホタルジャコ科)
本名を「ワキヤハタ」と言う。近似種で「オオメハタ」も合わせて通称シロムツと呼ばれている。水深120〜200m位の砂泥底に群れており、全長30cmくらいまで大きくなる。口と目が著しく大きく白っぽい銀色をしているのでシロムツの名前が付いたがスズキ科の魚である。白身で身離れの良い魚だが、意外と脂もあり塩焼きにすると大変美味しい。また、くせが無いので天ぷらや茶碗蒸の種としても良い味が期待できる。30cm近い大型の物は是非刺身でも食べてみてもらいたい。本命にはならない魚だが、知る人ぞ知る魚だ。 |
ムツ |
| シロサバフグ
|
(フグ目フグ科) 毒があることで有名なフグ族の中で珍しく無毒のフグである。同じ仲間でクロサバフグがいるがヒレ(特に尻ビレ)が白い事で区別ができる。良く安いフグのミリン干しや加工品が売られているが、このフグの場合が多い。味に関してはBランクだが調理の仕方によっては美味しく食べられる。 |
クロサバフグ |
| シロギス
|
(スズキ目キス科) 水のきれいな内湾や内海の砂底に生息して、主にゴカイ、イソメなどの虫類を主食にしている。全長30cmくらいまで成長するが30cmを超えるものは尺ギスと呼び釣り人の憧れの対象になっている。また、頭を握ったときに自分の肘を尾びれが叩くことから、「ヒジタタキ」とも呼ばれる。浜からの投げ釣りや船からの釣りも大変ポピュラーで日本全国の釣り人から愛されている魚である。ほぼ底にいて頭を下げて底のエサを探す泳ぎ方をしておりエサをくわえて頭を振りちぎるようにする為、ブルブルというアタリが特徴だ。上品な白身は天ぷら、フライ、塩焼き、干物、コブ締めなど色々な食べ方が楽しめる。 |
|
| ショウサイフグ
|
(フグ目フグ科) 一年中狙っている船宿もあるが、秋から春にかけてがベストシーズン、外房からたくさんの乗合船がでる。この魚は内臓などに毒を持っている為、素人が調理することができず、最近では船宿でフグ処理免許を所得し、捌いて持たせてくれることが人気の原因の一つでもある。食べても時期的にちょうど良い鍋や刺身、空揚げ、ヒレ酒など家族にはたいへん人気が高い。我が家でも初めての時は怖がってなかなか箸をつけなかったが、今ではあっという間に皿や鍋からフグが消えてゆく。これならばフグも本望であろう。 |
ゴマフグ |
| スズキ
|
(スズキ目スズキ科) 日本各地に生息していて非常に馴染みの深い魚である。分類学的にも代表的な魚で、スズキ目には多くの魚が分類される大所帯でもある。小魚を好んで捕食する典型的なフィッシュイーターであるが、エビなどの甲殻類も好むようだ。そんな性質からるあーで狙うターゲットとしても大変人気が高く、シーバスと呼ばれ一つのジャンルが確立されている。 |
|
| スズメダイ
|
(スズキ目スズメダイ科)
小型の磯魚でイサキ釣りなどで浅場を釣った時に良く掛かってくる。各種のプランクトンが主食で、昼間活発に活動する。あまり食べられることは少ないが、九州では(特に福岡)「アブッテカモ」と読んで焼き物にして珍重されている。結構脂が多く、焼くとジュウジュウと脂が滴り落ちるくらいである。骨っぽく身も少ないがしゃぶるようにすると結構イケル魚である。 |
|
| スソウミヘビ |
(ウナギ目ウミヘビ科) 初めて釣り上げた時はアナゴだと思ったが、色も顔つきもちょっと違う。オマケにタオルにも指にも噛み付こうとするので取り扱いに注意が必要だ。 |
|
| スナダコ
画像準備中 |
(八腕目 マダコ科)
砂地に生息する小型のタコ。 |
マダコ |
| スミイカ
|
(コウイカ目コウイカ科) 同じイカでもツツイカ科と違いからだの中に硬い大きな甲羅が入っていることからコウイカの仲間と呼ばれている。その中でも秋から初春にかけて釣り人を熱くさせるのがスミイカだ。名前のとおりこの小さな体の中にこんなにスミが入っているのかと思わせるほど良くスミを吐く。特に釣り上げた瞬間は要注意だ。なかなか落ちにくいスミなので顔や服、船に掛かったときは早めに流すことが大切だ。内湾の砂泥底に住んでおり、胴長45cm位まで大きくなる。専門に釣る場合はテンヤにシャコエサで狙うが、アオリイカ狙いの餌木にも良く乗ってくる。身はねっとりとして甘く、刺身や天ぷらで絶品だ。 |
カミナリイカ |
| スルメイカ
|
(ツツイカ目アカイカ科) 胴の中央がやや膨らんだ筒型の体型をしている。エンペラの形がトランプのスペードの形に似ており2本の触腕が長いのが特徴である。かなり獰猛な性格でヤリイカと同じく小魚を捕食するが、落ちてくる魚より、上へ上へと逃げる魚を追う性格である。したがって釣り方は大きく激しくしゃくることが大切となる。水深80〜150mの岩礁混じりの砂地を回遊するが、時間帯によって泳層が変わりので底から中層まで広く探ることが釣果につながる。沖干しや沖漬け、塩辛、肝炒めなどはスルメならではの美味しい食べ方である。初夏の小型をムギイカ、その上のサイズをニセイカなどとも呼ぶ。 |
アオリイカ |
| ソコイトヨリ |
(スズキ目イトヨリダイ科) 鮮やかなピンクに黄色い縦縞が鮮やかな美しい魚だ。本家イトヨリダイは黄色の縦縞が6本なのに対して、ソコイトヨリは3本、また腹が黄色いのが特徴である。(イトヨリダイは腹は黄色くない) 上品な白身の美味な魚で、旬の秋から冬にはマダイよりも旨いといわれているほどである。焼いても煮ても、蒸しても美味しい超高級魚なので、釣り上げたらじっくりと賞味してもらいたいものだ。、 |
|