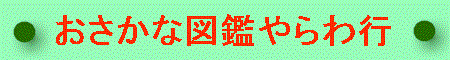 |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
・「あ」から始まる魚 ・「い〜え」から始まる魚 ・「お」から始まる魚 ・「か」から始まる魚 ・「き〜こ」から始まる魚
・さ行の魚 ・た行の魚 ・な行の魚 ・は行の魚 ・「ま」から始まる魚 ・「み〜も」から始まる魚
| 魚の名前 | 特徴 | 関連する仲間の魚 |
| ヤナギノマイ
|
(スズキ目メバル科メバル属) 全体に褐色または黄色がかった色をしている。体側後部にくっきりとした薄茶色の縦じまがあるのが特長。
|
ウケクチメバル |
| ヤマトカマス
|
(スズキ目カマス科) 相模湾で浅場のサビキ釣りで狙うのがこのカマスである。アカカマスに比べてあまり大きくならず、身がやや水っぽいのでミズカマスとも呼ばれる。アカカマスより黒っぽいが見分けるポイントは第一背ビレと腹ビレの位置で、ヤマトカマスはほぼ同じ位置か腹ビレが後方にある。(アカカマスは腹ビレが背びれよりも前)小魚を襲う獰猛さなどの習性は同じだがあまり深みには落ちないようだ。 |
アカカマス |
| ヨソギ
|
(フグ目カワハギ科) カワハギ釣りの外道で掛かってきたが、当初ウマズラハギの子供かな位にしか思っていなかった。 |
ウマズラハギ |
| ヤリイカ
|
(ツツイカ目ヤリイカ科)
スマートな体型で槍の先を思わせることから名前がついた。釣り上げると透明になったり、赤銅色になったり体色を著しく変化させる。小型がメス、大型がオスと言われており、春の産卵期にはそれぞれの群れが時間差で乗っ込んで来る。水深80〜200mの岩礁交じりの砂地を好み、底から10m位の範囲が生活圏である。小魚を捕食するが、上から落ちてくる物に強く反応することが多いので釣り方にも落とし込みのテクニックが必要になる。釣りたての透き通った刺身は釣り人冥利に尽きる一品である。旬の卵まぶしも絶品である。 |
アオリイカ |
| ユメカサゴ
|
(スズキ目メバル科ユメカサゴ属)
沖の深場で釣れる外道の代表選手。口の中から腹腔内が黒いので「ノドグロ」とも呼ばれている。25cmまでのものはどこでも良く釣れるが30cm以上のものはなかなか釣れない。深場釣りをやっていて大型のユメカサゴが釣れたらそのポイントはあまり荒れていない証拠である。100〜300mの砂泥底に住みオカズにするにはちょうど良い魚だ。身は白身で上品な中にも旨みがあり、浅場のカサゴに比べれば身が少しやわらかいが、塩焼き、煮付けは最高だ。大型ならば刺身でも良く旨みをじっくりと堪能することができる。 |
カサゴ |
| ヨリトフグ
|
(フグ目フグ科) 別名「ミズフグ」。深めのアジ釣りや中深場の根魚釣りなどで良いアタリがあって巻き上げると途中でハリだけなくなったり糸を切られたりする事があるが、正体はこいつの場合が多い。巻き上げるに従って重くなり、水面まで来ると水を思いっきり飲み込んでパンパンになったゴムマリみたいな状態にガッカリさせられる。無毒なのだが美味しくないので普通は食べない。釣り人には嫌われて海に投げつけられたりするが、ちょっとかわいそうな気もする。チカちゃんのあだ名が「ミズフグ」だが容姿から命名されたもので彼は嫌われる事などなく、皆に好かれている。 |
|
| ワラサ
|
(スズキ目アジ科) ご存知、代表的な出世魚である。関東ではモジャコ→ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ、関西ではモジャコ→ツバス→ハマチ→メジロ→ブリと名前が変わる。3kgを超えるとやっとワラサと呼ばれるが、2〜3kg位のものを「サンパク」と呼んだりもする。左の写真の魚が4.3kgだが、7kgを超えてやっとブリと呼ばれるので、ワラサとしてはまだ駆け出しと言う事になる。このサイズになると食いが立った時にはコマセに突っ込んでくるので、いかに「ここぞ」という時にコマセが撒けるかがポイントになる。食べてはブリではちょっとしつこいし、イナダでは少し物足りないと言う事で、ちょうど良い食べごろサイズと言う事になる。刺身、カマ焼き、照り焼き、大根との煮物と至れり尽せりだ。 |
イナダ |