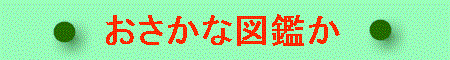 |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
・「あ」から始まる魚 ・「い〜え」から始まる魚 ・「お」から始まる魚 ・「き〜こ」から始まる魚 ・さ行の魚
・た行の魚 ・な行の魚 ・は行の魚 ・「ま」から始まる魚 ・「み〜も」から始まる魚 ・やらわ行の魚
| 魚の名前 | 特徴 | 関連する仲間の魚 |
| カイエビス |
(キンメダイ目イットウダイ科) 初めてこの魚を見た時は本当にビックリした。強いアタリに結構良い引き、そして水面を割ったときの鮮やかな赤い色。全身にヨロイのような硬く立派なウロコをまとい食べられるものなら食べてみろと言わんばかりである。同種のエビスダイと良く似ているが、側線より上方の鱗が2.5枚であり、3.5枚のエビスダイと区別できる。 |
|
| カイワリ
|
(スズキ目アジ科) アジの仲間ではもっとも体高が高く、型の良いものが釣れると知らない人は「シマアジだっ!!」と大騒ぎをする。岩礁帯よりは砂泥地に多く、虫類や甲殻類、大型のものは小魚まで食べている。味の方はすこぶる良く、刺身や塩焼きは絶品であり、この点においてはシマアジに一歩譲るものの勝るとも劣らないと言っても良いかもしれない。 |
シマアジ |
| カガミダイ
|
(マトウダイ目マトウダイ科)
アジ釣りで掛かったアジを半分飲み込んで上がってきたり、イカヅノをくわえてきたりするが水面でギラリと光り水圧のせいか結構引くので驚かされる。体表にウロコはなく名前の由来の通りカガミのように光っている。この皮は上手に乾燥させるとカッタクリに最高の疑似餌の材料になる。しかし身の方は面積の割には薄い身で味も今ひとつである。 |
マトウダイ |
| カゴカキダイ
|
(スズキ目カゴカキダイ科)
船釣りの対象ではないが、防波堤や磯の釣りではポピュラーな魚。この魚はカワハギ釣りの外道で釣れたもの。 縦じまが特徴で派手な装いと小型魚ゆえ食べる対象として見られないが、実は美味な魚として評価されているようだ。 |
|
| カゴカマス
|
(スズキ目クロタチカマス科)
同じ科のクロシビカマスとよく似ているが、皮が柔らかく薄い感じである。水深200〜500mに棲み群れていると考えられるが、クロシビカマスよりもずっと個体数は少ない。 同じ科でありながら食味は上、クロシビカマスの脂は好みが分かれるところだが、カゴカマスの脂は嫌味が無く美味しい魚だと評価されている。 |
クロシビカマス |
| カサゴ
|
(スズキ目メバル科カサゴ族)
岩場に住み障害物の陰や穴からギョロリとした目で獲物を探し、大きな口で餌を一気に飲み込むタイプ。この仲間は深さや環境で体色が変化するので、深場ほど鮮やかな赤い色のなることが多い。体は棘も多く厳つい顔だが、きれいな白身でとても上品な味わいである。背開きにして空揚げにするとヒレや小骨もぱりぱりとして美味しい。もちろん味噌汁にしても最高である。カサゴ釣りは根掛かりを恐れていては釣れない。軽い根掛かりは強く引かず、道糸の張っている方向の反対にチョンチョンと軽くあおりはずすテクニックも必要だが、オモリと予備の仕掛をしっかり用意して望むのが大切だ。根魚釣りの基本中の基本である。 |
アヤメカサゴ |
| カスザメ |
(カスザメ目カスザメ科) 変なサメである。いや、ふつうの人には、エイに見えるだろう。サメとエイの違いは、簡単に言えば鰓孔が腹面に開けばエイで、側面に開けばサメである。このカスザメの鰓孔は腹側から側面に開いている。こんな変な開き方をするのはカスザメ科だけである。 |
コロザメ |
| カスミサクラダイ
|
(スズキ目ハタ科) 赤橙色をした小型のハタの体型をしている。100〜200mの砂泥底に生息しており、アマダイ釣りの外道で良くかかってくる。背びれが黄色く中央あたりが深く切れ込んでおり、尾びれの縁が丸いのが特徴。全長は20cm前後までと小型ではあるがハタ科だけあって味は悪くない。干物にしたり、天ぷらなどで食べると同じアマダイの外道として有名なヒメコダイと遜色ない。 |
|
| カタクチイワシ
|
(ニシン目イワシ科) ご存知、煮干の原料になったりカツオ釣りやヒラメ釣りの活き餌になるイワシで「シコイワシ」とか「セグロイワシ」も呼ばれます。目が大きく、口が裂けたように大きく下顎が小さくイワシ類の中でも特徴のある顔つきなので見分けやすいでしょう。また「セグロイワシ」の名前の所以でもありますが、背中が青黒いのも特徴です。外房ではゴマ漬けや干物、目刺しなどにしてお土産として良く売っています。活きの良い物を手開きにしてショウガ醤油でいただくと病みつきになります。 |
ウルメイワシ |
| カタボシアカメバル
|
(スズキ目メバル科メバル属)
一昔前までは通称パンダメバルと呼ばれウケクチメバルと混同されていた。どちらも120〜300mくらいまでの中深場で外道で登場することが多く、エラ蓋に黒い模様があるのが特徴である。ウケクチメバルの模様が縦長なのに比べ、カタボシアカメバルは丸く小さい。 |
|
| カツオ
|
(スズキ目サバ科) 古来より日本人に馴染みの深い魚で、初夏に黒潮に乗ってやってきたカツオを「初ガツオ」、「上りガツオ」と言い江戸時代から親しまれてきた。また、三陸沖で夏を過ごし秋にはたっぷり太って南下を始める。これを「下りカツオ」と言い、脂が乗っったものを「トロカツオ」とも言う。最大1m、10kg以上にもなりハリががりしたときのパワーはものすごい物がある。ハリス16号でも引きちぎられたなんて話は良く聞かれる。一本釣り、イワシエサのフカセ釣り、カッタクリ、オキアミのビシ釣りとさまざまなつり方があるが、波と血しぶきを浴びながらカツオを釣るのは豪快そのものである。刺身、タタキも最高だが「カツオ節」は日本人原点である事を忘れてはいけない。 |
ハガツオ |
| カナガシラ
|
(カサゴ目ホウボウ科) 見た目も食味も良く似ているのでホウボウに間違われやすい。もちろん仲間なのだが、ホウボウの胸ビレは青、緑と鮮やかなのに対して、カナガシラは体色と同じ赤い色をしている事で見分けがつく。普通、あまり大きな物は釣れないが40cm位まで大きくなるようだ。味は良く鍋や椀物、塩焼きなどにして賞味すると良い。サッパリとした魚が好みの人には最適な魚だ。 |
ホウボウ |
| カナド
|
(カサゴ目ホウボウ科) 上記のカナガシラ同様ホウボウに間違えられやすい魚だ。胸ビレはホウボウほど全体が鮮やかな色はしていなく、中心部が青色になっているのが特徴。全体的に頭でっかちで寸詰まりな印象で、全長も25cm位までしか大きくならない。食味も悪くはないが仲間のホウボウやカナガシラには今一歩及ばないようだ。アマダイ釣りや冬の深場のシロギス釣りの外道で釣れる事が多い。 |
ホウボウ
|
| カミナリイカ
|
(コウイカ目コウイカ科) 最大5kg位まで成長する大型種。コウイカの仲間は雌雄で異なる体色斑紋パターンを示すものが多くいるが、カミナリイカのオスは細かい横縞の中に葉の気孔の様な模様が現れる。これがキスマークに似ているため、英語ではこのイカの事を"Kisslip
uttlefish"と言う。 |
スミイカ |
| カラスザメ 背ビレのトゲ |
(ヨロイザメ目カラスザメ科) キンメダイやアコウダイなど深場の釣りをやっていると掛かってくる嫌われ者。 なまじハリ掛かりすると針から外し難く、外そうと魚を持つと尾びれを曲げるようによじって背ビレのトゲを刺そうとするから始末に悪い。刺されると毒がありかなり痛むので注意が必要だ。 |
|
| カワハギ
|
(フグ目カワハギ科) おちょぼ口で餌をつついたり、吸い込んだり出したり、上下左右にヘリコプターみたいに泳ぐことができる元祖エサ取り名人(魚?)。ウロコがなくザラザラした皮は簡単に剥ぐ事ができることから、この名前が付いた。大きさの割に縦横に引く釣り味はかなり強く、大型に水面近くで横走りされると心臓が止まりそうになる。待ち釣り、タタキ釣り、タルマセ釣り等々さまざまなテクニックがあるが、基本はハリのマメな交換や、エサのアサリのつけ方など地道な基礎技術にある。食べては秋から冬に大きくなる肝にとどめを刺し、刺身の肝和え、肝入り煮つけや鍋は日本人に生まれてよかった度120%。浅場から50〜60mの砂と岩が混じるような場所を好む。40cm近くまで大きくなるらしいが、まるかつの記録は30cmを超えることができていない。残念。 |
ウマズラハギ |
| ガンゾウビラメ
|
(カレイ目ヒラメ科) ヒラメの仲間なので目は左側にあるが、丸い体型からカレイに見間違えられる事も多い。沖合いのやや深い砂泥地に住み、ヒラメ釣りやショウサイフグ釣りの外道でつれることが多い。体表に(目玉の様なの丸い斑紋)が1個あるのが特徴で5個あるタマガンゾウビラメ、6個あるムシガレイと間違えやすい。身も薄いのでムニエルや干物にして食べるが一塩して冷蔵庫で一晩置いたものは結構いける。 |
ヒラメ |
| カンパチ
|
(スズキ目アジ科) カンパチはブリやヒラマサと同じブリ属の仲間だが、体高がやや高く体色が赤みを帯びた灰色なので簡単に見分けがつく。また、小型のものは上から見たときに漢字の「八」の字に見える黒い帯状の模様がある。これが名前(間八)の由来とも言われている。ブリよりも高水温を好むようで南日本に多いが、島周りなどでは1.5〜2m、30kg以上などという大物も釣られている。ものすごい力で剛竿を根元から曲げるようなファイトに虜になり泳がせ釣りにはまる釣り人も結構いる。食べては刺身、寿司、焼き物、アラ炊きと何でも美味いが、大型は味が落ちるので5kg位までが食べるには最高だ。 |
ヒラマサ |