
東京都調布市とみさわ歯科医院
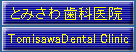
 |
東京都調布市とみさわ歯科医院 |
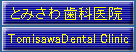 |
|||||||
Tomisawa Dental Clinic in Chofu -shi Tokyo |
|||||||||
わかりやすい矯正歯科の知識 |
|||||||||
骨は生きた組織といえます。生きているとは新陳代謝をしているということです。
骨はその機能単位としてOsteon(骨の栄養血管を入れるHarvers管を中心に、年輪状に並ぶ幾つかの骨薄板によってできた管)の集合体となって骨梁が形成されています。その骨は主にカルシウムを主成分とする骨基質、骨形成結合組織により形成されています。そして骨の中には骨芽細胞や破骨細胞などの細胞成分を有し骨の新陳代謝にかかわっています。ちなみに歯(歯髄以外の部分)は骨とは違い細胞成分がなく新陳代謝が行われていません。
骨折をしてもまた元通りに骨がくっつくのもこうした骨の新陳代謝があるからなのです。一方で歯の根が何らかの原因で折れてしまってももとに戻ることはありません。
歯の移動はこうした骨の新陳代謝を利用して行われます。
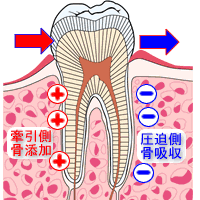
歯と骨は歯根膜といわれる繊維組織で繋がっています。そのため矯正力を加えると骨は歯根膜を介して片面は圧迫を受け、もう一方の面は牽引されることになります。骨に加えられた圧迫因子と牽引因子により、骨は違った反応を起こします。
その力が強い場合、歯根膜に重度の血流障害が起こり、線維などの細胞基質は変性し、硝子様変性と呼ばれる状態となります。こうした変性組織周囲には破骨細胞が歯槽骨表層に接近できないため骨髄側に出現した破骨細胞により歯槽骨壁の背面あるいは側面から吸収が進みます。これを間接性吸収といいます。一方、その力が弱い場合、歯根膜に軽度の血流障害が起こり、破骨細胞とマクロファージが出現し、破骨細胞による直接吸収が起こります。
牽引された線維に介在する血管の血流亢進が起こり、そこにある線維芽細胞、骨芽細胞、セメント芽細胞の分化、増殖、代謝活性が促進されます。その結果として歯根膜線維に沿った骨形成、セメント質形成、歯根膜線維の再配列が進行します。
矯正力による歯の移動はこうした歯根膜を介した骨の吸収と添加を利用して行われています。
参考文献:
「歯科矯正学」(葛西一貴他)
「病理学各論(飯島惣一他)