虫歯
虫歯診断の基礎知識
虫歯を診断する意味
病気を診断する目的は、その病気にあった治療方法を決めるためです。いろいろな病気を診断をする立場としては病因論的(原因をつきとめる)立場と形態学的(見た目の変化を区別する)立場に大別できます。
現在、虫歯の診断は主に形態学的立場が主流となっています。つまり虫歯の深さを区別することにより、処置方針(どうやってつめるのか、神経を取るかなど)を決めるためです。それはそれで意味のあることですが、いくら虫歯の深さをみても虫歯になった原因をつきとめることはできません。しかし一般の臨床(実際の治療場面)では病因論的立場の診断はあまり行われていないのが現状といえます。
虫歯進行のプロセス
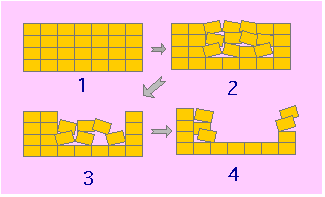
虫歯の進行は、たとえば青虫が葉っぱを食べるように、虫歯菌が歯をせっせと食べて穴が広がるような進行形態はとりません。歯の表層のエナメル質はハイドロオキシアパタイトという結晶構造を主体にできています。(象牙質ではエナメル質より有機成分が多くなります。) 虫歯は右図のように酸で結晶中のカルシウムが溶け出すと 2の様に結晶が崩れだします。さらに酸の侵食をうけると、3のように歯の表面構造が崩れだし微細な形態的変化が現れだします。そして4の様な齲窩(虫歯の穴)と発展していきます。
虫歯診断の難しさ
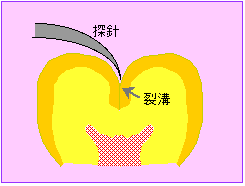
虫歯の診断は、単に歯にある穴の有無やその大きさを見て診断できるわけではありません。虫歯は歯の結晶の微細な変化からはじまり、目で判別できる穴になるまで連続的な変化をたどります。したがってどこからを虫歯と呼べるかは微妙に意見の分かれるところです。
虫歯を正確に診断するためには、歯科医は視診(目で見える変化)、探針という細い針金での触診(さわった変化)、レントゲン写真による検査といった手段を用います。
視診では 穴があればそれが虫歯であると診断が下せます。しかし2の状態では歯の平らな面では白濁してみえることもありますが、はっきり区別をすることはできません。ましてや唾液やプラーク(歯垢)のあるような奥歯の溝などでは視診だけで虫歯の存在を判別することはかなり難しいことです。そこで探針という道具を使って触診をしてみるわけです。
虫歯診断の教科書ではこの探針を溝に刺して引き抜くときに粘つくような感触があれば虫歯(C1:シーの1)と判断することになっています。しかしこうした探針の用い方は、図1の2の状態を無理に4の状態のようにしてしまう危険がり、慎重でなくてはなりません。図1の2の状態は削ってつめなくても、適切な予防策がとられれば再石灰化という現象によって十分もとにもどる可能性のあるところですが、4の状態になれば削ってつめる必要性が出てきます。
さらに歯と歯の間の虫歯となると視診も触診もやりにくくなるためレントゲン写真を用いることになります。この方法は比較的虫歯の存在をはっきりと判別することができますが、ちょっとした撮影角度のずれで判別しにくい場合もあります。また集団検診などでは設備面で用いにくい方法です。
深さによる診断基準
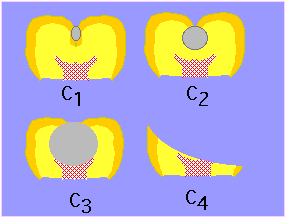
虫歯の進行度をあらわすために、このC1「シーイチ」C2「シーニ」・・・C4「シーヨン」という分類方法が、歯科検診などで比較的よく用いられます。
この分類方法は左図の様に
- C1はエナメル質に限局したした虫歯
- C2は象牙質に到達するが歯髄(神経)病変のおきてないもの
- C3歯髄病変のおきているもの
- C4は歯冠の大部分が崩壊し残根状態のもの
と分類されます。この分類方法も病変が連続的に変化するためはっきりとした境界線を引くことはできません。また視診だけでは判別することも難しく、レントゲンを撮影してみないと、正確な診断は下せません。
またC1と健全の間にグレーゾーンがあり、実際の臨床ではどう診断をつけたらよいのか迷うところです。
近年、学校歯科検診では先に述べた「粘つく感じ」があっても、明らかなエナメル質の軟化や実質欠損が確認できないものは、要観察歯CO「シーオー」として扱うことになっていますが、これもまた正確に区別することは難しいといえます。
虫歯予防先進国での診断
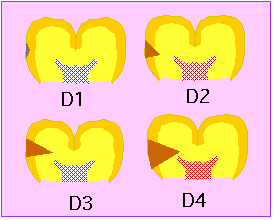
近年、日本も12歳児のDMFT(虫歯の歯、及び詰めたり抜かれた歯の合計本数)の減少は著しく2005年の文部科学省のデータでは1.8まで下がってきました。一方虫歯予防の先進国ともいわれる北欧の各国では1近くまで下がっています。。
さてこれらの国ではどのように虫歯の診断がなされているのでしょうか。下図のような分類が用いられています。
Enamel caries:(エナメル質齲蝕)
- D1= A caries lesion on a proximal surface with a V or U-shape on the X-ray, within the enamel and not reaching the dentine.(レントゲン所見としてエナメル質に限局し、象牙質到達しないもの)
- D2= A caries lesion on a proximal surface that looks like a V or U on the X-ray, reaching or slightly passing the enamel-dentine border.(エナメルー象牙境に到達あるいはわずかに通過したもの)
Dentine caries:(象牙質齲蝕)
- D3= A caries lesion on a proximal surface that on the X-ray shows to be reaching clearly into the dentine. (明らかに象牙質に到達したもの)
- D4= A caries lesion on a proximal surface, almost reaching the pulp.(ほとんど歯髄に到達しているもの)
とされています。ちなみにスウェーデンではD1,D2は予防の対象となり公式の歯科疾患統計では虫歯として取り扱われていないので、DMFT にも含まれないそうです。
リスクを考慮した虫歯診断
虫歯は簡単に診断を下せるものではありません。特に初期の虫歯は診断が難しいといえます。
それを削って詰めるべきなのか、予防策をとって経過観察をすべきなのか虫歯のリスク因子などもふまえて的確な診断を下さなくてはなりません。
