|
第79回配信
これはゴールではない
 |
| EU正式加盟を数時間後に控えた4月30日夜、首都リュブリャーナで演説するドゥルノウシェク大統領(大統領HPより 提供:ス共和国政府広報局) | 「91年以来の我々の夢が実現し、今夜国境は消滅する。明日ヨーロッパがここに来る。我々はヨーロッパに到着するのだ」。
5月1日の欧州連合(EU)正式加盟を数時間後に控えた4月30日夜、首都リュブリャーナ市中心部でドゥルノウシェク・スロヴェニア大統領が演説し、市民とともにこの歴史的出来事を祝いました。
読者の皆さんもご存知の通り、3月末の北大西洋条約機構(NATO)加盟に続き、旧ユーゴから紛争とともに独立して13年(国際的承認から12年)の若い国家スロヴェニアはEU加盟を果たしました。もちろん旧ユーゴ圏5カ国で最初のケースです。
この日は残念ながらスロヴェニアの現地取材に行くことが出来ませんでした。セルビアに住む筆者のスロヴェニアへの「少しひねくれた愛情」は、既に第49回配信で告白してしまっているのでくどくどとは繰り返しません。が、91年の独立紛争当時の現場にいて、その頃から「EU(当時はEC=欧州共同体、でしたけれども)へ、NATOへ」が目標として人々の口にのぼっていたことを思い出すと、祝いの一言もかけたい気持ちです。「おめでとう、でもこれはゴールじゃなくてスタートだ、これからも頑張ってくれ」では下手な結婚式のスピーチみたいですけれども・・・。
自動車のナンバープレートが新調される、イタリア、オーストリア、ハンガリーとのEU国境が事実上消滅しクロアチア国境の管理が厳しくなる、などの細かな話題も面白いものがありますが、今回配信ではもう少し大きなテーマとして最近のスロヴェニア経済・内政の状況と、EU加盟に伴う旧ユーゴ他地域との関係などを主に取り上げてみましょう。
スロヴェニア人のノーベル化学者
旧ユーゴ圏出身のノーベル賞受賞者はアンドリッチ(61年文学賞)、マザーテレサ(79年平和賞)の二人だけだと長年思い込んでいた筆者は、この2人よりはるか前に受賞した「3人目」がいることを最近になって偶然知りました。 | | F・プレーグル |
|---|
百科事典などにはオーストリアの化学者として記載されているフリデリク(フリッツ)・プレーグル(1869−1930、23年化学賞)です。実はプレーグルを調べているうちにルジチカ(39年化学賞)もヴコヴァル生まれのクロアチア系スイス人であることが分かりましたが、今回は話題を前者に絞ります。
スロヴェニア人を父、ドイツ人を母としてオーストリア=ハンガリー帝国のリュブリャーナ(独語名ライバッハ)に生まれたプレーグルは、同市の普通科中等学校を終了後現オーストリアのグラーツで医学を学びます。しかしオストワルト、フィッシャー(いずれもノーベル化学者)ら、当時のドイツ基礎科学先端研究に触れ、生理学などの基礎医学、さらに有機化学の方向へ関心が向かいます。04年から胆汁酸の研究を開始しますが、当時の技術では一度の化学分析に大量の試料を使わなければならず、これが有機化学、さらに人体の生理活動の物質的、化学反応的側面を研究する生化学の初期発展の障害になっていました。プレーグルはハンブルクの精密機器メーカーとともに精密な天秤を制作。それまでの10〜100分の1に当たる10mg程度の試料での分析法を開発し、炭素、窒素、ハロゲン、様々な有機化合物の微量分析を可能にしました。彼の有機化合物の微量元素分析法は「新発見ではないが既存の方法の改善革新により受賞に値する」とスウェーデン王立アカデミーから評価され、23年にノーベル化学賞を受賞しました。一次大戦後、生化学は飛躍的に発展しますが、ヴィーラント(コレステロール、胆汁酸)、ウィンタウス(ビタミン)、ハーデン(酵素・発酵)、オイラー=ケルピン(補酵素)ら、この時代プレーグルに続いてノーベル賞を受賞した化学者たちの研究にも彼の方法が貢献したと科学史家は評価しています。
昨年12月、プレーグルのノーベル賞受賞80周年を記念して、ス国立化学研の主催によりリュブリャーナ市でシンポジウムが開かれ、同市内のトスカニーニ広場に記念像が除幕されました。除幕式に同席したナグル・グラーツ市長は「リュブリャーナで生まれグラーツで死んだプレーグルは、今後とも両市の友好の象徴となるだろう。欧州文化都市に指定されたグラーツの経験を活かし、スロヴェニアのEU加盟後に生じてくる両市の様々な問題に協力しながら対処して行きたい」と述べています。
参考資料:(1)Zvonka Zupanic-Slavec, "Zdravnik Friderik Pregl, Nobelov nagrajenec slovenskega rodu - za 130-letnico rojstva -", (2)Kemijski institut Ljubljana, (3)Slovenia Business Week, (4)Wikipedija, (5)Microsoftエンカルタ百科事典2001
プレーグルの写真は版権が消滅していると思われ、複数のサイトが使用しているものを借用しました
|
3月17日ウォルフェンソン総裁ら世界銀行幹部がリュブリャーナにロップ首相、ムラモル蔵相を訪れました。このニュースはNATO、EU加盟ニュースの蔭であまり大きく取り上げられることはなかったものの、意義は深かったと思われます。  | | ウォルフェンソン世銀総裁(左)がロップ首相を訪れスロヴェニアが債権国になったことを報告。東欧圏の経済をリードしてきたスロヴェニアの「市場経済移行」は終わった(首相HPより 提供:ス共和国政府広報局) |
この会合でスロヴェニアの地位が少なくとも世銀内部では債務国から債権国に替わったのです。東欧諸国の中で初めてのケースで、南東欧研究センター(CSEES)のアナリストは「市場経済移行の終了を象徴する出来事」であり、スロヴェニア独自の移行戦略の勝利であると評価しています。
東欧諸国の経済を事実上指導監督する立場にある世銀、国際通貨基金(IMF)の基本方針は「小さな政府で緊縮財政、国営セクターの積極的民営化」です(各国政治家・経済学者からは異論も上がっています)。両機関は「スロヴェニアの民営化は遅すぎる」と評価し、90年代後半に入ってもリュブリャーナ側当局と方針対立を続けていました。しかしそれは第49回配信でも触れているように、国内経済が先進国の経済植民地にならないよう独自のテンポで民営化を進める戦略的な配慮でした。作戦参謀の一人、メンツィンガー元副首相は「東欧・ソ連圏のどの国でも民営化はマフィアの介入など経済犯罪の温床となった。もともと犯罪率の少なかったスロヴェニアをそんな国にしたくなかった。このため民営化には様々な方法が採用された。(もっぱら評判の悪い『古風な』)従業員持ち株制で民営化した会社さえ、全体数は少ないが概ねすぐれた業績を上げている」と独自戦略を説明します。もっとも01〜02年からは大型民営化・直接外国投資が本格化。銀行ではスロヴェニア信託銀行を仏ソシエテ・ジェネラルが買収、携帯電話網SIモービルはオーストリア・モビルコムが、ウニオンビールはベルギーのインテルブルーが筆頭株主になるなど、「民営化の遅れ」は過去の話になりつつあります。
かつての路線対立を乗り越え、スロヴェニアは今やウォルフェンソン総裁から「EUと、将来EU加盟を目指す南東欧各国のつなぎ役として、直接援助のみならずノウハウを伝えるなどの役割を期待したい」と言われるまでになりました。ムラモル蔵相も「世銀で債権国ステータスを得たことで国際的なイメージがさらに上昇するだろうし、実際に債権国として国際経済の場での発言力も高まっていくだろう。この大きな責任を引き受けていく覚悟だ」とし、エチオピア、ガイアナ、ナイジェリア、ケニアへの既存債権の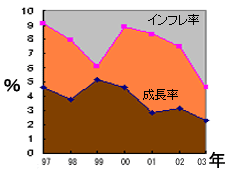 | | 過去7年間のインフレ年率とGDP成長率。成長率が少し頭打ちなのが気になるが、インフレは今後も3%台の低水準に抑えるのが政府目標だ(ス共和国統計局の発表を基に筆者作成) |
見直しも検討していることを示唆しました。
一国の経済力を示す重要な指標の一つである一人当たり国内総生産(GDP)は昨年12154ユーロ(政府発表。一般的にはドルで13714ドルと表示するのが常識ですが、最近のドル相場が不安定なのは皆さんもご存知の通りです)、EU既加盟国ギリシア、ポルトガルと同水準以上です。筆者の住むセルビアを初めとする南東欧から見れば羨ましい限りですが、かと言ってスロヴェニア経済は順風満帆というわけではありません。国内総生産(GDP)の成長率は昨年2・3%と過去10年で最低の伸びにとどまり、政府目標の3・7%を大幅に下回りました。2年間減り続けていた貿易赤字は再び増大しています。
今回の新規EU加盟国はすぐにEU統一通貨ユーロを使い始めるわけではありません。スロヴェニアの通貨トラールもまだ3〜6年ほどは生き残ることになりそうです。EUに加盟した国は自動的に経済通貨同盟(EMU)に参加したことになりますが、ユーロを導入するためには、その国の財政が健全で、導入前の自国通貨が十分に安定している(専門用語で言えば経済状況が「収斂している」)とみなされるための諸基準をクリアしなければなりません。これには財政基準、金利基準、為替基準などが定められていますが、このうち財政基準を例にとると、
(1)財政赤字が国民総生産(GNP)の3%以内であること
(2)公的債務残高がGNPの60%以下であること
とされています。新規加盟国のうちキプロス、マルタを除く8カ国でこれを比較してみましょう。ハンガリー、ポーランド、チェコ、スロヴァキアの人口上位四カ国は主に(1)が引っかかり、早くても基準達成は09年になる見通しです。各条件を現在ほぼ満たしているのはラトヴィアだけ、財政が黒字なのはエストニアだけで、バルト三国とスロヴェニア、つまり人口の小さい四カ国が上記四カ国をリードしている状態です。マクロ経済のある文脈においては「小さいことは有利」を証明する形になっています。後者四カ国に関しては07年には基準達成、欧州中銀などの青信号が出るのを待ってユーロ導入が実現可能と考えられています。
スロヴェニアの場合、ネックになっているのは上に書かれていないインフレ率の高さです。  | | ユーロ導入にはまだ課題を残す。あと数年はスロヴェニアの通貨トラールが使われ続けることに |
01〜02年と7%台だったインフレ率は昨年約4・6%。政府は将来ユーロ導入への最大の課題としてインフレ抑制を掲げています。これは東欧各国経済政策の最大の難関ですが、一方で筆者の住むセルビア=モンテネグロのように慢性インフレが当然だった国でも年率ひと桁が絵空事ではなくなっている現在、スロヴェニアの5%インフレは少し不思議な気もします。イラク情勢などの影響で不安定な原油価格も影響していますが、ス政府は国内でも努力できるところは努力して行きたいとしています。既に昨年ス中銀は公定歩合を225基本ポイント引き下げ。今後は電信郵便、放送、電力など競争の少ないセクターでの価格統制を強める他、外資系民営セクターが中心の部門でも政労使協調で給与アップの抑制を図る方針です。無論、ある程度のインフレは通貨切り下げの方向に働いて輸出を促進する要素となり得ます。実際02年にトラールは対ユーロで事実上4%切り下げられていますし、輸出を伸ばさなければ貿易赤字は縮小できないことは自明です。しかし、政府はインフレ抑制策を優先させるならば、今後は輸出業界を中心とするトラール切り下げ圧力により厳しい態度を示していかなければならないでしょう。不安を助長せずに「インフレ率今年3・2%、来年にはユーロ導入水準の3%以下」(ガスパリ中銀総裁)へと軟着陸できるか、蔵相から首相の座に就いたロップ政権の手腕が問われることになります。
◆
スロヴェニアのEU加盟が旧ユーゴとの関係に変化をもたらすのかどうか。眼を東に転じてみましょう。
加盟国内での物品、サービス、労働力が自由に移動できるのが、EUが「一つの国」であることの前提です。しかし労働市場を一気に自由化してしまうと、経済的に劣る新規加盟国から現加盟国に出稼ぎ労働者が大量流入することになり(ポーランドの失業率は20%、スロヴァキアは10%)、ただでも不況と失業問題に悩む先進国には頭痛の種になってしまいます。このため各先進国は新規加盟国からの労働者流入を許可制などで制限する時限措置を取ることに、 | | 隣国クロアチアとの対立が国際調停に持ち込まれる見通しのピラン湾 (ピラン市中心部、撮影・版権:Dragan Arrigler & Kodia Photo 提供:ス共和国政府広報局) |
また新規加盟国どうしでは5月1日以降労働市場が自由化されることになりました。
しかしスロヴェニアの場合は旧ユーゴの最先進地域として、むしろ出稼ぎを出すよりも受け入れていた国で
す。昨年時点でボスニアから約19000人、クロアチアから約7000人、セルビア=モンテネグロから約6500人などの季節労働者がスロヴェニアに
働きに来ており、EU新規加盟国からの流入は577人に過ぎません。これらは大半が土木、建築業で、スロヴェニア国内の失業者が「魅力を感じない」(ス商工会議所ゲルジニッチ建築局長)肉体労働、重労働です。
スロヴェニアとしては新規加盟国からの労働力流入を認めざるを得ない分、旧ユーゴ諸国などEU非加盟国への今年分の労働許可発行数を、昨年実績の半数以下に過ぎない17100人分と定めなければなりませんでした。このためクロアチア人出稼ぎ7000人の職場は大半が「ポーランド人などに取られてしまう」とクロアチアの日刊ヴェチェルニ・リスト紙は指摘しています(4月5日付)。
しかしクロアチアとの二国間にはさらに深刻な諸問題が存在します。その最大の一つがピラン湾問題です。
地図をご覧になればお分かりのように、山国スロヴェニアにも47キロだけ海岸線があり、観光地ポル
トロージュ、ピランや商港コペルなどの町が海沿いに並んでいます。しかし国際法の通常の解釈では、スロヴェニアの領海はその外側でクロアチア、イタリア両国の領海に「塞がれる」形になり、スロヴェニアは領海から直接公海にアクセスが出来ないような線引きになってしまいます。イタリアは旧ユーゴ時代から現行の領海・公海線でやっていたわけですから問題の対象とはなり得ません。スロヴェニア、クロアチア両国の二国間協定で解決すべき問題として独立直後から懸案になっていました。
2001年、ドゥルノウシェク[ス]・ラーチャン[ク]両国首相(当時)は(1)ピラン湾の8割をスロヴェ
ニア領とする(2)クロアチアとイタリアの海の国境は失われない(3)公海にアクセスするための幅7キロのスロヴェニア領海を確保する、で合意しましたが、議会の反対もあり仮調印より先に話が進みません。
逆にクロアチアは昨年になってこの譲歩を撤回、スロヴェニアの公海アクセスを白紙に戻す新案を発表し、
一度は進展したかに見えたピラン湾問題は再び元の地点にほぼ逆戻りしてしまいました。
 | | スロヴェニア資本のメルカトル・ベオグラード支店は02年暮れオープン。セルビアで最初の本格的ハイパーマーケットだ(画像提供:吉田正則氏) |
去る4月9日、ルペル[ス]、ジュジュル[ク]両外相がリュブリャーナで再度会談しましたが、結局二国間で
は結論は出せず、年末までに国際調停へ動き出すことで合意したにとどまりました。独立紛争から13年、
スロヴェニアがEUに加盟してもまだ旧ユーゴからの(やや強引な)独立が微妙な影を落としているわけです。しかし以前のような相互嫌がらせのムードは消え、「これからも地域の安定のために両国の協力は続く。クロアチアのEU加盟へスロヴェニアとしても努力したい」(ルペル・ス外相)、「友好国どうしの二国間問題はいつか解決できる。スロヴェニアのNATO・EU加盟を祝いたい」(ジュジュル・ク外相)とE
U加盟国、次期加盟候補国らしい優等生発言が続きました。
EU加盟によりスロヴェニアがマケドニア、ボスニアなどと結んでいた関税特恵措置が廃止になります。この結果旧ユーゴ各国でのスロヴェニア製品が値上がりすることになりますから、同地域への輸出は若干のマイナスを蒙ることが予測されています。しかしスロヴェニアの輸出全体に占める旧ユーゴ4カ国のシェアは17・8%で、EU(旧来加盟15カ国)相手の59・4%に較べれば大けがにはならないでしょう。いやむしろ、筆者の住むセルビアで見ている限りスロヴェニア製品への需要は、今後多少の値上がりがあっても減ることがないようにさえ思えます。
既に第74回配信でも触れているベオグラード最初の本格的ハイパーマーケット、メルカトルはスロヴェニアを代表するスーパーチェーンです。一昨年暮れに総投資額4300万ユーロをかけて敷地総面積52000平米のハイパーがオープンした当時は、セルビアの未だに低い購買力や旧紛争相手国への心理的要因など、成功に対する懐疑論もありました。しかし開店当初の大混雑の時期を過ぎてもメルカトル人気は衰えず、昨年ベオグラード店の総売上高は6000万ユーロ、今年1月の売り上げは一昨年同月比50%増を記録しました。クラフチュク社長は「今後5年でセルビア市場に2億ユーロを投資、ノヴィサド、スボティッツァ、クラグイェヴァッツ、ニシュなど主要都市にも店舗を拡大したい」と強気です。
旧ユーゴ圏の他の国に対して今回のEU東方拡大とスロヴェニアの加盟はどんな影響を及ぼすのか。  | | テオカレヴィッチBeCEI所長「スロヴェニアのEU加盟は他の旧ユーゴ諸国にも長期的には利となる」 |
なかんずく、同じバルカンのブルガリア、ルーマニアに加盟レースで後塵を拝しているセルビア=モンテネグロについて、セルビアのシンクタンク、ベオグラード欧州統合センター(BeCEI)のテオカレヴィッチ所長に聞いてみました。
「短・中期的にはセルビアにとって望ましくない影響が考えられる。(1)EUからの経済援助は、既に加
盟候補国となったブルガリア、ルーマニアに対して増加し、他国には頭打ちか縮小されることは明らかだ。
このためセルビアとこのバルカン2カ国との経済格差も拡大してしまう可能性がある。(2)セルビアのE
U向け輸出は農産品、原料が主だが、旧来加盟国に対し新規加盟国がこれらの(EU域内)輸出を拡大しこそすれ縮小はしない。セルビアのEU関税特恵措置は続くが、対EU輸出が伸びる要因はない。
しかしスロヴェニアの正式加盟は旧ユーゴの加盟であることは事実なのだから、我々の成功だと評価してもいいのではないかと私は思う。ブルガリア、ルーマニアも含めNATOとEU国境がどんどんセルビアに迫ってくることになるわけで、これは長期的には地域の政治上、安全保障上の安定につながると確信している。無論セルビア(=モンテネグロ)の加盟が近づくと、社会主義旧体制の企業が競争で潰れるなどEU加盟懐疑論が出てくる素地はあるが、今は未分化のセルビア内政が『親EU派』『反EU派』に再編されるだろうし、それらはセルビア(=モンテネグロ)の加盟前進へのプラス要因になるだろう」。
◆
スロヴェニアには非スロヴェニア人が少ない、というのは事実です。そしてそれが91年の独立紛争を短期で終わらせることが出来た原因の一つであるということもほぼ間違いなく言えると思います。しかしサッカーの国家代表にはスロヴェニア人がむしろ少ないことも触れましたし(第56回配信参照。このHPではナニナニ人という場合は国籍に関係なく民族出自を示しています)、ボスニア人、セルビア人など無視できない数の旧ユーゴ諸国系住民が住んでいることも確かです。一方、スロヴェニアの右派や極右は独立当初から存在し、ここに来て特別に伸長も衰退もしていません。しかし内政面で最近、排他主義を右派野党が声高に要求
する傾向が表面化しています。注目を集めたのは定住権剥奪問題とモスク建設反対運動でした。
独立直後の92年2月、スロヴェニア政府は旧ユーゴ諸国出自の住民約12000人が持っていた、国籍に準ずる常時滞在(定住)権を剥奪しました。確かに旧ユーゴ連邦軍の元軍人でそのままスロヴェニアに残ったケースなどは「スパイ」「潜在敵」として睨まれるのは分かりますが、実際は老若男女、ボスニア人、マケドニア人もセルビア人、コソヴォのアルバニア人も関係なかったようです。旧ソ連解体後にバルト諸国で見られたロシア人いじめにも似た現象です。 | | 民主主義を望んでユーゴから独立したスロヴェニア。しかしEUの国となってもなお民主主義の質は問われ続ける(リュブリャーナ市中心部、画像提供:長束恭行氏) |
これを不当だとする係争が続いていましたが、昨年憲法裁はこれら住民に対する権利を戻すよう決定しました。この憲法裁決定を受けた議会は法律を制定し、12000人のうち4000人について定住権を戻すことが法的に可能になりました。既にこの時点で憲法裁決定は(8000人分?)骨抜きになっているわけですが、社民党(ヤンシャ元国防相)、新スロヴェニア・キリスト教人民党(バユク元首相)など野党右派・極右勢力はそれでも、4000もの「非スロヴェニア人住民が増えるのはケシカラン話だ」とし、この法律を認めるべきかどうか国民投票に掛けるべく運動を開始しました。憲法裁が一度決定し、法律も議会を通過している以上あまり意味はありませんが、憲法裁は「投票の結果が如何なる拘束力も持たないならば、国民投票の実施自体は違憲ではない」と判断しました。こうしてまったく無意味な国民投票が4月4日に行われ、投票率はわずか31・4%、「権利復帰に反対」票がその95%を占めました。31%の低い投票率をスロヴェニア中道以左の良識と見るべきか、有権者の約30%が右派とともに外国人排斥に賛成していることを憂慮すべきか、ウォッチャーの意見は分かれています。
同様に右派はリュブリャーナ市内に建設が予定されていたモスクの建設反対運動を進め、これも5月に国民投票に付そうとしましたが、こちらは憲法裁が却下しました。スロヴェニア国内のイスラム教徒は推定5万。リュブリャーナは現在の欧州各国の首都では珍しくモスクが皆無の町で、主にボスニア人、一部アルバニア人が中心になって30年来建設要請が続いていました。右派が首都市内で建設反対、国民投票実施への署名を集めれば、ボスニア人住民らが中心となってデモを組織するなど反=反対運動も盛り上がりました。
これら二つの「運動」で、右派としては投票と自らの主張が通るかどうかよりも、秋に予定されている議会選に向けて支持率を探り、あわよくば与党連合の分裂を狙いつつ存在を誇示することが重要でした。
思惑通りと言うべきか、与党連合内のス国民党は、政府主流派の意向に逆らい定住権の国民投票支持に回りました。
これがきっかけとなってロップ政権から同党三閣僚が離脱、4月20日に小改造された内閣が再発足しましたが、今度は新閣僚がルペル外相の降板を要求して閣内で対立。秋に予定されている総選挙まであと半年足らず、現在の中道・中道左派大連合政権内に少し不協和音が聞こえています。
憲法裁の却下決定が出た直後の日刊デーロ紙論説(4月16日付)は、「モスクはいつかここに建つだろ
う。ただ信教の自由と、建設反対の自由のどちらを優先させるべきかというのは確かに難しい問題だ。投票が実現してなおかつモスク建設賛成票が上回れば理想だったかも知れないが、そうなったところで法治国家らしいとは言い切れまい」とコメントしています。またセルビアの週刊ヴレーメ誌に定住権問題の動きをレポートしたヴァソヴィッチ=メキナ記者は「EU加盟を控えた国としては評判を大きく落とす危険な出来事」(4月7日号)と評価。こうした良識派言論が今のところは多数なのが救いです。
後に初代大統領となるクーチャン議長率いるスロヴェニア社会主義共和国共産主義者同盟が、ユーゴ連邦からの離脱路線をはっきり打ち出した89年の党大会のスローガンは、「今こそヨーロッパ(Evropa, zdaj)」
でした。我々が指向するのは市場経済と民主主義の欧州(西欧)であって、非民主社会主義のベオグラード=セルビア=ユーゴ連邦ではない、というのがそこに込められたメッセージだったはずです。それから十数年、対外的には旧ユーゴ諸国の模範となり、東欧諸国を経済で大幅にリードしながら、今スロヴェニアは欧州=EUの一員となりました。しかしモスク建設問題など、国内でなおも民主主義の質が問われていることも確かです。いや、市場経済が限りなく発展への努力を続けなければならないものなのと同様に、民主主義とは常にそのあり方を問われ続けていくものなのでしょう。やはりこれはゴールではなくスタート、ですね。
(2004年5月上旬)
本稿の執筆に当たっては数多くの紙誌、インターネット資料を参考としました。煩雑さを避けるため、日付等の詳細を本文中に示すのは一部にとどめました。以下に参考紙誌及びサイト名(プレーグル関連の囲みを除く)を列挙します:[スロヴェニア]ス共和国政府広報局、ス共和国大蔵省、ス共和国憲法裁判所、24Ur.com、日刊デーロ、日刊リュブリャンスケ・ノヴィツェ、スロヴェニア通信スロヴェニア・ニュース、新リュブリャーナ銀行 [クロアチア]日刊ヴェチェルニ・リスト、日刊ヴィエスニク HThinet [セルビア]日刊ポリティカ、週刊ヴレーメ、ベオグラード欧州統合センター [旧ユーゴ圏以外]日本国外務省、EU、BBC、IWPR、CSEES、Seeurope、Yahoo!ニュース
画像を提供して頂いた下記各位に謝意を表します:スロヴェニア共和国政府広報局 吉田正則氏 長束恭行氏 画像・本文とも無断転載はかたくお断りいたします。
Zahvaljujem se za sodelovanje: Urad Vlade RS za informiranje, g.M Yoshida, g. Y Nagatsuka. Prepovedna je vsaka uporaba slik in teksta brez dovoljenja.
|

