審美歯科の基礎
歯科における色彩
白い歯とは
単純に「白い歯」とはいえ、様々な白さがあります。少し黄ばみがあるとか、やや茶色っぽいとかいった色相の違いがあります。さらにその鮮やかさ、明るさ、透明感など様々な要素により、歯の色は特徴付けられています。歯ははえている位置により色が違います。1本のはでも先端と中央と根本では色が違います。
色彩の基礎
色相(Hue)
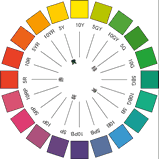 Wikipediaより
Wikipediaより
色相と「赤」「青」「黄」といった色を表します。1927年アメリカの画家マンセル(munsell)が考案した表色系が基礎となっています。
明度(Value)
視覚的な色の明るさ暗さを表します。反射率ゼロを理想の黒、反射率100%を理想の白としてこの黒を明度0、白を明度10とします。白黒でいえば黒から灰色を経て白まで明度は上がっていきます。種々の色にも明度の違いがあります。たとえば「春は曙」の空、東の空は明度の低い紫色をしています。日の出が近づくにつれて、明度の高い紫色へと変わっていきます。
彩度(Chroma)
彩度は色のあざやかさを示す尺度です。色の濃さと大体同じと考えられています。リンゴの赤とスイカの実の赤を比べると、リンゴのほうがにぶい赤で、スイカの方があざやかな赤色をしています。
歯における色彩
歯における明度の差
明度の差の具体例をお見せします。この写真は中央の原画を画像処理ソフトを使用して歯の部分のみ明度を変えてみました。明度が高くなると歯はより白く輝いて見えます。一方明度を下げると暗く見えるのが分かります。

歯における彩度の差
彩度のさの具体例をお見せします。彩度が高くなると歯の色が濃くなった感じに。低くなると薄くなった感じになります。

色の3要素以外の色彩要素
歯の色彩は、実際に、この3要素だけで決まるほど単純ではありません。他に大切な要素として歯の透明感、光沢によって見え方は違ってきます。また歯の解剖学的構造からすると内部は象牙質というやや不透明な層があり、表面はエナメル質という透明感の強い層で覆われているため、その厚みによっても見え方は違ってきます。
歯の色に影響を与える要因
年齢的変化
一般的には年をとるにつれて明度は低下し、彩度が上がりります。これは加齢による歯の質的変化、歯磨きによる表面の性状の変化、各種金属イオンの沈着などによるものです。

歯種と歯の色
歯の色は全ての歯で同じ色をしているわけではありません
一般的なパターンとしては中切歯、側切歯、犬歯の順に明度が下がり、彩度が上がっていくパターンが多いようです。高齢になるほどこの違いは顕著となっていきます。
セラミックスなどで前歯を治療する場合、全ての歯を同じ色調で作ってしまうと、不自然なかんじになってしまう場合があります。