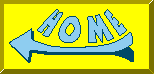虫歯発生メカニズムから考える予防方法
虫歯予防のために「歯みがきをすること」「甘いものを食べ過ぎないこと」はよく知られていることです。しかし実際にはいくら歯みがきをしている人でも、甘いものを控えたつもりでいる人でも、虫歯に悩まされる人は多くいます。そういった方のために虫歯発生のメカニズムから予防方法を考えてみましょう。 虫歯とは
歯垢細菌の特徴
酸と歯の戦い
齲蝕発生のメカニズムから考える予防方法
虫歯とは
歯垢細菌の特徴
酸と歯の戦い
齲蝕発生のメカニズムから考える予防方法
虫歯とは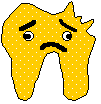
石灰岩を塩酸に浸けると泡が出て溶けることはご存知のことかと思います。虫歯も同様で歯というカルシウムを主体にした結晶が歯の表面の細菌(歯垢細菌)が作り出す酸により溶けていく現象です。

歯垢細菌の特徴
- 歯の表面に定着するための糊(菌体外多糖)を合成できる。この様な細菌が一旦定着すると糊を作れない他の細菌もその集団のなかで一緒に増えいく。
- このような細菌のかたまりは、うがいで流し落とすことはできない。歯ブラシなどで機械的に落とすしかない。
- 通常の歯みがきでは歯の表面の細菌をゼロにすることはできない(104-6個/mm2は残る)ましてや毛先の届きにくいところにはもっと多くの細菌が残る。
- 歯垢細菌は、5%程度の砂糖液(通常、清涼飲料は10%以上の糖液)を口に含むと2-3分以内に酸をつくりだし、歯垢pは歯を溶かすpH5.5以下となり、その状態は20分近く続く。

酸と歯の戦い
- 食事をしてもアメを1個食べても、清涼飲料を1口飲んでも歯垢pHは5.5以下となり、歯のカルシウム分は少量ずつぬけます。(図1)
図1
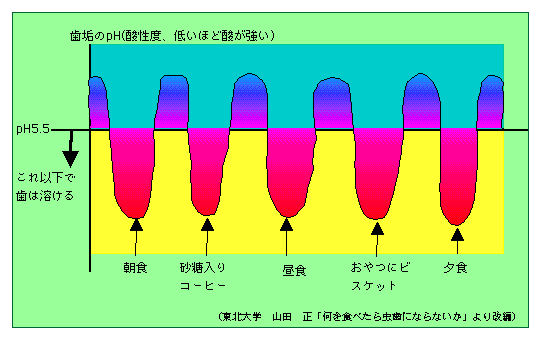
- しかし唾液の力でこの酸は中和され、1度溶けだして歯垢の中に残っていたリン酸とカルシウムはまた歯の中にしみこんで歯の結晶は修復されます(再石灰化といわれる現象)。
- 1日3度の食事と1-2回の間食程度では虫歯は簡単にはできません。
- この酸性の状態はうがいをしても歯みがきをしても、ほとんど戻すことはできません。
 1日に何個となくアメをなめたり、砂糖入りコーヒーを何度も飲んだりしていると、歯から流れ出すカルシウムの量が、再石灰化の量を上回ってしまい虫歯ができてしまうのです。
1日に何個となくアメをなめたり、砂糖入りコーヒーを何度も飲んだりしていると、歯から流れ出すカルシウムの量が、再石灰化の量を上回ってしまい虫歯ができてしまうのです。

 齲蝕発生のメカニズムから考える予防方法
齲蝕発生のメカニズムから考える予防方法
- 1日にとる砂糖の量ではなく回数を制限する。
- アメやガムを頻繁に食べたり、ジュースを何回にもわけて少しずつ飲んだりしない。
- 甘いものを食べたり、ジュースを飲むときはできるだけ1度に食べたり飲んだりする。
- どうしてもアメやガムをやめられない人はシュガーレスのものを選ぶ。
- 甘いものを食べるたびに歯みがきをしても予防の効果はあまりないので、歯みがきの効果を過信しない。
- もちろん酸を作り出す細菌の絶対量を減らすため歯みがきをする。
- フッ素などにより酸に溶けにくい歯を作る。

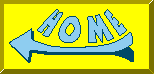
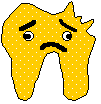
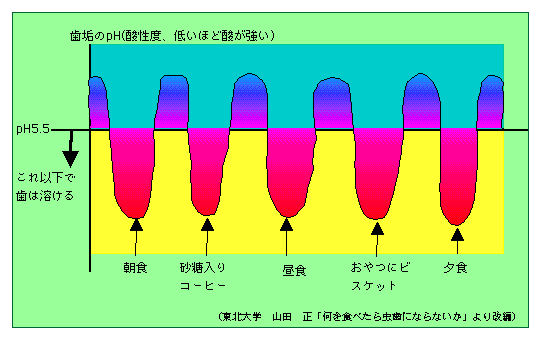
![]() 1日に何個となくアメをなめたり、砂糖入りコーヒーを何度も飲んだりしていると、歯から流れ出すカルシウムの量が、再石灰化の量を上回ってしまい虫歯ができてしまうのです。
1日に何個となくアメをなめたり、砂糖入りコーヒーを何度も飲んだりしていると、歯から流れ出すカルシウムの量が、再石灰化の量を上回ってしまい虫歯ができてしまうのです。