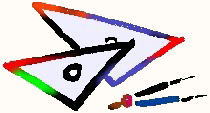
河川上流中流と海岸を回復させるための
新たな工事方法
2019年8月1日一部変更、2016年3月17日一部変更
2015年12月11日一部変更、2015年8月20日掲載
(イ)新しい工事方法の効果
河川の最上流部では斜面が崩壊した場所にも多くのダムが建設されています。
それらのダムでは、多くの土砂をその上流側に堆積させて土砂の流下を防いでいるように見えます。
しかし、それらの沢では、崩壊地点からダムまで或いはずっと下流まで、崩壊した土砂が剥き出しのまま続いていることも多いのです。
それらの谷間や斜面では草々や木々が生育するのは容易ではありません。
そのような沢では砂防堰堤を建設したために、かえって植物の生育を妨げていると考えられるのです。
それらの沢では、崩壊斜面や谷間が林や森に変わることが無く、崩壊地点の侵食と土砂の流失が止まることもありません。
河川の上流では、そのようなダムを幾つも連続させた小さな沢を多く見ることが出来ます。
「植生の回復を早めるダム」は、このような治山、砂防ダムの欠陥を克服して、崩壊斜面を形成している沢への植生の回復を早めるものです。
「植生の回復を早めるダム」は、降雨の時にだけ水流が発生して、通常は水流が無い沢をその設置場所として考えています。
常に水流がある場所には必ずしも適した方法ではないと考えています。
上述した従来の治山、砂防ダムでは、降雨による水流が発生するたびに、ダムの上流側のほとんどの場所の表面土砂が移動するので植物の生育を妨げています。
「植生の回復を早めるダム」は、その欠点を無くしています。
(ロ)新しい工事方法の考え方法
崩壊斜面やその谷間に降雨があった時に、従来型の治山、砂防ダムでは、上流側の表面土砂のほとんどが水流によって移動してしまいます。
多い雨量の時も少ない雨量の時も、崩壊斜面のほとんどの場所の表面の土砂が、水平な高さを持つ下流端のダムに向かって移動してしまうので、
植物の小さな芽生えも直ぐに流されてしまいます。
少し成長したとしても規模の大きな降雨があれば、小さな植物は根こそぎ流されてしまいます。
新しい工事方法では、大量の降雨の時と少ない降雨の時とで、崩壊斜面を流れる水の流下位置を変えることによって、
小さな芽生え時の植物の生育期間を長くします。
少ない降雨時の少ない水量の時、水流はダム下流端より少し上流側の最もその高さが低い堰堤上部より下流に流れ落ちます。
多い降雨時の大量の水量の時には、最も低い堰堤上部だけでなく、堰堤下流端からも大量の水が流れ落ちます。
その時には、水流と共に流れる大量の土砂が堰堤下流端の上流側に堆積します。
これらの事により、崩壊斜面下流端にあるダムのすぐ上流側には、少量の降雨の時には水流に晒されることのない土砂が堆積して、
その表面では植物が生育し易くなります。
雨が多い日本では様々な降雨の機会がありますが、ほとんどの機会でその時間当たりの降雨量は多くはありません。
ですから、崩壊斜面の下流端にあるダムの上流側では植物の生育が始まり易くなります
。崩壊斜面下流端のダムのすぐ上流側から植物が成長を始めれば、やがて植物はその生育範囲を次第に広げていくことでしょう。
(ハ)「植生の回復を早める治山、砂防ダム」の特許
植生の回復を早める治山、砂防ダムの方法は、その名前を「植生の回復を早めるダム」として特許を取得しています。しかし、その特許内容は充分な内容ではありませんでした。
ですから、特許権を主張してその対価を要求すれば、その最適の方法が用いられることなく、従来の方法と同じような結果をもたらす可能性があります。
もしかすると、混乱が生じた結果として崩壊斜面を回復させる事業が遅れることも考えられます。
そのような状況は、河川や山地の治水状況の一日も早い回復を願っている私の望むものではありません。 したがって、「植生の回復を早めるダム」は私の特許権を保持したまま、無料で解放します。
(ニ)「植生の回復を早めるダム」の注意点
「植生の回復を早めるダム」の特許公報では、要点の説明が必ずしも明確ではありませんでした。以下に、それについて記述します。
(1)「植生の回復を早めるダム」の特許公報の【図1】
では崩壊斜面の片側のダム開始地点よりそのまま上流側に向かって、ダムが建設されていますが、必ずしも開始地点より直接上流側に向かう必要はありません。
開始地点より真っ直ぐ正面に向かいその後に上流側に向かっても構いません。
崩壊斜面の状況は様々ですから、それぞれの状況に応じて適切な選択をすれば良いと考えています。 その例として【図3】を示します。
肝心なことは、ダムの開始地点から、その相対する対岸の正面よりも上流側にダムの終端を設置することだと考えています。


(2)「植生の回復を早めるダム」の特許公報では、ダム上端の最もその高さを低くする箇所の位置と、その形状について曖昧な表現でした。
最もその高さが低くなる位置は、ダムの下流端よりも上流側にあれば良いのですが、その説明だけでは不十分でした。
その高さが最も低くなる場所は、ダムの下流端より上流側にあるほどダムの効果が大きいと考えられますが、
あまりに上流側に近づけば、岸辺を侵食する可能性が生じてしまいます。
どの位置が最も良いかは、建設する場所のそれぞれの状況に応じて決定します。
「植生の回復を早めるダム」の特許公報では、最も低くなる場所の形状について「徐々に低くする」以上の説明はありませんでした。
最も低くなる場所は、U字型或いはV字型の形状を考えていましたが、必ずしもその形状だけでなく、凹字型でも可能だと考えています。
ただし、全くの凹字型では水量の増減によって水流の位置が定まらなくなる事が予想されますので、
それを避けるため、凹字型の形状を小さくする、あるいは凹字型の内側を階段状にすることが好ましいと考えられます。
また、U字型、V字型、凹字型のそれぞれの場合で、その形状のそれぞれの位置をどの程度低くするかは、 予想される水量及びその形状により、それぞれの状況に応じて決定することになります。 ですから、U字型、V字型、凹字型の構造の全ての部分をダムの下流端の高さよりも低くする必要はありません。
(3)「植生の回復を早めるダム」の特許公報では全く触れられていませんが、建設するダムの全体の高さについても考慮する必要があります。
ダムの高さはなるべく低くしたほうが良いと思います。鉄筋コンクリート製のダムであれば、その寿命は50年位はあるでしょう。
それでもダムは何時かは崩壊します。おそらく、その時にはダムの周囲は森林や林になっている事でしょうが、高さが高いダムでは崩壊した時の影響を逃れる事は出来ません。
それが低いダムであれば、その影響も僅かで済みます。低いダムならその影響のほとんどは周囲の樹木やその他の植物が吸収してしまうのではないでしょうか。
なるべく低い高さのダムを建設して、その高さの不足分はダムの数によって補うべきでしょう。 低いダムが幾つかあり水流がジグザグに流れるようであれば、治水的効果も大きくなると考えられます。
(4)「植生の回復を早めるダム」では、ダム本体の下部に水抜き穴を設置することが必須だと考えています。
ダムの上流側に堆積した土砂の上に植物が生育するのです。樹木の根の深い場所に不必要に水分が多いようでは健全な樹木の生育はないと考えられます。
(5)「植生の回復を早めるダム」の特許公報では全く触れられていませんが、ダムには必ず外階段を設置して頂きたいと思います。 柵も無い只の石段だけの簡単な構造で良いと考えています。
河川の上流で見る治山、砂防ダムの多くでは、ダムの上流側への移動が極めて困難です。
ダムの外側に鉄製のハシゴが埋め込まれている事もありますが、それらはダム本体の寿命に至らない内に腐食してしまいます。
筆者はこれらの状況について、極めて残念に思っています。
つまり、従来の治山、砂防ダムでは、ダムの上流側への定期的な観察や維持管理がほとんどなされていなかったのだと考えられるのです。
ダム上流側への定期的な観察があれば、上流側の斜面やダム本体の経年変化も明らかになるので、ダムの効果も或いは欠点も知ることが出来ます。
それによって、上流側の改良や、他の場所での新たなダムへの工夫も可能になります。
公開特許公報の表示方法
取得した特許の詳細は以下に示す方法で公開特許公報をダウンロードしてご確認ください。
公開特許公報の表示方法
(1)独立行政法人 工業所有権情報・研修館のトップページを開いて下さい。
http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
(2)「特許情報プラットホーム」のページが表示されますから、 左上の「特許・実用新案」にポインターを移動させて「1.特許・実用新案番号照会」をクリックして下さい。
(3)「1.特許・実用新案番号照会」のページを開いたら、 文献番号の「種別」に「特許公報・公告特許公報(B)」を選択して、「番号」に 5524783 を入力して「照会」をクリックして下さい。
(4)「照会結果一覧」に 登録番号 特許5524783 が表示されますから、それをクリックして下さい。
(5)特許5524783号 が表示されますから、右上の「文献単位PDF表示」を選択してください。 新たな画面で表示された認証用番号を送信して、PDF画面を表示させてください。PDF画面から印刷が可能になります。