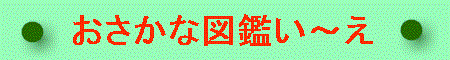 |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
・「あ」から始まる魚 ・「お」から始まる魚 ・「か」から始まる魚 ・「き〜こ」から始まる魚 ・さ行の魚
・た行の魚 ・な行の魚 ・は行の魚 ・「ま」から始まる魚 ・「み〜も」から始まる魚 ・やらわ行の魚
| 魚の名前 | 特徴 | 関連する仲間の魚 |
| イイダコ
|
(八腕目マダコ科) 内海の浅い砂地に住んでいて2枚貝を主食にしている。その為白い物(貝)に抱きつく性質があり、これを利用して小型のテンヤにラッキョウ、豚の白身、白い瀬戸物などをくくりつけて釣る。産卵期の2〜5月にメスがご飯粒のような卵を持つことが名前の由来になっている。おでんやサトイモと煮物、天ぷらにすると大変美味しい。 |
マダコ |
| イサキ
|
(スズキ目イサキ科) 水深20〜60mくらいの潮通しの良い岩礁帯を好み、大きな群れを作る。最大50cmくらいまで成長するが幼魚は黄色い縞がありウリンボと呼ばれる。5〜6月が旬と呼ばれ眞子や白子を持ち釣り易い季節と言われるが、個人的には冬から春にかけて腹にびっしりと脂を持った寒イサキのほうが味は上だと思っている。その方が産卵期の種の保存にも良いのではなかろうか?(眞子の煮付けや白子の塩焼きも捨てがたいが)刺身、塩焼きは言うに及ばずどんな料理も美味しい魚だ。我が家では干物の評価が大変高い。 |
|
| イシガレイ
|
(カレイ目カレイ科) 黒っぽい表側に石状の突起があるのが特徴で、名前のマガレイ由来にもなっている。昔は東京湾でもたくさん釣れたらしいが、最近ではほとんど見かけなくなった。マコガレイと同じような場所で釣れるが混じる程度である。マコガレイに比べて大きくなり最大50cm以上にも成長する。やや泥臭さが強いのが食味の特徴だが、これがハゼやカレイの好きな通人には堪えられないらしい。黒っぽい表皮に白い斑点があることも多く、特徴のひとつになっている。 |
マガレイ |
| イシガキダイ |
(スズキ目イシダイ科) イシダイとごく近い仲間で姿形、生態が非常に良く似ている。体の模様が異なっている他、イシダイよりやや温かい海を好むようで分布域が南に片寄っている。 |
|
| イシモチ
|
(スズキ目ニベ科) 東京湾で良く釣られるイシモチは正式には「シログチ」と言う名前である。仲間にはニベ、イシモチがいるがこの仲間には目の後ろの内耳に大きな石があることからイシモチ(石持)と呼ばれている。釣り上げるとグーグーと鳴くがこれは浮き袋を使って音を出している。40cmくらいまで大きくなり、砂泥地に群れで住んでいる。身は淡白な白身で、刺身よりは味噌を混ぜた粗いタタキにすると美味しい。煮るよりは塩焼きが良く、すり身にすると最高の食材に変身する。手を掛けて作ったさつま揚げやつみれ汁は歯ごたえ最高で、高級カマボコの材料でもあるイシモチを見直してしまうこと請け合いである。 |
|
| イシダイ
|
(スズキ目イシダイ科) イシダイは磯釣りの代表魚種でこれを専門に狙う人たちがいる。しかし、船釣では一部のマニアが専門に狙う以外は外道で釣れる程度で、それも2kg程度までの物がほとんどだ。荒い岩礁帯に住んでいるが船釣りの場合はマダイねらいのコマセ釣りやウィリーシャクリで釣れる事が多い。大型のイシダイはササエ、アワビ、イセエビ、ウニなど人間が食べたい物を好んで食べているが、小型のものはオキアミ、アミコマセなども良く食べる。小さくても身は良く締まっており刺身や塩焼きにするとすこぶる美味である。特に皮の湯引きは秀逸で滋味とコリコリ感が味わえる。 |
|
| イシナギ
|
(スズキ目ハタ科) イシナギは日本近海に生息するスズキ科の魚の中で一番大きく成長する魚である。全長2mに達するものも少なくない。普段は400〜500mの深海に生息しているが、産卵期の春から初夏には100m前語の浅場に寄ってくる。また左の写真のような幼魚は比較的浅いところで生活しているのでムツ釣りの外道として釣り上げられることも多い。白身の美味しい魚で、刺身、塩焼き、照り焼き、煮魚などが良いが、釣りたては身が硬く魚というよりは獣肉のような感じである。また、え卵巣や肝臓は有毒成分を含んでいるので、注意が必要である。 |
|
| イズハナダイ |
(スズキ目ハタ科) なかなかお目にかかれない珍しい魚。清水に遠征した時に釣れたのだが、名前が判らず調べるのに苦労した。中深場の岩礁帯に住んでいて30cm位まで大きくなる。 食べてみたがきれいな白身でなかなか美味しい魚であった。 |
|
| イタチウオ
|
(アシロ目アシロ科)
アカムツ釣りの外道で150mの底で釣れた。 最初はドンコ(チゴダラ)かと思ったが、良く見ると尾びれの形が違う。口の周りには3対のヒゲがあり、ドンコとの区別がついた。 捌いた感触と食べた感想はほとんどドンコとは区別が付きにくい。まだまだ研究の余地の多い底物の世界の様だ。 |
ドンコ |
| イトヒキハゼ
|
(スズキ目ハゼ科) 内湾の浅い砂泥底を好んで住む暖海性のハゼ。普通は10cm前後で体の割に口が大きいのが特徴。 |
マハゼ |
| イトベラ |
(スズキ目ベラ科) ベラ族の中でも比較的お目にかかることが少ない小型のベラである。カワハギ釣りなどの外道で登場する事があるが持ち帰る人はほとんどいない。食べるよりは水槽で飼って観察してみたいような魚だ。習性は他のベラの仲間達と同じである。 |
オハグロベラ |
| イナダ
|
(スズキ目アジ科) ご存知、代表的な出世魚である。関東ではモジャコ→ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ、関西ではモジャコ→ツバス→ハマチ→メジロ→ブリと名前が変わる。30〜50cm位のものをイナダ(ハマチ)と呼びイナダとワカシの中間の2〜3kgサイズをサンパクと呼んだりもする。釣り人は小振りなワラサだと喜ぶが、仲間や船頭は大きなイナダだとからかうのである。ワラサ、ブリ級だと結構脂の乗りが良く、人によってはしつこく感じるのだが、イナダは背側はサッパリ、腹側はコッテリと1匹で二通りの味が楽しめるのです。また、釣り方もカッタクリ、エサ釣り、ルアーとさまざまな楽しみ方ができ、程よく数が釣れるので人気の釣りものの一つである。 |
ワラサ |
| イネゴチ
|
(カサゴ目コチ科)
深めの場所(100m前後)の砂地に生息するコチの仲間。全身に黒い斑紋があるのが特徴で、マゴチに比べると顔が細長く口が突き出している。 |
マゴチ |
| イラ
|
(スズキ目ベラ科) ベラの仲間だが体高があり、側偏する体型である。背ビレから胸ビレにかけて幅広い暗色の帯が斜めに走るのが特徴である。20〜40cmの大きさで岩礁帯の回りの砂地を好んで住む。この魚はカワハギ釣りの外道で釣れたものであるが、かなり引きが強く、良型のカワハギかと期待させておいて水面でガッカリさせられる事が多い。食べては肉質が水っぽく美味しい魚とは言えない。 |
テンス |
| ウッカリカサゴ
|
(スズキ目メバル科カサゴ属)
色と言い、形と言いカサゴを大きくしたような魚で、名前の由来が「うっかりしてカサゴだと思い込んでいた。」と言うのだから呆れてしまう。カサゴよりも水深の深い100〜150mに棲んでいる事を除けば岩礁帯や砂礫帯を好むことや食性、捕食特性などもカサゴと同じである。カサゴは水深により体色が黒っぽい場合もあるが、この魚は深みにいるのできれいなオレンジががった赤である。狙って釣れる魚ではないが、釣れれば1kg以上なので釣った人は大喜びする。食べても締まった白身は大変美味しく、刺身、鍋物、煮ても焼いても楽しめる。 |
カサゴ |
| ウツボ |
(ウナギ目ウツボ科) カサゴ釣りの外道で掛かると「ギャー!」とか「ヒェー!」と喜ばれる事はない。それも凶暴そうな顔と噛み付かれたらひとたまりも無い鋭い歯のせいだが、実は襲い掛かってくるような獰猛な性格ではないらしい。しかし、釣り針に掛けられたような攻撃された時は別で執拗に噛み付こうと鎌首を擡げてくるので要注意だ。 |
|
| ウケクチメバル
|
(スズキ目メバル科メバル属)
別名パンダメバル。120〜200mくらいまでの中深場で外道で登場することが多い。エラ蓋に黒い模様があるのが特徴である。大きくても30cmくらいまでしか成長しない。深いところから上がってくるのでいつも目玉が飛び出してしまいごめんね。煮付けや塩焼きでいつも我が家の晩御飯に登場してくれる常連である。 |
カタボシアカメバル |
| ウスバハギ
|
(フグ目カワハギ科)
普通に釣れるカワハギの仲間では一番大きい種類。 しかし身は淡泊ながら味は悪くない。また平べったい割りに身が多く取れるので料理しがいのある魚だ。 |
ウマヅラハギ |
| ウスメバル
|
(スズキ目メバル科メバル属)
オキメバルとかアカメバルと呼ばれることも多い。30m位の浅場でクロメバルと一緒だったり、100mい上の深場でウケクチメバルと同居していたりする。メバル類の中では一番大きく成長し、50cm近くまで成長する。大きくなるにつれ深場に移動してゆくのかもしれない。また底や根の頂上付近に群れを作ることが多く、大型ほど群れの上にいることが多い。小型が掛かる用であればタナを少し上げるのもコツである。またハリ数の多い胴突仕掛を使うことが多いが、一度にたくさん掛けるように操作するのもポイントになる。クロメバルに比べるとやや身が水っぽいが、塩焼き、煮付け、空揚げなどで楽しめる。たくさんつれたときは是非干物を作ることをお勧めする。最高です! |
ウケクチメバル |
| ウマズラハギ
|
(フグ目カワハギ科) 外道王と呼んでもふさわしい外道中の外道だが、私はオカズとしてはとてもお世話になっており重宝している。引きも強く大型が掛かったときはドキッとさせられるが間抜けな馬づらを見た瞬間に力が抜けてしまう。普通の釣り人は扱いが雑になってしまうのだが、我々の仲間内では大型(45cm位まで大きくなる)はタモで掬って、すぐに締め肝を除き内臓を捨ててしまう。これをビニール袋に入れて大切にクーラーへ入れるのである。カワハギに比べれば身も肝もかなわないが、なかなか美味しい魚である。 |
ウスバハギ |
| ウミタナゴ
|
(スズキ目ウミタナゴ科)
磯の小物釣りでお馴染みの魚だがメバル・アイナメ釣りの外道で釣れる事がある。住んでいる環境によって体色が異なり、アカタナゴ、キンタナゴ、ギンタナゴなどと呼ばれる事もある。魚類では珍しく卵胎生で秋に交尾し翌年の春から初夏にかけて小魚を産み落とす。生まれる時に逆子で生まれる事から地方によっては妊婦に食べさせると縁起が悪いと嫌う事もある。肉質がやや水っぽいが塩焼きや煮付けにするとオカズになる。 |
|
| ウメイロ
|
(スズキ目フエダイ科)
熱帯亜熱帯に多く、伊豆諸島や小笠原諸島で良く獲れる。この魚は勝浦沖のイサキ釣りで混じったが、近年潮温の関係か姿を見る様になった様だ。 体色は暗い青で背から尾びれにかけて鮮やかな黄色。魚を取り込む時に良く目立ち、直ぐに判るほどである。 |
タカベ |
| ウルメイワシ
|
(ニシン目ニシン科) 目が脂瞼(透明な膜)に覆われていて、潤んでいるように見えることからこの名前が付いている。この魚は狙っては釣れません。巻き上げ途中や仕掛を入れるときなどに群れにあたると....。ずばり、刺身が美味しいです。おろした生姜との相性はバッチリ、時期にはマイワシを上回るかもしれません。 |
カタクチイワシ |
| ウロハゼ
|
(スズキ目ハゼ科)
マハゼより鱗が大きく色も黒っぽい。大きくなりマハゼの大型と間違えられる事があるようだ。 |
イトヒキハゼ |