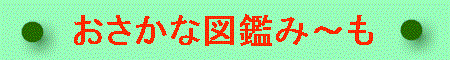 |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
・「あ」から始まる魚 ・「い〜え」から始まる魚 ・「お」から始まる魚 ・「か」から始まる魚 ・「き〜こ」から始まる魚
・さ行の魚 ・た行の魚 ・な行の魚 ・は行の魚 ・「ま」から始まる魚 ・やらわ行の魚
| 魚の名前 | 特徴 | 関連する仲間の魚 |
| ミシマオコゼ
|
(スズキ目ミシマオコゼ科)
アンコウのように上に向いて大きく開いた口、ブルドックのようなしゃくれた面相が特徴である。岸から少し離れた砂地に住み、日中は砂の中に体を潜らせ、口と目だけを出して通りかかる小魚などを待ち伏せにしている。狙って釣れる魚ではなく、まるかつも平塚からアマダイ釣りに行った時に一度だけ釣った事がある。千葉の漁師は「キハチワ」と呼ぶが、これは薪を八把燃やしても身が柔らかくならないくらい身が硬いという意味だ。しかし、洗いにしたり煮た物はシコシコして大変美味しい。オニカサゴやアカイサキなども同じ系統だが筋肉組織にそのような特徴があるのだろう。 |
|
| ミドリフサアンコウ |
(アンコウ目フサアンコウ科) これを釣り上げた時は本当にビックリした。 奇怪な姿かたちに似合わず食味は良く、他の赤い魚と一緒に水炊きにして頂いたがなかなか美味しい魚であった。 |
|
| ムシガレイ
|
(カレイ目カレイ科) 実はまるかつが大変気に入っている外道代表選手のひとつだ。理由はズバリ食味で、鱗を落としてから塩をまんべんなく摺込み、キッチンペーパーとラップに丁寧にくるんで冷蔵庫で二晩。これをグリルで焼いたり、フライパンでバター焼きにすると最高。オニカサゴやアマダイを狙って中深場を攻めた時に混じる程度なのだが、家族分釣れる訳ではない。従っていつもまるかつが独占して味わっている。水深100m前後の砂地に生息しており、虫類や甲殻類を捕食しているが身エサにも食ってくる。大きさは最大50cmにもなるらしい。 |
イシガレイ |
| ムツ
|
(スズキ目ムツ科) 水深100〜300mの深場の岩礁帯に生息する。肉食性で小魚や甲殻類を捕食する。目が大きく大きな口と鋭い歯が特徴だ。幼魚は浅い岩礁帯の藻場で成長し、次第に深場に落ちてゆくことが知られている。50cmくらいまで大きくなるが、同種のクロムツはより深い場所に住み、体色がより黒いことで区別がつく。アタリは大変強く、竿先をガクンガクンと揺さぶる。途中までは強い引きが続くが最後は浮き袋を出してしまうので引きも弱まり浮いてしまうこともある。白身で脂があり、刺身、特に煮付けが美味しい。」 |
アカムツ |
| ムラソイ
|
(スズキ目メバル科メバル属)
比較的最近、知名度が上がってきた魚である。カサゴと同じような体型で住んでいる場所も岩礁帯と同じである。食性や釣り方も共通点が多い。カサゴよりもずんぐりとしているので、同じサイズだと目方が重いかもしれない。以前はカサゴと混同されていたふしもあるが、最近ではルアーでも専門に狙うほど身近な存在になりつつある。身はきれいな白身で2日ほど冷蔵庫で寝かせてから刺身で食べると甘味があり、たいへん美味しい。また、この魚は皮が絶品で刺身にした時の皮を湯引きして細かく刻み、ワサビ醤油で食べると病み付きになること請け合いだ。 |
キツネメバル |
| ムロアジ
|
(スズキ目アジ科) マアジに比べてスマートな体型で尾びれが黄色味がかり、エラブタに黒い点があるのが特徴。マアジやマルアジに比べて側偏しておらず、細長く円筒形をしている。沖合いの中層を群れをなして行動しているが、ヒラマサ、カンパチなどの大型青物やモロコなどの泳がせ釣りで活き餌として使われる事が多い。人間が食べてもタタキなどにして美味であるが、伊豆諸島のクサヤの原材料としても有名である。 |
アカアジ |
| メイタガレイ
|
(カレイ目カレイ科) 身が厚く体高が高いひし形の体型をしている。また口は小さく両目が突き出しており目の間に硬い骨板が飛び出しているのが特徴である。沿岸のやや深い砂泥底に住んでいてイソメやゴカイなどの虫類やエビなどの底生小動物や貝類を捕食している。20cm位までの大きさがほとんどだが、30cm位まで大きくなるようだ。味は良く肉量も多いので評価は良い。 |
イシガレイ |
| メイチダイ
|
(スズキ目フエフキダイ科)
目を貫くような茶色の縞が特徴。 きれいな白身で大変美味しい魚、40cm位まで大きくなるがあまり市場には出回らない。 |
|
| メゴチ
|
(スズキ目ノドクサリ科)
シロギス釣りの外道でお馴染み。学術的にはネズミゴチやネズッポ、ノドクサリ等の名前で分類されたり呼ばれたりしている。しかし、釣り人には総称して「メゴチ」が一番通りが良い。体表はウロコが無く粘液で覆われており、後頭部に後ろ向きの一対の鋭い丈夫なトゲを持っているのが特徴。大きいものでも20〜25cmにしかならないが、天ぷらダネとしては極上である。我が家ではメゴチとシロギスの天ぷらを並べると、メゴチからなくなっていくくらいである。マゴチを狙って端物道具を下ろすときには釣れた小型のメゴチが格好のエサになることを覚えておくと良いだろう。 |
|
| メジマグロ
|
(スズキ目サバ科) ご存知、最高級マグロの「クロマグロ」の子供である。小さい物では1〜2kgのものから10kg以上の物までメジマグロと呼ばれ高級外道として人気がある。クロマグロは大きくなると200kgを超える大物だが、小さな物はカッタクリやオキアミのコマセ釣りで釣れる事がある。またキハダマグロの幼魚はキメジと呼ばれて区別されている。時期は秋から初冬だが大原辺りでヒラメ釣りのイワシ餌に大型が掛かり話題になる事も良くある。本マグロより脂が多くなく、あっさりした中にも旨みがあり美味しい魚だ。 |
キメジ |
| メジナ
|
(スズキ目メジナ科) 磯釣りのスーパースターだが、船のコマセ釣りなどで外道として登場することも多い。引きが大変強いのでイサキ釣りなどの細ハリスで掛かると何が釣れたのかとハラハラさせられる。沖で釣れた物は磯のものより磯臭さが少ないが、丁寧に血抜きすることが大切だ。そうすれば刺身(特に皮付き)が美味しく食べられる。また、中落ちで作る潮汁も絶品で細かいケシ粒にような脂が浮き、一杯呑んだ後などこたえられない。 |
|
| メダイ
|
(スズキ目イボダイ科) 目が大きいのが名前の由来であるが、干物でお馴染みのイボダイの仲間とは驚きである。どうりで味が良いわけだが大きなものほど味が良いと言われている。全長1m近くまで大きくなるが小型のものは青っぽい色、大型のものは赤っぽくなる。水深100〜300mの底近くにおりハリ掛かりしてからのファイトは強烈で水面まで猛烈に引きまくる。水圧変化にも強いのでタモに入れるまで気が抜けない。サメかと思って上げて来たら型の良いメダイだったなんて事が良くある。体表のヌルヌルがきついので、ヌメリとウロコを取ってビニールに包んでクーラーにしまえば他の魚やクーラーをヌルヌルにしてしまうことは無い。食べては刺身、焼き物、煮物、鍋、フライ何でも来いである。 |
|