
☆WIN98化に用意するもの
- マイクロドライブ1G内蔵(好みによりますが私の独断的にはこれがベストマッチ)内蔵の方法はこちらを参考にしてください。
- PC110で稼動するWIN95が入ったハードディスク(これのドライバを使います)
- ポートプリケータとFDD(FDDなしでマイクロドライブでDOSを立ち上がればいりません)
- LANカード等のカードドライバー
- WIN98のCD-ROMとSP1のCD-ROMもあると便利
☆WIN98をインストールします(合言葉は「気長に・・・・」)
-
マイクロドライブで起動できるようにbootフラッグを立てます。私の場合はDOS7のFDISKではうまく行かなかったので、DriveImage
Ver2を利用して、PCMCIAタイプⅢに入ってるwin95をMicroDriveにコピーし起動できるようにしました。
-
TP235のPIMCIAスロットルを使って、1のMicroDriveの全てのフォルダ・ファイルを削除し、①win98というファルダーを作り、ここにWIN98のCD-ROMをコピー②win98sp1というファルダーを作り、ここにWIN98サービスパック1のCD-ROMをコピー③DownLoadというフォルダを作り、ここに必要と思われるドライバーをコピー④PC110が動いてるハードディスクから「es488.vxd es488.drv essfm.drv」を抽出し、essというフォルダを作り、ここにコピーします。
-
他のPCで作ったWIN98の起動FDDで起動する。
-
C:\WIN98\SETUP /nm /is /id 」を実行する。/nmはコプロセッサーのチェックを外す、/isはスキャンディスクを外す(私の場合Dドライブ<4Mb内蔵フラッシュメモリーが異常と弾かれるので>) /idはHDの空き容量のチェックを外します。その他のセットアップのオプションはThinkPad徒然草が参考になります。
-
気が遠くなるほどの時間の後、インストールが順調にいけば数回の再起動の後win98が立ち上がります。特にシステムのチェックには時間が掛かりますし、フリーズすることもあります。
-
このままでは音がでないので、sairixさんの所から、「sairix製infファイル
for Windows98」をDownLoadし、実行します。ただし、win98のファイル名をwin98s等と変更しておかないとwin98CD-ROMのドライバーがインストールされてしまいます。ドライバーの先を聞かれたら、先ほど作った2-④のフォルダを指定します。
-
PCMCIAを使えるようにするには、私の場合は標準でインストールされた「PCICまたは互換PCMCIAコントローラ」で上下のスロットルが使用できましたが、win95のIBM
Smart PC Cardドライバをインストールしないとだめな場合が多いようです。このあたりはみみラボさんにお教えいただきました。
-
最後にサスベンドの時にまるでフリーズしたようになるので、「システムのデバイス」の「アドバンス パワー マネージメント サポート」を使用不可に変更します。
☆★☆★これでPC110でWIN98が起動するようになります。★☆★☆

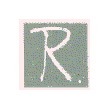
PC110withWin98の頁に戻る


