思いつきSSログ保管庫
*このページに直接来られた方へ、TOPページはこちらです。
雑記掲載SS保管庫 2008年第4期
10月26日〜 FORTUNE ARTERIAL sideshortstory「楽屋裏狂想曲〜鬼ごっこ〜」
12月30日 夜明け前より瑠璃色な SSS”手段と目的”
12月25日 originalshortstory 冬のないカレンダー #11
「ねぇねぇ、キミっておっぱい好きなの?」
12月22日 ミア・クレメンティス誕生日SSS「約束の証」
12月13日 originalshortstory 冬のないカレンダー #10
「毒食らえば皿までって、どこまでが毒なんだろう?」
12月8日 Canvas2 SSS”次元”
12月2日掲載 originalshortstory 冬のないカレンダー
Appendix Episode #9「・・・それはいろんな意味でまずいと思います」
11月30日 夜明け前より瑠璃色な SSS”二人の時間”
11月25日 originalshortstory 冬のないカレンダー #9
「目が点になるとは、こう言うときに言うんだな」
11月21日 桐葉誕生日SS FORTUNE ARTERIAL Another Short Story Re,
Appendix Episode「しあわせのかたち」
11月17日 originalshortstory 冬のないカレンダー #8
「百聞は一見に如かずって言うけど」
11月10日 originalshortstory 冬のないカレンダー #7
「勝者無き勝敗ってどういう意味?」
11月9日 夜明け前より瑠璃色なMoonlight CradleSSS”雨の天使”
11月3日 夜明け前より瑠璃色なMoonlight CradleSSS”背中”
10月31日 Canvas2 sideshortstory 「はろういんらぷそでぃ」
10月14日 Canvas SSS”雨の誕生日”
10月14日 FORTUNE ARTERIAL SSS”えりにゃたんじょう”
10月14日 FORTUNE ARTERIAL SSS”魔女の正装”
10月12日 夜明け前より瑠璃色なMoonlight CradleSSS”帰還”
10月7日 夜明け前より瑠璃色な sideShortstory「巫女麻衣前夜」
10月4日 陽菜誕生日SSS「特別な特別」
12月30日
・夜明け前より瑠璃色なMoonlight Cradle SSS 「手段と目的」
「ただいま」
俺は家に入ると真っ先に洗面所に向かった。
なんてことはない、ただ用を足すだけだ。
俺はドアを開ける。
「え?」
開けたドアの先には、制服姿の麻衣が座っていた。
「や、やだっ!」
その時水が流れるような音が聞こえ始めた。
「ご、ごめん!!」
俺は神速の速度で回れ右をし、そこから離脱し扉を閉める。
そのままの勢いでリビングへ行くと、ソファに思わず座り込んでしまった。
「・・・はぁ」
事故だとはいえ、まさかトイレの中で麻衣と出会ってしまうとは思っても
みなかった。
「怒ってるよなぁ」
そんなことは言うまでも無い事だろう。
・・・俺は覚悟を決めた。
パタン。
リビングの扉が開く音がした。
麻衣がリビングに入ってきた。
「麻衣、ごめん!」
俺は振り向くと麻衣と目を合わせるより先に頭を下げた。
「・・・」
無言の麻衣。気まずい雰囲気が流れる。
「あ、あれは事故だったんだから、お兄ちゃんもそんなに気にしないで」
そう言うと俺の横を通り過ぎていく麻衣。
「それでも俺が悪い、だからすまない、ごめんなさい」
「・・・」
「事故とはいえ、麻衣に恥ずかしい思いをさせたのは俺だ。
だから・・・」
「・・・お兄ちゃん、それじゃぁ私のお願い聞いてくれる?」
「お願い?」
「うん、私のお願いで今回のこと許してあげる」
「それで麻衣が許してくれるならいいさ」
その時麻衣の目が妖しく光った気がした。
その光に俺は一瞬たじろぐ。
「じゃぁね、お兄ちゃん。お兄ちゃんも出しているところ見せて」
「・・・え?」
「2度も言わせないで」
「えっと、でも・・・」
「・・・私、すっごく恥ずかしかったんだよ?」
「・・・わかった、麻衣がそれを望むなら俺も恥ずかしい思いをする」
「それじゃぁ、お兄ちゃん。ここじゃ濡れちゃうかもしれないから
お風呂場で待っててね、私着替えてくる」
その時の麻衣の微笑みは少女のものではなく、女の物だった・・・
12月25日
・originalshortstory 冬のないカレンダー #11
「ねぇねぇ、キミっておっぱい好きなの?」
「・・・」
まどろみから覚醒した俺は、悲鳴をあげそうになってそれを飲み込んだ。
その行為は相手の為ではなく、俺自身のプライドのためだった。
その相手というと・・・
「ん・・・」
俺に抱きついて眠ったまま、可愛い寝言をもらしていた。
「・・・だるい」
それに頭痛がする。
起きようにも身体の方は覚醒してないのか、動く気がしない。
まぁ、もっとも抱きつかれてるから自由に動かせないだけのような気も
しないでもないが。
俺はぼんやりしながら、昨夜何があったかを思い出しつつあった。
「乾杯!」
グラス同士が触れ合う乾いた音とともに、クリスマスパーティーが
開かれた。
俺の親父は単身赴任、アイツの所も相変わらず出張続き。
そんな家族ぐるみのつきあいがある俺達は、アイツの家でのクリスマス
パーティーに呼ばれたのだった。
俺はこう言うのに興味はあんまりは無い、けど。
「メリークリスマス、だよ♪」
アイツの楽しそうな笑顔がみれるなら悪くは無いな、と思う。
そんなアイツはオーソドックスなサンタクロースの格好に仮装していた。
ズボンじゃなくてミニスカートという辺りに、どうも誰かの策略を感じるが
似合ってるから気にしないでおこう。
「楽しいか?」
「うん、楽しいよ♪ 大好きなキミと大好きなお母さんと、大好きなおばさんと
みんな一緒なんだもん♪」
おじさんの名前が出てこない事に心の中で俺は涙する。
「ねぇ、楽しくないの? やっぱり迷惑だった?」
突然そんなことを聞いてくる。俺はそんな顔をしてたんだろうか?
「だいじょうぶよ、照れてるだけだから」
「おふくろ、余計なこと言うな!」
「余計なことって言うことは本心ね? 聞いた?」
「うん、聞いた聞いた。良かったわね」
「うん、ありがとう♪」
女三人よればかしましいとはよく言うが、本当だったんだな・・・
「ねぇねぇ、これ美味しいよ。食べてみて」
そう言うとアイツはチョコを俺の口に押しつけようとする。
「自分で食べれるって」
「あ、そっかぁ、口移しの方がいいのかな?」
「いえ、謹んで自分で食べさせていただきます」
思わずそれもいいかも、とか思ったりしたのは内緒だ。
二人だけならそうしても良いんだけど、今目の前に敵に回したくない人物が
二人もいる、その二人に格好の餌を与える訳にはいかない。
「はい、どうぞ♪」
俺の拒否にもめげずアイツはチョコを渡してくれた。
それを口の中に運ぶ。
かじった瞬間、中から甘くどろどろとした何かが喉に流れ込む。
「っ、これは・・・ボンボンか?」
あまりにきついその液体の、熱さに俺はシャンパンを口にした。
「これきついぞ?」
俺はアイツにそう訴えようとして・・・
「大丈夫だよ、美味しいよね♪」
平気でチョコレートボンボンを食べてるアイツの姿を見て
何も言う気が起きなかった。
思えばこのとき、俺も酔っていたのかもしれない。
「なんだか暑いね〜」
「そりゃそんな厚手の服を着てれば暑いだろうに」
「暑いよ〜」
そう言いながらアイツは上着のボタンを外す。
そこにはアイツの胸の谷間が・・・
俺は慌てて視線を逸らす、だが逸らした先に二人の悪魔が微笑んでいた。
「見ました? 奥さん」
「えぇ、見ましたとも、奥さん」
「・・・」
思わずツッコミをいれようとして、今の会話に何も間違いがないことに
気付く。二人とも結婚してるわけだし、だから俺達がいるわけだし・・・
「あの子ったらおっぱい好きだものね〜」
「待ておふくろ、あること無いこと言いふらすな」
「ねぇ、私の息子になったらおっぱいさわらしてあげようか?」
「おばさん、勘弁してください」
「んもぅ、照れ屋さんなんだから、それと私のことはお義母さんって呼んでって
いつも言ってるでしょう?」
「あー、だめだめ、貴女じゃ無理よ」
「ん? なんで?」
「あの子ったらテクニシャンなのよ? 私のおっぱい吸うときすごかったんだから」
「いつの話してるんだよ!!」
「そうね〜、まだ1歳になってなかったかしら?」
「・・・」
一気に脱力した。
「ねぇねぇ、キミっておっぱい好きなの?」
アイツが話に加わってきた。
「ねぇねぇ、私のおっぱい、見る?」
「ちょっと待て! 何故にそうなる?」
「だって、おばさん、気持ちよかったっていってるでしょ?
そんなの嫌だもん、私も気持ちよくなりたいもん」
すでに会話が成り立たなくなってきている、これはまずい傾向だ。
「なぁ、おふくろ。そろそろお開きにしないか?」
「そうね〜、お子さまはもう寝る時間よね〜」
「私たちは2次会始めるわ、もっと飲みましょう♪」
「おー」
「おー!」
・・・おふくろたちを無視して俺はアイツを部屋へと運ぶことにした。
「ほら、送っていくぞ」
「んにゃ〜、ありがとうなの〜」
肩に手を回し支えて立ち上がる。
「だめよね〜、そこでお姫様抱っこしないと」
「まったく、へたれよね〜」
「・・・」
二人を無視してアイツを部屋へと運ぶ。
「私たちは上には上がらないからごゆっくり〜」
「ちゃんと避妊はしてよね〜」
・・・もはや言い返す気力がなかった。
「ほら、ついたぞ」
ベットに座らせるとアイツはそのまま倒れ込む。
「ちゃんと着替えて寝るんだぞ?」
「んー、何処いくの?」
「おふくろの所だけど」
あのまま放っておくとどうなるかわからない、様子を見に行くつもり
だったのだが。
「やっぱりおばさんのおっぱいがいいの?」
「ちょっ、なに言ってるんだよ?」
「私のだって大きいんだよ?」
そう言って一気に上着のボタンを外し、がばっと前を開く。
そこにはブラに包まれた、大きなふくらみが・・・
「おい、風邪ひくからちゃんと着てろ」
「嫌、わたしのおっぱいが良いって言ってくれないと嫌」
「誰も嫌いだなんて言ってないだろう」
「本当?」
なんだか会話が恥ずかしい、だけど
「・・・俺が好きなのは・・・なんだから・・・さ」
俺も相当酔ってるようだ、こんな恥ずかしい事をいってしまうだなんて!
「えへへ〜、私も大好きだよ♪」
そう言って抱きついてくる。
俺はそっと抱きしめる。
むにゅ!
そんな音が聞こえた気がした。
アイツは上着の前をはだけたまま、俺に抱きついてきている。
当然俺の胸にアイツの胸が当たってるわけで。
視線を下ろすとアイツの嬉しそうな顔のしたに、つぶされてるけどそれでも
柔らかそうな大きな胸と、その谷間が見えていた。
「あー、私のおっぱい見てる♪、やっぱり私のが一番なんだね」
「・・・」
それを肯定するのはなんだか悔しかったから、黙秘することにした。
「黙っても無駄だよ♪、だってキミの気持ちつたわってきてるもん」
「・・・」
「ねぇ、良いんだよ?」
「いや、今日はやめておこう、下に厄介な人達がいるから」
「そんなの関係ないもん」
「・・・」
「んー、私悲鳴あげちゃうぞ?」
「なっ!」
突然そんなことを言い出すアイツ。
「襲ってくれないと襲われたって悲鳴あげちゃうぞ?」
「それ何かがおかしいから!」
酔った人ほど酔ってないっていう、そんなフレーズを思い出し
あぁ、これがそう言うことなのか、と冷めた部分で実感する。
「さぁ、どうする?」
「・・・」
俺は無言のままアイツを抱き寄せて、そっと頭を撫でる。
「んんっ・・・気持ちいい」
「少し落ち着けよ、俺は嫌だって言ってるわけじゃないんだからさ」
「・・・うん」
「こう言うのは雰囲気も大事だしさ、下にはおふくろ達もいるし」
「そっかぁ、しちゅえーしょんが大事なんだね」
「は?」
「うんうん、やっぱりサンタさんでするばあいはキミはトナカイさんの
仮装する必要あるんだね♪」
「・・・」
「あ、逆でもいいよ。これキミが着てくれれば私はトナカイさん」
そう言って上着とズボンを一気に脱ぎ捨てる。
ブラとお揃いのシンプルなショーツを穿いているアイツの姿に思わず
見とれる。
「だから脱ぐな!」
「・・・」
「ん? どうした?」
「・・・うにゅ〜」
奇妙な言葉を発したアイツはそのままベットの上に倒れ込んだ。
どうやら睡魔にまけたようだった。
「まったく・・・」
このままじゃ風邪をひく、せめて布団だけでもかけておかないと。
そっと布団を掛けようと近づいた瞬間、俺はアイツに抱き寄せられていた。
「んにゅ〜」
「おい、離せって。こら、やめろ!」
アイツは俺に抱きついて離れないどころか、脚を絡ませてきた。
「俺は抱き枕じゃないぞ」
そう言ってみたけど、アイツは起きる気配がない。
・・・さて、どうしたものか、考えようとしたけど、考えがまとまらない。
それどころかもうどうでも良いような気きもしてきた。
「ま、いっか」
そう結論ずけた俺は、そのまま闇へと落ちていった・・・
目が覚めても動けなかった俺達を起こしに来たおふくろ達に見つかり。
格好の餌を与えてしまったことは言うまでも無かった。
「うー、なんだか頭がずきずきするよ〜、私の頭ぶった?」
「んなわけあるか!」
俺は別な意味で頭が痛くなってきた。
12月22日
・夜明け前より瑠璃色な sideshortstory 「約束の証」
「さぁ、がんばらなくっちゃ!」
私はえいっと気合いを入れてキッチンの前に立ちます。
今日の夜、みなさんが私のために誕生パーティーを開いてくださいます。
そのみなさんをおもてなしするために・・・
それは私が地球に、達哉さんと一緒に住むようになって最初の冬でした。
「なぁ、ミア。もうすぐ誕生日なんだって?」
「え? もうそんな時期になってたんですね」
ホームスティではなく、朝霧家の一員として地球に住むようになってから
とても充実していて、時の流れを忘れるくらいでした。
「誕生日はいつなんだ?」
「えっと、月の暦になりますけど12月22日です」
「そっか、よかった。まだ間に合う」
「何が間に合うんですか?」
「準備だよ、ミアの誕生日を祝う準備」
誕生日をお祝いする準備・・・
「と、とんでもないです! 私はお世話になりっぱなしの身。
それなのにパーティーを開いてくださるなんて申し訳ないです」
姫様と一緒に地球に上ってきて、ホームスティが始まった最初の頃
歓迎会が開かれたことを思い出します。
あの時は姫様を歓迎されるパーティーだったので私も気兼ねなく参加
出来ましたけど、今回は私の為のパーティー、恐れ多いです。
「ミアらしいな」
達哉さんは優しい顔で微笑んでいます。
私は思わず見とれてしまいました。
「でもな、ミア。みんなの気持ちも考えないとな」
「みなさんの気持ち?」
「あぁ、ミアを祝ってあげたい気持ちを、ミアは受けてくれないのかい?」
私を祝ってくださる気持ち・・・
「ずるいです、そう言われると何も言えなくなっちゃいます」
「ごめんごめん、でも俺もミアを祝ってあげたいしさ」
「は、はい・・・ありがとうございます」
「よし、それじゃおやっさんに報告して段取りを・・・」
その時私は一つ思いつきました。
「あの、達哉さん!」
「ん?」
「あの・・・その、誕生会のお料理を私に作らせていただけませんか?」
「え?」
「駄目でしょうか?」
「いや、ミアは主役だろう? 祝われる側が誕生会の準備をするなんて・・・」
「達哉さん、私の誕生日プレゼントを思いついたんです」
「プレゼント?」
達哉さんの言葉を遮るように、私は達哉さんに伝えます。
「私は、みなさんにお料理を美味しいって言って食べて欲しいんです。
その時のみなさんの笑顔が大好きだから・・・だから、私がお料理を作るんです」
「ミア・・・」
「駄目、でしょうか?」
「・・・ミアの気持ちも考えないとな」
「達哉さん・・・」
「でも、俺も手伝うよ。ミアと一緒がいいからさ」
「はい!」
それから毎年この日は私のお料理でおもてなしをする日となりました。
「ミアちゃん、誕生日おめでとう!」
「ありがとうございます、みなさん!」
誕生会に集まっていただいたみなさんのお祝いの言葉でパーティーは
始まりました。
「たくさん作りましたので、みなさんいっぱい食べてくださいね」
「俺も運んできます」
「毎年そうだから当たり前のようになっちゃってるけど、やっぱり
お祝いするミアちゃんが料理してるのって違和感あるわよね」
「そうでもないぞ、菜月。俺はこの日が楽しみだからな」
「はいはい、達哉には聞いてないから」
「ふふっ、菜月ちゃん。焼かないの」
「さ、さやかさん!」
「お、今度は月の料理か」
「はい、マスター。どうぞ」
「ありがとう、ミアちゃん」
前もって月人居住区で買っておいた食材で月の料理も振る舞います。
「・・・仁もこれくらい出来るようになってくれれば安心なんだがな」
「何を言う、親父殿。僕はデザートでは誰にも負けないよ?」
「兄さん、それってデザート以外は負けてるって言ってるようなものでしょう」
「はははっ、そんな細かいことは気にしちゃいけないよ。
それに我が妹殿は最初からミアちゃんに追い抜かれてるではないか」
「い、いまは自炊してるから少しは追いついてると思う・・・んだけどなぁ」
「菜月さん、今度お料理を一緒に作りましょう!」
「うん。ミアちゃんよろしくね」
「ミアちゃん、我が妹につきあうと料理が真っ黒に・・・」
突然仁さんの動きが止まって、そのまま倒れてしまわれました。
「仁さん!」
「気にしないで良いわよ、ミアちゃん」
「そうだ、仁の事は放っておけ」
「はぁ・・・」
何かが後頭部に刺さってるような気がしますけど、だいじょうぶそうなので
みなさんの言われるとおりに放って置くことにしました。
「ミアちゃん、今左門さんの所でもお勉強してるんでしょう?」
「はい、イタリア料理は初めていただいた時から覚えたかったんです。
いつか姫様に私のイタリア料理を作ってあげるんです」
「そっか、頑張ってね」
「ありがとうございます、麻衣さん」
「そろそろだな、タツ。厨房からあれを持ってきてくれ」
「了解!」
みなさんが食事を終わられた頃、マスターが達哉さんに何かを頼みました。
「ミアちゃん、今年も美味しい料理をありがとうな」
「いえ、どういたしまして」
「でもな、俺も料理人だからな。これだけは譲れないんだよ」
「?」
「おやっさん、おまたせ」
「タツ、準備を頼む」
「はい!」
達哉さんは何か箱を持ってこられました。
それをテーブルの真ん中に置いて、ふたを開けます。
「あ・・・」
「マスター左門特性のバースディケーキだ。ミアちゃん、誕生日おめでとう」
「おめでとう、ミアちゃん!」
みなさんがお祝いの言葉をくださいます。
「あ、ありがとうございます!」
「あのぉ、後かたづけは・・・」
私は顔を上げて達哉さんを見上げます。
「みんながやってくれてるからミアは心配しないでいいんだよ」
パーティーの後、私と達哉さんはパーティー会場を追い出されました。
「みんな気を利かせすぎだよな、ミア」
「は、はい・・・」
「それより、俺と一緒にこうしているのは駄目かい?」
私は達哉さんの胸に背中を預けて座っています。
そんな私を達哉さんがそっと私を抱きしめてくださってます。
「駄目な訳ありません、むしろ嬉しいです」
「あ、あぁ・・・もうちょっと力いれるな」
「は、はい・・・」
達哉さんがそっと力を込めると、私は達哉さんに包まれていきます。
とても温かくとても幸せで・・・そしてとても切なくなります。
だって・・・
「た、達哉さん、その・・・向きを変えてもいいですか?」
このまま向きを変えると、達哉さんにいつもしてもらってる格好に
なってしまいます。ちょっと恥ずかしいですけど・・・
「その・・・達哉さんと、キス・・・したいです」
「・・・」
達哉さんは無言のまま私の向きを変えて抱き合う形にして、そして
「ん・・・」
ふれるだけの優しいキスをくださいました。
「誕生日おめでとう、生まれてきてくれてありがとう。
そして、俺の隣に居てくれて・・・ありがとう、ミア」
「達哉さん・・・ありがとうございます。私を選んでくれて・・・」
「ミア」
「達哉さん・・・」
・・・身体は満足感いっぱいで、とてもだるくて、眠りたいと言ってる、けど。
心はまだ眠りたくないと言ってる、そんな気怠い、でも心地よい気持ちの中。
私は左手の薬指にはめてもらった銀の指輪を目の前に持ってきます。
「ミア・・・その、な・・・」
「達哉さん?」
「お、俺にはまだこれしか買えなかったけど・・・」
そう言うと達哉さんは小さな小箱を取り出しました。
「その、はめてもらえる・・かな?」
「あ・・・」
「ミ、ミア?」
「ごめんなさい、達哉さん、とても嬉しくって・・・」
突然涙を流した私を見て慌ててしまった達哉さん。
いつもなら大丈夫って言えるのに、今は涙が止まりません。
「もらっても、良いんですよね?」
「当たり前だよ、ミアのためだけに買ったんだから」
「ありがとうございます、達哉さん」
私はそっと左手を出す。
「はめてもらっても、いいですか?」
私は左手の薬指にはめてもらった銀の指輪を見る。
その指輪の向こうには眠っている達哉さんの顔がある。
疲れて先にお休みになられてしまった達哉さん。
「達哉さん、愛しています」
私は達哉さんの唇に触れるだけのお休みのキスをして。
達哉さんに寄り添うと、心も満足したからだろうか、急激な眠気に
襲われる、でもそれは達哉さんが守ってくれる温かい闇。
「お休みなさい、達哉さん。ふつつか者ですがよろしくお願いします」
12月13日
・originalshortstory 冬のないカレンダー #10
「毒食らえば皿までって、どこまでが毒なんだろう?」
土曜の午後、本屋にでも行こうかと商店街を歩いてた俺は遥か前方に
おばさんの姿を見かけた。
その瞬間、俺の脚は目的地と違う方向へと進もうとする。
「あら〜、なんで急に道を曲がっちゃうのかしらね〜?」
「・・・」
結構距離が離れてるはずなのに、おばさんの声は俺の耳に良く届く。
「こんにちは、良いところであっちゃったわ〜、さっすが私の息子になる子よね」
「俺的には悪いタイミングなんですけどね、それと俺はおばさんの息子じゃない
ですから」
「もぅ、私のことはお養母さんって呼んでって言ったでしょ? めっ、だぞ!」
「・・・」
こういう台詞と、人差し指を立てて頬にあてる仕草。
ちゃんと片目もつぶってる、そんな仕草が似合ってしまうのがちょっと怖い
気がするけど、ここはつっこんだら負けだと思う。
俺はおばさんの足下にあった一番大きい買い物袋を持った。
「それじゃぁ帰りましょうか」
「あら、持っていってくれるの? 嬉しいわぁ」
「最初からそうさせるつもりじゃなかったんですか?」
「思った以上に安くて買いだめしちゃったの、えへ」
「・・・」
本当にそう言う仕草が似合うのが末恐ろしいと思う。
アイツの母だって知らなかったら俺だって絶対勘違いしそうだよな。
「ただいま〜、ここまで持ってきてくれてありがとうね」
「いえ、それじゃぁ俺は・・・」
「せっかくだから台所まで持っていってね♪」
「・・・了解、おじゃまします」
「あら、違うわよ? ただいま、でしょ?」
「お邪魔します」
「もぅ、素直じゃないんだから♪」
いつものやりとりを軽く流しつつ、俺は買い物袋を台所へと運ぶ。
「・・・」
「おばさん、これここで良い?」
「え? あ、うん。ありがとう」
「どうかしたんですか?」
なんか様子がおかしかった気がするから聞いてみる。
「・・・ううん、なんでもないわ。
ねぇ、ついでにこれ、片づけてもらってもいい?」
そう言うと買い物袋から取り出したものは、シャンプーとリンスだった。
「洗面所に置いておいてくれればいいわ。よろしくね」
「わかりました、ここまで来れば毒食らえば皿までです」
「そう、男の子ならその意気よ!」
無駄にテンションが高いおばさんに見送られて台所を後にした。
「毒食らえば皿までって、どこまでが毒なんだろう?」
おばさんやおふくろの仕掛けの場合、何処まで行っても皿が出てこない
毒だけのような気がする。そう思いながら廊下を歩く。程なくして洗面所に着く。
勝手知ってる我が家、じゃないけど、家族ぐるみでのつきあいがあったから
この家の配置も良く知っている。
「たしか、シャンプーは洗面所のあの棚だったっけ」
置き場所を思い出しつつ、洗面所の扉をあける。
ここは脱衣所もかねていて、この先にお風呂もある。
「あ、お母さん。シャンプー買ってきてくれたの? ありがとー」
「は?」
洗面所へ通じる扉をあけた瞬間、さらにその奥の扉の向こうから
アイツの声が聞こえてきた。
「ちょうどよかったぁ、こっちに渡してくれる?」
そう言って風呂場へ通じる扉が開く
「ま、待て!」
「え?」
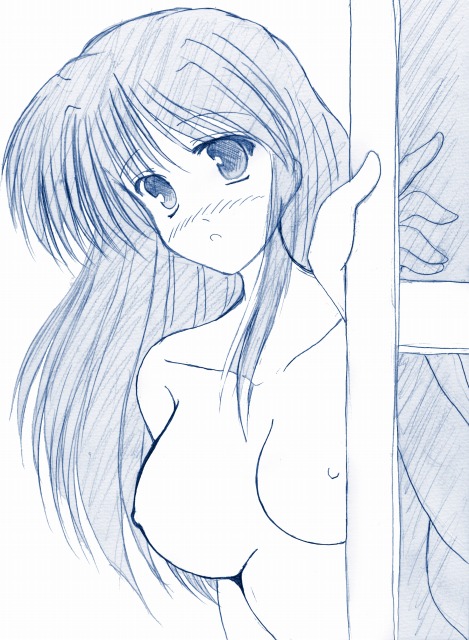 俺の制止の言葉は遅く、風呂場へ通じる扉が開かれる。
そこには一糸纏わぬアイツが・・・
「・・・」
「・・・」
俺はとっさにアイツを抱きしめる。
「いいか、まず落ち着け!」
俺は濡れたアイツの髪をそっと撫でる。
こうするとアイツは落ち着くからだ。
「俺が今日きたのはおばさんに捕まったからだ、そしてここにいるのは事故に
過ぎない、わかるか?」
「う、うん・・・」
「それでな、このまま悲鳴をあげられるとおばさんにからかわれる、だから
落ち着け」
「・・・もう、だいじょうぶだよ」
「そっか・・・」
とりあえず最大の危機は脱出できたようだった。
「心の準備が無いと大変だけどね、いまはもう大丈夫だよ」
「準備?」
「だって、キミのここが・・・その、私のお腹に・・・」
裸のアイツを抱きしめてる俺は、どうやらしっかりと反応してしまっていた。
「だから、いいよ・・・」
「いや、今は駄目だ。おばさんに見つかったらそれこそ取り返しがつかない」
俺は理性を総動員して、このまま押し倒したい衝動を抑える。
「いいか、俺はこれから目をつむる。そして回れ右してここを出る。
おまえは湯冷めしないようもう一度暖まってから出てこい。わかったな?」
「う、うん・・・残念だけどそうするね」
俺はまず目を閉じてアイツから離れる。
その瞬間、唇に軽い何かが触れる感触があった。
「また後でね」
「・・・」
洗面所から出た瞬間、俺はその場に座り込んだ。
「あらあら、とんだハプニングだったわね〜」
気付くとおばさんがそこに立っていた。
「確信犯でしょう?」
「今回は違うわよ」
「本当ですか?」
「本当よ、誓ってもいいわ」
そこまで言われると今回は本当のハプニングだったんだろう。
「だって、狙ってた場合なら、こんなに美味しいシチュエーション見逃す訳
ないじゃない♪」
「・・・」
今回は本当に偶然だったようだ・・・
「あら、洋服濡れちゃってるわね、どうしたの? お湯でもかけられた?」
「いえ、その・・・」
抱きしめたとはとても言えない。
「そのままだと風邪ひいちゃうわよ、ほら、乾かすから脱いで」
「脱いでって、俺代わりに着る物ないですよ?」
「お風呂でもはいってなさい、その間に乾かしておくから」
確かにそれなら問題なさそうに聞こえるが・・・
「今、アイツが入ってますよ?」
「あらぁ、そうだったかしら?」
今度は確信しての犯行だった。
お詫びにっていう理由でこの日の夕食をごちそうになっていくことになった。
何故かその場に俺のおふくろが招待されているのが気になるが、これも深く
追求しちゃ行けないことなんだろうな。
「それでどうだった? 我が娘の一糸纏わぬ姿は?」
「お母さん、恥ずかしいこと聞かないでよ」
「いいじゃない、私たちの最高傑作なんだから♪」
「ちゃんと見て無いのでコメント出来ません」
「へたれね、据え膳食わねば男の恥って言葉しらないの?」
「おふくろが息子に言う言葉ですか・・・」
「へたれじゃないわよ、純情なだけよ、ねぇ?」
「おばさん、もう勘弁してください・・・」
夕食に招待されたことを後悔し始めた瞬間だった。
俺の制止の言葉は遅く、風呂場へ通じる扉が開かれる。
そこには一糸纏わぬアイツが・・・
「・・・」
「・・・」
俺はとっさにアイツを抱きしめる。
「いいか、まず落ち着け!」
俺は濡れたアイツの髪をそっと撫でる。
こうするとアイツは落ち着くからだ。
「俺が今日きたのはおばさんに捕まったからだ、そしてここにいるのは事故に
過ぎない、わかるか?」
「う、うん・・・」
「それでな、このまま悲鳴をあげられるとおばさんにからかわれる、だから
落ち着け」
「・・・もう、だいじょうぶだよ」
「そっか・・・」
とりあえず最大の危機は脱出できたようだった。
「心の準備が無いと大変だけどね、いまはもう大丈夫だよ」
「準備?」
「だって、キミのここが・・・その、私のお腹に・・・」
裸のアイツを抱きしめてる俺は、どうやらしっかりと反応してしまっていた。
「だから、いいよ・・・」
「いや、今は駄目だ。おばさんに見つかったらそれこそ取り返しがつかない」
俺は理性を総動員して、このまま押し倒したい衝動を抑える。
「いいか、俺はこれから目をつむる。そして回れ右してここを出る。
おまえは湯冷めしないようもう一度暖まってから出てこい。わかったな?」
「う、うん・・・残念だけどそうするね」
俺はまず目を閉じてアイツから離れる。
その瞬間、唇に軽い何かが触れる感触があった。
「また後でね」
「・・・」
洗面所から出た瞬間、俺はその場に座り込んだ。
「あらあら、とんだハプニングだったわね〜」
気付くとおばさんがそこに立っていた。
「確信犯でしょう?」
「今回は違うわよ」
「本当ですか?」
「本当よ、誓ってもいいわ」
そこまで言われると今回は本当のハプニングだったんだろう。
「だって、狙ってた場合なら、こんなに美味しいシチュエーション見逃す訳
ないじゃない♪」
「・・・」
今回は本当に偶然だったようだ・・・
「あら、洋服濡れちゃってるわね、どうしたの? お湯でもかけられた?」
「いえ、その・・・」
抱きしめたとはとても言えない。
「そのままだと風邪ひいちゃうわよ、ほら、乾かすから脱いで」
「脱いでって、俺代わりに着る物ないですよ?」
「お風呂でもはいってなさい、その間に乾かしておくから」
確かにそれなら問題なさそうに聞こえるが・・・
「今、アイツが入ってますよ?」
「あらぁ、そうだったかしら?」
今度は確信しての犯行だった。
お詫びにっていう理由でこの日の夕食をごちそうになっていくことになった。
何故かその場に俺のおふくろが招待されているのが気になるが、これも深く
追求しちゃ行けないことなんだろうな。
「それでどうだった? 我が娘の一糸纏わぬ姿は?」
「お母さん、恥ずかしいこと聞かないでよ」
「いいじゃない、私たちの最高傑作なんだから♪」
「ちゃんと見て無いのでコメント出来ません」
「へたれね、据え膳食わねば男の恥って言葉しらないの?」
「おふくろが息子に言う言葉ですか・・・」
「へたれじゃないわよ、純情なだけよ、ねぇ?」
「おばさん、もう勘弁してください・・・」
夕食に招待されたことを後悔し始めた瞬間だった。
12月8日
・Canvas2 SSS”次元”
「せんせー!」
美術準備室の扉を勢いよく開けて入ってきたのはちびっこ小説家だった。
「む? 今余計な形容詞無かった?」
「・・・それよりも部屋に入るときはノックくらいしなさい」
萩野は入ってきた扉を閉める。
それからおもむろに扉を2回たたく。
「しつれーしまーす♪」
内側に入ってからノックして失礼しますって・・・
「ま、いいか。所で今日は何の用だ?」
「せんせーとの愛を確かめたくて来ちゃいました〜」
「帰れ」
「即答!? せんせー酷い!!」
「もうすぐ部活動が始まるんだ、とっとと帰りやがりなさいませ」
「丁寧なのに乱暴? って話が進まないじゃない。せんせー話聞いてよ」
「話を逸らしたのは誰だよ」
「せんせー」
「・・・で、何の用事だ」
いい加減話を促した。このままずるずると時間が過ぎていくと部長に何言われるか
わかったものじゃないからな。
「ねぇ、せんせー。昔女の子を振ったときの事覚えてる?」
「女の子を振った?」
脳裏に校舎の屋上の夕焼け空が浮かび上がる。
そこにいた女の子の、あの顔とともに・・・
「・・・覚えてないな」
「せんせーがこの学校に来て最初の年だったと思うんだけどね」
撫子に来て最初の年・・・なら、霧じゃないな。
ほっと胸をなで下ろす。
「その時せんせー、こう言ったんだって?
「俺は誰かに好かれるような人間じゃない」って」
俺、そんなこと言ったか?
「ねぇ、せんせー」
萩野が俺の正面に立つ、その顔は真剣だった。
「な、なんだ?」
「せんせー、もしかして・・・3次元に興味ないの?」
「・・・は?」
「ほら、絵描きさんだから、絵に描いた2次元しか興味ないのかなぁって」
「そ、そうなんですか?」
いつの間にか美術室との扉が開かれていた。
そこには竹内が・・・
「って、どういう意味だ!」
「上倉先生がそう言う態度をとるって、現実に興味が無いって事だったんですね」
「2次元は裏切らないんでしょ、せんせー?」
「お・ま・え・ら・・・くだらないこと言ってないでとっとと帰りやがれ!」
「ただいま」
まったく、萩野のせいせ余計な噂が立っちまった。
あいつらは一体俺をなんだと思ってるんだ?
「お帰りなさい、お兄ちゃん」
「おぅ、ただいっ!?」
家に帰るとエリスがエプロンをして出迎えてくれた。
そして何故か肌色が多く見え隠れする。
「お兄ちゃんが2次元しか興味無いっていうから、3次元にも興味を持って
欲しいから、頑張っちゃいました」
「エリスが・・・エプロンして・・・もしかして料理したのか!?」
「お兄ちゃん、驚くところそこなのね・・・」
「当たり前だろう!」
その時奥から何か煙が流れてきた。
「あっ、いっけなーい! 火をかけっぱなしだった!」
「早く消せ」
「う、うん!」
そういって後ろを向いたエリス。
そこには可愛いお尻が・・・
「って、なんて格好してるんだ!」
「お兄ちゃん、気付くの遅いよ・・・」
「す、すまん。じゃなくて早く火を!!」
この日の夜は店屋物を頼むことになり。
その後しっかりとエリスを叱っておいた。
翌朝・・・
「ねぇ、浩樹」
「なんだ?」
「シスコンロリコン天然ジゴロの上に、とうとう現実から目を背けたんだって?」
「・・・もう勘弁してください」
11月30日
・夜明け前より瑠璃色な SSS "二人の時間"
カラン
グラスの中の氷が溶けて、琥珀色の液体の中に落ちていく。
横には親友のさやかが、何も語らず私と同じようにグラスを
手に持ち、琥珀色の液体を揺らしている。
その姿を視界の端におさめながら、私はグラスの中の液体を
喉に流し込む。
冷たいはずの液体は、熱く喉を潤す。
カレン、誕生日おめでとう
そう言ってさやかが連れてきてくれたのはいつものバー。
今日はおごりよ、と楽しそうに笑うさやか。
せっかくの日曜日、早く仕事も上がれたのだから家族の元へと
戻れば? との私の問いかけにさやかは笑いながらこう答える。
今の時間に帰ると、達哉君に怒られちゃうって。
最初はいつものようにたわいもないおしゃべり。
そうしてしばらくすると、さやかは1通の封筒を渡してくれた。
中には手紙と招待状が入っていた。
とても楽しそうなさやかの顔。
これは? 問いかける私に、読めばわかるわよ、とさやか。
手紙には朝霧家への招待状の事が書かれていた。
達哉君と麻衣さんの連名私を、夕食に招待してくれるそうだ。
ただし、左門の休業日限定と、注意書きが書かれていた。
これが私たち家族からの、カレンへのプレゼントよ。とさやかは
微笑みながら言う。
家族団らんにお邪魔するのは悪いとは思う、けど招待状まで用意しての
誕生日プレゼントとなると、断る方が悪い気がする。
何れ機会があればお受けする旨をさやかに伝える。
その答えにさやかは満足そうに笑うと、グラスの中身を飲み干す。
私もそれにならってグラスを空ける。
会話も少しずつ減っていき、今は二人でただ飲むだけ。
時折二人視線を合わせ絡ませ、そして離れる。
そしてグラスの中の琥珀色の液体を喉に流し込む。
いつもと同じ、親友と飲む時間。
なのに。
今夜の酒はとても美味く感じる。
このまま夜が明けるまで、ずっとこうしていたい。
だが、先ほどの手紙の最後に書かれている文面がそれを押しとどめる。
申し訳ないですけど、姉さんをよろしくお願いします、と。
さやかを見る、まだ酔っているようには見えない。
だが、きっとまっすぐ歩けないほど酔いが回っているだろう。
バーのマスターを呼ぶ、精算して車を回してもらうために。
だが、マスターは車の手配だけしかしてくれなかった。
もう、先にもらってますよ、と私に言う。
ふふっ、さやかったら自分が酔う所まで考えていたのね。
払えなくなる前に払っておくなんて、抜け目無いわ。
抜け目無いけど、結局私が送っていく事になるんだから、詰めが
甘いわね。
それがさやからしく、とてもおかしかった。
外に車が来たようだ。
時計を見るともうすぐ日付が代わる時間。
まずはさやかを送らないとね。
マスターに別れを告げてから、タクシーに乗り込む。
言い慣れた住所を伝えると車が走り出す。
さやかを見るとは寝息を立て始めている。
眠っているさやかに、そっと感謝の意を伝える。
楽しい誕生日をありがとう、さやか。 ・・・と。
11月25日
・originalshortstory 冬のないカレンダー #9
「目が点になるとは、こう言うときに言うんだな」
「ねぇ、今度の休み空いてる?」
リビングでくつろいでる俺におふくろが声をかけてくる。
「今度って連休の時だっけ?」
「そう、友達がねチケット当たったって言って誘ってくれたのよ。
行かない?」
「何処に?」
「日帰り温泉」
温泉か・・・足を延ばして風呂にのんびり入れるのは良いかも。
「親父はどうするんだ?」
「急には帰ってこれないわよ、また今度ね」
単身赴任してる親父を急に呼び出すのは無理みたいだ。
「だから、私につきあうと思って、ね?」
今度の連休、特に俺の予定もないしアイツと出かける予定も無い。
「いいよ、つきあうよ」
「ありがとう、さすが我が息子よね」
「いや、そこに息子は関係ないから・・・」
そう、ただの日帰り温泉にちょっとつきあうだけのはずだった。
「・・・で、これはどういう意味でしょうか? お母様?」
俺は問いつめるときに使う呼び方でおふくろを呼ぶ。
「いやん、怖い声ださないで」
・・・思わず年齢を考えろと言いたい所だが、そういう仕草が妙に
似合ってしまう我が母。
見た目だけなら若く、俺と一緒にいると姉弟に見られるくらいだ。
「だめだよ、おばさんをいじめちゃ」
「でもたまには良いんじゃない? 良い薬になるし」
「酷い、二人とも!」
そうツッコミをいれるのはアイツと、おばさん。
おばさんも見た目が若いから、アイツと仲の良い姉妹に見られることが
多い。
つまり、見た目なら俺の回りに妙齢の美女3人。
「・・・」
そうなると回りの視線がかなり痛い。
「とりあえず電車出ちゃうから行きましょう」
「「おー!」」
おふくろのかけ声に反応するアイツとおばさん。
「ほら、行くわよ」
「あ、あぁ・・・」
このとき、事の経緯を聞きそびれたことに気付いたのはもっと後になって
からだった。
「それじゃぁプールの前で待っててね」
そういって3人で女子更衣室に入っていくのを見送る。
「はぁ・・・」
俺はため息を付きながら男子更衣室へと向かう。
水着なんて持ってきてないと言った俺におふくろは
「こんなこともあろうかと、貴方の鞄に入れておいたわよ」
「・・・確信犯だろう?」
「あら? 何の事かしら?」
なんてやりとりがあったばかり。なんだかもう疲れた。
「温泉っていうけど、これじゃリゾート施設だよな」
着替えながら入り口で見た案内を思い出す。
室内温水プールに、温泉プール。室外にも露天の温泉があり、すべて水着
着用の混浴だった。休憩施設もあり、宿泊用の部屋もあるそうだ。
「さてっと」
着替えが終わって室内プールの前で待つ。
女の子は着替えが大変だから時間がかかる・・・
「いや、まて、俺の思考。ちょっと訂正」
女性の着替えは時間がかかる、これでよし。
「おまたせ」
俺の後ろから声をかけてきたのはアイツ。
白いパーカーを羽織っている。
そう言えば、つい最近水着を買いに行くのをつきあったっけ。
新しい水着は結局教えてくれなかったが、今着ているのだろうか?
その時ふと疑問に思った。何故タイミング良く水着を買いに行く
事が出来たのだろうか?
「・・・おまえ、もしかして今日のこと知ってたんじゃないか?」
「ううん、知らなかったよ」
「この前の水着を買いに行ったよな?」
「うん、お母さんに勧められたんだよ」
「・・・」
犯人はおばさんのようだ。
「おばさん達遅いな」
「そうだね」
「せっかくだし、少し泳ぐか?」
「うん、泳ごう♪」
そう言ってパーカーを脱ぐアイツを見て・・・
目が点になるとは、こう言うときに言うんだな。
紺色の厚めの生地に、アイツの身体はすっぽりと包まれている。
胸元に縫いつけられている名前。
それはどこからどう見ても、いわゆるひとつの「スクール水着」だった。
「さ、泳ごうか」
プールに向かおうとするアイツの頭を掴む。
「えぅ!」
「おまえは何着ているんだ!」
「んとね、スクール水着」
「だから、なんでそんなの着てるんだって聞いとるんだ!」
「お母さんがね、キミを悩殺するにはこれがいいって言って勧めてくれたの」
「・・・」
「健全な男子はスクール水着で萌えてくれるんだって。」
おばさん・・・貴方は実の娘に何勧めてるんですか・・・
「ねぇねぇ、キミは萌えた?」
「この前買った水着はどうした?」
「一応持ってきてるよ?」
「それに着替えてこい」
「えー?」
「えーじゃない」
「・・・キミはスクール水着じゃ萌えないの?」
頭が痛くなってきた。しかしここで負けるわけには行かないし、何より
回りの視線が痛すぎる。
「せっかくこの前かった可愛い水着、俺は見てみたいんだよ」
「本当?」
「あぁ・・・」
「うん、それじゃぁ着替えてくるね!」
そう言ってアイツは更衣室に駆けていった。
「やるわね〜」
「聞いちゃった、可愛い水着姿みたいだなんて、えっちよね」
「・・・おばさん、どういうことか説明してもらえるんでしょうね?」
俺は声のする方を振り向く。
そこには妙齢の美女2名・・・おふくろを美女と言うには息子として
抵抗あるんだけど、普通に見ただけなら本当に美女だったりする。
「何度言ったらわかるの? 私のことはお養母さんって呼んで」
「・・・おふくろも一枚かんでるんじゃないだろうな?」
「今日は私のことはお姉さんって呼びなさい」
「・・・はぁ」
今回のこの施設の招待券は家族4名のものだったそうだ。
おばさんがもらったのだが、おじさんは仕事の都合で来れないそうだ。
だから、俺達親子が誘われたわけだが・・・
「今日は私のことお養母さんって呼んでね」
「あー、はいはいわかりましたよ、おばさん」
「だめだよ、今日は本当にお母さんって呼ばないと」
アイツが珍しくフォローする。
「そして私はお姉さんよ」
「・・・どういうことだ?」
家族の招待券故に、家族でなくちゃいけない。
だから、母一人にあとは姉弟、という事にしたそうだ。
その時、おふくろとおばさんで、どっちが姉役かでもめたそうだ。
ゲームで勝負を決めることになったそうだが・・・
「私2度目だよ、盤面真っ白のオセロって」
1度目は俺と戦った時だったよな。
なんていうか、やっぱり親子だなって思った。
「でもさ、おばさん・・・いえ、お養母様なら別に姉でも通るんじゃないかな?」
「さっすが我が息子になる男の子よね、見る目しっかりしてるわ〜」
「だめだめ、一応引率者が必要だったしね。それと誰が我が息子になる子だって?
この子はあげないわよ」
「えー」
「えーじゃないっ!」
「・・・」
やっぱり親子だよなぁ・・・
「おまたせ」
「遅・・・」
振り向くと着替えて戻ってきたアイツが立っていた。
 「どう・・・かな?」
白いワンピースの水着、胸元に赤い小さなリボンが付いている。
先ほどより薄手の生地で・・・スクール水着が厚すぎるのだが、その差を
ボディラインがはっきりと教えてくれている。
大きな胸から細いウエストへと続くラインは腰回りで柔らかくふくらんでいる。
「・・・か」
「可愛いわ〜、さすが我が娘よね。スクール水着じゃなくても充分悩殺出来るわね」
「やっぱり女の子は良いわよね〜、ね、早く家にお嫁に来ない?」
「だめよ、お嫁になんかあげないわ。彼に婿に来てもらうんだから」
「・・・ふぅ、あの二人は放っておいて泳ぎに行くぞ」
「・・・うん」
苦笑いしながらアイツは俺に付いてくる。
「仲が良いよね、お母さん達」
「良すぎるのも問題だけどな」
「・・・」
「・・・」
「・・・可愛いよ」
「え?」
「ほら、泳ぎに行くぞ!」
俺はアイツの手を取ってプールサイドを歩き出す。
「ねぇ、今なんて言ったの? もう一度言って欲しいな」
「言えるか!」
「いぢわる」
そう言いながら微笑むアイツの顔は凄くまぶしかった。
「どう・・・かな?」
白いワンピースの水着、胸元に赤い小さなリボンが付いている。
先ほどより薄手の生地で・・・スクール水着が厚すぎるのだが、その差を
ボディラインがはっきりと教えてくれている。
大きな胸から細いウエストへと続くラインは腰回りで柔らかくふくらんでいる。
「・・・か」
「可愛いわ〜、さすが我が娘よね。スクール水着じゃなくても充分悩殺出来るわね」
「やっぱり女の子は良いわよね〜、ね、早く家にお嫁に来ない?」
「だめよ、お嫁になんかあげないわ。彼に婿に来てもらうんだから」
「・・・ふぅ、あの二人は放っておいて泳ぎに行くぞ」
「・・・うん」
苦笑いしながらアイツは俺に付いてくる。
「仲が良いよね、お母さん達」
「良すぎるのも問題だけどな」
「・・・」
「・・・」
「・・・可愛いよ」
「え?」
「ほら、泳ぎに行くぞ!」
俺はアイツの手を取ってプールサイドを歩き出す。
「ねぇ、今なんて言ったの? もう一度言って欲しいな」
「言えるか!」
「いぢわる」
そう言いながら微笑むアイツの顔は凄くまぶしかった。
11月21日
部屋の襖をそっと開ける。
薄暗い部屋の中にひかれてる布団の中で寝てるのは支倉君と伽耶。
いえ、旦那様と私の可愛い娘。
音を立てずにそっと近づく。
「ふふっ、二人とも可愛い寝顔」
別々の布団で寝ていたはずなのに、伽耶ったら旦那様の布団に潜り込んで
抱きついて眠っている。
私は無言のまま、携帯のカメラでこの光景を撮影する。
それからそっと二人を起こしにかかる。
「旦那様、伽耶。もう朝ですよ。起きてくださいませ」
そっと身体を揺する。
それでも二人とも起きない。
「旦那様、伽耶」
・・・やっぱり起きない。
これは以外に手強いわね。こうなったら・・・
私は布団を持つと力を込めて取り上げる。
「ひゃぁ!」
「う・・・」
「目が覚めたかしら、二人とも。顔を洗って来てくださいね」
朝食の席。
私は注意深く味付けをした料理を机の上に用意した。
ご飯にみそ汁、生卵にあじの干物に浅漬けの御新香。
私の生まれた時代ではこんな豪華な朝食など見たことがなかった。
今の時代だと、これでも質素なのだろうとは思う。
でも、私にはこれしか作れないから・・・
「どうぞ、召し上がれ」
「「いただきます」」
二人の声がはもる。
「・・・」
味覚が鈍い眷属である私は人に料理を作ることが出来ない。
同じ眷属である支倉君・・・いえ、旦那様にあわせた味付けなら
簡単だけど、ここには伽耶がいる。
伽耶にあの味付けは酷という物、だから私は本を読みながらその
味付けを真似してみた。
「・・・どう、かしら?」
「美味い、紅瀬さん」
「あぁ、良い味だぞ、桐葉」
「・・・二人とも、呼び方が違うわよ?」
ほっとした事を表に出さずに、呼び方を直させる。
「ほら、旦那様も伽耶も」
「・・・わかったよ、き・・・桐葉」
「仕方がないな・・・その・・・母上」
「良くできました、さぁ食事を再開しましょう」
・FORTUNE ARTERIAL Another Short Story Re,
Appendix Episode「しあわせのかたち」
それは、私の誕生日から始まった。
「誕生日おめでとう、紅瀬さん!」
部屋に招待された私を待っていたのは、誕生日を祝うために集まった
家族、だった。
親友の伽耶、伽耶の娘の瑛里華さん、そして瑛里華さんの眷属の支倉君。
東儀さんもいた。驚いたことに伊織君もその場にいた。
「んー、紅瀬ちゃんのこの顔を見るだけでもここに来た甲斐はあったね」
「伊織、茶化すな」
「ほら、紅瀬さん。そんなところに立ってないで中に入って!」
「え、えぇ・・・」
私は促されるままに、部屋の中に入る。
「誕生日おめでとう、紅瀬さん!」
「まさか、この歳になって私の誕生日を祝われるとは思っても見なかったわ」
「何を言う、あたしの大事な親友だぞ? 祝わない訳がないじゃないか!」
「今まで祝ってくれなかったのに?」
「う゛・・・」
「もぅ、紅瀬さんったら照れ隠しに母様をいじめないでよ」
「照れてなんていないわ」
「説得力無いよ、紅瀬ちゃん」
確かに私は照れているのかもしれない。
でも、それ以上に嬉しかった。
こうしてみんなで何かを分かち合える事が出来た、その事実が。
「プレゼントだけどな、桐葉。あたしからはこれをあげよう」
「・・え?」
そういって伽耶が差し出した、というか支倉君の背中をおした。
「ちょっと待ってよ、母様。孝平は私のなのよ?」
「俺は瑛里華の持ち物か?」
「娘の物は母の物という諺があるの、知らないのか?」
「あるわけないでしょ!」
母と娘の漫才を見ながら、私は一つアイデアを思いついた。
「伽耶、私は別に支倉君、いらないわ」
「それはそれで傷つくんですけど・・・」
あら、支倉君も可愛いところあるのね。
「まぁ、支倉は冗談だけどな」
「あながち冗談ではないかもしれないわよ、伽耶」
「ん?」
「伽耶、それに支倉君、私の欲しい物、くれるかしら?」
そして、支倉君は私の旦那様役、伽耶は私たちの娘役で1日過ごす。
それが私の欲しいプレゼントになった。
「なぁ、母上。あたしと遊ぼう」
一生懸命に娘役を演じる伽耶。
「そうね、洗濯物が終わったら遊びましょう」
私は洗濯機を動かす。
本当は昔みたいに手で洗っても良かったのだが、せっかくの時間が
勿体ないから。
そう、1日しか無いのだから・・・
「一番はじめは一宮♪」
「いっちばん、はじめは、いちのみやっ!」
「二は日光、東照宮♪」
「にーは、にっこー、とうしょうぐうー」
「三は讃岐の金比羅さん♪」
「さんっは、讃岐のっ! 金比羅さんっ!」
「桐葉はお手玉凄く上手だな、見とれちゃうくらいだよ」
「えっ?」
支倉君の言葉に思わずお手玉を落とす。
「もぅ、からかわないで」
「いや、からかってないよ。それに比べて伽耶ちゃんは・・・」
「う、うるさい! そんなに言うならはせ・・・父上もやってみてはどうだ?」
「よし、俺の腕前を見せてやろう!」
・・・
「二人とも、下手ね」
「うぅ・・・」
「こんなはずでは・・・」
「伽耶ちゃん、紙飛行機って知ってる?」
「馬鹿にするな、それくらい知ってるぞ?」
「それじゃぁ競争しようか?」
「受けて立つぞ」
若干会話が堅い気もするけど。
「二人ともちゃんと、親子してるじゃない」
「今のはあたしの方が飛んだぞ?」
「いや、俺の方が飛んだ!」
「大人げないぞ、父上?」
「う・・・それを言われると辛い」
そうしてあっという間に1日は過ぎていった。
「旦那様、伽耶をお風呂に入れてあげてくださいな」
「あぁ・・・って、ちょっとまった!」
「き、桐葉っ!」
「何?」
「さすがにそれはまずいんじゃないか?」
「そうだぞ、あたしがなんで」
「なんで? 父親が娘とお風呂に入るのに何か問題あるのかしら?」
「そ、それは幼い頃だけだろう?」
「旦那様、伽耶は幼いわよ?」
「・・・」
「・・・」
「旦那様、お風呂にはいってくださいな。伽耶、髪を洗ってもらいなさい」
「・・・」
「・・・」
「返事は?」
「「はい・・・」」
ふふっ、ちょっとやりすぎたかしら?
夕食も終わり、そろそろ寝る時間になってしまった。
私は寝室に3つの布団を敷く。
この布団に入って、眠りについて、朝になればいつもと同じ関係に戻って
しまう。
それが当たり前の関係。
・・・出来るのなら、この幸せが続いて欲しかった。
だけど、それは敵わぬ望み。
私は人ではないのだから、人並みの幸せは望めない・・・
「桐葉、伽耶さん眠っちゃったよ」
「あら、伽耶ったら・・・」
寝室に旦那様が伽耶を抱いて入ってきた。
「伽耶をここに」
「あぁ」
真ん中の布団に伽耶を寝かせる。
「ふふっ、凄く可愛い顔してるわね」
「あぁ、これが本当の伽耶さんなんだろうな」
嫌々受けた私の願い、だけど伽耶もまんざらじゃなかったようだ。
「・・・なぁ、紅瀬さん」
「桐葉よ」
「・・・桐葉」
「何でしょう、旦那様」
「・・・」
1日そう呼んできたのに、まだ照れてるのね。
私がそれを指摘するよりも先に支倉君が口を開いた。
「このプレゼントは桐葉のためというより、伽耶さんのために思えるんだけど
違うかい?」
私は軽く驚いてしまった。
「やっぱりな」
私は一度深呼吸してから、思ってることを伝えた。
「支倉君、私の幸せは伽耶が幸せになることなの。私にはそれしか望めないから」
「・・・違うな、桐葉」
「え?」
「伽耶さんの幸せは、みんなで幸せになることなんだよ。桐葉だけ伽耶さんに
幸せを押しつけちゃいけない」
「支倉君・・・」
「伊織先輩も東儀先輩も、瑛里華も桐葉も、そして俺も。
みんなで幸せになるのが、俺達の償いだから」
「・・・」
「だから、桐葉の幸せも見つけよう」
「・・・えぇ、わかったわ」
伽耶を変えてくれた支倉君。
そんな彼は私をも変えてくれようとしてくれる。
私と伽耶の幸せは、支倉君がきっともたらしてくれる、そう確信した瞬間だった。
「あの時の支倉君の言葉、今でも忘れられないわ」
「そう言われると恥ずかしいんですけど・・・」
「何を言う、支倉がそうさせたのだろう?」
2度目の修智館学院での学生生活、その中で迎えた私の誕生日。
週末を使って千堂家に帰り、今年も3人で過ごしている。
あれからどれくらい時がたったのだろう。
それでもあの時の思いは変わらずみんなで幸せに過ごしている。
「ところで支倉君。娘はいつもらってくれるのかしら?」
「ぶっ!」
「き、桐葉っ! いきなり何を言う!」
「そ、そうですよ。伽耶ちゃんは瑛里華の母親ということは俺にとって母でも
あるわけで!」
「そんなこと関係ないわ、私たちは法の外の存在なのだもの」
「・・・桐葉、娘であるあたしよりも、未婚の母である桐葉が先にもらわれる
べきじゃないのか?」
「か、伽耶っ!?」
「まんざらでもなさそうだな」
「も、もぅ、知らない!」
---
・FORTUNE ARTERIAL Another Short Story Re,
Appendix Episode Plus「しあわせのかたち-if-」
ANOTHER VIEW 孝平
「旦那様・・・いえ、支倉君。今日のお礼がしたいの」
後は布団に入って寝るだけの時間、桐葉がお礼をしたいと言い出した。
「お礼なんていいよ、もとより紅瀬さんの誕生日プレゼントなんだからさ。
それに、俺も楽しんだし」
遊び疲れて俺の横の布団で眠っている伽耶さん。
その楽しそうな寝顔をみれただけでも、紅瀬さんにつきあった甲斐が
あったものだ。
「紅瀬さんもそろそろ寝よ・・・って、ちょっと?」
俺が紅瀬さんの方に振り向いたとき、紅瀬さんは着ていた着物を脱いでいた。
すでに帯ははずされており前がはだけている。
「・・・」
制止すべき言葉が俺の口からは出てこない。
胸元の谷間、お腹の所に見える小さなくぼみと、そこからのなだらかなラインは
淡く黒い草原に続いている。
シュル・・・という音とともに紅瀬さんは一糸纏わぬ姿になった。
瑛里華がフランス人形だとすれば、紅瀬さんは日本の人形というべきか。
それほど美しく、人離れしていると思う。
俺の視線を受け、頬を赤らめながら紅瀬さんはその場に正座した。
俺はその様子をただ見ているだけだった。
大きな胸と、正座した、その足の付け根に目がいってしまう。
紅瀬さんは三つ指を立てて、頭を下げる。
「ふつつか者ですが、よろしくお願いします」
「あ、いえ、こちらこそ・・・じゃないっ!」
「声が大きいわよ、伽耶が起きちゃうじゃない」
俺は慌てて自分の口をふさぐ。
「く、紅瀬さん、落ち着いて考えようよ」
「私は落ち着いてるわ」
「だからって何もそんなことしなくても・・・」
「支倉君、私がお礼をしたいと言ってるのよ。だから受け取って」
「な、なにを受け取るんだ」
「私の初めて」
「っ」
直球の言葉に俺の鼓動は早くなる。
「女がここまでしてるのに、恥をかかせる気なの?」
「でも・・・」
俺には瑛里華がいる、だから・・・
「支倉君は今日だけは私の旦那様、今だけは私を見て・・・」
「桐葉・・・」
「お情けを、旦那様」
「・・・わかった、今の俺は桐葉の主人だからな。
でも、ごめん。愛せるのは今だけだ」
「いいのよ、それで・・・一夜限りで・・・」
「桐葉・・・」
「旦那様・・・」
11月17日
・originalshortstory 冬のないカレンダー #8
「百聞は一見に如かずって言うけど」
一回の経験よりも百回聞いた方が良い場合もあるかもな。
俺は目だけで回りを見回す。
そこにある布、布、布と、女の子と女の子と女性店員。
「ふぅ・・・」
思わずしゃがみ込みたくなるが、そんな行動は異様に見えることだろう。
「・・・はぁ」
口から出るのはため息だけだ。
「なぁ、今日は買い物につきあうだけだったよな」
「うん、そうだよ」
「どうしても俺が行かないといけないって言う話だったよな?」
「うん♪」
「てっきり荷物持ちかと思って諦めて来たんだけどな、ここは何処だ?」
俺の問いかけに一瞬悩むような仕草をしたアイツはにこっと笑いながら
「駅前のショッピングセンターの中だよ」
と、真面目に返事した。
「・・・で、この店が目的地みたいだが、何の店だ?」
「見てわからない? 水着のお店だよ」
「・・・」
「じゃぁ、行こう!」
俺の手を引っ張って店の中へと入ろうとするアイツの頭を鷲掴みにする。
「えぅ」
「あのな、ここが男にとってどれだけ致命的な場所かおまえは知ってるのか?」
「そうなの? 普通の水着売り場だよ?」
「・・・全部女性用に見えるんだが?」
「だってそう言うコーナーだもん」
「・・・」
「ほら、行こう!」
「パス」
「えー?」
こんな所に男の俺が入ると間違いなく好奇な目で見られるに決まってる。
俺はきびすを返し、帰ろうとした。
「私と一緒にお買い物、そんなにいやなの?」
「・・・」
目を潤ませながら、少しうつむいて俺の方を見るアイツ。
嘘泣きだってわかってる、わかってるんだ。騙されるな、俺!!
「・・・俺は選ばないぞ」
「うん、ありがとう!」
そう言って抱きついてくる。
はぁ・・・また俺は勝てなかったか。
そう言うわけで俺達は水着売り場に突入した。
「でも、おまえ小遣いあるのか?」
「あー、だいじょうぶ。お母さんに水着の話ししたらお小遣いもらっちゃった」
なんか嫌な予感がする。
「水着でキミを悩殺して落としちゃいなさいだって♪」
・・・おばさんとは一度拳で語り合いたくなってきた。
「でも、お母さんも変なこというよね」
「ん?」
珍しくまともなことを言うな。
「だって、もうキミは私にぞっこんだもん。落ちるも何もないよね」
「・・・おまえ、歳いくつだ?」
ぞっこんだなんて言葉まだ使われてたのか・・・
「あ、これ可愛い♪ これも可愛いなぁ・・・ねぇ、どれが似合うと思う?」
「・・・」
「ねぇねぇ、これなんてどう?」
「・・・」
「むー、さっきからなんで黙ってるの?」
「俺は選ばないと言っただろう? それに前にも言っただろう?
バカップルは公害なんだぞ?」
「えー? 私たちバカップルじゃないよ? ただの恋人どうしだよ?」
俺が口を開ける前に、近くで笑い声が聞こえた。
思わず振り向いた先にはお店の女性店員さんが口元を押さえていた。
「・・・わかった、とりあえず数着にしぼれ。それから俺も選んでやる」
「本当? ありがとう♪」
「ねぇねぇ、こっちに来て」
俺は手を引かれて店の奥へと連れてこられた。そこには・・・
「試着室?」
「うん、着てみないとわからないしね、だからここで待っててね」
「マジか?」
「じゃぁ行ってきまーす!」
そう言って元気良く試着室の中に入っていった。
「・・・」
何故か冷静に分析してみる。
女性用水着売り場の試着室の前に男が一人・・・
「頼む、早く着替えてくれ・・・」
早く着替えることを望む俺だったが、布ずれの音に当たり前のことを
気付かされた。
このカーテンの向こうにアイツが水着に着替えてる。
水着に着替える訳だから・・・
「・・・」
やばい、まずい、とにかく危険だ。
かといって逃げる訳にもいかず、いるだけで精神が摩耗していくのを
実感させられる。
「・・・まだか」
「おまたせ♪」
そう言ってカーテンを開けた瞬間、俺はカーテンを閉じた。
「え?」
「おまえ、何着てるんだよ!」
「水着だよ? お母さんが薦めてくれた悩殺水着♪」
「恥ずかしいだろうが!」
「そう? だって見て良いのキミだけだもん、恥ずかしくないよ」
一瞬くらっと来た。不意打ちは卑怯だと思う。
たまには反撃しないと、俺の立場が無くなってしまうかもしれない。
「よし、そこまで言うなら見てやろう」
俺はカーテンの中に首を突っ込む。
「え?」
目をぱちくりしてるアイツの着ている水着はビキニタイプの物。
だが、布地が少なすぎる。ブラもパンツも身体の側面は紐しかない。
「・・・」
「・・・」
大きすぎず小さくもない、胸とほっそりとしたウエストから流れる
ラインに思わず見とれてしまう。
「・・・」
「・・・」
その時アイツの異常に気付いた。これは・・・
「えぅ!」
「逃げるな!」
俺は頭を鷲掴みにして動きを止める。
「うぇぇぇん、やっぱり恥ずかしいよぉ」
「わかったから、その格好のまま外に出ようとするな!」
「えぅぅ・・・」
「ともかく着替えろ」
「うん・・・」
そう言って背中に手を回す。
「ちょ、まて、俺が出てからにしろ!」
俺は慌ててカーテンの外に逃げる。
「・・・疲れた」
あの後、ファッションショーはなく、水着を買って店を出た。
「で、結局何を買ったんだ?」
「それは今度のお楽しみだよ♪」
「今度か・・・夏はまだ先だな」
どんな水着を買ったか気になる。あの場では見たいとは思わなかったが
こうして今になると見てみたいと思う。
「ふふっ」
「?」
「なんでもない、帰ろう!」
「あぁ」
手をつないでの帰り道。
振り返ってみればこんな1日もあってもいいと・・・
「思うわけないだろ!」
もう2度と水着売り場に近づかないことを心に誓った。
11月10日
・originalshortstory 冬のないカレンダー #7
「勝者無き勝敗ってどういう意味?」
「ねぇ、これで遊ぼうよ」
そういって取り出してきたのは・・・
「チェス・・・か?」
「うん、お母さんが持っててね、私も覚えたの」
テーブルにチェス盤を置いて駒をおいていく。
「俺、チェスしらないぞ?」
「だいじょうぶ、お母さんの持ってる本があるから」
そう言って取り出したのは、チェス入門。
「おまえなぁ、初心者以下の俺が勝てるわけ無いだろう?」
「大丈夫だって、ね、遊ぼ♪」
仕方が無く、俺はその入門書を片手に、ルールを覚えながら
実戦に参加する事になった。
「むぅ・・・ねぇ、この手待った!」
「・・・いいけど」
俺は駒を一手前に戻す。
「んとね、じゃぁ・・・こうする!」
「それじゃぁこうだ」
「えぅ・・・いぢわる」
「・・・おまえさ、本当に勝負に弱いな」
頭は悪くないんだよな。
勉強も出来ないわけじゃないし、ゲームのルールの飲み込みは早い。
だが、勝負というのに全くもって弱い。
以前、オセロを持ち出してきたときのことだった。
「ねぇ、お母さんがオセロ持ってたの。遊んでみようよ」
「いいぞ、手加減しないぞ?」
「もっちろん♪」
「・・・」
「・・・」
盤面のオセロは全て白色だった。
「・・・いぢわる」
「・・・ごめん、俺も驚いてる、完勝は初めてだからな」
「うー、もう一回!!」
その後、今度は俺はわざと一番駒をひっくり返せない場所に置くという
事を試してみた結果でさえ、俺の勝ちだった。
「今度はトランプしよう!」
「いいけどさ・・・せっかくの休みの日に家で遊んでていいのか?
どっかに行っても良いんだぞ?」
「私は構わないよ、だって一緒にいられるなら何処でも幸せだもん♪」
さらっという言葉にくらっとくる。
こいつはたまに俺をドキっとさせることを平気で口にする。
天然なのか、言ってる本人はなにも意図してないようだが、それだけに
破壊力は大きい。
「それに、外は寒いから家の中がいいよ」
「・・・寒いなら厚着しろよ」
「いや、だってこのスカート着たかったんだもん」
 そのスカートは寒くなったこの時期に着るには厳しいほど、ミニだった。
膝上何センチっていうより股下何センチレベルのミニスカート。
さっきから立ったり座ったりするたびに太股と、その先の白い布地が
目に毒だった。
「・・・そのスカート、短すぎないか?」
「そう?」
「見えちゃうぞ」
「別にいいよ、だって見てるのってキミだけだもん」
「・・・俺だって男なんだぞ? 我慢出来なくなったらどうするんだ?」
「別に良いよ、我慢なんかしなくたって・・・」
そう言って俺にすり寄ってくる。
そしてそっと目を閉じて・・・
「ちょっと待て」
「えー?」
「えーじゃない、こう言うときはたぶんな・・・」
俺は立ち上がって部屋の扉を開ける。
「あら?」
そこにはあいつのお母さんが扉に張り付いてる格好のままで固まっていた。
「何してるんですかおばさん」
「もう、いつもいってるでしょう? 私のことはお義母さんって呼んでって♪」
「お母さん、なんでドアのすぐ外にいたのよ!」
「我が娘の成長を確かめるためよ!」
「・・・で、本音は」
「お母さんも混ぜて欲しいなって」
俺のツッコミに即返事する。
「だーめ! 私だけのもんだもん!」
「娘の物は母の物っていうことわざが」
「あるわけないです!」
「えぅ」
俺のツッコミに涙を流すおばさん。
「もぅいいから出ていってよ!」
「えーん、私も一緒に遊びたいのにぃ・・・」
「・・・」
はぁ、あれで俺のおふくろと同じ歳だなんて思えないよな。
性格はさすがは俺のおふくろの親友だけのことはあると思う。
「それじゃぁゲームの続きしよう♪」
「構わないけど、おまえ絶対負けるぞ?」
「んー・・・良いよ、だって勝てる自信ないもん」
「おい」
「キミに惚れた弱みってやつ?」
・・・また来た。
油断した瞬間を狙うように俺の心に入り込んでくる一言。
「だから勝てないよ、私はキミに」
「ふぅ・・・完敗だよ」
「え? なんで? 私一度も勝ってないよ?」
惚れた弱みなら俺の方が上だろうな。
「どうして私が勝ちなの?」
「いいからそう言うことにしておけよ、今日だけだからな?」
「んー、それじゃぁ私が勝ったご褒美欲しいな」
頭をがしっとつかむ。
「えぅ」
「調子に乗るな」
すぐ調子に乗る、だけど・・・
「俺の負けだからな」
「え? ・・・うん♪」
嬉しそうに目を閉じるアイツに、俺は苦笑いした。
そのスカートは寒くなったこの時期に着るには厳しいほど、ミニだった。
膝上何センチっていうより股下何センチレベルのミニスカート。
さっきから立ったり座ったりするたびに太股と、その先の白い布地が
目に毒だった。
「・・・そのスカート、短すぎないか?」
「そう?」
「見えちゃうぞ」
「別にいいよ、だって見てるのってキミだけだもん」
「・・・俺だって男なんだぞ? 我慢出来なくなったらどうするんだ?」
「別に良いよ、我慢なんかしなくたって・・・」
そう言って俺にすり寄ってくる。
そしてそっと目を閉じて・・・
「ちょっと待て」
「えー?」
「えーじゃない、こう言うときはたぶんな・・・」
俺は立ち上がって部屋の扉を開ける。
「あら?」
そこにはあいつのお母さんが扉に張り付いてる格好のままで固まっていた。
「何してるんですかおばさん」
「もう、いつもいってるでしょう? 私のことはお義母さんって呼んでって♪」
「お母さん、なんでドアのすぐ外にいたのよ!」
「我が娘の成長を確かめるためよ!」
「・・・で、本音は」
「お母さんも混ぜて欲しいなって」
俺のツッコミに即返事する。
「だーめ! 私だけのもんだもん!」
「娘の物は母の物っていうことわざが」
「あるわけないです!」
「えぅ」
俺のツッコミに涙を流すおばさん。
「もぅいいから出ていってよ!」
「えーん、私も一緒に遊びたいのにぃ・・・」
「・・・」
はぁ、あれで俺のおふくろと同じ歳だなんて思えないよな。
性格はさすがは俺のおふくろの親友だけのことはあると思う。
「それじゃぁゲームの続きしよう♪」
「構わないけど、おまえ絶対負けるぞ?」
「んー・・・良いよ、だって勝てる自信ないもん」
「おい」
「キミに惚れた弱みってやつ?」
・・・また来た。
油断した瞬間を狙うように俺の心に入り込んでくる一言。
「だから勝てないよ、私はキミに」
「ふぅ・・・完敗だよ」
「え? なんで? 私一度も勝ってないよ?」
惚れた弱みなら俺の方が上だろうな。
「どうして私が勝ちなの?」
「いいからそう言うことにしておけよ、今日だけだからな?」
「んー、それじゃぁ私が勝ったご褒美欲しいな」
頭をがしっとつかむ。
「えぅ」
「調子に乗るな」
すぐ調子に乗る、だけど・・・
「俺の負けだからな」
「え? ・・・うん♪」
嬉しそうに目を閉じるアイツに、俺は苦笑いした。
11月9日
・夜明け前より瑠璃色な Moonlight Cradle SSS ”雨の天使”
夕方から降り出した雨は今もしとしとと降っている。
「お兄ちゃん、お姉ちゃん傘持っていって無いと思うの」
「わかった、行って来る」
「お願いね」
俺は自分の傘を差し、姉さんの傘を持って博物館へと向かった。
月人居住区に入ると、空気が変わった気がする。
俺達も普通に出入りできる場所にありながら、未だに異国として見られる
この月人居住区。
商店の閉まる時間も早く、ここだけ夜が訪れるのが早いと思わせる場所だった。
「・・・あれ?」
小さな公園の広場の真ん中に人がいるのが目に付いた。
この時間にこの居住区で出歩く人は少ないから、というのもあるが
その人は、雨の中傘も差さずに夜空を見上げていた。
「何してるんだろう?」
近づくとその人が女の子だと言うことが判った。
黒いミニスカートの法衣に、白いケープを纏っている。
あの格好は確か、月の教団の物だったとおもう。
夜空を見上げる女の子の金色の髪は後ろで一つにまとめられている。
「・・・」
なんだろう、そこに女の子がいるのに、いないようにも見える。
濡れた髪が淡く輝いてるように見えるからだろうか?
「・・・」
「こんばんは、どうされたんですか?」
「え?」
突然その女の子から話しかけられた。
「あ、いや、その、キミこそ傘も差さずにどうしたのかなって」
「心配してくださったのですね、ありがとうございます。そして
ごめんなさい。私の個人的な趣味で、傘を差さなかったんです」
そう言って頭を下げる女の子。
「そ、そうですか・・・でも風邪をひきますよ?」
「大丈夫です、こう見えても丈夫ですから」
そういって胸を張る女の子。その強調された胸に思わず目がいきそうに
なるのをこらえる。
「それでも、油断すると風邪をひきます。だから、これを使ってください」
俺は差している自分の傘を差し出す。
「でも」
「はい」
俺は無理矢理女の子に傘を持たせる。
「貴方はどうなされるんですか?」
「姉さんに傘を届けたら、一緒にいれてもらいます。だから大丈夫です」
女の子は困ったような顔をしている。
余計なお世話だったかもしれないかな・・・
「ありがとうございます、傘をお借りしますね」
にこっと笑う女の子の顔を見て、ほっとする。
「それじゃぁ、夜も遅いですから気をつけてくださいね」
「はい、貴方もお気をつけて」
「あら、達哉君。迎えに来てくれたの?」
「あ、姉さん」
そこには傘を差した姉さんが立っていた。
「あらあら、ずぶぬれじゃないの。達哉君の傘はどうしたの?」
「あぁ、そこにいる女の子に貸したんだ」
「女の子? 何処にいるの?」
「え?」
俺は慌てて女の子がいる方を見たけど、もうそこには誰もいない。
「あれ?」
「そんなことよりも達哉君、傘差さないと風邪ひくわよ」
「あ、うん」
俺は仕方なく持っていた姉さんの傘を差す。
「それよりも姉さん、傘持ってたんだ」
「えぇ、この前の雨の時に買った傘があったの。言ってなくてごめんなさいね」
「いや、いいよ。姉さんが濡れて風邪ひかなければそれに越したことは無いさ」
「ありがとう、達哉君。帰ろうか」
「うん」
月人居住区を後にする。
居住区を抜ける前に一度だけ振り返ってみる。
「・・・」
夜のとばりが落ちている居住区に人の気配は全くなかった。
俺は幻でも見ていたのだろうか?
「ただいま〜」
「おかえりなさい、お兄ちゃん、お姉ちゃん」
姉さんの傘を畳んで、傘立てに置こうとして・・・
「あれ?」
そこには俺の傘があった。
確かに出かけるときに俺が使って、あの女の子に貸した俺の傘。
それが何故か玄関にある。
傘を広げてみると、確かに雨で濡れていた。
「・・・」
「どうしたの、達哉君?」
「あ、いや、なんでもない」
「お兄ちゃん、お姉ちゃん。お茶が入ったよ〜」
「は〜い、行きましょう達哉君」
一体あれは何だったんだろうか?
幻をみたのだろうか、それとも何かに騙されたのだろうか?
「・・・」
明日礼拝堂へ行ってみるか、何かが判るかもしれないから・・・
11月3日
・夜明け前より瑠璃色な Moonlight Cradle SSS ”背中”
「参ったね、朝霧君」
突然の夕立に襲われた俺と翠は、翠の家に避難する事にした。
「もぅ、制服びっしょりだよ」
そういってスカートを気にする翠を見た俺は翠の制服が濡れて透けて
しまっていることに気付いた。
慌てて視線を逸らす。
「ん? どうしたの、朝霧君?」
「あ、いや、なんでもない。それよりも翠、タオルで身体拭かないと風邪
引くぞ?」
「そうだね、でも朝霧君も同じだよ?」
「俺は大丈夫だよ」
「そう言う人こそ風邪ひくんだよね、ほら、とりあえず上がって!」
そう言うと翠は俺の手を引いてリビングに案内する。
「はい」
「ありがと」
一度部屋に戻って着替えてきた翠からタオルを受け取る。
大雨で全身濡れてるせいか、シャツが張り付いて気持ちが悪い。
ここで脱ぐわけにもいかないから仕方がないか。
「ほら、朝霧君も制服脱いで」
「そ、そういうわけには・・・」
「大丈夫、お風呂わかしてあるから。その間に乾かしちゃうからね」
「そう言うことなら・・・」
「はい、一名様ご案内〜」
「ふぅ・・・」
張ってもらったお湯に使って一息つく。
雨に濡れた身体が芯から暖まっていくのがわかる。
「・・・広いな」
自分の家の風呂場もそれなりの広さがあると思ってたけど、こうしてみると
翠の家の風呂場は広い。
一人で湯船に使っても余裕がかなりあるくらいだ。
「朝霧君、湯加減どう?」
「あぁ、ちょうど良いよ。ありがとうな」
「それじゃぁ私も入ろうかな」
「・・・え?」
「お邪魔しまーすっ」
「お、おい、翠・・・」
慌てて視線を逸らそうとしたが間に合わず、そこにはタオルだけを巻いた
翠が立っていた。
「朝霧君、もしかして期待した?」
「・・・期待しようにもそんな時間すら無かったじゃないか」
「そっか、もう少しじらせば良かったんだね。こんなふうに?」
そう言うと翠はタオルの下の端を持ち上げる。
太股が全てあらわになって、そして・・・
「残念でした♪」
ばさっと言う音とともにタオルが床に落ちる。
そこには水着に包まれた翠が立っていた。
「今度は期待した?」
期待してしまった事を伝えたらなぜだか負けてしまう気がした。
「べ、別に・・・」
「んふふっ、強がりは良くないよ? 朝霧君♪」
「別に強がってなんて・・・」
「はいはい、それじゃぁ背中流してあげるからこっちに来て」
「・・・はい?」
「ほら、背中流してあげるの。早く出て来て」
「えっと、俺は水着着てないんですけど?」
「タオルがあるからだいじょぶでしょ?」
「でも」
「私じゃ、だめ?」
「・・・とりあえず向こう向いてくれないか?」
「じゃぁいくね。痛かったら言ってね」
そう言うと翠は俺の背中を洗い始める。
「どう? 朝霧君」
「もう少し強くてもいいかな」
「えっと、これくらいかな?」
いつも自分で洗う力にはほど遠い、でも手が届かない所まで洗って
もらえてるせいか、とても気持ちが良い。
「気持ち良いよ、翠」
「うんうん、私が洗ってるんだもの、当然よね」
「・・・朝霧君の背中って大きいよね」
「そうか?」
「うん・・・」
その時翠が俺の背中に寄りかかってきた。
「温かい・・・」
「み、翠?」
「私ね、家族でお風呂に入った事あまり覚えてないの」
「・・・」
「本当に小さい頃はお父さんもお母さんも一緒だったんだけどね。
二人とも忙しくなってきてからはいつも一人だった。
こうして家族の背中を流してあげたこと、あったのかな・・・
覚えてない」
・・・翠もいろいろとあるんだな。
今は手が届かない父さんの背中、か・・・
「でも、今は朝霧君がいてくれるから平気だよ」
そう言うとシャワーで背中の泡を流す。
「はい、おしまい。それじゃぁ今度は前を洗ってあげるね」
「え? 前はいいよ」
「何を恥ずかしがってるのかな、朝霧君。ここまで来たら一蓮托生だよ?」
「それ意味違うから、それよりも翠の背中流してやるよ」
「へ? あ、えっと・・・」
「・・・ごめん、聞かなかったことにして」
女の子の背中を洗うだなんて、俺には出来ない。
「ううん・・・その、良かったら洗って欲しい・・・かな。だめ?」
幸い翠が着てた水着はビキニで、上は紐だったので脱がずに背中を
流すことが出来る。
「それじゃぁ痛いかったら言えよ?」
「う、うん・・・よろしくおねがいします」
俺はスポンジにボディソープをなじませると、そっと翠の背中に
ふれる。
「やんっ!」
「あ、ごめん」
「あ、ちがうの。ちょっと冷たかったかなって、あはは・・・」
「そ、そっか。それじゃぁ続きを」
「う、うん・・・」
今度は驚かせないよう、そっとスポンジで背中を流す。
「あ・・・んっ、なんだかくすぐったいよ」
「そう言われても・・・」
「ん・・・それに、なんだか・・・えっちだよ」
「そ、そんなことは」
「本当に無いの?」
「・・・」
即答できなかった、翠の声に反応してる自分がいる。
「わ、私はね・・・その、お風呂に入るときから・・・」
「・・・」
「期待・・・してたんだよ? 達哉・・・」
「・・・翠」
外では恥ずかしいといって俺の名前を呼ばない翠。
その翠が俺の名前を呼ぶとき、それは・・・
「翠、いいのか?」
翠はこちらを振り向かないまま、そっと頷いた。
・
・
・
「ふぅ、温かいね〜」
二人で湯船に浸かる。
俺の胸に背中を預けるように翠も一緒に入っている。
「ねぇ、達哉、私の水着はどうだった?」
ビキニタイプの水着で、ブラの部分は布地面積が少なすぎる。
「・・・あれは駄目だ」
「え、なんで?」
「他のやつに見せたくない」
「た、達哉・・・言ってて恥ずかしくない?」
「そう言う翠も顔真っ赤だぞ?」
「わ、私はのぼせてるだけだよ」
「そうか?」
「うん・・・達哉にのぼせてるだけだから」
その一言で俺は思いっきりのぼせてしまった・・・
「ねぇ、達哉。他の人にも見られても良い水着、買いに行こうよ。
それでね、温水プールでデートしよっ!」
10月31日
・Canvas2 sideshortstory 「はろういんらぷそでぃ」
「ふっふっふっ、これで準備は完璧だ・・・ふぅ〜」
さすがに眠くなってきた。時計を見るともう3時を回っている。
エリスが自室に戻ってから俺は用意してあった材料を使ってこの時間まで
ひたすらクッキーを焼いていた。
「ハロウイン・・・これで乗り切れるな。でも少し作りすぎたか?」
こういうお祭りに参加してくるメンバーの顔を思い出す。
全員に渡してもかなりあまる量を焼いてしまった。
「まぁいいか。あとで美術部の連中に配っても」
最後のクッキーを袋に詰めて、紙袋にしまう。
「ふっ・・・俺って完璧」
朝まで時間はほとんどないが、少し寝ておくか。
朝、いつものように朝飯を作ってエリスを文字通りたたき起こしてから
学園へ向かう。
「せんせー、おはよー!」
「おはよう、萩野」
「せんせー、今日は」
「ほらよっ!」
萩野が何かを言う前にクッキーを小分けした袋を渡す。
「え、えー! 私まだ何も言ってないのにぃ」
「結果は同じだ」
「ぶーぶー、おーぼー!」
「・・・クッキー返せ」
「やだなぁ、せんせー。大人げないよ?」
慌ててクッキーの袋を後ろ手に隠す萩野。
「それじゃぁまたな」
これで最初の難関突破、朝一番で最大の難関を突破出来たことに俺は安堵
していた。
another view 可奈
「可奈、おはよー」
「おはよー」
クラスメイトの友達が登校してきた。
「あれ、それ何? クッキー?」
「うん、さっきせんせーからもらったの」
「先生って上倉先生?」
「そうだよ」
「いいなぁ、美味しそう。1個ちょうだい」
「あっ」
返事を待たずに袋を取ると、中から1個クッキーをとりだして食べてしまった。
「もぅ、私のなんだから!」
そう言って袋を取り戻す。
「・・・」
「あれ? どうしたの?」
「美味しい・・・これすっごく美味しいよ! もっとちょうだい!」
「だーめー! これは私のなの! そんなに欲しければせんせーにもらってくれば
いいじゃない!」
「えー、そんなの無理だよ。いくら最近丸くなってきたからって。
私は可奈ほど上倉先生と仲良く無いし」
「それじゃ、魔法の言葉教えてあげようか?」
「魔法の言葉?」
「うん、今日はハロウインだよ、だからね・・・」
another view end
「あら、こんな時間に職員室にいるなんてどうしたの?」
霧が職員室に入ってきた。
「そう何度も遅刻する訳にはいかないからな」
そうなんども遅刻したわけじゃないが、口うるさい教頭に捕まるのは
やっかいだった。
「あれ? その紙袋は何?」
「これはお菓子だよ」
「お菓子? 作ったの?」
「何で買ってきたっていう発想は無いんだ?」
「だって浩樹ですもの、それより私の分は?」
「おまえは子供か?」
「いいじゃない、けち・・・あ、そっか。浩樹、トリックオアトリート」
「ハロウインは子供のする事だぞ?」
「あら、浩樹は私の悪戯がご所望なのかしら?」
「はい、どうぞお納めください」
「返事が早いのが納得行かないけど、ありがと、浩樹」
「上倉先生、何をされてるんですか?」
「教頭・・・」
「神聖なる職員室でそのような行為をされるとは、どういう事ですかな?」
いや、行為ってお菓子をあげただけなのですけど。
教頭は何か勘違いしてるんじゃないだろうか?
「あら、いいではありませんか」
「理事長代理! おはようございます」
教頭の態度が180度変わる。
「おはようございます」
「おはようございます、教頭先生、上倉先生、桔梗先生」
俺達の挨拶にちゃんと挨拶する。
どこかの教頭と違って立派だった。
「上倉先生は季節の行事を生徒とともに大事にされてるのですわ。
とても立派だと私は思います」
「は、はぁ・・・確かに」
「ですから、問題あるどころか、立派な行動だと思いますけど、どう思いますか?
教頭先生」
「も、もちろん立派です、教師の鏡だと思います」
・・・よくわからないけど、俺は立派にされてしまった。
しばらくして教頭は俺の前から去っていった。
「ところで、上倉先生。Trick or Treatですわ」
「・・・はい?」
「あら、私にはお菓子をくださらないのですか?」
お菓子をねだるのは子供のはずだが、理事長代理の仕草は子供ぽっかった。
「えと、俺の手作りでよろしければどうぞ」
「ありがとうございます、これがそうなのですね。今日1日は大変でしょうけど
がんばってくださいね」
「大変?」
どういう意味だ?
「浩樹、大変よ!」
いつの間にか職員室からいなくなってた霧が戻ってきた。
「何がだ?」
「浩樹、貴方狙われてるわよ!」
「・・・はい?」
意味が分からない、なんで俺が狙われなくちゃならないんだ?
霧が話してくれた事情を聞く。
なんでも俺がとても美味しいクッキーを持ってる事がみなに知られていて
それを合理的にもらう魔法の言葉が知れ渡っているそうだ。
「・・・嘘だろ?」
「こんな嘘いってどうするのよ」
すでに撫子学園中にこの話は広がっていて、何人かの女生徒のグループが
俺を待ち受けているという話だった。
「いったいどうして・・・って考えるまでもないよな」
萩野可奈、犯人は一人しかいない。
犯人はわかったが、それで対処出来るわけではなさそうだ。
「どうするの、浩樹?」
「・・・逃げる、準備室で籠城する」
「それしかないわよね。がんばってね」
幸い1・2時間目の授業は無い。
1時間目の授業が始まるのを待ってから準備室へと無事に移動する。
そして鍵を閉める。
「よし・・・とりあえず寝るか」
当面の驚異よりも、昨日の寝不足の方がきついので眠ることにした。
コンコンと、ドアをノックする音が聞こえた。
「だ、誰だ?」
「・・・竹内です、呼んだのは先生じゃないですか」
「あ、あぁ、すまん。回りに竹内以外に誰かいるか?」
「少し遠目に何組かのグループがいますけど・・・」
「よし、今鍵を開ける」
俺は鍵を開けると竹内を引き寄せる
「きゃっ!」
そしてすぐに扉をしめて鍵もかける。
「せ、先生?」
「すまない、竹内。今はこうするしかないんだ」
「先生、今はまだ、その・・・お気持ちは嬉しいんですけど・・・」
「竹内?」
「は、はい!」
「今日のこの後の授業と部の事だが」
「・・・」
急にむすっとする竹内。
「どうした?」
「いえ、自分に腹が立っただけですから気にしないでください!」
なんだか急に機嫌がわるくなったようだが、今の俺にそれを模索する
余裕なんてなかった。
「実はだな・・・」
「なるほど、そう言うことなんですね。回りの女生徒が騒いでた理由が
ようやく解りました」
「だからこの後の授業を部を頼む」
不幸中の幸いというべきか、午前のこの後の授業は竹内のクラスだった。
美術部部長の竹内なら、俺が不在でも授業を進めることができる。
そしてそのまま放課後の部もまかせることが出来た。
「わかりました、事情が事情なのでお受けいたします」
「ありがとう、恩に着る」
「でも、私にもメリットが欲しいですね。上倉先生」
「・・・わかった、今の俺にはこれしかないけど、いいか?」
「ありがとうございます。これが噂になるほどの・・・」
竹内にクッキーを渡して、交渉は成立した。
早退も考えたが、手続きが面倒なのとあの教頭に会いたくないので
放課後部活動が終わるまでずっと準備室で過ごした。
「・・・むなしい」
どこでどう計画が頓挫したのだろう。
・・・もうそんなことはどうでもいいか。
「上倉先生」
ドアの外から竹内の声が聞こえる。
「今日の部活動が終わりました」
「そうか、いろいろ済まなかったな」
「いえ・・・その、クッキー美味しかったです」
「そ、そうか。ありがとう」
「はい、それでは失礼いたします」
竹内が去ってからしばらくしてから準備室から出る。
一度職員室に戻り日誌を提出する。
「ふぅ・・・もう大丈夫だろう」
「お兄ちゃん」
「!?」
突然声をかけられて驚いた。
「な、なんだ。エリスか・・・藤浪もいたのか」
「何よ、いちゃ悪いの?」
「いや、そんなこと無いが・・・もう遅い時間だからな。帰り気をつけろよ」
「・・・」
「藤浪?」
「ほら、朋子ちゃん」
「えと・・・その・・・」
何かを言いたいのに、なかなか言えない藤浪。
「はっ、もしかして校舎裏への呼び出し」
「そんなところに呼び出して何するのよ、変態!
ただトリックオアトリートって言えないだけよ!!」
「・・・」
「あっ・・・」
思いっきり言ってると思うぞ。
「まぁ、いっか。ほら」
俺は藤浪の手にクッキーの袋を手渡す。
「よかったね、朋子ちゃん」
「く・・・屈辱だわ」
喜ぶエリスと肩をふるわせる藤浪。
「と、ともかく俺は帰るぞ」
「あ、お兄ちゃん。私朋子ちゃん送ってから帰るね」
「あぁ、気をつけてな」
俺も送って行ってあげたいが、俺にはそこまでの余裕はなかった。
「ふぅ、疲れた・・・」
我が家に帰ってきた俺はそのままソファに倒れ込んだ。
何が原因だったのかわからないがもういい。
今日を無事乗り越えられたのだから・・・
「ただいま〜」
「おかえり」
リビングに入ってくるエリスは俺の目の前に立つととびっきりの笑顔を
俺に向ける。
「ねぇ、お兄ちゃん。言うこと聞いてくれないと悪戯しちゃうぞ!」
「・・・そこは普通、トリックオアトリートだろう?
お菓子をくれないと悪戯するんだろう?」
「だってお兄ちゃんお菓子いっぱい用意したんでしょ?
だったらこうしないと悪戯できないじゃない♪」
「・・・ごめん、もうお菓子で勘弁してください」
10月14日
・Canvas SSS”雨の誕生日”
「ふぅ・・・」
部屋の窓を開ける。空は雲で覆われている。まるで私の気分のようだ。
10月14日、今日は私の誕生日。
この日はいつも大輔と藍が私の誕生パーティーを開いてくれる日。
学生時代はささやかに、でも温かいパーティーだった。
卒業してから進路はばらばら、それでもこの日はみんなで集まるのが
当たり前になっていた。
私のモデルの仕事は、プロデュースが鷺ノ宮ブランド、つまり藍の会社
だからスケジュールはいくらでも調整が出来る。
でも、藍は社長としての仕事も、バイオリニストとしての仕事も多忙。
大輔も画家としてあちらこちらに呼ばれていて忙しい。
今日は3人が出会って初めての、誰もそろわない私の誕生日になってしまった。
「・・・雨」
気付くと雨が降ってきていた。
開け放してた窓をしめ、部屋の中に戻る。
パジャマ代わりに着ている大輔のYシャツ姿のまま、部屋からでる。
「おい、恋。ちゃんと服を着ろよ、目の毒なんだから」
「恋ちゃんとっても可愛いですわぁ」
いつもだったらそう聞こえてくる麻生家だけど、今日は何も聞こえてこない。
私はそのまま大輔の部屋へと向かう。
「・・・」
当たり前だけど、そこに大輔はいない。
描きかけの絵にカバーがかぶせてある。
「・・・大輔」
カバーをかぶせてあるキャンバスに手をかけて・・・離す。
私はそのまま、大輔のベットに倒れ込む。
「・・・ん、大輔の匂いがする」
大輔の掛け布団を身体を使って丸めて、抱く。
「大輔・・・」
寂しさが少し和らいだ気がする。たぶん、それは思いこみ。
だけど・・・
「温かい」
そっと目を閉じる。
「早く帰ってきてよね、大輔。
でないと、可愛い恋ちゃんの誕生日が終わっちゃうよぉ・・・大輔・・・」
・
・
・
「ん・・・」
「おはよう、恋」
「え・・・大輔?」
気付くと目の前に大輔がいる。嘘・・・じゃないよね?
「な、なんで起こしてくれないのよ!」
「あまりにぐっすりだったから、起こすの悪いかなって思ってさ」
「でも、起こしてくれたら大輔と一緒にいられたのに」
「恋?」
「あ、今の無し! なんでもない! 違うの!」
私ったら何言ってるのよ!
「ごめん、先方の誘い断って急いだんだけど・・・それは理由にならないな。
ごめんな、恋。寂しい想いさせちゃって」
そっと私は大輔に抱かれる。
「・・・ばかっ、そう思うなら、もっともっと優しく抱いてよ」
「ごめんな、恋。それと・・・」
「大輔?」
「誕生日おめでとう、恋」
「・・・ありがとう、大輔」
10月14日
・FORTUNE ARTERIAL SSS”えりにゃたんじょう”
ばさっ!
突然ベランダから物音がする。
「またかなでさんか?」
たまには表から入ってきて欲しいんだけどな、そう思いながら俺は
ベランダの扉を開ける。
「・・・あれ?」
ベランダには誰もいない。確かに何かの気配は会ったはずなのに・・・
「孝平、扉閉めて」
「瑛里華?」
いつの間に部屋の中に?
俺は扉を閉めてから振り返り・・・
「・・・え?」
そこには確かに瑛里華と思われる人物が存在していた。
・・・いや、人物って言っていいのか?
「瑛里華・・・だよな?」
「私が他の誰にみえるのよ!」
「いや・・・その、俺が知っている瑛里華と姿が違うんだけど」
そう、そこにいるのは確かに瑛里華だとおもう。
でも身長がいつもの半分くらいに縮んでいるし、何より頭に猫の耳っぽい
ものがついている。
「これ本物か?」
俺はその耳っぽいものをつまんでみる。
「いた、いたいにゃ! 孝平やめて!」
「・・・」
今発音がおかしかった気がする。
「もぅ、いきにゃり耳をひっぱらにゃいでよ」
耳をそっと手で押さえる瑛里華・・・いや、えりにゃと言うべきだろうか?
「・・・そう言えば今夜は雨だったよな」
「気持ちは分かるけど、いきにゃり現実逃避しにゃいでよね・・・」
逃げるのに失敗した。
「気付いてたらこうにゃってたのよ。私も初めてで、どうしたらいいか
わからにゃくて」
「俺もどうしたらいいかわからないぞ?」
「うー・・・やっぱり兄さんに聞くしかにゃいのかなぁ」
伊織さんに相談したとしたら・・・きっと面白がられるな。
「もしこのままだったらどうしよう?」
「大丈夫だよ、瑛里華。きっとなんとかなるさ」
「孝平・・・ありがとうにゃ」
そう言って俺に寄りかかってくるえりにゃ。
「・・・ん?」
今頃気付いたけど、瑛里華のお尻の所からしっぽが生えていた。
「へぇ、しっぽまであるんだ」
俺はしっぽをさわってみる。
「ふにゃぁん!」
「へ?」
突然えりにゃが声を上げた。
「どうしたんだ?」
「にゃ、にゃんだかびりっときたの」
「どれ?」
「にゃっ、そんにゃに強くにぎらにゃいで・・・あん」
突然色っぽい声をあげるえりにゃ。
「もぅ・・・やめて」
「あ、あぁ、ごめん」
「・・・」
「瑛里華?」
「やっぱりやめないで・・・孝平がその気にさせたんだからね?」
「はい?」
「孝平・・・」
そう言うとえりにゃは俺に覆い被さって・・・
ごんっ!
「いたっ!」
俺は床に頭をぶつけていた。どうやたベットから落ちたらしい。
「いてて・・・しかしなんて夢だよ」
瑛里華に猫みみ・・・結構可愛かったかも。
ばさっ!
突然ベランダから物音がする。
「・・・」
どこかで見た展開のような気がする・・・
俺はおそるおそるベランダの扉をあける。
「・・・」
そして知っている展開の通り、そこには誰もいない。
と、いうことは・・・
「孝平、扉閉めて・・・」
10月14日
・FORTUNE ARTERIAL SSS”魔女の正装”
「ねぇ、孝平。どう?」
俺の目の前にいる瑛里華はいつもと違う服装をしていた。
着ている服は、そのままどこかの学校の制服って言われてもおかしくない
オーソドックスなブレザータイプのYシャツにベスト、プリーツスカートに
ネクタイまでしている。
「・・・それ、何の仮装だ?」
それだけなら普通の服装なのだが、その上から黒いマントを羽織っており、
頭には三角帽子、わかりやすく、魔法の杖っぽいものまで持っている。
「ハロウィンの魔女よ、見てわからない?」
「いや、魔女っていうより魔法少女っぽい格好だよな」
確かに魔女っていわれればそう見えないこともないけど、やはりマントの下に
来ているのがどこかの学校の制服っぽいから、魔法少女の仮装にしかみえない。
「んー、魔法少女って言われる方が可愛くて魔女より良いわね。
ありがと、孝平」
「どういたしまして。で、その衣装を着てどうするんだ?」
「もちろん、今度のハロウィンパーティーを盛り上げる為よ!」
生徒会と白鳳寮、共同で行われるハロウィンパーティー。
そのための準備と言うことか。
「なぁ、瑛里華。俺達は裏方だぞ?」
「わかってるわよ、でも気分くらい味わせてくれたっていいじゃないの」
気分を味わうって、魔女の仮装してる段階で楽しむ気満々だろうに。
「ねぇ、孝平。Trick or treat!」
「へ?」
「どうなの? 孝平」
いきなりそう言われても、何も準備なんてしていない。
「くすっ、それじゃぁ悪戯しちゃおうかな」
そう言う瑛里華の目は紅く光っている。
「って、瑛里華。なんで目が紅いんだ?」
「さぁ、何ででしょうね? くすっ、孝平。
今日は私も黒のストッキング穿いてるのよ?」
確かに普段は素足の瑛里華が珍しく黒いストッキングを穿いている。
「孝平は、どうしたい?」
靴を脱いだ瑛里華の足が迫ってくる。
「でも、孝平の意見は聞いてあげない。
だって、私が悪戯するんですもの、ふふっ」
今夜の瑛里華は魔女でも魔法少女でも、吸血鬼でも無く。
サキュバスと呼ばれる存在そのものだった・・・
10月12日
・夜明け前より瑠璃色な Moonlight Cradle SSS ”帰還”
今日もなんとか仕事を終えた俺は部屋で一息つく。
「参ったなぁ・・・」
今日も上司にお見合いを勧められた。
「だから、俺は誰ともつきあう気は無いんですって」
「そうは言ってもいられんだろう?」
善意から進めてくるお見合い、でも相手にとって善意であっても
俺にとってはそうではない。
「姉さんに相談出来れば良いんだけど・・・」
最高責任者であった姉さんはまた月へと留学している。
そのため館長も館長代理も不在の博物館、館長代理の代理が、今の俺の上司。
「・・・ふぅ」
別に俺だって女の子に興味が無い訳じゃない。
だけど、どんなに綺麗な人を見ても可愛い人を見ても・・・
「リースには敵わないよな」
リースとの約束、俺が出来るただ一つの事。
それは、リースの帰ってこれる場所を守ること。
だから俺は誰ともつきあわない、だって俺の横はリースの為の場所なんだから。
「・・・」
「タツヤ・・・」
・・・なんだ? 疲れてるから寝させてくれないか?
「起きて、タツヤ」
誰だ? 俺を起こそうとするのは・・・
「もぅ、おっきろーー!」
「うわっ!」
いきなり耳元で大声を出された俺は勢いあまってベットから転がり落ちた。
「いてて・・・起こすならもうちょっと優し・・・く?」
ベットに腰掛けている、俺を起こした人物は姉さんや麻衣じゃなかった。
黒いミニスカートの法衣に、白いケープ。胸元のペンダントは月の教団の物だ。
黄金色に輝く髪を後ろで一つにまとめた、優しそうな顔をした女の子。
「・・・誰だ?」
「もぅ、忘れちゃったの? 私よ、わ・た・し!」
・・・忘れる以前に見覚えが無いんですけど。
「今日の話聞いたわよ、タツヤ。私のためにお見合い断ってくれたんでしょう?」
お見合い・・・断る、私のため?
「その話聞いてもう我慢できなくなっちゃって、帰ってきたの!」
「えっと?」
「だから、今日から一緒よ! タツヤ!」
そう言うと俺に抱きついてきた。
「わわっ!、離れて!」
「どうして?」
「どうしてって、その・・・」
ふくよかな胸が押しつけられる感触が、その、たまらないからなんて言えない。
「ははーん、そーゆーことか」
女の子の顔が何かを見つけたような、なんていうか、そのたくらんでいるって
いうか、そう言う表情になった。
女の子は俺から離れる。
俺はそっと息を付く。
「ねぇ、タツヤ。見て」
「っ!」
女の子は自分で胸を持ち上げる。
「ほら、タツヤの為にこんなにおっきくなったんだよ?
タツヤだけのおっぱいだよ?」
そういって自らの胸をもむ。服の上からでも柔らかいってわかる、その動き。
「だから、ね? タツヤ」
彼女の紅い瞳に、俺は引き寄せられそうになる。
・・・?
紅い・・・瞳?
違う、リースの瞳は翠色だ。紅い瞳は・・・
「っ! 痛っ!」
俺はベットの上から転げ落ちたようだ。
慌てて部屋の中をみると、誰もいない。仕事から帰ってきたときの状態から
何も変わっていない。
「・・・寝ちゃったのか」
スーツの上着だけを脱いだまま、俺はどうやら寝てしまってたらしい。
皺になるので部屋着に着替えてスーツはハンガーに掛ける。
「しかしなんて夢なんだよな・・・」
よく考えてみれば、リースだって成長しているのだから、将来スタイルが
良くなるのが当たり前だ。
だからといって・・・
「あれはさすがにないだろう」
自分の夢に自分でツッコミをいれる。
「・・・ふぅ」
風呂にでも入ってさっぱりするか。
「くすっ」
このとき朝霧家遥か上空で、長いポニーテールを風に揺らされている女の子が
いただなんて、俺はそれこそ、夢にも思わなかった。
10月7日
・夜明け前より瑠璃色な sideshortstory 「巫女麻衣前夜」
「ねぇ、お兄ちゃん。相談があるんだけどいい?」
姉さんが仕事で帰ってこれない夜、二人だけの食事が終わった後
麻衣はお茶を持ってきながら俺に相談を持ちかけてきた。
「俺でよければいいぞ」
「ありがと、お兄ちゃん」
そう言うと麻衣は俺の横に座る。
「その前にお願いがあるの。相談、笑わないでちゃんと答えてね」
「あ、あぁ・・・」
麻衣がそこまで言う相談って一体なんなんだ?
なんだか緊張してきた。
「あのね、お兄ちゃん。巫女さんの着ている服って知ってる?」
「巫女? 神社にいる女性の事か?」
「うん」
巫女を思い浮かべてみる。
昔の和装っぽい、白い着物と赤い袴。たぶんこの巫女であってると思う。
「わかるけど、それが何?」
「あのね、巫女さんの袴だけど・・・普通の長いのとミニとどっちが良いと思う?」
「・・・へ?」
思わず変な声が出る。
「いまいち意味がわからないんだけど・・・」
「ねぇ、どっちが良いと思う?」
麻衣は真剣だった。だから真剣に考えてみる。
あの巫女さんの袴がミニだったとしたら・・・
麻衣が着たら可愛いかもしれないな。って、麻衣が着てどうするんだ?
それに可愛いだろうけど、何か違う気がする。
ミニの袴の巫女さんというのが上手く想像できないせいもあるのか、やっぱり
オーソドックスの方が良い気がする。
「よくわからないけど、俺は普通の方が良いんじゃないかと思う」
「そっか、ありがとう、お兄ちゃん」
麻衣は笑顔でお礼を言う。
「これくらい大したこと無いけど、相談ってこれだけ?」
「うん♪ それじゃぁ私、お風呂にお湯入れてくるね」
「あ、あぁ。よろしく頼む。俺はイタリアンズの散歩に行ってくる」
「いってらっしゃい、お兄ちゃん」
このときの答えの結果は後日学園祭で知ることになった。
学園祭での「舞」を見て、ミニじゃなくて良かったと心の底から思った。
あの舞をミニで舞ったら、見えてしまうかもしれないからだ。
「というわけで、遠山。言い訳を聞かせてもらおうか?」
学園祭の時には逃げられた遠山を捕まえる。
「やだなぁ、朝霧君。この前言ったじゃない。麻衣が舞うから舞いだって」
「その話じゃなく、巫女装束の事だ」
「それはほら、朝霧君の好みの方がいいかなぁって・・・ね?」
「・・・」
「・・・」
「遠山?」
「ごめんなさい」
わかってくれたようだ。
「今度からもうちょっと朝霧君の好みをリサーチするね。やっぱり体操着とか
学園指定水着とかの方が良かった?」
「違うだろ!」
わかってくれなかった・・・
10月4日
「ん〜」
目が覚めた私はベットの上で身体を伸ばす。
「ふぅ」
なる前の目覚ましのスイッチを切り、ベランダへ通じる扉を開ける。
「空気が澄んでて気持ちがいいな」
朝特有の澄んでいる空気を身体いっぱいにあびて、空を見上げる。
朝日が昇ったばかりの雲一つない青空。
「うん、今日もがんばるぞ!」
・FORTUNE ARTERIAL sideshortstory「特別な特別」
「あ、おはよう! 孝平くん」
「おはよう、陽菜。待たせちゃったか?」
「ううん、そんなに待ってないよ」
談話室で孝平くんが来るのを待つ朝、約束した訳じゃないけど、それが
私の、私たちの朝の始まり。
「それじゃぁ行こうか」
「うん」
寮を出て私は空気の冷たさにちょっと驚く。
「朝晩は少し冷え込んできたね」
「そうだな、ついこの前まで夏だったのに、もうすっかり秋だな」
そう言いながら孝平くんはそっと私に手を出す。
いつもなら手をつないで一緒に登校する所だけど。
「えいっ!」
「え?」
孝平くんの差し出してくれた腕に私は抱きつく。
「こうすると暖かいよね」
「あ、まぁ・・・そうだけど・・・」
孝平くんが何か気まずそうな顔をしてる。ちょっとやり過ぎちゃったかな?
「その、陽菜・・・当たってる」
抱きつくと言うことは、孝平くんの腕は私の胸の中にある。
「くすっ、私の胸は嫌い?」
「そんなこと無い!」
即答してくれる孝平くん。
「でも、その・・・朝から我慢出来なくなるとまずいから」
「そっか、残念だけど学校遅れるわけにいかないものね」
私は腕をほどくと、そっと手をつなぐ。
「それじゃぁいこう、孝平くん」
「おはよう!」
「あ、おはよう陽菜。今日誕生日なんでしょう? おめでとう!」
「ありがとう」
教室に入るとみんなが集まってきておめでとうってみんなが言ってくれた。
「ねぇ、誕生会はどうするの? もう予定あるの?」
「特に無いよ」
「え? なんで?」
驚いた顔をするクラスメイト。
「みんな忙しいから、特に何かするっていう事はないの」
「・・・」
「ねぇ、支倉君。どういうこと?」
クラスメイトの一人が孝平くんに尋ねる。
「陽菜が言ったとおりさ。特に何も無い」
「どうして? 支倉君は悠木さんの彼なんでしょう?」
「だからだよ、陽菜が望むならそうしてあげたいから」
そう、誕生会をしないと言うことを望んだのは私。
孝平くんもみんなも忙しいし、それに私には孝平くんがいてくれるから。
それだけで良かったから。
「でも!」
その時孝平くんは小声で何かを伝えたみたい。
その言葉を聞いたクラスメイトは納得してくれたみたいだった。
「陽菜さん、誕生会がなくてもプレゼントは受け取ってくれるよね?」
「もちろんだよ、ありがとう!」
「陽菜、昼は学食?」
「うん、委員会に行く前に食べていくよ」
「一緒に行くか?」
「うん♪」
食券の販売機の前で私はちょっと悩む。
今日は何にしようかな・・・うーん、たまにはこれにしてみようかな。
「えい」
そうして出てきた食券を持って調理場の方へと向かう。
「あれ?」
「え?」
私が頼んだのは焼きそば。孝平くんが頼んだのはみそラーメン。
「孝平くん、珍しいね」
「陽菜こそ珍しいな」
「うん、私はちょっと気分転換、かな」
「・・・俺も」
「・・・そうだ、良い考えがある」
「何?」
「陽菜、こう言うのはどう?」
この日の昼食は私も孝平くんも半ラーメンに半やきそばになった。
午後は美化委員の仕事。
制服に着替えて校内の美化に努める。
孝平くんは監督生室にいってたまった仕事をかたづけるそうだ。
本当は美化委員の活動の監督に来て欲しかったんだけど、お互いのするべき
事をする、それが私たちの約束だから。
「でも、残念」
「おつかれ、陽菜」
「あれ? 孝平くん。今日はもう終わりなの?」
私が制服に着替えて出てきたところに孝平くんが待っていた。
「あぁ、なんとかな。少し残ってるけど会長に追い出された」
「千堂さんに?」
「早く帰りなさいってさ。」
「そっか、後でお礼言っておかないとね」
「そうだな。陽菜、夕食食べてから帰るか?」
「うん、ご一緒していいかな?」
「もちろんだよ」
寮で一度別れた後、私は部屋に戻って部屋着に着替える。
「今日は・・・うん、あの入浴剤を使ってみようっと」
この前買ってきた入浴剤を試したいから、今日は部屋備え付けの
お風呂に入ることにする。
「どんな感じかな、楽しみ」
お風呂上がりは談話室でみんなからお祝いを受けた。
誕生会を開かなかったけど、有志で集まったみんなの気持ちを
受け取らないわけにはいかない。
「ありがとう、みんな!」
「ちょっと遅くなっちゃった」
みんなに囲まれて帰るに帰れず、いつもよりちょっと遅い時間に
孝平くんの部屋に着く。
お茶会、もうみんな始めちゃってるかな?
「陽菜、待ってたよ」
「ごめんね、待たせちゃって」
部屋の中にはみんながそろっていた。
「それじゃぁお茶会始めましょう!」
千堂さんの一言でお茶会は始まった。
9時を過ぎてお茶会は解散。
私は洗い物をするために部屋に残っていた。
「結局みんなにお祝いもらっちゃったね」
「いいんじゃないか? みんなの気持ちなんだから」
お茶会は小さな誕生会になった。
「うん、そうだね、とても嬉しかった」
「・・・なぁ、陽菜。一つ聞いていいか?」
「何?」
「なんで、誕生会を断ったんだ?」
誕生日が近づいた頃、誕生会の話を私から断った。
「だってみんな忙しいでしょう? その上に準備の時間を増やしたら
大変なことになっちゃうから」
「そうだけどさ、せっかくの特別な日なんだからさ」
「ねぇ、孝平くん」
「何?」
私は洗い物の手を止めて、孝平くんに向かう。
「私に特別じゃない日なんて、ないよ」
「陽菜?」
「孝平くんにまた会えた、そしてもう一度孝平くんを好きになれた。
そして、彼女にしてもらえた」
「・・・」
「こうして毎日を過ごせる私にとって、毎日が特別だよ?」
「・・・俺の負けだよ」
「それじゃぁ私の勝ちかな?」
「なら陽菜。今日は特別の中の特別な日にしよう!」
「孝平くん・・・きゃっ」
私は孝平くんの胸の中に抱きしめられた。
「改めて言うのも恥ずかしいけどさ・・・
陽菜、誕生日おめでとう」
「孝平くん・・・ありがとう」
私はそっと目を閉じる。
「・・・んっ」
特別な毎日の中の、特別な日のプレゼントは、私が一番欲しい物だった。
「やっぱり私の負け、かな。ねっ、孝平くん!」
[ 元いたページへ ]
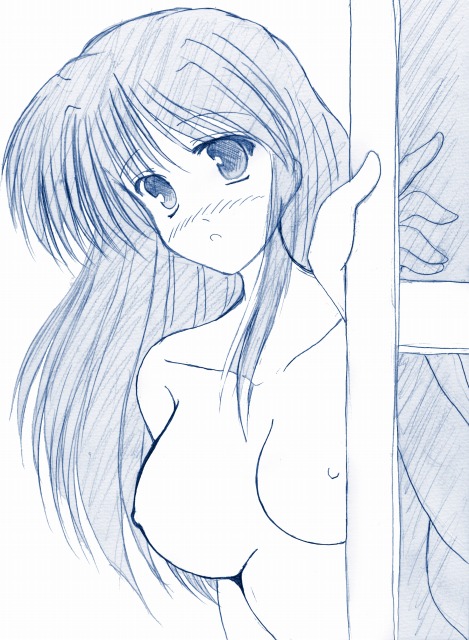 俺の制止の言葉は遅く、風呂場へ通じる扉が開かれる。
そこには一糸纏わぬアイツが・・・
「・・・」
「・・・」
俺はとっさにアイツを抱きしめる。
「いいか、まず落ち着け!」
俺は濡れたアイツの髪をそっと撫でる。
こうするとアイツは落ち着くからだ。
「俺が今日きたのはおばさんに捕まったからだ、そしてここにいるのは事故に
過ぎない、わかるか?」
「う、うん・・・」
「それでな、このまま悲鳴をあげられるとおばさんにからかわれる、だから
落ち着け」
「・・・もう、だいじょうぶだよ」
「そっか・・・」
とりあえず最大の危機は脱出できたようだった。
「心の準備が無いと大変だけどね、いまはもう大丈夫だよ」
「準備?」
「だって、キミのここが・・・その、私のお腹に・・・」
裸のアイツを抱きしめてる俺は、どうやらしっかりと反応してしまっていた。
「だから、いいよ・・・」
「いや、今は駄目だ。おばさんに見つかったらそれこそ取り返しがつかない」
俺は理性を総動員して、このまま押し倒したい衝動を抑える。
「いいか、俺はこれから目をつむる。そして回れ右してここを出る。
おまえは湯冷めしないようもう一度暖まってから出てこい。わかったな?」
「う、うん・・・残念だけどそうするね」
俺はまず目を閉じてアイツから離れる。
その瞬間、唇に軽い何かが触れる感触があった。
「また後でね」
「・・・」
洗面所から出た瞬間、俺はその場に座り込んだ。
「あらあら、とんだハプニングだったわね〜」
気付くとおばさんがそこに立っていた。
「確信犯でしょう?」
「今回は違うわよ」
「本当ですか?」
「本当よ、誓ってもいいわ」
そこまで言われると今回は本当のハプニングだったんだろう。
「だって、狙ってた場合なら、こんなに美味しいシチュエーション見逃す訳
ないじゃない♪」
「・・・」
今回は本当に偶然だったようだ・・・
「あら、洋服濡れちゃってるわね、どうしたの? お湯でもかけられた?」
「いえ、その・・・」
抱きしめたとはとても言えない。
「そのままだと風邪ひいちゃうわよ、ほら、乾かすから脱いで」
「脱いでって、俺代わりに着る物ないですよ?」
「お風呂でもはいってなさい、その間に乾かしておくから」
確かにそれなら問題なさそうに聞こえるが・・・
「今、アイツが入ってますよ?」
「あらぁ、そうだったかしら?」
今度は確信しての犯行だった。
お詫びにっていう理由でこの日の夕食をごちそうになっていくことになった。
何故かその場に俺のおふくろが招待されているのが気になるが、これも深く
追求しちゃ行けないことなんだろうな。
「それでどうだった? 我が娘の一糸纏わぬ姿は?」
「お母さん、恥ずかしいこと聞かないでよ」
「いいじゃない、私たちの最高傑作なんだから♪」
「ちゃんと見て無いのでコメント出来ません」
「へたれね、据え膳食わねば男の恥って言葉しらないの?」
「おふくろが息子に言う言葉ですか・・・」
「へたれじゃないわよ、純情なだけよ、ねぇ?」
「おばさん、もう勘弁してください・・・」
夕食に招待されたことを後悔し始めた瞬間だった。
俺の制止の言葉は遅く、風呂場へ通じる扉が開かれる。
そこには一糸纏わぬアイツが・・・
「・・・」
「・・・」
俺はとっさにアイツを抱きしめる。
「いいか、まず落ち着け!」
俺は濡れたアイツの髪をそっと撫でる。
こうするとアイツは落ち着くからだ。
「俺が今日きたのはおばさんに捕まったからだ、そしてここにいるのは事故に
過ぎない、わかるか?」
「う、うん・・・」
「それでな、このまま悲鳴をあげられるとおばさんにからかわれる、だから
落ち着け」
「・・・もう、だいじょうぶだよ」
「そっか・・・」
とりあえず最大の危機は脱出できたようだった。
「心の準備が無いと大変だけどね、いまはもう大丈夫だよ」
「準備?」
「だって、キミのここが・・・その、私のお腹に・・・」
裸のアイツを抱きしめてる俺は、どうやらしっかりと反応してしまっていた。
「だから、いいよ・・・」
「いや、今は駄目だ。おばさんに見つかったらそれこそ取り返しがつかない」
俺は理性を総動員して、このまま押し倒したい衝動を抑える。
「いいか、俺はこれから目をつむる。そして回れ右してここを出る。
おまえは湯冷めしないようもう一度暖まってから出てこい。わかったな?」
「う、うん・・・残念だけどそうするね」
俺はまず目を閉じてアイツから離れる。
その瞬間、唇に軽い何かが触れる感触があった。
「また後でね」
「・・・」
洗面所から出た瞬間、俺はその場に座り込んだ。
「あらあら、とんだハプニングだったわね〜」
気付くとおばさんがそこに立っていた。
「確信犯でしょう?」
「今回は違うわよ」
「本当ですか?」
「本当よ、誓ってもいいわ」
そこまで言われると今回は本当のハプニングだったんだろう。
「だって、狙ってた場合なら、こんなに美味しいシチュエーション見逃す訳
ないじゃない♪」
「・・・」
今回は本当に偶然だったようだ・・・
「あら、洋服濡れちゃってるわね、どうしたの? お湯でもかけられた?」
「いえ、その・・・」
抱きしめたとはとても言えない。
「そのままだと風邪ひいちゃうわよ、ほら、乾かすから脱いで」
「脱いでって、俺代わりに着る物ないですよ?」
「お風呂でもはいってなさい、その間に乾かしておくから」
確かにそれなら問題なさそうに聞こえるが・・・
「今、アイツが入ってますよ?」
「あらぁ、そうだったかしら?」
今度は確信しての犯行だった。
お詫びにっていう理由でこの日の夕食をごちそうになっていくことになった。
何故かその場に俺のおふくろが招待されているのが気になるが、これも深く
追求しちゃ行けないことなんだろうな。
「それでどうだった? 我が娘の一糸纏わぬ姿は?」
「お母さん、恥ずかしいこと聞かないでよ」
「いいじゃない、私たちの最高傑作なんだから♪」
「ちゃんと見て無いのでコメント出来ません」
「へたれね、据え膳食わねば男の恥って言葉しらないの?」
「おふくろが息子に言う言葉ですか・・・」
「へたれじゃないわよ、純情なだけよ、ねぇ?」
「おばさん、もう勘弁してください・・・」
夕食に招待されたことを後悔し始めた瞬間だった。
 「どう・・・かな?」
白いワンピースの水着、胸元に赤い小さなリボンが付いている。
先ほどより薄手の生地で・・・スクール水着が厚すぎるのだが、その差を
ボディラインがはっきりと教えてくれている。
大きな胸から細いウエストへと続くラインは腰回りで柔らかくふくらんでいる。
「・・・か」
「可愛いわ〜、さすが我が娘よね。スクール水着じゃなくても充分悩殺出来るわね」
「やっぱり女の子は良いわよね〜、ね、早く家にお嫁に来ない?」
「だめよ、お嫁になんかあげないわ。彼に婿に来てもらうんだから」
「・・・ふぅ、あの二人は放っておいて泳ぎに行くぞ」
「・・・うん」
苦笑いしながらアイツは俺に付いてくる。
「仲が良いよね、お母さん達」
「良すぎるのも問題だけどな」
「・・・」
「・・・」
「・・・可愛いよ」
「え?」
「ほら、泳ぎに行くぞ!」
俺はアイツの手を取ってプールサイドを歩き出す。
「ねぇ、今なんて言ったの? もう一度言って欲しいな」
「言えるか!」
「いぢわる」
そう言いながら微笑むアイツの顔は凄くまぶしかった。
「どう・・・かな?」
白いワンピースの水着、胸元に赤い小さなリボンが付いている。
先ほどより薄手の生地で・・・スクール水着が厚すぎるのだが、その差を
ボディラインがはっきりと教えてくれている。
大きな胸から細いウエストへと続くラインは腰回りで柔らかくふくらんでいる。
「・・・か」
「可愛いわ〜、さすが我が娘よね。スクール水着じゃなくても充分悩殺出来るわね」
「やっぱり女の子は良いわよね〜、ね、早く家にお嫁に来ない?」
「だめよ、お嫁になんかあげないわ。彼に婿に来てもらうんだから」
「・・・ふぅ、あの二人は放っておいて泳ぎに行くぞ」
「・・・うん」
苦笑いしながらアイツは俺に付いてくる。
「仲が良いよね、お母さん達」
「良すぎるのも問題だけどな」
「・・・」
「・・・」
「・・・可愛いよ」
「え?」
「ほら、泳ぎに行くぞ!」
俺はアイツの手を取ってプールサイドを歩き出す。
「ねぇ、今なんて言ったの? もう一度言って欲しいな」
「言えるか!」
「いぢわる」
そう言いながら微笑むアイツの顔は凄くまぶしかった。
 そのスカートは寒くなったこの時期に着るには厳しいほど、ミニだった。
膝上何センチっていうより股下何センチレベルのミニスカート。
さっきから立ったり座ったりするたびに太股と、その先の白い布地が
目に毒だった。
「・・・そのスカート、短すぎないか?」
「そう?」
「見えちゃうぞ」
「別にいいよ、だって見てるのってキミだけだもん」
「・・・俺だって男なんだぞ? 我慢出来なくなったらどうするんだ?」
「別に良いよ、我慢なんかしなくたって・・・」
そう言って俺にすり寄ってくる。
そしてそっと目を閉じて・・・
「ちょっと待て」
「えー?」
「えーじゃない、こう言うときはたぶんな・・・」
俺は立ち上がって部屋の扉を開ける。
「あら?」
そこにはあいつのお母さんが扉に張り付いてる格好のままで固まっていた。
「何してるんですかおばさん」
「もう、いつもいってるでしょう? 私のことはお義母さんって呼んでって♪」
「お母さん、なんでドアのすぐ外にいたのよ!」
「我が娘の成長を確かめるためよ!」
「・・・で、本音は」
「お母さんも混ぜて欲しいなって」
俺のツッコミに即返事する。
「だーめ! 私だけのもんだもん!」
「娘の物は母の物っていうことわざが」
「あるわけないです!」
「えぅ」
俺のツッコミに涙を流すおばさん。
「もぅいいから出ていってよ!」
「えーん、私も一緒に遊びたいのにぃ・・・」
「・・・」
はぁ、あれで俺のおふくろと同じ歳だなんて思えないよな。
性格はさすがは俺のおふくろの親友だけのことはあると思う。
「それじゃぁゲームの続きしよう♪」
「構わないけど、おまえ絶対負けるぞ?」
「んー・・・良いよ、だって勝てる自信ないもん」
「おい」
「キミに惚れた弱みってやつ?」
・・・また来た。
油断した瞬間を狙うように俺の心に入り込んでくる一言。
「だから勝てないよ、私はキミに」
「ふぅ・・・完敗だよ」
「え? なんで? 私一度も勝ってないよ?」
惚れた弱みなら俺の方が上だろうな。
「どうして私が勝ちなの?」
「いいからそう言うことにしておけよ、今日だけだからな?」
「んー、それじゃぁ私が勝ったご褒美欲しいな」
頭をがしっとつかむ。
「えぅ」
「調子に乗るな」
すぐ調子に乗る、だけど・・・
「俺の負けだからな」
「え? ・・・うん♪」
嬉しそうに目を閉じるアイツに、俺は苦笑いした。
そのスカートは寒くなったこの時期に着るには厳しいほど、ミニだった。
膝上何センチっていうより股下何センチレベルのミニスカート。
さっきから立ったり座ったりするたびに太股と、その先の白い布地が
目に毒だった。
「・・・そのスカート、短すぎないか?」
「そう?」
「見えちゃうぞ」
「別にいいよ、だって見てるのってキミだけだもん」
「・・・俺だって男なんだぞ? 我慢出来なくなったらどうするんだ?」
「別に良いよ、我慢なんかしなくたって・・・」
そう言って俺にすり寄ってくる。
そしてそっと目を閉じて・・・
「ちょっと待て」
「えー?」
「えーじゃない、こう言うときはたぶんな・・・」
俺は立ち上がって部屋の扉を開ける。
「あら?」
そこにはあいつのお母さんが扉に張り付いてる格好のままで固まっていた。
「何してるんですかおばさん」
「もう、いつもいってるでしょう? 私のことはお義母さんって呼んでって♪」
「お母さん、なんでドアのすぐ外にいたのよ!」
「我が娘の成長を確かめるためよ!」
「・・・で、本音は」
「お母さんも混ぜて欲しいなって」
俺のツッコミに即返事する。
「だーめ! 私だけのもんだもん!」
「娘の物は母の物っていうことわざが」
「あるわけないです!」
「えぅ」
俺のツッコミに涙を流すおばさん。
「もぅいいから出ていってよ!」
「えーん、私も一緒に遊びたいのにぃ・・・」
「・・・」
はぁ、あれで俺のおふくろと同じ歳だなんて思えないよな。
性格はさすがは俺のおふくろの親友だけのことはあると思う。
「それじゃぁゲームの続きしよう♪」
「構わないけど、おまえ絶対負けるぞ?」
「んー・・・良いよ、だって勝てる自信ないもん」
「おい」
「キミに惚れた弱みってやつ?」
・・・また来た。
油断した瞬間を狙うように俺の心に入り込んでくる一言。
「だから勝てないよ、私はキミに」
「ふぅ・・・完敗だよ」
「え? なんで? 私一度も勝ってないよ?」
惚れた弱みなら俺の方が上だろうな。
「どうして私が勝ちなの?」
「いいからそう言うことにしておけよ、今日だけだからな?」
「んー、それじゃぁ私が勝ったご褒美欲しいな」
頭をがしっとつかむ。
「えぅ」
「調子に乗るな」
すぐ調子に乗る、だけど・・・
「俺の負けだからな」
「え? ・・・うん♪」
嬉しそうに目を閉じるアイツに、俺は苦笑いした。