ご存知の方も多いと思いますが、ボスニアは戦争で対立していた3勢力のうちクロアチア人とボスニア人が「ボスニア連邦」、セルビア人が「セルビア人(スルプスカ)共和国」を作りました。デイトン和平後に境界線の出入りはありましたが戦争中の支配地域を中心に現在も事実上この2つの「部分(エンティティ)」に分かれています。2つの国としてバラバラのままやっていくのか、デイトンで定められたように3民族による中央政府が何とか機能するのか。96年の最初の総選挙の争点は2年後の今回もあまり変わりません。分かりやすく言えば、「バラバラ」色を押す政党と、「一緒」色を出す政党の争いがポイントです。もちろん「バラバラ」側が強いほど難民帰還は遅れるでしょうし、経済復興のペースも上がらない、ということになってしまいます。
今回の選挙では昨年の地方選の補選も含めて、様々なレベルで選挙が行われました。このうち重要なものは両「部分」の3民族が一人ずつ代表を出す幹部会と、民族系(「バラバラ」派)、親欧米系(「一緒」派)が激しく争ったセルビア人共和国の大統領、議会選の3つだと考えられます(ボスニア連邦の大統領は連邦議会が選出します)。
96年に続いて選挙を仕切ることになった全欧安保協力機構(OSCE)や民生部門のトップであるデイトン和平履行会議上級代表事務所(OHR)、さらに軍事的に平和の実施に当たる和平安定化部隊(SFOR)といった西側の関係者の間では、当初楽観論が支配的でした --- 95年のデイトン和平で予見されていたほどの速さではないにしても、曲がりなりにも復興は進んでいるし、今までバラバラだった旅券や通貨、車のナンバーなどの統一も進められている。親欧米系が勝つ限り平和と経済発展を享受できることが住民にも明らかになった今は、民族派は苦戦するのではないか。 ---
○は当選、×は落選
| 選挙対象 | 親欧米系 | 民族系 |
| 幹部会員(ボスニア人枠) |
| ○イゼトベゴヴィッチ |
| 幹部会員(クロアチア人枠) | ×ズバク | ○イェラヴィッチ |
| 幹部会員(セルビア人枠) | ○ラディシッチ | ×クライシュニック |
| セルビア人共和国大統領 | ×プラヴシッチ | ○ポプラシェン |
ところがフタを開けてみると、上表のように民族派がしぶとく生き残る結果となりました。個人選出の上4レベルでは西側の期待していた「一緒」派は1勝3敗です。セルビア人共和国議会にしても絶対多数を取る政党がなく、組閣や力関係で今後の紆余曲折が予想されるものの、第一党となったのは戦犯カラジッチの流れを汲むクライシュニックのセルビア民主党でした。
しかし私は西側の期待していたような和平プロセスの加速こそないものの、この結果によって今までの和平路線が大きく変わることはないと思います。今まで通りゆっくりとしたペースで全てが進むのではないか、と。それよりも問題だと思ったのは、OSCEが今回の選挙実施に関しては信用を落としかねないようなことをいくつかやったことでした。
9月15日(選挙終了の翌々日)に予定されていた結果の中間発表は中止、公式に最終結果が発表されたのは月末になってからのことでした。既に中間発表がなくなった時点で記者の間で、また住民の間で結果の操作が噂されていました。
去年までセルビア人共和国の暫定首都だったパレに住むPさん(セルビア人男性、三十代)。「投票用紙が細かい字でいろいろ書いてあって、似たような名前の政党名も多いし分かりにくかった。私のような若い者はいいが、母などは苦労していた。それに鉛筆書きじゃなければいけないというのも疑問だ。」
 |
| ラディシッチ新幹部会員はボスニア連邦に比べ経済発展が遅れるセルビア人共和国の復興のカギを握るか(選挙ポスターから) |
|---|
日本の選挙は鉛筆書きですが、旧ユーゴでは珍しいケースです。OSCEは日本のマークシート試験に似た用紙を作って早く集計するため、としていましたが、結果が出るのも遅かったし、住民に与える効果はマイナスだったようです。
上の表で親欧米系が勝ったセルビア人の幹部会員選にしても、当選したラディシッチと次点のクライシュニックの差は約4万5千票(有効投票の6%)と比較的小さく、大統領選と逆の結果が出たことからも?マークが付いて不思議ではない結果でした。OSCEが選挙を「仕切る」のは今回が最後とのことですが、何よりも西側がまた一つ何かを押し付けた、という印象が住民の間に残されたのが残念でした。
両「部分」の代表が集まるのは幹部会と合同議会(上院、下院)ですが、96年の総選挙後の2年間で3民族の共通の利益に関して実のある決定は何も出来なかったと言っていいと思います。唯一決定できたのは統一パスポートの発行でしたが、これが討論されていた時は私もサライェヴォでテレビを見ていました。表紙のデザインにはキリル文字も入れるべきだ。同じ字の大きさにしろ。じゃあどっちが上でどっちが下だ。いやどうせなら英語だけにした方がいい、等々、等々。第三国の人間が見ているとどうでもいいような話でケンケンガクガク熱論が続いたのを覚えています。
統一の国旗が長野オリンピックの直前に定められたのは記憶に新しいところです(実際に長野に参加したのは連邦の選手だけでした)が、夏以降統一通貨が定められ、車のナンバーもボスニア連邦、セルビア人共和国共通のものになりました。
3民族の支配地域では、クロアチア人の支配地域でクロアチア・クーナが通貨として、セルビア人共和国ではユーゴ・ディナールが、ボスニア人の地域では独自のボスニア・ディナールが通用していました。まあどれもお世辞にも強い通貨ではありませんから、旧ユーゴ全体で流用しているドイツマルクが並行してどの地域でも使われていましたけど・・・
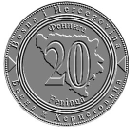 |
| 近い将来発行される新20フェニング硬貨のデザイン |
|---|
この夏以降の新ボスニアマルクは、価値を人工的に1ドイツマルク=1ボスニアマルクに固定して全土で使えるようにしようというものです。当初は若干の混乱があったようですが、9月に見た時点では何とか定着しつつありました。今までは紙幣だけでした(最小は1マルク)が年末までにはコインも発行される予定で、単位はやはりドイツと同じように1マルク=100フェニングになります。
しかしそれよりも重要な意味を持つと思われるのは統一ナンバーです。従来は3地域がそれぞれの紋章の入ったマークのナンバーのみを認めており、しかも登録地が分かるようになっていました。ボスニア人地域のナンバーでSAと、あるいはセルビア人地域のものでBLと書いてあれば「こいつはサライェヴォだな」「こいつはバニャルーカ」、とすぐ分かってしまうわけです。これではこの間まで銃を向け合っていた敵の地域に自動車で入ることが難しい。移動の自由がない限り統一国家はあり得ません。もちろんナンバーではわからなくても警察の検問があれば「どちらの人間か」はわかりますから、急に両「部分」の行き来が増えたわけではないのですが、少し時間をかけながら、いい方に向かって行くと思います。
 |
| 左上の旧来のSAナンバーでは連邦側のサライェヴォ出身なのが一目瞭然だ。しかし新統一ナンバーで使われるアルファベットは一文字、それもキリル・ラテン文字共通のA、K、Mなど数種類だけで、どの町から来ているか分からない。 |
|---|
そんなわけで、和平プロセスは少しずつ前進しています。ただこうした国旗や通貨やナンバーを定めたのは西側を代表するOHRであって、幹部会でも議会でもありませんでした(OHRは最近まで国歌も公募していましたので、来年前半には新国歌が決められることと思います)。この夏ボスニアの人々と仕事をした時も新国旗が話題になったことがありましたが、「ああTROKUT(三角)ね、ハハハ・・・」と冷ややかな反応でした。
OHR、OSCE、SFOR。和平の成立と前進には西側の介入が必要でしたし、これからもその状態は続くでしょう。欧米としては「自分たちで何も決められないならこっちが決める」というのが正論なのでしょうが、ボスニアの人々の気持ちは「和平が前進している」と「押し付けられている」の間で揺れ動いています。
とは言うものの、ボスニア発の経済関係のニュースが最近元気です。
フォルクスワーゲン(VW)と地元の総合企業ウニスは、92年に閉鎖になったままのサライェヴォ郊外ヴォゴシュチャ地区の自動車工場の生産再開で7月に合意。8月末から実際に稼動を始めました。この工場では戦争前ゴルフ、ジェッタ、ビートルなどのVW車を作っていましたが、今度はシュコダ・フェリシアの組み立ての契約が交わされました(第3回配信で昔のシュコダのことをだいぶコケにしましたが、クルマに詳しくない私も今のシュコダがVW資本の立派なものだというのは知っていましたよ)。VWからの投資額は約3億ドル。VW側は「チェコより安く生産できることを期待」しての2年契約です。このジョイントヴェンチャーは今後のボスニアでの投資が成功するかどうかのテストケースとして広く注目を集めそうです。
 |
| シュコダ・フェリシアの看板(サライェヴォにて) |
|---|
携帯電話の大手エリクソン(本社・スウェーデン)は7月末5900万ドルの大型入札に成功。3年半で地上回線20万件、携帯電話3万件の新設が目標です。
イスラム諸国も負けていません。イスラム14カ国からなるイスラム発展銀行(IDB)代表団は6月末、新規投資とジョイントヴェンチャーに8430万ドルの拠出を発表。中小企業振興やモスタルでの住居建設、鉄鋼への参入などを計画しています。またパキスタンのクレスト投資銀行はサライェヴォに支店を設ける予定で、同国繊維製品などのヨーロッパ市場向け生産・輸出拠点としてボスニアが浮上しているとのことです。
クウェート投資コンサルタント企業(KCIC)は中部ゼニツァ市の鉄鋼企業とサライェヴォの上述ウニス社ビジネスセンターの復興に9200万ドルの投資を決定しました。同企業のサミア・アルハメイディ社長は、「これは人道援助でも無償供与でもない。もちろん結果的にはボスニア経済を助けることになるが、まず我々としては利益を期待している」と言います。3200万ドルを受けるウニス側は「これがうまく行ってさらに外国の投資意欲を刺激できれば」(ファルク・サミルベゴヴィッチ社長)。ゼニツァの鉄鋼企業は社会主義型の巨大企業で、92年には操業をほぼ止め、和平後もほとんど開店休業状態でした。これには戦争の影響もありますが、やはり旧体制からの非効率が大きな問題となっていました(原料の鉄鉱石は南部のヘルツェゴヴィナで採れるのに工場が中部にあるという事実自体が旧自主管理体制の非効率そのものだと思うのですが)。その再建に6000万ドルが予定され、年間生産80万ー130万トンが見込まれています。クウェート資本50%の「ボスニアヘルツェゴヴィナ鉄鋼」として再出発することになります。ゼニツァ側は「6000人の雇用が新たに確保できる」(ハムディヤ・クーロヴィッチ取締役)と期待しており、今後の展開が注目されます。
 |
| 戦争前ホテル・ブリストルは高級ホテルだったが今も休業中で、建物の左側に見えるように砲弾の痕も生々しい。その近くには携帯電話の大看板が立っていた。今のサライェヴォでは珍しくない光景だ。 |
|---|
上のアルハメイディ氏がいみじくも言っているように、これらの投資は、従来の「援助」の姿勢が欧米にしてもイスラム諸国にしても「ビジネス」の方向に変わってきて、実際の収益を期待していることを示しています。発展を続けている他の東欧諸国と同じようなノーマルな形と言ってもいいでしょう。そうだとしたら、これらは「押し付け」ではないボスニア自力復興への第一歩ではないでしょうか?
ただ上に挙げた例は大半が旧国営大企業の復興に関わるもので、たとえ形の上で民営化が為されるとしても、非効率だった社会主義(自主管理)企業の体制を温存することになるのは避け得ません。またこうした大企業の上層部はおしなべて現与党と強く結びついていますから、政治利権を強める色彩のものであることも確かです。今後も不透明なカネの流れやスキャンダルが出てくる可能性はかなりあるでしょう。でも、今は先を行くチェコやハンガリー、スロヴェニアも最初はそうやって動き出しました。始まったばかりのボスニアの市場経済への移行を見守りたいと思います。(98年11月中旬)

