サッカーW杯ではわがユーゴスラヴィアはオランダに敗れベスト8進出はならなかったものの、日本に苦しめられてちょっと大丈夫かな、と思わせていたクロアチアがベスト4進出(この原稿の執筆時点)。応援はしていましたが、正直に言ってまさかここまで来るとは思いませんでした。
ただクロアチア対日本戦の後でちょっと困った問題が発生しました。試合後の記者会見用にクロアチアのブラジェヴィッチ監督に国際サッカー連盟(FIFA)が用意した通訳がセルビア語を話すセルビア人で、監督は「我が国の言葉ではない」と厳重抗議したというのです。曰く、「独立後のクロアチアの公用語であるクロアチア語はセルビア語とは関係のない独立した言語である。」うーむ。確かにFIFAもドジだったけれどブラジェヴィッチもちょっと頑張り過ぎではないかな、と思ってしまいました。まあ確かにW杯ほどナショナリズムがまかり通るイベントもそれほどありませんけどね。
私が9年前ベオグラードのある学校で教わった言葉はセルビアクロアチア語(またはセルボクロアチア語、旧ユーゴ時代のクロアチアでは主にクロアチアセルビア語と言っていました)で、「セルビア語」でも「クロアチア語」でもありませんでした。しかしちょうど旧ユーゴ全体で共産主義が退潮し民族主義が一気に噴出してきた時代、セルビアではセルビア語、クロアチアではクロアチア語と大っぴらに言い出した頃です。ある知人に「セルビアクロアチア語では・・・」と言ったら「そんな言い方をする必要ないよ、セルビア語だ、セルビア語」と直されてしまったのを覚えています。やがてボスニアでも戦争勃発に前後してボスニア語、と言うようになって行きました。
セルビア、ボスニア、クロアチアで話されている言葉には確かに方言程度の差はあり、これを同じ言葉とみるか違う言葉とするかは難しい問題です。もともと3地域の方言には語彙、語順、正書法などにも微妙な違いはありましたが、最近になってかなり人工的にセルビア方言との差を拡大しようという動きがあります(千田善氏の講談社現代新書「ユーゴ紛争」でも少しこの問題に触れられています)。しかしお互いのコミュニケーションには99%まで問題はありません。東京育ちの人が名古屋や大阪でほとんど困らないのと同じレベルです。私は、旧ユーゴ以外の言語学者が集まって多数決を取ったらセルビア、ボスニア、クロアチアの各「言語」は同じ言葉だという結論になるのではないかと心のどこかでは思っています。むしろマケドニア語とブルガリア語の方が微妙な問題ではないか(マケドニアのグリゴロフ大統領がソフィアを訪問した際、彼のマケドニア語での声明がブルガリア側のニュースで字幕なしで放送されて話題になったことがありました)と考えていますが、言語学者がどう言おうと、それとは別の複雑さがあるのです。マケドニアについては置いておいて、取りあえず問題を3カ国の言葉に絞りましょう。
最近はインターネットの時代になり、あまり短波放送でニュースを聞くことがなくなってしまいましたが、冷戦時代に西側メディアが反共プロパガンダを目的として東欧・ソ連圏の言語で流していた放送は相変わらず健在です。しかしヴォイス・オブ・アメリカ、ドイチェ・ヴェレ(ドイツの声)、英BBCの各放送は「セルビア語」「クロアチア語」を別のプログラム(内容はほぼ同じで、上に書いた方言程度の差をつけて前者はセルビア人、後者はクロアチア人のアナウンサーが読む)で放送していますし、プラハに本拠を置く「ラジオ自由ヨーロッパ」は統一プログラムながら「南スラブ諸語(複数形)による放送」としています。
うーむ、困った。議論の方は言語学者に任せておきますが、通訳としては困る。ブラジェヴィッチ監督の言うように二つの言葉が別の言語だということになると、ベオグラードに住んでセルビア方言を話す私はクロアチアやボスニアでは商売できなくなってしまいます(上の写真の通り、私は営業用に「セルビア語・クロアチア語通訳」と名刺に入れていますが、本当は「ボスニア語」も入れたいと思っています)。クロアチアでもボスニアでも私のセルビア方言自体が問題になったことは少ないのですが、私が「セルビア語の通訳でクロアチア語は出来ない」と日本人に勘違いされて仕事を逃したことが一回と、クロアチアでの仕事で、さる地元のお役人に「あなたはベオグラードの人だから」と初対面でいきなり拒絶反応を示されたことが一回だけありました。後の方の例では「確かに私が話す言葉はクロアチア語ではないのは認めるし、ベオグラードに住んでいる以上クロアチアという国に対する誤解があるかも知れない。でもクロアチア語は話せないまでも聞けば分かるし、ここでは日本人テレビチームのために通訳に徹するから、あなたはご自分の立場を心おきなく語ってほしい」と言って何とか理解してもらい仕事に入りました。最後には別れ際に「ボーク」とクロアチア語の挨拶を笑顔で交わし合えるようになりました。まあ誠意(と通訳料を失いたくがないゆえの必死さ?)は分かってもらえたわけです。
東京の大学院生の友人Y君はなかなか語学力の優秀な人ですが、この春日本の公的機関が招へいしたボスニアの技術研修生3人の通訳をつとめました。ご丁寧にセルビア人、ボスニア人、クロアチア人が一人ずつという構成でした。実習の実施先で「この人たちが喋っているのは何語ですか」と聞かれ、「この人はセルビア語、この人はボスニア語、この人は・・・」と答えざるを得なかったそうです。すると「あなたは3つも言葉が出来て偉いですねえ」だって。
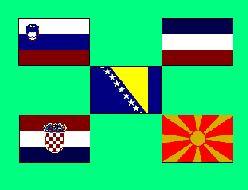 |
|
セルビア人がセルビア語、クロアチア人がクロアチア語と言う以上、ボスニア人がボスニア語と言っていけない法はないはずです。ただボスニアの場合はもう一つ難しい問題があります。ボスニアのスラブ系イスラム教徒が「イスラム教徒」という名の民族(一部の日本のマスコミは依然「ムスリム人」と言っていますが、ちょっと変な気がします)として認められたのはティトーのユーゴになってからの70年代で、それまでは「イスラム系セルビア人」「イスラム系クロアチア人」と考えられていました。彼らは第二次大戦中セルビア人からも、「クロアチアの華」とイスラム教徒を持ち上げたナチス傀儡のクロアチア国家からも手ひどく扱われた過去があります。ですから旧ユーゴが解体し、ボスニアが戦争に突入するのに前後して、ボスニアは独立国になるのだから「イスラム教徒」ではなく「ボスニア人」なんだ、ボスニア人の「ボスニア語」なんだ、という考え方が現与党勢力を中心に打ち出されてきたのはある意味で当然の動きでした。しかしクロアチア人やセルビア人の間では、彼らが独自の民族であり、彼らの言語がセルビア語でもクロアチア語でもないボスニア語であるという了解が、まだほとんどありません。逆にボスニア当局側は旧来の「3民族」を「カトリック、正教、イスラム教のボスニア人」と規定しようとしていますが、セルビア人、クロアチア人側は反発しています。これは両民族の公式筋がデイトン和平とは別に、現在の「ボスニア国家」の存在をあまり歓迎せず認めるような認めないような半端な態度を取っていることとも並行した関係にあります。
「あなたの母国語は何語ですか」という質問は、旧ユーゴ、特にボスニアのような微妙な状況下にある国の人々にとっては、「あなたは何人ですか」という意味とほとんど同じです。そして場合によっては「あなたはボスニアという国を認めますか」という意味にもなります。自分がナニ人であると思っているか、というアイデンティティに、また政治に強く関わってくる質問なのです(アイデンティティの問題については、また機会と視点を少し変えて取り上げようと思っています)。
通訳の現場で困るのは、特にボスニアで「ナニナニ語では(何と言うんでしたっけ)」とか聞かなければならない場合です。セルビア人の民族主義者に「ボスニア語では・・・」とわざと言って挑発する場合もまれには考えられますが、大抵はイスラム名前の人には「ボスニア語では・・・」、カトリック名前の人には「クロアチア語では・・・」等々、ということになります。時には取材対象を怒らせ、多くの場合は相手にコビる。通訳が苦労するところです。
ボスニア人に対してボスニア語を認めないことは、デイトン和平が成立していなければボスニアを分割・併合しかねない勢いだったセルビアやクロアチアの民族主義に迎合することにもなり得ます。
また逆にボスニアのセルビア人とクロアチア人に対してボスニア語しか認めないことは、セルビア人、クロアチア人の存在を認めないことにつながってしまいます。それは日本に住んでいて日本語を話しながら国籍を持たない人々を封じ込める論理とどこか通底するものがないでしょうか。
「ボスニア語」が「ボスニア住民」全体の言語であると言えるような平和共存を早く実現してもらうしかない、外国人の私たちにはどうしようもない問題です。でもこれからも私は現場でこの答えの出ない問題にぶつかって行くことになります。
ところでセルビアクロアチア語という、「私の学んだ言語」はなくなってしまったのでしょうか。そんなことはありません。コソヴォのプリズレンという町に住む私の友人エディ、アナの兄妹はアルバニア人とセルビア人の両方の血を継いでいますが、彼らが母国語として話す二つのうちアルバニア語でない方の言葉はセルビアクロアチア語だと言っていました。ベオグラードの友人アレクサンドラは、両親ともセルビア人ですが、自分は「学校で教わった国語はセルビア語とは言わなかったわ。私の母国語はセルビアクロアチア語だし、自分はユーゴスラヴィアに住むユーゴスラヴィア人だと思ってる」と言います。私にとってはこういう人々と話す時が一番安心できる時なのですが、彼らのこうした言い方も、例えばユーゴのユの字ももう見たくないと思っているクロアチアやボスニアの人々、あるいはセルビアの超右翼にとっては「政治的な」立場を表したものだということになってしまいます。学者から見ればたぶん同じ言語の呼び名から始まって、すべてが旧ユーゴでは政治(ここでは民族主義という「悪政」を考えています)の周りをぐるぐる回っているのです。私の第一外国語はいったい何語と言うべきなのでしょうか。(98年7月上旬)
人名の一部には仮名を使用しています。

