| 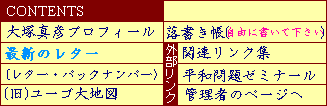 |
| 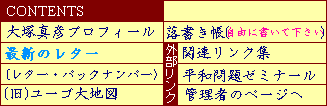 |
|
第66回配信 イラク危機関連緊急特集
召集令状が届いたら、銃を手に取るか脱走兵になるしかない。60年前の戦争をテーマにした映画ではなく、私の住んでいるベオグラードで91年にそういう状況が起こっていますし、ユーゴ連邦全土が戦争状態を宣言した99年のユーゴ空爆ではさらに切迫した形でこれを見聞きしています。
旧東欧の優等生スロヴェニアは、昨秋立て続けにNATO、EU加盟の「内定」を取り付けました(いずれも正式加盟は2004年メド)。この間11月には旧ユーゴ社会主義連邦時代から最長不倒の元首の座にあったクーチャン大統領の任期満了に伴う大統領選が行われ、ドゥルノウシェク首相が大統領に当選。新大統領が率いる与党・自由民主党のロップ蔵相が首相に、ルペル外相ら要職が留任するなど最小限の異動だけで、中道・中道左派連立政権は従来路線の継続を打ち出した新政府を樹立しました。現与党連合(2000年10月〜)は閣外協力8議席を含めると議会定数98のうち66議席、つまり3分の2以上を押える安定政権で、これによりドゥルノウシェク路線は安心してEU、NATOへの接近政策を進めて来たわけです。
野党と世論は「NATO・EU加盟を問う国民投票の実施」を要求、3月23日にスロヴェニア全土で実施されることになりました。NATO加盟反対を主張する野党側は憲法施行法などを変更してこの国民投票の結果に法的拘束力を持たせようとしていますが、結果には拘束力のない「参照型」国民投票になる見通しです。しかしたとえ拘束力がなくとも、加盟反対の結論が出た場合には内政・外交両面に重大な影響が出る可能性があります。このためこれから1ヶ月強にわたり、国を二分する議論が白熱することは必至です。 反対派の議論には堅実なスロヴェニア人らしい国民性が見えます。代表的日刊紙デーロの論説は「スロヴェニアの国民総生産は推計2億ドルだから、もしアメリカに軍事拠出を0・5%か1%増加させるよう要求された場合、国家全体の失業対策費が吹っ飛んでしまう」と警告。また国内では知名度の高い経済学者のメンツィンゲル・リュブリャーナ大学学長も反対の立場からこう言います。「ルペル外相は『西に向かいたいからNATOへ』と言っているが、今やNATOに入ることはむしろ東(の論理)にとどまることを意味するようになっていないか。ロシアを隣国に控えているエストニアのような国ならいざ知らず、スロヴェニアの地理的位置ではロシアの脅威はあり得ない。99年に新規加盟したチェコ、ハンガリー、ポーランドの経済はいずれも後退しており、この10年経済力が伸びているのはアイルランドとフィンランドで、ともにNATO非加盟国だ」。
「スロヴェニア軍の演習だけで徴兵の若者が何人も事故で命を落としている。NATOの大規模演習などに加わらない軍の方がいいだろう。加盟反対」(「リヒトホーフェン伯」さん) 「イラクの戦争には反対、アメリカはバツだがNATO加盟には賛成。クロアチアがNATOに入って、スロヴェニアが非加盟国というのは現実的だと思うか?」(アンドレイさん) 「EU加盟賛成、NATO反対。経済同盟(EU)と軍事同盟(NATO)の2つには何のつながりもない」(アレシュさん) 「アメリカの不況がNATOの政治危機を生み出しているとしたらけしからん話だ。長期的に見れば軍にカネを掛けない方が経済にとってはプラスに決まっている。EU加盟賛成、NATO反対」(マティッチさん) NATO加盟を巡る揺れ動きが続いていた中で、スロヴェニアは今回のイラク危機の高まりを迎えました。 2月5日、スロヴェニアなど次期NATO加盟7か国とクロアチア、マケドニア、アルバニアの第2陣候補国の10カ国(通称「ヴィルニュス10」)は「アメリカはイラクが禁止されている兵器を隠し、査察を欺き、国際テロ組織とつながっている実態を明らかにした。大量破壊兵器を持つ独裁者は民主主義の脅威であるから、ともに立ち上がらねばならない」という趣旨の共同声明(以下、ヴィルニュス声明)を発表しました。
NATO加盟強硬論者として知られるルペル外相は、これ以前にも同外相を揶揄する内容の記事が掲載された報道機関や記者のブラックリストを発表し、マスコミと冷戦状態に突入し掛けるなど失点を重ねています。TVのイラク危機特番放送中に行ったアンケートでは、介入反対の声が80%を超えましたが、この結果について外相は「どうしてこんなに独裁者フセインの支持があるのか分からない」と発言し、また加盟反対派・反戦派を怒らせています。 政府は先頃、「NATO加盟への努力をより広く理解してもらうため」、NATO加盟無料電話案内を開設しましたが、ネット先進国らしくすぐにインターネット上で加盟反対派がそのインチキぶりを暴露。「私がまず加盟のプラス面を3つ挙げてくれ、と電話で聞くと、オペレーターはキーボードを打って『10のメリット』を列挙しました。次にデメリットを3つ挙げるよう言うと、『そのような点はコンピューターには出ていません』という回答だったんです!」。 加盟反対派は2月15日の世界一斉反戦運動で勢いをさらに加速させたいところです。首都リュブリャーナの参加者2000、副都マリボルでは500。数は確かに今ひとつでしたが、シムシッチ・リュブリャーナ市長ら各界の有名人も数多く参加。「戦争は悪だ、アメリカよ目覚めよ」などのプラカードを掲げて市内を行進し、政府に対し国連・EU決議の遵守、イラク軍事介入の際にはNATO軍の領空・領土・領海通過禁止などを要求しました。 現在のところ、マスコミの理解を得てNATO加盟反対派が押し気味に国民投票キャンペーンを進めていることは疑いなさそうです。国民の支持を裏付けにNATO接近政策を進めてきたはずだった政府にとっては、イラクが、というより米英の暴走がとんだ躓きの石になってしまいました。国民投票は政府が渡る大変危険な橋であることは間違いありません。
旧ユーゴ諸国の中で、週末の世界一斉反戦デモに最も敏感に応じたのはクロアチアでした。
15日は首都ザグレブのほか10都市で集会が開かれました。海岸の主要都市スプリットでは「ブッシュは世界平和への最大の脅威」「血まみれの原油なら要らない」などのプラカードを掲げる参加者がイラク介入反対、NATO加盟反対などの署名を集めました。最大規模となったのはイストラ半島のプーラで参加数千人。武力行使を容認するヴィルニュス声明にサインした政府に閣外から協力するヤコヴチッチ前EU統合担当相は、「閣外協力をしている以上、クロアチアのNATO加盟に反対する署名は出来ないが、国連を無視したイラクへの武力介入には反対なので参加した」と述べました。 各地の集会で中心になった反戦市民団体の一つ、「戦争はもうこりごり(Dosta je ratova)」は主張します。「アメリカは世界支配の口実として『人権擁護』論を悪用している。彼らの恣意のために今や世界戦争直前の状態になってしまった。われわれは戦争と貧困、政治的抑圧に反対する。イラク軍事介入の支持者には『われわれの名前で介入するな』を叫ぼう。別の形でグローバリズムが可能であることを示そう。別の形の世界が可能であることを示そう」(同団体HPより)。 週明けの17日には、従来必ずしも鋭い体制批判をしていたわけではない日刊紙ヴィエスニクが、ヴィルニュス声明の撤回を明瞭に求める与党連合批判の論説を発表しました。「クロアチアはイラクの罪なき市民への殺戮にも、世界で起こり得る恐ろしい事態にも加担してはならない。イラクへの侵略を支持したヴィルニュス声明の撤回は政府が示すべき倫理である」(F・ノヴァリッチ客員論説委員)。 同じ日の別の日刊紙ヴェチェルニー・ノーヴォスティは「ヴィルニュス声明の内容は曖昧でしかも強制力がない。クロアチアが米英ではなく独仏の側に付くチャンスは残されている」という趣旨の記事を発表し、ラーチャン首相ら政府を弁護する形になりました。
クロアチアは地力の割に「西へ向かうレース」では他の中東欧諸国に大幅な遅れを取り、NATO・EU加盟に関してはブルガリア、ルーマニアなどとともに候補第2陣に名を連ねることが出来たばかりだけに、少々のアセりが早まったアメリカ支持発表につながったと言えるかも知れません。 またこのHPの第59回配信などでも報告している通り、この国は2000年の政変で成立した連立政権内の協調体制がなかなか整わず、昨夏には有力政党の分裂により内閣改造が行われたばかりです。しかし最近に来てこの第2次ラーチャン内閣も有力企業の民営化など経済政策で不協和音が目立ち始め、そこにイラク危機が拍車を掛けようかという形になっています。連立中核の中道右派・クロアチア農民党と中道左派・社民党が独断で政策を仕切っているとして、左派2つの小政党が合同協議に不参加を続けるなど連立政権は機能麻痺に限りなく近い状態。任期を1年残して前倒し選挙の可能性も再び囁かれています。しかし現政府が倒れた場合には、せっかく3年前に倒した民族主義の難航不落の牙城、クロアチア民主連合が再伸張することは確実です。 ク民主連合は親米路線を明らかにしているので、反戦気運の盛り上がりは直接野党の支持には結び付きません。しかし内政で手詰まり状態、足元の不確かな政府としては、今市民から出てきている強い声が反政府色を帯びて来ることが一番の恐れです。
読者の皆さんは意外に思われるかも知れませんが、旧ユーゴで最もイラク反戦運動の盛り上がりを欠いているのは99年のユーゴ空爆を実際に市民が経験したセルビア=モンテネグロです。
ユーゴ政変後のセルビア政府は、ミロシェヴィッチ政権時代とは異なりNATOを敵視することはありません。国際社会への早期復帰をめざし、NATOとの協力機構「平和のためのパートナーシップ」への加盟がやはり外交目標の一つとして挙げられています。しかしスロヴェニア、クロアチアのようにNATO加盟へ積極的に働きかける状態には至っていないこと(ユーゴ空爆の過去がある以上、この国の場合将来的にもEUと異なりNATOへの接近は慎重に進められるでしょう)が一つ。また反NATOに積極的なのはミロシェヴィッチ時代の政権党(セ社会党、セ急進党など)であり、現政府はこうした野党を勢いづかせたくないという思惑もあります。このため現在のところ「イラク危機に関しては中立でありたい」というジンジッチ・セルビア共和国首相の発言以外は政府が「”反”でも”親”でもない」不鮮明な態度を取っており、世論喚起もほとんど感じられません。 ミロシェヴィッチ政権は確かに悪だったかも知れない。しかしそれに対する「人道的介入」もまた悪であったことは、トマホークが落ちて来(得)る場所で空襲警報と爆音を毎日聞かされていた市民が一番良く知っているはずです。 沈黙でいいのか?という声は上がり始めています。どちらかと言えば保守基調の論を張る日刊紙ポリティカ、週刊誌ニンなどに寄稿しているベテランのジャーナリスト、D・ランチッチ氏が興味深い論稿を発表しましたので紹介します。
そうした中で近い将来の開戦が不可避ということならば、領空通過を許す程度にはNATOに寄ることを善しとした上で、セルビア市民のこのような経験をきちんと国際社会に訴えながらEU、特に独仏に対するポイントを稼ぐのが得策ではないか、というのがランチッチ氏の論旨です(ポリティカ紙2月12日付)。論の当否はともかく、盲目的国粋主義とも盲目的親欧主義とも一線を画すセルビア保守論調の基盤となっている日刊紙で、かなり明瞭な口調で「独仏接近」が言及されたことは、今後のセルビアの進む政治的方向を示唆しているかも知れません。 3月24日で、あのユーゴ空爆開始から4年になります。それまでにセルビアの世論と政治はイラクを巡ってもう少し動くのか、現在の沈黙に近い状態を続けるのか、まだ何とも言えませんが、私もウォッチングを続けましょう。 「反」か「親」か。「米英」か「独仏」か。「お前は態度を明らかにしろ」―――旧ユーゴ各国の内政はイラクなしでも十分(?)不安定な状態です。そんな中、困ったタイミングで各国への召集令状が突き付けられてしまいました。 (2003年2月19日) 画像を提供して頂いた下記諸氏に謝意を表します。加藤健二郎(東長崎機関)、スロヴェニア共和国政府情報局、D・リュービッチ(戦争はもうこりごり)、P・コラクシッチ 本文執筆には各国のインターネット、新聞等の文献を参照しましたが、煩雑さを避けるため出典の表示は一部省略してあります。画像の一部は2000年9月、2002年11月に日本のテレビ局の取材に通訳として同行した際、私(大塚)が撮影したものを含みます。これらのこのページへの掲載に当たってはクライアントの承諾を得ています。本文・画像とも無断転載をかたくお断りいたします。 Zahvlajujem se za sodelovanje/suradnju/saradnju: K.Kato, Urad vlade RS za informiranje, Darko Ljubic (Dosta je ratova), Predrag Koraksic Corax. Prepovedna je vsaka uporaba teksta in slik brez dovoljenja / Zabranjena je svaka upotreba teksta i slika bez dozvole. |
<プロフィール> <最新レター> <バックナンバー> <旧ユーゴ大地図>
<落書き帳(掲示板)> <関連リンク集> <平和問題ゼミナール> <管理者のページ>
当サイトは、リンクフリーです(事後でもいいので連絡ください!→筆者メール)。
必ずカバーページ(http://www.pluto.dti.ne.jp/~katu-jun/yugo/)にリンクをはってください。
| CopyRight(C)2003,Masahiko Otsuka. All rights
reserved. Supported by Katsuyoshi Kawano & Kimura Peace Seminar |