CD仌嬋栚夝愢![]()
| 侓偙偺応強偱偙偺堦嬋侓 |
| 1丄 戉彜搒巗僷儖儈儔偺楍拰傪傒傢偨偣傞儂僥儖偺儗僗僩儔儞乮僔儕傾乯 2丄 僞僉僔儔偺僕儑乕儕傾乕儞堚愓偺撪掚乮僷僉僗僞儞乯 3丄 僟儅僗僋僗丄媽巗奨悽奅嵟屆偺媔拑揦慜偺彫偝側峀応丅乮僔儕傾乯 4丄 儔儂乕儖丄儔儂乕儖僼僅乕僩拞掚偺抮偺忋偵嶌傜傟偨晳戜丅乮僷僉僗僞儞乯 5丄 僄乕僎奀僄僊僫搰傾億儘儞恄揳乮僊儕僔儍乯 6丄 僆僇僶儞僑僨儖僞偱巹偑攽傑偭偨僉儍儞僾偺儊僀儞搹偺僥儔僗偺傕偺偡偛乕偔戝偒側庽偺壓乮儃僣儚僫乯 7丄 儀儖僎儞偺柉懎懞丄峘傪尒壓傠偡峀応乮僲乕儖僂僃僀乯 8丄 儔儞僗丄僒儞丒儗儈惞摪乮僼儔儞僗乯 9丄 傾償傿僯儓儞丄儘乕儅帪戙偺愇愗応乮僼儔儞僗乯 10丄 僯儏乕丒儓乕僋丄儊僩儘億儕僞儞旤弍娰偺僄僕僾僩恄揳偺晹壆 |
丂
乽巹偺儀僗僩丒僥儞乿偲尵傢傟傞偲杮摉偵崲傞丅巹偼壗偵偮偄偰傕偦傟側傝偵乽儂乕僆丄側傞傎偳柺敀偄乿偲巚偊傞僞僀僾偺恖娫側偺偱壗偐偵弴斣傪偮偗傞傛偆偵塢傢傟傞偲杮摉偵柪偆偺偱偁傞丅
偁偲巹偺嬯庤偲偡傞傕偺偼寛傑偭偨擔忢惗妶丄枅擔摨偠偙偲偺孞曉偟偼偡偖偵偁偒偰偟傑偆偑丄墘憈壠偺婎杮偼抧摴側楙廗丄怴嶌傪墘憈偡傞帠偺懡偄巹偺惗妶偼朲偟偄偲梋寁偵扨挷側惗妶偵側偭偰偟傑偆丅偦偺惗妶偐傜巹傪媬偭偰偔傟傞偺偑擭偵俀丄俁夞偺奀奜墘憈椃峴丅摿偵尰嵼偺擔杮乮搶嫗偲偄偆偐丠乯偲戝偒偔堘偭偨暥壔傪堢傫偱偒偨抧堟偵弌偐偗傞偺偑戝曄偵巋寖揑偱偁傞丅
偦偙偱巹偑朘傟偰暤埻婥偑偲偰傕婥偵擖傝丄偙偙偱偙偺嬋傪抏偄偰傒偨偄偲姶偠偨応強傪偁偘偰傒偨偄丅
偙偙偱偼尰幚偲偟偰偼峫偊偰偄側偄偺偱婥徾忦審丄晽丄嵒丄懢梲丄幖婥丄堎忢姡憞側偳偼峫椂偵偄傟側偄傕偺偲偡傞丅
嘆偺僷儖儈儔偺堚愓偼僔儕傾嵒敊偺拞墰晹偵埵抲偟丄摿偵婭尦慜堦悽婭枛亅婭尦屻嶰悽婭傑偱斏塰偟偨僔儖僋儘乕僪増偄偺戉彜搒巗丅
偙偙偵廧傫偱偄偨恖娫偺姶忣偺傛偆側傕偺偼偲偆偵忩壔偝傟幚偵椙偄乽婥乿偺偨偩傛偆応強偱丄巹偼抧柺偵墶偨偊傜傟偨楍拰偺傂偲偮偺忋偵怮偦傋偭偰傂偲帪傪夁偛偟偨丅嬋偼嵅摗憦柧乽恄彽嬚乿乮擇廫尲獾乯偙偙偱偙偺嬋傪抏偄偨応崌偳偺傛偆側恄條偑崀傝偰偙傜傟傞偺偐偼晄柧丅
嘇僈儞僟乕儔嵟戝偺堚愓孲僞僉僔儔丄僕儑乕儕傾儞堚愓偵偼憁堾偺撪掚傪埻傫偱29偺彫幒偑桳傞丅偙傟偼AD俀悽婭亅係丄俆悽婭偵悽奅拞偐傜暓懮偺嫵偊傪妛傃偵偒偨妛惗偑嵋憐傪偟偨応強偩偲偄偆偙偲偱丄巹偼偦偙偵嫃傞偩偗偱怱偑桙偝傟偨丅
嬋偼惣懞楴乽棶棡嬚乿乮擇廫尲獾乯
嘊偙偺応強傕拫娫偩偲傑傢傝偺偒偨側偝偑栚棫偮偺偱媔拑揦暵揦屻偺p.m11:00埲崀偑棟憐丄揦偺慜偺僕儍僗儈儞偑偐傜傑傞堜屗偺慜偁偨傝偵獾傪抲偄偰丄嬋偼媑徏棽乽偡偽傞偺屲僣乿乮擇廫尲獾乯偍媞條偵偼壒妝偲惎偺椉曽傪妝偟傫偱捀偗傑偡丅婣傝偵偍姪傔偼僉儕僗僩傕曕偄偨丠偲偄傢傟傞僟儅僗偺僗乕僋乮僶僓乕儖乯側偳偺偁傞媽巗奨偺栭拞偺嶶嶔丄偙傟偼恄旈揑偱偡傜偁傞丅梻挬偺偨傔偺僷儞傗僋僢僉乕傪從偄偰偄傞揦傕偁傝丄尰幚偺惗妶傕偟偭偐傝擿偗傞丅
嘋儉僈儖挬傾僋僶儖掗偑憂愝丄僔儍乕丒僕儍僴乕儞掗側偳偑庤傪壛偊偨忛嵡丅
彮乆庤擖傟偑埆偄偲偙傠偑屆傃偨偄偄枴傪偩偟偰偄傞丅
偙偙偱偼寧偑晄壜寚側偺偱嵟屻偺傾僓乕儞偑廔椆屻偺栭丄寧偼嶰擔寧偐傜敿寧偺娫偔傜偄偑傛偄丅嬋偼惣懞楴乽僞僋僔乕儉乿乮擇廫尲獾乯栭娫偼椻偊傞偺偱偍弌偐偗偺嵺偼暈憰偵拲堄偑昁梫丅忛嵡傊偁偑傞摴楬偼偲偰傕峀偔弌棃偰偄傞偺偱徾偱偍弌偐偗偺曽傕屼埨怱壓偝偄丅
嘍戜晽偱暵偠崬傔傜傟巚傢偸懾嵼傪偟偨搰偩偭偨偑丄偙偙偱偼傾億儘儞恄揳偺懠偵峘偺崅攇傪挱傔側偑傜堸傫偱偄偨僶乕偱偺儔僀僽傕幪偰偑偨偄丅
墱偱傂偭偦傝偲搎偗帠傪偟偰偄偨嫏巘偺偍偠偝傫偨偪傕枴偑偁偭偨偟丅嬋偼怴幚摽塸乽惵偺搰(偍偍偺偟傑)乿乮擇廫尲獾擇柺乯
嘐偙偺戝偒側庽偼條乆側捁偺廧張偵側偭偰偍傝丄巹偼傛偔偙偺庽偺壓偱拫怮傪偟偨傝杮傪撉傫偩傝偟偨偑僸乕儕儞僌偦偺傕偺丅嬋偼抮曈怶堦榊乽徑偵偰乿乮擇廫尲獾乯僥儔僗偺奜懁偵偼恖埲奜偺媞憌傕婜懸偱偒傞丅
嘑傗傢傜偐側屵屻偺梲傪梺傃側偑傜惷偐側儀儖僎儞偺榩傪尒壓傠偡応強偱嬋偼媑徏棽乽柌偁傢偣柌偨偑偊乿乮擇廫尲獾丄Cl,Vn,Vc乯
嘒儔儞僗偺戝惞摪偺椬偵惷偐偵樔傓偲偰傕壏偐側暤埻婥偺偁傞惞摪丅
嬋偼幠揷撿梇乽幍抜墦壒乿乮擇廫尲獾乯
嘓揤慠偺斀嬁斉傪攚晧偭偰偄傞偺偱嬁偒偑慺惏傜偟偄丅
嬋偼搾愺忳擇乽撪怗妎揑塅拡戞俁斣丂嫊嬻乿乮擇廫尲獾丄広敧乯
嘔僯儏乕丒儓乕僋傪曕偒旀傟偨恖偺宔偄偺応丄偙偙偼傗偼傝屆揟獾嬋乽棎乿
偙偺傛偆偵暲傋偰傒傞偲巹偑偳偺傛偆側忬嫷偱墘憈偟偨偄偲巚偭偰偄傞偺偐偑摟偗偰傒偊傞丅恖岺揑偵憿傜傟偨応偱偼側偔丄塱偄擭寧偵傛傝忩壔偝傟偨戝婥偲帺慠偑壒妝傪傂偒偩偟偰偔傟傞応強偲偱傕偄偭偨傜傛偄偐丅偄偮傕偼偁傑傝堄幆偼偟偰偄側偄偺偩偑傗偼傝巹偼擔杮恖偱朚妝恖丅
媑懞丂幍廳
| 乽The Art of Koto乿僔儕乕僘丂婇夋堄恾 |
2000敪攧 丂丂 VOL,嘥丂
2001丄俉寧丂丂 VOL. 嘦丂from Yatsuhashi to
Miyagi
2003 , 2寧丂丂 VOL.嘨丂20-stringed Koto
Celestial Harmonies偺Eckaet Rahn巵偺 僾儘僨儏乕僗偵傛傞VOL,1偐傜VOL.4傑偱偺巐枃慻CD丅撪梕偼獾偺楌巎偵揧偭偰媑懞幍廳偺壒妝傪徯夘偡傞傕偺偱偁傝丄慖嬋偵偮偄偰偼媑懞幍廳偵堦擟偝傟偰偄傞丅侾丄俀廤偼揱摑屆揟壒妝偐傜媨忛摴梇傑偱丄俁丄係廤偼擇廫尲獾偵傛傞尰戙偺壒妝傪寁夋偟偰偄傞丅
獾偺楌巎媦傃嬋栚夝愢偵偮偄偰偼妛弍榑暥巇條偺儗儀儖傪丄偲偄偆Rahn巵偺梫朷偵傛傝崙撪奜偺妛幰偐傜嵟傕憡墳偟偄妛幰傪慖擟偟偨丅嫗搒巹棫寍弍戝妛偑俀侽侽侽擭偵僆乕僾儞偟偨丄擔杮揱摑壒妝僙儞僞乕彆嫵庼Steven
G.Nelson巵丅懾擔尋媶惗妶偑挿偔擔杮岅偵傕姮擻偱擔杮壒妝偵懳偡傞抦幆偑朙晉偱偁傞丅
壗傛傝丄巵偺妛幆偼偼婘忋偺傒側傜偢幚慔傪敽偄抧壧乮獾丄嶰尲丄壧乯傪埫晥偱墘憈弌棃傞恖偱偁傞丅
壒偮偔傝偺僄儞僕僯傾偼30擭棃偺晅偒崌偄偺僩儔儞僗丏儔僀僽彫搰娹巵丅Eckaet
Rahn巵偼偙偺僠乕儉傪丄Steven G.Nelson巵丄彫搰娹巵丄媑懞幍廳偺姰帏側巇帠偲偄偭偰偄傞丅
| 乽The Art of Koto乿儈僯忣曬 |
UA乵united air line乶偺婡撪僆乕僨傿僆偵嵦梡偝傟傑偟偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂2003擭俆寧丂丂Vol.3傛傝乽嬔栘偵傛偣偰乿
丂丂丂丂丂丂丂丂2002擭俆寧丂丂Vol.2傛傝乽弔偺奀乿乽悾壒乿
| 乽The Art of Koto Vol.1乿丂婇夋堄恾 |
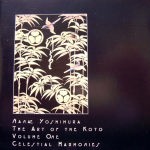
偙偺CD偺僾儘僌儔儉屲嬋傪慖傇偵摉偨傝師偺係揰偵棷堄偟偨丅
1丄 擔杮偺獾嬋偼峕屗帪戙偺側偐偱敪揥偟姰惉偟偨偺偱丄偦偺楌巎偺棳傟傪尒偰偄偔帠
2丄 峕屗帪戙偺拞偱擭戙弴偵戙昞揑側宍幃傪5偮慖傇偙偲丄
3丄 獾嬋奅偑惗傒弌偟偰偒偨戙昞揑側嶌嬋壠傪5恖慖傇帠丄
4丄 1丄2丄3丄偱慖傫偩嬋偑僾儘僌儔儉偲偟偰姰寢偡傞帠丄
懘偺寢壥丄榋抜丄棎傟丄巆寧丄屲抜媘丄愮捁偺嬋傪慖傫偩丅
傑偢巒傔偺擇嬋乽榋抜乿偲乽棎乿偼摨偠乮抜傕偺乯偺宍幃偱偁傝側偑傜嬋偺惈奿偑懳嬌偵偁傞柺敀偝偑偁傞丅乮抜傕偺乯偺宍幃偼抜乮堦偮偢偮偺償傽儕僄乕僔儑儞乯偺拞偺攺巕偺悢偑寛傑偭偰偄傞偺偩偑乮榋抜偼1抜偑102攺偢偮乯丄乽棎乿偩偗偼摿暿偱奺抜偺攺悢偑僀儗僊儏儔乕偵側偭偰偄傞丅枖晛捠丂彉丄攋丄媫偲偄偆條偵偩傫偩傫憗偔側傝嵟屻偵備偭偔傝偵栠傞偺偩偑丄乽棎乿偼嬋偺搑拞偱備偭偔傝偵側偭偨傝懍偔側偭偨傝偲偄偆偙偲偑偁傞丅偟偨偑偭偰乽榋抜乿偼旕忢偵僔儞僾儖偱椡嫮偔乽棎乿偼壺楉偱曄壔偵晉傫偱偄傞丅偦偟偰嶌嬋幰偺敧嫶専峑偼偙傟傑偱昁偢壧傪敽偭偰偄偨獾偺壒妝偵丄撈憈嬋偲偟偰乮抜傕偺乯傪搊応偝偣傞傛偆側戝抇側夵妚傪峴偭偨揤嵥偱偁傞丅
乽巆寧乿偺宍幃偼乮庤帠暔乯偲尵偄嫗搒偱敪払偟偨傕偺偱慜屻偺壧偺娫偵攈庤側婍妝偩偗偺晹暘傪帩偮丅偙偺嬋偼崅夒側庯偒偑偁傝忋昳偱媄弍揑偵傕崅搙側傕偺傪帩偭偰偄傞丅嶌嬋偼曯嶈岡摉丅
懕偔乽屲抜媘乿丄偙傟偼獾偺挷尲偑崅壒堟乮D傪堦尲偵偟偨杮塤堜挷巕乯掅壒堟乮壓2慄G傪堦偵偟偨暯挷巕乯偲偄偆壒堟偺堘偆偺獾偵傛傞夋婜揑側擇廳憈丅獾嬋偵偼壒堟偺堘偆獾偳偆偟偺崌憈偲偄偆宍幃偼偙傟傑偱側偐偭偨偺偩偑偙偺嬋偼桞堦偺崌獾嬋偲偄偊傞丅峕屗啵弉婜偵妶桇偟偨岝嶈専峑偼丄敧嫶専峑偺峫偊偵栠傝怴偟偄抜傕偺傪嶌嬋偟偨丅
乽巆寧乿乽屲抜媘乿偲椡偺偙傕偭偨柤嬋偑懕偄偰彮偟帹偑旀傟偨偲偙傠偱丄憉傗偐側乽愮捁偺嬋乿傪挳偄偰偄偨偩偒偨偄偲巚偆丅
乽愮捁偺嬋乿偼乮屆崱慻乯偲偄傢傟傞傕偺偱屆崱挷巕偲偄偆摿暿側挷尲傪帩偮丅峕屗埲慜偺獾偺壒妝偵栠傞堄巙傪帩偮媑戲専峑偺桪夒側嶌昳偱偁傝丄僾儘僌儔儉
偺嵟屻偵傗偡傜偓傪抲偄偰傒偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂2000丂3/17丂丂媑懞幍廳
| 乽The Art of Koto Vol.2乿丂婇夋堄恾 |
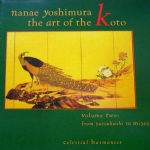
vol.1偵懕偒vol.俀偱偼丄獾嬋屆揟偺婎杮偱偁傞丂獾慻壧丂偐傜媨忛摴梇傑偱傪僾儘僌儔儉偟偨丅
1丄乽巐婫偺嬋乿乮敧嫶専峑丒侾俈悽婭乯丄
敧嫶専峑偑拀巼棳獾嬋偐傜妛傫偩獾嬋傪夵掕偟乽敧嫶偺廫嶰慻乿偲偟偰惂掕偟偨拞偺堦嬋丅
丂丂丂丂丂丂丂壧丄廫嶰尲獾
2丄乽敧抜乿乮敧嫶専峑乯丄
堦廤偱擖傟偨丄乽榋抜乿丄乽棎乿偲摨偠抜傕偺丅
丂丂丂丂丂丂丂丂廫嶰尲獾
3丄乽晼偺壴乿丂1897丂丂乮獾懼庤晅偒擇廳憈丄柧帯帪戙怴嬋乯
丂丂丂丂丂丂丂丂壧丄廫嶰尲獾擇柺丅乮懼庤丄怺奀偝偲傒乯
4丄乽旜忋偺徏乿乮峕屗帪戙揱嶌幰晄徻丄獾庤晅媨忛摴梇乯
丂丂丂丂丂丂丂丂壧丄廫嶰尲獾丄嶰枴慄乮怺奀偝偲傒乯
5丄乽悾壒乿丂丂1923丂廫嶰尲獾丄廫幍尲獾
媨忛摴梇偑峫埬偟偨掅壒獾廫幍尲獾傪巊梡偟偨偼偠傔偰偺廫嶰尲獾偲偺崌憈嬋丅
6丄弔偺奀丂丂1929丂丂廫嶰尲獾丄広敧乮嶰嫶婱晽乯
朚妝奅嵟崅偺儀僗僩僙儔乕嬋丅
| 乽The Art of Koto Vol.3乿丂婇夋堄恾 |
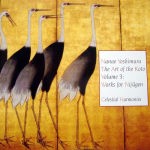
The Art of Koto嶰枃栚偺CD偼20悽婭偺壒妝丄尰戙壒妝偲側傞丅
1969擭惗傑傟偺怴妝婍擇廫尲獾偵傛傞墘憈側偺偱丄嶌昳偼1969擭偐傜偼偠傑偭偰偄傞丅
90擭傑偱偵嶌嬋偝傟偨屲嬋傪廂榐丅
揱摑揑側廫嶰尲獾偺墑挿慄忋偲偟偰丄怴偨側壜擻惈偵挧愴偡傞偨傔偵憂埬偝傟偨偙偺獾偼丄嶌嬋壠偲墘憈壠偺憃曽偺梸媮偐傜惗傑傟偨丅埲棃30擭偵傢偨偭偰嶌嬋壠偲墘憈壠偺嫤椡娭學偺拞偐傜桪傟偨嬋傗墘憈偑惗傒弌偝傟偰偒偨偲尵偊傛偆丅
崱夞偺CD慖嬋偵偁偨傝丄擇廫尲獾偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨嶌嬋壠丄偦偟偰擇廫尲獾偺怴偨側柺傪堷偒弌偟偨偲巚傢傟傞嬋傪慖傫偩丅
弶婜偺柤嶌傪嶰嬋
擇廫尲獾偵偲偭偰弶傔偰偺婰擮偡傋偒嬋乽揤擛乿丅
抔偐側恊偟傒堈偄儊儘僨傿偱擇廫尲獾偺僼傽儞奐戱偵峷專偟丄弶傔偰擇廫尲獾傪抏偔恖偑昁偢抏偔嬋乽屲偮偺彫昳乿丅
獾傗広敧偺墘憈奣擮傪曄妚偟偨乽廐偺嬋乿丅
師偼1982擭埲崀巹偑塱擭堦弿偵壒妝傪偟偰偄偔偙偲偵側傞嶌嬋壠偺拞偺屼擇恖丅
揱摑偺懇敍偐傜敳偗偰傕偭偲獾偺墱怺偄儖乕僣傪尒偮傔丄帺桼側敪憐偱妝婍偲偟偰傒偨擇廫尲獾偵嬋傪彂偄偨乽幍廳乿
擇廫尲獾偺抋惗傪廽暉偟偰恄偑廻傞傛偆偵偲偺婩傝傪崬傔偰偐偐傟偨乽恄彽嬚乿丅擇廫尲偺旤偟偄壒怓偑垽偱傜傟偰偄傞丅
偦傟偧傟偵擇廫尲獾偺壒怓丄墘憈朄偵岺晇傪嬅傜偟妋屌偲偟偨壒妝悽奅傪帩偮柤嶌偱偁傝丄偙傟傜偺嬋偵傛傝怴妝婍擇廫尲獾偼惗柦傪梌偊傜傟晛曊揑側獾偲偟偰偺抧埵傪妋棫偟偨丅
媑懞幍廳
| The Art of Koto丂廂榐嬋栚丂擔杮岅夝愢 2003/4/18媑懞幍廳丂獾儕僒僀僞儖亙屆揟偵傛傞亜僾儘僌儔儉傛傝敳悎 夝愢丗僗僥傿乕償儞丒G丒僱儖僜儞丂嫗搒巗棫寍弍戝妛擔杮揱摑壒妝尋媶僙儞僞乕彆嫵庼 |
侓巐婫偺嬋丂敧嫶専峑丂屆揟獾嬋慻壧
彉丄壴偺弔棫偮挬(偁偟偨)偵偼丄擔塭塤傜偱擋傗偐偵丄恖偺怱傕偍偺偯偐傜丄怢傃傜偐側傞偧巐曽嶳丅
堦丄弔偼攡偵轵丄鏤鏟(偮偮偠)傗摗偵嶳悂丄嶗偐偞偡媨恖偼丄壴偵怱堏偣傝丅
僯丄壞偼塊偺壴媖丄偁傗傔楡(偼偪偡)側偱偟偙丄晽悂偗偽椓偟偔偰丄悈偵怱堏偣傝丅
嶰丄廐偼峠梩幁偺壒(偹)丄愮憪乮偪偖偝乯偺壴偵徏拵丄婂(偐傝)柭偒偰梉曢傟偺丄寧偵怱堏偣傝丅
巐丄搤偼帪塉(偟偖傟)丂弶憵丄枧(偁傜傟)丂杪(傒偧傟)丂偙偑傜偟丄嶀偊偟栭(傛)偺弻丄愥偵怱堏偣傝丅
丂嬤悽獾嬋偺慶丄敧嫶専峑(1614乣1685)嶌嬋偺獾慻壧丅敧嫶廫嶰慻偺偆偪丄摿偵廳偄乽墱嫋偟嶰嬋乿偺堦偮偵悢偊傜傟傞丅壧帉偼巐婫偺婫戣傪捲偭偨巐偮偺壧偵亀尮巵暔岅亁偺弶壒偺姫偺朻摢晹暘偵傛傞彉偺壧傪晅偟偨傕偺丅戞堦壧埲壓偼丄敧嫶専峑偵懡戝側塭嬁傪媦傏偟偨偲偝傟傞拀巼獾偺亙巐婫亜側偄偟亙廐嶳亜偺壧帉傪傎傏偦偺傑傑堷偒宲偄偱偄傞偑丄壒妝揑側撪梕偵娭偟偰偼拀巼獾偺嬋偵帡偨偲偙傠偑彮側偄偨傔丄敧嫶専峑偑壧帉傪嵞曇偟偰怴偨偵慻壧宍幃偱嶌嬋偟偨偲巚傢傟傞丅
丂巐婫偲偄偆偺偼丄戝愄偐傜擔杮恖偵岲傑傟偨僥乕儅偱丄捄愶榓壧廤偺姫棫偰偐傜旤弍岺寍昳偺儌僠乕僼偵帄傞傑偱擔杮暥壔巎偺拞偱戝偒側栶妱傪壥偨偟偰偒偨丅偙傟偑丄扨偵婫愡偵懳偡傞擔杮恖撈帺偺朙偐側姶庴惈偵傛傞偲偄偭偰偟傑偊偽偦傟傑偱偱偁傠偆偑丄偙偺嬋偺壧帉偐傜偼傕偆彮偟怺偄堄枴崌偄傪撉傒庢傞偙偲偑弌棃傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偡側傢偪丄彉偺壧偵乽偺偳偐側棫弔偵側傞偲巐曽偺嶳傪尒傞恖乆偺怱傕傂偲傝偱偵偺偳偐偵側傞乿偲偁傞傛偆偵丄帺慠偦偺傕偺偲偄偆傛傝傕丄帺慠偲恖娫偲偺娭學偵徟揰偑摉偰傜傟偰偄傞丅帺慠偺愛棟偺拞偵惗偒偰偄傞恖娫偼丄偦偺弞娐傪堄幆偟丄傑偨惛恄揑偵挻墇偟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄懚嵼偱傕偁傞丅偦偆峫偊偰偙偦丄戞堦壧偐傜戞巐壧偺寢傃偺嬪乽乣偵怱堏偣傝乿偺堄枴偑惗偒偰偔傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂崅搙偵條幃壔偝傟偨獾慻壧宍幃傪偲傝側偑傜丄強乆偱屄乆偺婫戣偺昤幨偵獾偺摿挜揑側媄朄傕岠壥揑偵梡偄傜傟偰偄傞丅偙偺乽屆揟拞偺屆揟乿偲屇傇傋偒夒傃側嬋挷偑丄媑懞偝傫偺獾偲壧偱偳偆昞尰偝傟傞偐丄戝偄偵妝偟傒偱偁傞丅
侓晼偺壴丂徏嶃専峑
乵慜抏乶
丂壴偺柤巆傕偁傜偟嶳丄乵崌乶徑偙偢傦偺愺椢乵崌乶徏悂偔晽偵偼傜偼傜偲丄
丂丂丂丂丂丂乵崌乶嶶傞偼晼偺壴側傜傫丅乵崌偺庤乶
丂墎(偄偣偒)傪搊傞庒埣偺丄偝偽偟傞悈偺悈饽傝(傒偛傕傝)偵丄柭偔傗壨幁偺惡悷傔傞丄
丂丂丂丂丂丂戝墎(偍偍偄)偺娸偧夰偐偟偒丅
[庤帠]
丂愳忋偺墦偔傎偲偲偓偡丄[崌]偟偺傇弶壒偵偁偙偑傟偰丄[崌]廙偝偟偺傏偟尒偵峴偐傫丄
丂丂丂丂丂丂屗柍悾偺墱偺娾鏤鏟(偮偮偠)
嫗搒偺徏嶃弔塰(1854乣1920)偑柧帯30擭崰偵丄獾崅掅擇晹崌憈偺偨傔偵嶌嬋偟偨庤帠暔宍幃偺柧帯怴嬋丅徏嶃偼丄亙弔偺嬋亜側偳柤屆壆偺媑戲専峑嶌嬋偺屆崱慻巐嬋偵庤帠偲懼庤傪曗嶌偟偨偙偲偱崱偼桳柤偱偁傞偑丄斾妑揑曐庣揑偩偭偨柧帯帪戙偺嫗搒偱怴宍幃偵傛傞嶌嬋傪傕峴偭偨丅嶌帉幰偼旜嶈幊晇偱丄壧帉偼嫗搒棐嶳偺斢弔偐傜弶壞偺晽暔傪暯柧側幍屲挷偱壧偭偨傕偺丅戣柤偺晼偼壴晼偲傕偄偄丄梩偵愭棫偭偰彫偝偔偰峠怓偺壴偑巐寧崰偵嶇偒丄栘慡懱偑峠偔尒偊傞丅慜壧偺壨幁偼僇僕僇僈僄儖偺帠偱丄梇偼旤惡偺帩偪庡偱偁傞丅
丂嬋偼昗弨揑側庤帠宍幃偱丄慜壧偲屻壧偵嫴傑傟偨庤帠偼嫗晽庤帠暔偺宍幃傪堷偒宲偄偱丄儅僋儔丒慜僠儔僔丒庤帠丒屻僠儔僔偲偄偆峔惉偲側偭偰偄傞丅偟偐偟壒偺悽奅偱偄偊偽丄偙偺庤帠偵偼慇嵶側塁偲梲偺懳徾偑暦偙偊偨傝丄堎側偭偨壒堟偵挷尲偝傟偨擇柺偺獾偑怐傝惉偡廳壒惈傕摿挜揑偱丄柧帯怴嬋偵偍偗傞條幃夵妚偺岲椺偲偄偊傛偆丅傑偨慜壧偲屻壧偼偲傕偵搑拞偱堦扷惷傑偭偰偐傜僥儞億傪懪偪懼偊偰丄埲壓丄愳偺棳傟傪昤幨偡傞偐偺傛偆偵棳楉側儕僘儉偲側傞丅媑懞偝傫偺杮庤(崅壒)偲怺奀偝傫偺懼庤(掅壒)偱嬋偺偙偆偟偨摿挜偑廫擇暘偵昞尰偝傟傞偙偲偩傠偆丅
侓棎丂敧嫶専峑
乽棎椫愩(傒偩傟傝傫偤偮)乿偲傕屇偽傟傞偙偺嬋偼丄敧嫶専峑嶌嬋偲揱偊傜傟傞獾偺撈憈婍妝嬋偲偟偰亙榋抜亜丒亙敧抜亜偲暲傫偱旕忢偵桳柤偱偁傞丅杮棃丄偙偆偟偨抜暔偼獾慻壧偺乽晅偗暔乿丄偮傑傝晅懏嬋偲偟偰嫵廗丒揱彸偝傟傞傕偺偱偁偭偨偑丄旂擏側偙偲偵尰嵼偱偼慻壧偼柵懡偵墘憈偝傟偢丄抜暔偑媡偵嬤悽獾嬋偺嵟屆揟嬋傪戙昞偡傞傛偆側懚嵼偲側偭偰偟傑偭偨丅
丂亙棎亜偼丄懠偺抜暔偲偼堘偭偰丄奺抜偺攺巕悢偼堦掕偟偰偄側偄丅偝傜偵丄僥儞億偺嶌傝曽傕懠偺抜暔偲偼堘偭偰偍傝丄備偭偔傝巒傑偭偰師戞師戞偵懍搙傪憹偟偰偄偔偺偱偼側偔丄墘憈壠偺夝庍師戞偱偼偁傞偑丄嬋拞偺強乆偵娚媫偺曄壔偑偄傠偄傠傒傜傟傞丅偮傑傝丄抜偺攺巕悢偺柺偱傕僥儞億偺柺偱傕丄偄傢偽帺桼帺嵼偵怢傃弅傒偟偰偄傞偺偱偁偭偰丄偙傟偑乽棎乿偲偄偆柤偺桼棃偵側偭偨偲峫偊傜傟偰偄傞丅
丂獾慻壧偵斾傋偰丄抜暔偺惉棫帠忣偼暋嶨偱丄懡偔偺帠偑偄傑偩晄柧偱偁傞丅亙棎亜偺敧嫶専峑嶌嬋愢偑弶傔偰彞偊傜傟偨偺傕埬奜抶偔丄1779擭偺彉傪帩偮亀獾嬋戝堄彺亁偺墱彂偵偍偄偰偱偁偭偨丅偙傟偵懳偟偰丄1822擭偺亀栱擵堦憼斉媘偺晥亁偵偼憅嫶専峑(?乣1724)嶌嬋偲偄偆愢偑婰偝傟偰偄傞丅敧嫶専峑偑妶桇偟偨17悽婭摉帪偵偼丄偡偱偵堦抜偁傞偄偼嶼抜峔惉偺亙傝傫偤偮亜乮亙椦愥偲傕亜乯偑柉娫偱棳峴偟偰丄獾丒嶰枴慄丒堦愡愗(広敧偺堦庬)偺崌憈偑峴傢傟偰偄偨傜偟偄.堦曽丄拀巼獾偵傕嶰抜峔惉偺亙椫愢亜偑偁偭偨丅撪梕揑偵偼柉娫偺亙傝傫偤偮亜偵傛偔帡偰偄傞偑丄偦偺愭峴娭學偑晄柧偱偁傞丅側偍丄謵啵偲偼杮棃偼夒妝偺獾偺媄朄偺堦偮偱偁傞偑丄偄偮偺傑偵偐婍妝嬋偺柤徧偲側偭偰偄偨偺偱偁傞丅
丂嶰抜峔惉偺傕偺偑暋嶨側峔惉偵敪揥偟偰丄偦傟傪崱偺宍偵嬤偄傕偺偵惍偊偨偺偑敧嫶専峑偁傞偄偼憅嫶専峑偲偄偆偙偲偵側傞偩傠偆偐丅偄偢傟偵偟偰傕丄偙偺晄媭偺柤嬋偼偙傟偐傜傕獾嬋偺戙昞揑側嶌昳偲偟偰揱偊傜傟偰偄偔偩傠偆丅崱夞偺墘憈偱偼丄崅搙側媄朄傪梫媮偡傞尰戙嬋傪悢懡偔墘憈偟偰偒偨媑懞幍廳偝傫偑丄亙棎亜偑愽嵼揑偵旛偊偨乽寖偟偝乿傪壒嬁偲偟偰偳偺傛偆偵嬶懱壔偡傞偐丄偦偟偰丄偦傟偵傛偭偰偙偺嶌昳偺怴偟偄柺傪偳偺傛偆偵愗傝奐偄偰偄偔偐丄戝偄偵婜懸偟偨偄丅
侓巆寧丂曯嶈擋醕
[慜抏]
丂堥曈偺徏偵梩塀傟偰丄[崌]壂偺曽(偐偨)傊偲擖傞(偄傞)寧偺丄岝傗柌偺悽傪憗偆(偼傛偆)丄
丂丂丂丂丂丂[崌]妎傔偰恀擛(偟傫偵傚)偺柧傜偗偒丄[崌]寧偺搒偵廧傓傗傜傫丅
[庤帠丂弶抜丒擇抜丒嶰抜丒巐抜丒屲抜丒僠儔僔]
丂崱偼揱庤(偮偰)偩偵濷栭(偍傏傠傛)偺丄[崌]寧擔偽偐傝傗傔偖傝棃偰丅
丂姲惌擭娫(1789乣1801)慜屻偺戝嶁偱妶桇偟偨丄曯嶈擋醕(惗杤擭枹徻)嶌嬋偺庤帠暔偺柤嶌亙巆寧亜偱偁傞丅曯嶈擋醕偼丄亙愥亜側偳偺抂壧偺嶌嬋壠偲偟偰傕桳柤偱偁傞偑丄戝嶁偵偍偗傞嶰枴慄庤帠暔宍幃偺妋棫偵戝偒側栶妱傪壥偨偟丄亙屷嵢巶巕亜亙墇屻巶巕亜側偳嶌昳傕懡偄丅偦偺拞偱傕亙巆寧亜偼摿偵擄嬋偲偝傟丄庤帠偺傒側傜偢丄壧堄偺昞尰傗愡偺媄岻偱傕曯嶈擋醕偺戙昞嶌偲昡偝傟偰偄傞丅
丂嶌帉幰偼晄柧偱偁傞偑丄戝嶁廆塃塹栧挰偺徏壆朸偺柡偑庒偔偟偰杤偟偨偺偱丄偦偺捛慞嬋偲偟偰嶌傜傟偨傜偟偄丅嬋柤偼屄恖偺朄柤乽巆寧怣彈乿偵偪側傓偲偄偆丅壧帉偼抁偄偑丄庒偄恖偺巰偵憳嬾偟偰堚偝傟偨恖乆偺怺偄斶偟傒傗嬻偟偝傪捝愗偵昞尰偟偰偄傞丅壧偼壧堄偵傆偝傢偟偔掅偄壒偱巒傑傝偢偭偲掅壒堟偑懕偔偑丄偦偆偟偨拞偱丄乽寧偺搒偺乣乿埲壓偱偺崅壒堟偺巊梡偼嵺棫偭偰岠壥揑側寢壥傪傕偨傜偡丅