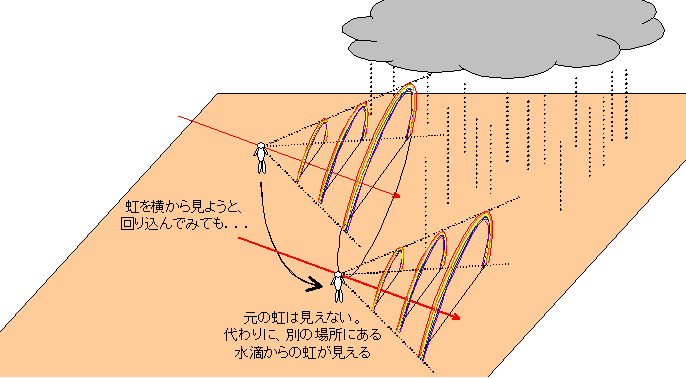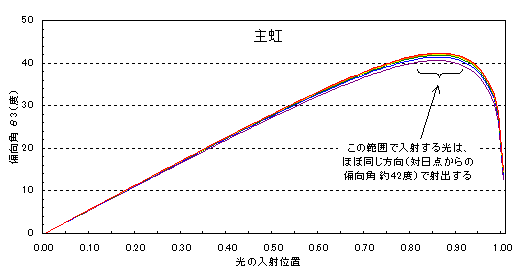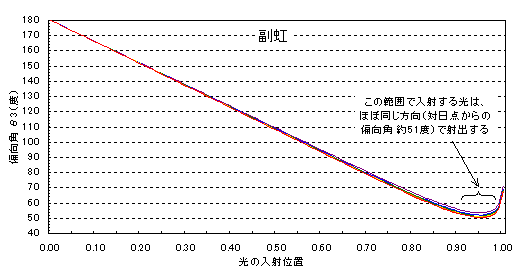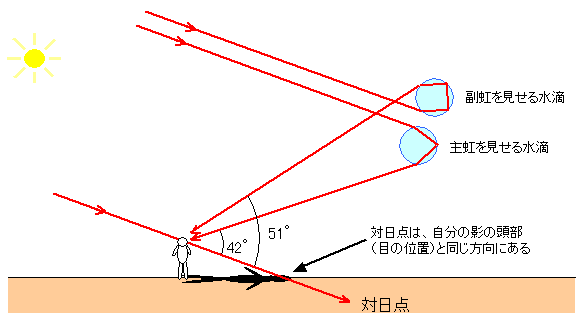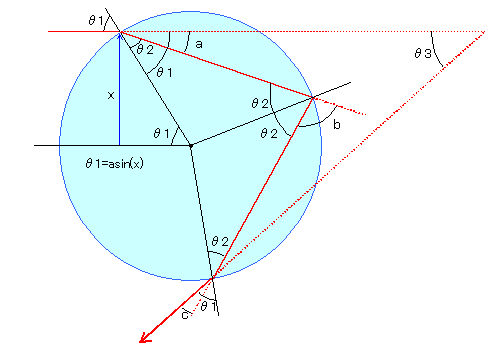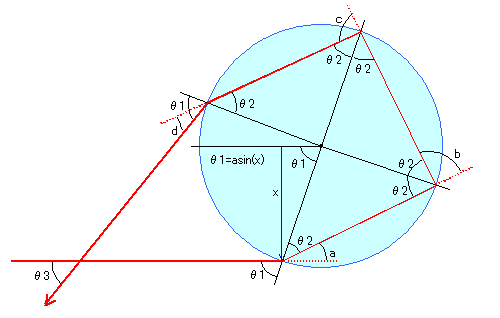太陽と雨がもたらす七色の光。
それは雨上がりの空に、突然現れた。
暗い空をバックに、鮮やかに立ち上がる2本の虹。
道行く人々が立ち止まり、空を見上げ、感嘆の声をあげる。
虹は、だれもが知っているけれども、いつも目にできるとは限らない天からの贈り物。
期間限定、音なし、短時間上映の自然科学映画だ。
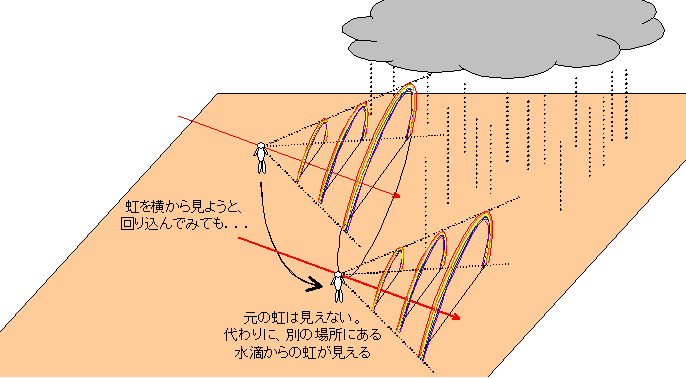
「虹 その1」で書いたように、虹(主虹)は観測者から見て太陽の真反対である”対日点”を中心とし、半径約42°の円上に(正確には「円錐面」上に)現れる。 図のように虹の横に回り込もうとしてみても、元の虹があったはずの場所には何もなく、別の雨粒からの虹が、同じく対日点方向の円錐面上に見えるだけだ。
残念だけど、「虹の出ている場所」とか「虹が立ち上がっている場所」というものは存在しないのだ。近づいてゆけば、虹はそのぶん遠ざかってゆく。

また、虹は42°の円錐面上に無数に分布する雨粒から屈折・反射してくる光なので、虹までの距離も特定できない。
例えば右の写真は足元からスプレー状の水が噴き出すプール施設で、太陽を背にして足元方向に現れた虹を撮影したものだ。このようなとき、虹はすぐ近くにあるはずだ。
しかし、約42°の円錐面上にある水滴すべてからの光が虹になっているわけだから、虹に触ることはできない。虹には実体がなく、触れそうで、触れない。虹は虚像でしかないのだ。
虹のできる原理は前回書いたけど、今回はさらに突っ込んで、いつものように(?)、ちょっとだけ理屈っぽく見てみよう。
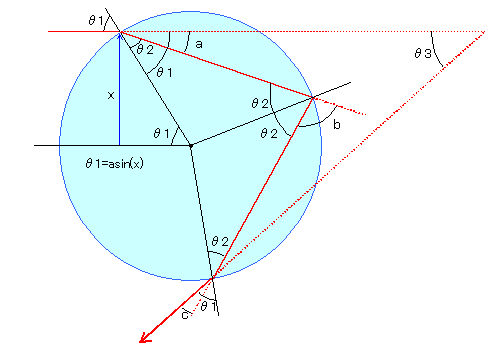
○主虹
球形の雨粒に太陽光が入射して内部で1回反射して出てくる様子を図示すると、左図のようになる。 雨粒の半径を1として、光が入射する位置をxとする(xは0〜1の数値)。 このときθ1は
θ1=asin(x)
で求められる。
空気の屈折率をn1、水の屈折率をn2として、光が入射角θ1で入射したとき、屈折の法則(スネルの法則)より
n1sin(θ1) = n2sin(θ2)
変形して
θ2 = asin(n1sin(θ1)/n2)
となる。
そして偏向角θ3は、下式で求められる。
θ3=180-(a+b+c)
=180-((θ1-θ2)+(180-2θ2)+(θ1-θ2))
=4θ2-2θ1
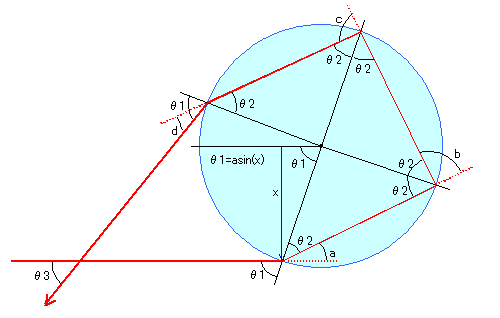
○副虹
ついでに副虹についても見てみよう。
副虹は、図のように雨粒内で2回反射して出てくる光によるものだ。 このとき、
θ2 = asin(n1sin(θ1)/n2)
となるところまでは主虹と同じだ。
次に副虹の場合の偏向角θ3を求めると、
θ3=a+b+c+d-180
=(θ1-θ2)+(180-2θ2)+(180-2θ2)+(θ1-θ2)-180
=2θ1-6θ2+180
となる。
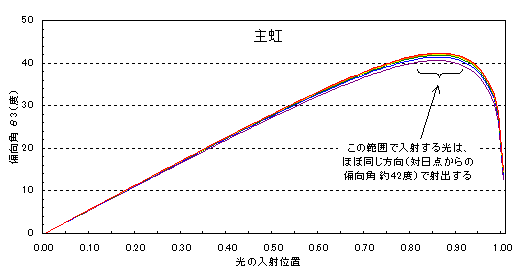
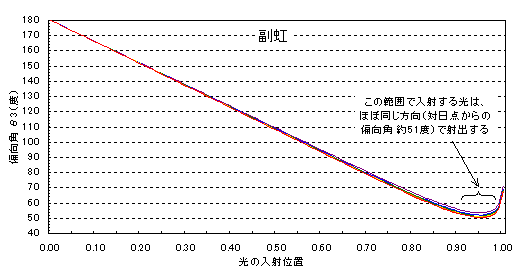
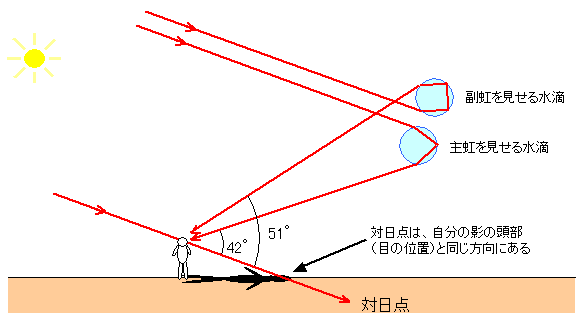
空気に対する水の屈折率は光の色(波長)によって違うが、可視光では1.3311(赤)〜1.3435(紫)程度。そこでn1=1, n2=1.3311〜1.3435を代入して、それぞれ入射位置xと偏向角θ3の関係を計算した結果が、上のグラフになる。
グラフを見るとわかることとして、主虹は偏向角42°付近に、副虹は51°付近に極値がある。雨粒に一様に入射した光は、様々な方向に屈折・反射して出てくるが、それが集中する方向がある。それが入射方向に対して約42°と約51°の位置で、そこに虹が見えるというわけだ。そこ以外に出てくる光は広い範囲に分散してしまい、様々な色が混じってしまうので色付いて見えることもない。
主虹と副虹でグラフの向きが逆なのは、主虹に対して副虹は光が上下に「ひっくり返って」出てくるためと解釈できる。この関係で、主虹と副虹では色の並び方が逆になっている。
副虹が主虹に対して幅広く薄く見えるのも説明できる。まず、薄く見えるのは1回反射の回数が多いために光が減ってしまう(反射する光もあるが、屈折しながら外に出ていってしまう光もある)から。次にグラフの極大部分を見ると、紫〜赤まで主虹は約2°の範囲だが、副虹は約3°と幅広くなっている。副虹は主虹よりも1.5倍程度の幅に広がって見えるというわけだ。
さらにグラフをよく見ると、主虹は約42°の極大よりも小さい方向(主虹の内側)には光が出ているが、大きい方向(主虹の外側)には出ていない。副虹の場合は約51°の極小より小さい方向(副虹の内側)には光は出ない。
これでどうなるかと言うと、主虹と副虹の間は屈折・反射して出てくる光が無いので、それ以外の場所より暗く見えるということになる。下の写真を見ても、それがお分かりいただけるかと思う。
5月上旬のこの日は上空の寒気の影響で、朝から雨が降ったり止んだりの不安定な天気だった。夕方、一時的に雲の切れ間から太陽の光が差し込むと、始めは一部だけ見えていた虹が、急速に鮮やかになった。
虹自体はけっこう頻繁に目にするが、空高く、端から端まで、アーチ全部がはっきり見える虹には、滅多に出会えない。
これほどはっきりとした虹を見るためには、太陽の光が強く、それに対して虹の背景が暗くなくてはならない。そのためには、降雨域と晴れている場所が混在しながら、それぞれがはっきり分かれている必要があるし、降雨域も均一に広がっている必要がある。また、大きなアーチ状になるためには太陽高度が低い、早朝か夕方でなくてはならない。しかし虹を出現させるような驟雨(にわか雨)は普通、西から東へと移動するから、虹は西に晴れた空と夕陽、東に雨雲がある夕方にしか見ることができない。会社勤めの場合、夕方は最も忙しい時間帯であることが多く、なかなか空を見上げる機会もない。
そんなわけで、大きな虹はかなり運が良くないと見られない、天に架かる橋なのだ。

○撮影データ(ページ上の写真より)
・1段目
日時:2009年5月8日 場所:東京都江東区
カメラ:ペンタックス *istDS レンズ:SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC
その他:プログラム露出 F6.7 1/125秒 ISO200相当 JPEG撮影
道行くサラリーマン・OLが空を見上げ、空高くアーチを描く虹を携帯電話のカメラで撮影していました。
・2段目
日時:2003年8月23日 場所:埼玉県滑川町
カメラ:ニコン ニコノスV レンズ:Wニッコール35mmF2.5
フィルム:ベルビア50 +1増感
埼玉県の武蔵丘陵森林公園にあったプール(平成17年度で営業終了)に、足元から霧状の水が噴出する場所がありました。水中眼鏡がないと目も開けてられないくらいの勢いで水が出ていて、足元にはっきりとした虹を見ました。
・3段目
日時:2009年5月8日 場所:東京都江東区
カメラ:ペンタックス *istDS レンズ:SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC (撮影時22mm)
その他:プログラム露出 F6.7 1/180 ISO200相当 JPEG撮影
この日、東京では各地で、とても綺麗な虹を見ることができました。ここまではっきりと、端から端まで均一に虹が見えるのは滅多にないことです。しかし35ミリ判換算で28mm程度の広角レンズでは、虹の全体を撮ることはできません。こんなときに限って、超広角レンズを持ってきていなかったりするのです。
|
|