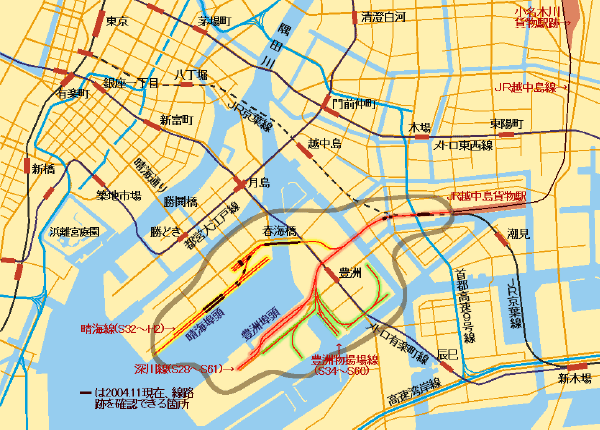ここでは番外編として、空だけではなく地上の風景についても採り上げてみます。最初は、東京港にかつて存在した貨物鉄道についてです。
子供の頃よく見た国鉄の貨物列車。オレンジ色に塗られたディーゼル車が、長大な貨車の列を引っ張っている。
いったい何両の貨車を引っ張っているのか興味をもち、1両…2両…3両…と、連結されている貨車を数えた。
数えるのが飽きるほど貨車の列は長く続き、30両を超える編成も珍しいものではなかった記憶がある。
それらに積まれた貨物は、体内の血管を流れる血のように、鉄道によって全国を流通する。だけど、けっきょく貨物列車というのはレールが敷かれている所しか移動できないわけで、したがって貨物駅の周辺でしか、その大量輸送の恩恵にあずかれない。
二酸化炭素排出量の削減をはじめとする地球環境の保全のためには、鉄道による貨物輸送を効果的に組み合わせたほうが優れているはずだが、そういう環境に配慮した考え方が主流になったのは、かなり後になってから。
産業の発達に伴って、好きな場所へ、好きな時間に、しかも鉄道よりも早く荷物を輸送できる自動車(トラック・トレーラー)輸送にその主役を奪われていったのは、仕方ない流れだったのかもしれない。
輸送量の減少した貨物路線は旅客用に変更され、再びたくさんの列車が往来する路線として復活することもごく稀にある。でも大部分が、そのまま線路一式まるごと廃止されることになる。
そして線路は周辺の再開発の波に飲み込まれ、道路になったり建物が建ったりして、その跡を消してゆく。運良く消えずに残った線路も、手入れが全くされないから、草に覆われ朽ちてゆく。
その、俗に「廃線」と呼ばれる鉄道の線路跡は、朽ち具合・消え具合が何とも言えない雰囲気を醸し出すようになる。

○都会の廃線
例えば自転車で都心から湾岸の新木場・お台場方面へ向かうとき、日比谷→銀座→築地を通り勝どき橋で隅田川を渡り、勝どき→晴海→豊洲→東雲を経て湾岸道路へ抜ける晴海通りを使うのが最短ルートだ。
この途中、晴海と豊洲の間にある春海橋を渡るとき、すぐ近くに平行して赤錆びた鉄橋が架かっているのに気づく。
よく見ると橋には単線の線路が敷かれているものの、その先に線路の続きは見えないし、そもそも地図にも線路なんか載っていない。
後日、改めて周囲を探索してみると、かなり断片的だけど線路の跡らしきものを発見した。それが今回の主題、東京都専用線(深川・晴海線)を知ったきっかけだった。
ふつう廃線というと、人里離れた山の中を連想しがちだが、ここは有楽町や銀座といった都心部からわずか数キロの、近代的なビルや高層マンションが立ち並ぶ場所だ。こんな所に廃線があるなんて面白い。なんとも探究心をくすぐられる物件ではないか。
いつも空や雲を見上げていた視線を地面にも向けさせてくれた、これがそのきっかけだった。

○東京都専用線
東京港を管理する東京都港湾局が敷設した、東京都専用の臨港鉄道。臨港鉄道とは、港湾に出入りする貨物を運ぶのを主たる機能とする鉄道のことをいう。
その中で深川・晴海線と呼ばれる路線は、江東区塩浜二丁目の国鉄越中島駅(現在のJR越中島貨物駅)を起点として西へと伸び、晴海や豊洲の各埠頭の間とを結んでいた。さらにこれらの東京都専用線から、民間会社専用の分岐線もいくつか作られ、それぞれの会社の敷地内へと引き込まれていた。
ちなみにJR越中島貨物駅は今も健在で、構内にあるJR東日本の東京レールセンターから搬出される鉄道用のレールを、小名木川貨物駅跡を通り亀戸駅付近で総武本線と合流して新小岩操駅へと至る、JR越中島線で運んでいる。(右の写真)
このJR越中島線、線路や駅などの施設は総武本線の枝線としてJR東日本が保有しているが、列車の運行はJR貨物が行っており、実態としては貨物(レール輸送)専用線となっている。
さて、本題の東京都専用線の深川・晴海線は、以下の三つの線路群に分けられる。いずれも15年以上前に、すべて廃止されている。
- (1)深川線 (国鉄越中島駅〜豊洲石炭埠頭間)…昭和28年開通、昭和61年廃止
- 昭和25年に豊洲石炭埠頭が開業したのにあわせて整備された、国鉄越中島駅の分岐点から塩浜・豊洲を経て、豊洲石炭埠頭へと至る延長約2.6kmの東京都専用線。豊洲では石川島播磨重工業の東京第一工場と第二工場の中を抜けていた。
現在、同工場は移転し、再開発が急速に進んでいる。この深川線、豊洲埠頭付近では豊洲線と呼んだこともあったようだ。
昭和36〜45年頃は豊洲物揚場線と合わせて年間100万トン程度の貨物を取扱っていた。約80%は石炭・コークスで、他に鉄鋼や鉱石類を運んでいた。
- (2)豊洲物揚場線 (深川線分岐〜豊洲物揚場)…昭和34年開通、昭和60年廃止
- 深川線の分岐線として、主に内貿(国内の港との貿易)雑貨を扱う豊洲物揚場へと延びていた専用線。略して物揚線と呼ぶこともあった。
途中で分岐し、かつて存在した東京電力の新東京火力発電所や東京ガスの基地へ石炭・コークスを運ぶ線路もあったが、石炭から石油・LNGへの燃料転換が進んだため、早々に姿を消した。
- (3)晴海線 (深川線分岐〜晴海埠頭)…昭和32年開通、平成元年廃止
- 豊洲三丁目の中央付近にあった深川線分岐から晴海通りの踏切を通り、豊洲と晴海を隔てる晴海運河をあの赤さびた鉄橋で渡り、晴海埠頭へと至る線。かつて晴海にあった東京国際貿易センター(晴海見本市会場)の脇を通り、突端にある晴海客船ターミナルの手前まで達していた。主な取扱貨物は新聞用巻取紙、輸入小麦・大豆など。
埠頭沿いの線路脇には1号から5号までの上屋(うわや、と読む。貨物船から降ろしたり積んだりする際に、貨物を一時的に仮保管するのに使う倉庫のこと。屋根があるから雨に濡れないため、新聞用巻取紙などの仮保管に最適。)と野積場(石炭など雨に濡れてもいいものを仮保管した。上屋より保管料金が安い。)、そして民間会社の倉庫が並び、ピーク時の昭和46年には70万トンを超える取扱貨物量があった。晴海通りに近い部分には線路がいくつにも分岐した、ヤードと呼ばれる貨物列車の操車場があり、貨車の入換え作業が行われていた。
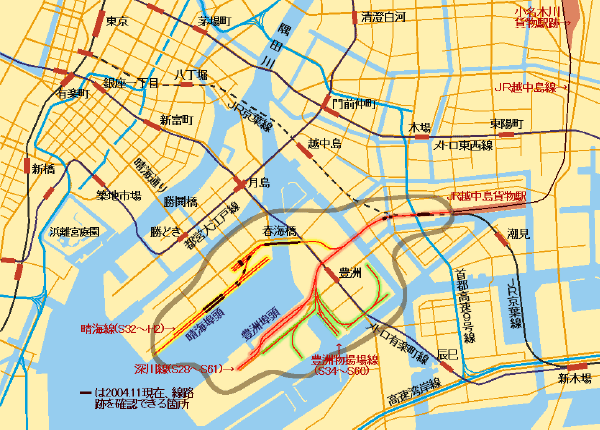
貨車は、例えば深川線では重量約60t、1000馬力の動力車(ディーゼル機関車)で引っ張られていた。昭和60年頃の専用線設備使用料は、貨物1トンにつき100m毎に9円で、専用線設備のうち動力車のみの使用料は、その5割の額だった。
鉄道の運行管理は当初東京都港湾局が行っていたが、昭和44年に(社)東京ポートサービス協会へ、昭和56年に(財)東京港サービス公社へ、昭和63年に(財)東京港埠頭公社へと委託されていった。
ちなみに全線が廃止されている現在、管理は所有者である東京都港湾局が行っている。さらに細かく言うと、土地については未利用地として東京港防災事務所の埋立地管理課が、今も残る鉄道施設は東京港管理事務所の港務課がそれぞれ管理している。
○東京都専用線の現在
昭和40年前後を中心に隆盛を誇った臨港鉄道も、昭和40年代後半から高速道路など道路網の拡大を背景とする、自動車輸送への転換が進んでゆくに伴い、取扱貨物量も減少していった。
この流れは変化することなく続き、昭和60年1月16日には豊洲物揚場線が供用を廃止、昭和61年1月13日には豊洲三丁目にある晴海線との分岐から豊洲石炭埠頭に至る深川線が廃止され、最後まで残った晴海線も平成元年2月10日に廃止されたことにより、東京港の臨港鉄道は全て姿を消すことになった。
東京港で水揚げされた大量の貨物を運び、国鉄(JR)の鉄道を通して全国へ輸送した臨港鉄道。その歴史は戦前から始まり、日本の高度経済成長を支えてきた。しかしわずか半世紀の後には、ディーゼル機関車と貨車の列は、人々の記憶の中へと走り去った。

全線廃止から15年を経た今、かつて鉄道の走っていた地区は再開発が進んでいる。ほとんどの区間で線路は剥がされ、ビルやマンション、道路や駐車場になっている。
それでも、当時の名残りを残す箇所や、線路そのものが残っている部分もある。
その代表と言えるのが、晴海と豊洲の間にある晴海運河に架かる例の鉄橋、昭和32年に完成した東京都専用線 晴海橋梁だ。アーチ型の鉄桁の表面は赤錆だらけだが、存在感あるがっしりした作りからは、手入れさえすればまだ使えそうな雰囲気が伝わってくる。
ちなみにこの晴海橋梁の発注者は東京都港湾局だが、設計は国鉄施設局が、製作は石川島重工業株式会社(現在の石川島播磨重工業株式会社)が行なった。開床式(橋の床が開いている)の鉄橋で、下路式鋼アーチ橋の一種、ローゼ桁と呼ばれる構造をしている。
アーチ橋というのはトンネルや深い谷に架かる橋によく見られる、半円状のアーチ構造で重量を支える構造の橋のこと。鋼材を用いているから鋼アーチ橋と言い、アーチ構造の下に線路があるから”下路”式という。
ローゼ(Lohse)桁というのは、その構造を考案した人の名前からきている。優雅な曲線を描く上弦のアーチと下弦の直線状の部材には、曲げ剛性のある丈夫な鋼材が使われ、両者の間は垂直の吊材で繋がっている。これがローゼ桁の特徴だ。
鉄道用の橋としてはかなり珍しいタイプのようで、その風格ある外観と共に、歴史的な建造物といった雰囲気を感じさせる。

これ以外にも、例えば晴海埠頭沿いの上屋や倉庫の立ち並ぶ所に、わずかだが線路の跡を確認できる場所がある。
当時ここには何本もの線路が走り、貨物列車が行き交っていた。今その場所はトラックやトレーラーが走る道路になっているが、レールを剥がさずそのまま上からアスファルトが敷かれたため、路面に微妙に線路の凸凹が浮き出ていたり、アスファルトの破損部分からレールが覗いている箇所がある。(右の写真)
現在、この近くで晴海から東雲への晴海通りの延伸に伴う晴豊1号橋(仮称)の工事が行われている。そこでは地形じたいが変わってしまって廃線どころではないが、東側にもまだ線路が残っている箇所がわずかに見られる。
豊洲周辺は石川島播磨重工業の工場移転に伴う公園や大学の建設、また豊洲六丁目の豊洲埠頭周辺は上記の晴豊1号橋(仮称)の工事や新交通ゆりかもめの有明〜豊洲間延伸工事など再開発ラッシュ中で、線路跡は残っていないし、もしあったとしても工事中のため、基本的に立ち入ることはできない。
一方、深川線の越中島貨物駅方面は、一部だが線路や、その名残を確認できる箇所がある。豊洲運河には橋桁部分は撤去されたものの橋脚が残っているし、塩浜二丁目の都道319号西側には10m程度だが、線路がそのまま残されている。
その他、かつて線路のあった場所の多くは駐車場や空き地になっているが、微妙なカーブ度合いが鉄道のあったことを彷彿させる所もある。
○東京都専用線の今後
前述したようにこの周辺は再開発がめざましく、現在廃線が残っている箇所も来年(平成17年)早々にはほとんど撤去され、更地にしてしまう予定になっているようだ。
流通・交通の分野は、常に新しいものや効率的なものを追い求める。おまけに再開発の著しい都心部にあっては、こういう過去の遺構が保存されずに廃棄されるのは珍しいことではない。あと何年か経ったら、廃線の完全消滅と共に、東京港に鉄道が走っていたという事実も風化してゆくことになりそうだ。
ただし東京都専用線 晴海橋梁については、東京港管理事務所に問い合わせたところ、とりあえず撤去する予定は今のところ無いとの事だった。なにしろあれだけ大きくて頑丈そうな橋だから、撤去するとしても数億円といった単位の費用が必要になる。今にも腐り落ちて事故になりそうな橋ならともかく、さしあたって撤去する緊急の理由がない橋に多額の撤去費用をかけるほど、東京都の財政に余裕はないのだろう。
要するに東京都の財政難のお陰?で、東京都専用線の晴海橋梁はしばらくは生き残りそうだ。
それともうひとつ、東京都港湾審議会の出している「第7次改訂港湾計画の基本方針」に、運河ルネッサンスというものが提言されている。これは都市機能と港湾機能の秩序ある共存を目指して、水辺の賑わい・魅力づくりのために運河を再生・活用するという構想だ。この運河ルネッサンス構想の一環として、かつて東京港を走っていた臨港鉄道のモニュメントとして東京都専用線の晴海橋梁が採り上げられれば、観光資源として整備・保存される可能性も開ける。
実際、この橋は建設から50年近い歴史をもちつつ、今後もある程度の使用に耐えられそうな建造物だ。個人的にはぜひとも観光資源としての保存が実現して欲しいなと思う。

さらに、晴海のとある場所に現存する古ぼけた機関庫の中には、15年の年月を経て今も2台の青いディーゼル機関車が眠り続けている。
所有している東京港管理事務所では、引き取ってくれる人を探しているようだ。(来年までに引き取り手が見つからない場合、残念ながらスクラップとして解体される運命にある。)
参考までに、この機関車の仕様は下記の通り。
| 機関車名 |
60-7 |
60-8 |
| 品名 |
ディーゼル機関車 |
ディーゼル機関車 |
| 型式 |
HG60BB型60D |
日立D60-8型60t |
| メーカー |
汽車製造株式会社 |
株式会社日立製作所 |
| 重量 |
約 60t |
約 60t |
| 製造年 |
昭和37年 |
昭和43年 |
| 車体寸法 |
14.3m×2.6m×3.822m |
14.3m×2.6m×3.822m |
最後に、東京都専用の臨港鉄道についての年表を掲載しておきます。赤字が、今回採り上げた深川・晴海線関連の出来事です。
(参考文献「東京都専用線のあゆみ」より引用)
|
年 表
|
- 昭和5年7月31日
- 東京市、芝浦臨港鉄道敷設工事完成
(汐留駅〜芝浦駅)
- 昭和5年8月1日
- 鉄道省、汐留駅〜芝浦駅間 開通
- 昭和16年5月20日
- 東京港 開港
- 昭和19年9月2日
- 東京都、越中島駅敷地を鉄道省に引継ぐ
- 昭和20年3月
- 鉄道省、小名木川駅〜越中島間に鉄道を敷設
- 昭和25年11月17日
- 東京都、豊洲石炭埠頭開設
- 昭和28年7月20日
- 深川線(越中島〜豊洲石炭埠頭)開通
国鉄による入換、仕訳作業(小名木川駅分岐東京都専用線深川線使用開始)
- 昭和29年10月11日
- (社)東京ポートサービス協会設立
- 昭和32年12月17日
- 晴海線(深川線分岐〜晴海埠頭)開通
国鉄による入換、仕訳作業開始
- 昭和33年5月8日
- 東京都、晴海埠頭構内線の貨物仕訳作業を(社)東京ポートサービス協会に委託
- 昭和33年11月10日
- 国鉄、越中島駅(※現在のJR越中島貨物駅)を開設
- 昭和34年3月30日
- 豊洲物揚場線(深川線分岐〜豊洲物揚場)開通
- 昭和34年3月31日
- 東京都、芝浦埠頭線改良一部竣功
- 昭和34年4月1日
- 東京都、専用線補修作業を(社)東京ポートサービス協会に委託
- 昭和35年4月1日
- 東京都、越中島駅分岐以降の都専用線及び会社専用線における貨車仕訳作業を(社)東京ポートサービス協会に委託
|
|
- 昭和36年4月1日
- 東京都、専用線(芝浦線)貨車仕訳作業を(社)東京ポートサービス協会に委託
- 昭和39年3月31日
- 東京都、日の出埠頭線の改良工事完成
- 昭和40年4月1日
- 晴海埠頭日通倉庫進出に伴い晴海線延伸
- 昭和40年4月1日
- 東京都、専用線(日の出線)貨車仕訳作業及び日の出線列車諸施設点検、整備、維持、補修等を(社)東京ポートサービス協会に委託
- 昭和41年10月1日
- 国鉄、越中島駅において貨車仕訳及び列車組成作業開始
- 昭和44年4月1日
- 東京都、(社)東京ポートサービス協会への作業委託を管理委託へ移行
- 昭和55年12月18日
- (財)東京港サービス公社設立
- 昭和56年3月31日
- (社)東京ポートサービス協会解散
- 昭和56年4月1日
- (財)東京港サービス公社が事業を引継ぐ
- 昭和60年1月16日
- 豊洲物揚場線(深川線分岐〜豊洲物揚場)供用廃止
- 昭和60年3月1日
- 東京都専用線(芝浦・日の出線)供用廃止
- 昭和61年1月13日
- 深川線(晴海線分岐〜豊洲石炭埠頭)供用廃止
- 昭和63年3月31日
- (財)東京港サービス公社解散
- 昭和63年4月1日
- (財)東京港埠頭公社が事業を引継ぐ
- 平成元年2月10日
- 晴海線(深川線分岐〜晴海埠頭)供用廃止
|
参考文献:
東京都専用線のあゆみ 東京都港湾局、(財)東京港埠頭公社 平成元年2月発行
東京港利用案内 1984-85 (社)東京都港湾振興協会
東京港と京葉港 海洋出版企画(株) 1988年10月10日発行
東京港史 東京都 昭和37年3月31日発行
東京港史 東京都 昭和47年3月31日発行
東京港史 第一巻 通史1 各論1 東京都港湾局 平成6年3月31日発行
東京港史 第二巻 資料 東京都港湾局 平成6年3月31日発行
鉄道廃線跡を歩くVII JTBキャンブックス、宮脇俊三 編
鉄道構造物探見 JTBキャンブックス、小野田 滋 著
鉄道ジャーナル 1989年2月号 鉄道ジャーナル社
図解 橋梁用語辞典 山海堂 佐伯彰一 編 昭和61年11月30日発行
三千分の一地形図 東京都建設局刊 昭和37年 他
|
※追記(平成17年11月)
その後、機関庫は平成17年10月、撤去されました。
○撮影データ(ページ上の写真より)
・1枚目
日時:2004年11月 場所:東京都中央区
カメラ:ペンタックス MZ-5 レンズ:ペンタックス SMC F Fish-eye Zoom 17-28mm F3.5-4.5
フィルム:ベルビア100 その他:絞り優先F3.5
晴海通り・春海橋の歩道から魚眼レンズで見た、東京都専用晴海線 晴海橋梁。
・2枚目
日時:2004年11月 場所:東京都江東区
カメラ:ミノルタ TC-1 レンズ:ミノルタ G-ロッコール 28mm F3.5
フィルム:ベルビア100 その他:絞り優先 F5.6
亀戸と越中島貨物駅を結ぶ単線・非電化のJR越中島線、撮影場所は江東区新砂。近くには踏切も数箇所あり、都会では珍しくなった風景が沿線で見られます。ディーゼル機関車(DE10)がレール輸送専用の貨車(車両番号チキ)を引っ張り、一日数往復します。推定も入っていて定かではありませんが、私が見た限りでは、越中島貨物駅に貨物列車が到着する時刻が9:25と12:45と15:10、レールを積んで出発する時刻が10:00と13:20と15:45というのが標準のようです。
・3枚目
日時:2004年11月 場所:東京都江東区
カメラ:ミノルタ TC-1 レンズ:ミノルタ G-ロッコール 28mm F3.5
フィルム:ベルビア100 その他:絞り優先 F8
豊洲側から見た、夕暮れの東京都専用晴海線 晴海橋梁。背後に晴海二丁目のセメント工場が見えます。
・4枚目
日時:2004年11月 場所:東京都中央区
カメラ:ペンタックス MZ-5 レンズ:ペンタックス SMC F Fish-eye Zoom 17-28mm F3.5-4.5
フィルム:ベルビア100 その他:シャッター速度優先1/125秒
晴海埠頭の倉庫街。今はアスファルトで舗装されていますが、レールを剥がさずに舗装されたために、かつての線路の面影を偲ぶことができます。
・5枚目
日時:2004年11月 場所:東京都中央区
カメラ:ミノルタ TC-1 レンズ:ミノルタ G-ロッコール 28mm F3.5
フィルム:フォルティア その他:絞り優先 F3.5 -0.5EV補正
雑草と低木の生い茂る中にひっそりと残るレールと、右手奥にある機関庫。湾岸の埋立地に、このような雰囲気の場所が存在していること自体が、一つの奇跡です。
|
|