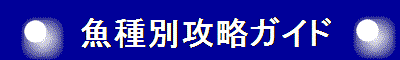 |
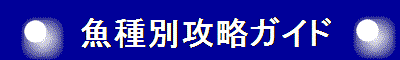 |
魚種別攻略ガイドは2016年11月末まで@Niftyつりに掲載されていた物を再掲したものです。
クロメバル(正式名はメバル:カサゴ目フサカサゴ科)
メバルの仲間内では一番岸に近い浅場に住んでいる。住みか(岩場、藻場)の色によって黒や金、白っぽい褐色と体色に違いが出る。
また、釣り方やエサによってもイワシメバル、エビメバル、魚皮メバルなどと呼ばれ方が変わる。初春の小型活きイワシをエサにしたイワシメバルは軟らかい竿で穂先が海中に絞り込まれるまで食い込ませる小さな大物を泳がせで狙う楽しい釣りの一つだ。
食べても筍と一緒に薄味に煮たタケノコメバルなんて季節を表す言葉もある。でも、タケノコメバルという種類のメバルの仲間もいるから話は厄介だ。春告魚とも言われ、季節を感じさせる魚の代表だ。
【タックル】
メバルは向こうあわせの釣りなので、エサを加えた時に違和感を感じさせないような6:4位の胴調子竿が適している。長さも2.4〜3mの長目の竿が食い込みが良く、視覚的にも楽しい。
しかし、風の強い日は竿が煽られて釣り難いだけでなくアタリも分かり難くなってしまうので短目を予備竿として持参すると安心だ。使用するオモリが地域、船宿により20〜50号と違いがあるので要注意、50号で理想的な竿が30号でも良い訳ではないので実際にオモリを下げてみて、やや負け気味位が良い。
リールは小型両軸にPE2〜3号が100m以上巻いてあればOK、水深の変化が激しい根周りを釣るのでクラッチ操作がしやすい機種が望ましい。
【仕掛け】
一部の地域で行われるコマセを使った釣り方を除けば、ほぼ胴突仕掛けが使われている。
使用するエサによってハリスの長さが多少異なるが、目が大きく良いとされているためか全般的に細めの仕掛けで接続具に金物を使用しない場合が多い。幹糸2〜4号、ハリス1〜3号30〜60cmで透明なクロスビーズ小を使って接続する。枝間はハリスの2倍の長さを目安とし、ハリ数は2〜4本、ハリは軽めのメバル専用10〜11ヤマメバリ10〜11号、丸セイゴ12〜14号、丸カイズ12号などを使用する。サルカンやスナップ類も可能な限り小型のタイプを使用したい。
【まるかつの仕掛け】
外房・茨城用として幹糸4号×ハリス2.5号30cm丸セイゴ5本バリ、ソイ兼用で幹糸4号×ハリス3号30cm丸セイゴ2本バリ、活きイワシ用で幹糸2号×ハリス1号50cmメバル専用2本バリ、エビエサ用で幹糸2号×ハリス1.5号30cmメバル専用3〜4本バリの4種類のバリエーションで仕掛けを常時ストックしている。根係りやハリスのパーマで消耗が激しいので予備の仕掛けも多めに用意しておきたい。替えハリスの準備も必要だ。
【エサ】
シコイワシ、エビ、イカナゴ、サバ短冊などを使用するが、生餌があれば反応がより高くなる。
【釣り方】
まずエサの付け方だが、真っ直ぐになるように丁寧に付ける事が重要だ。曲がった状態や中心から外れた状態だと水中で回転しハリスがすぐにパーマしてしまう。また活きエサの場合は手早くエサ付けし、弱らせないように注意しよう。
底近くに群れている魚だが大型ほど群れの上の方にいると言われている。(エサをとるのに有利)底ダチを取ったら50cmからmタナを切って静かに待つが、タナが低すぎるとベラやカサゴに食われる事が多くなってしまう。
但しクロメバルの釣れる根には、ヒラメ、クロソイ、ムラソイ、ヒラメなどの大型も潜んでいる。強いアタリが来たら、直ぐに根から引き離し早めに巻き上げる様にしたい。
(クロソイ)
よっぽど活性が高い時は別だが一気に食い込んでハリ掛かりすることは少ない。エサを見つけて咥えたりつついたりする時に小さなアタリが来るがこの時に竿を動かしてしまうとまずハリ掛かりしない。食い込んで反転した時にキューンと竿先が絞り込まれるが、ここまで我慢する事が肝心で決して合わせてはいけない。
あとは小気味良い引きを楽しみながら静かにリールを巻けば良い。
食いが良くハリ数が多い場合はリールを一巻きして追い食いを待つが、欲張って待ちすぎて最初の魚をバラしてしまわない様ほどほどのところで巻き上げに入ったほうが良い。しかし、メバルは群れている魚なのでこの辺りの加減が難しい所だ。
メバルは最初の一撃は強烈だが、後は断続的な引きになる。仕掛けが細いので船が波で持ち上げられた時に突っ込まれてリールを巻く手を止めないと簡単にハリスがプッツンという事になってしまう。型が良いなと思ったら巻き上げ途中にも気を使い、あらかじめドラグの調整もしっかりしておくことが大切だ。