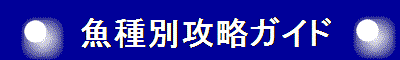 |
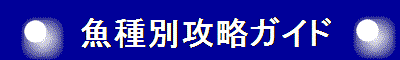 |
魚種別攻略ガイドは2016年11月末まで@Niftyつりに掲載されていた物を再掲したものです。
ブリスズキ目アジ科)

![]()
ご存知、代表的な出世魚である。関東ではモジャコ→ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ、関西ではモジャコ→ツバス→ハマチ→メジロ→ブリと名前が変わる。
3kgを超えるとやっとワラサと呼ばれるが、2〜3kg位のものを「サンパク」と呼んだりもする。左の写真の魚が3.5kg〜4.5kgだが、8kgを超えてやっとブリと呼ばれる。
イナダ・ワラサクラスはコマセで釣るのが大半(一部泳がせも)だが、ブリクラスは泳がせで狙う。使う餌によって、イカブリ・アジブリ・カマスブリなどと呼ばれ晩秋から初冬に乗合船が大磯〜網代辺りで出る。
食べては刺身、カマ焼き、照り焼き、大根との煮物、しゃぶしゃぶなど、脂の乗り切った最高食材を堪能できる。
【タックル】
2m前後の短めで胴のしっかりしたワンピースロッドが掛かってから主導権を魚に取られる事なくオマツリやバラシが少ない。
掛けてからサメにやられずグイグイ巻き上げる事ができるパワーのある中型以上の電動リールが必須。道糸はPE6号以上が300m以上巻けるスペックが必要だ。カマスブリなどはカマスの泳層が200mを超える場合もあるので、余裕のある糸巻き量または替えのリールも視野に入れて準備したい。
【仕掛け】
幹糸20号1mの先に親子サルカンを介してハリスを接続、捨て糸は無しでダブルスナップなどで直接接続する。オモリは海域・船宿によっても異なるが120〜150号を使用する。
ハリスはフロロカーボン12〜16号を使用する。
ハリはヒラマサ14〜16号、ムツ19〜20号などの軸のしっかりしたタイプを使用する。
予想される魚が大きい場合はハリのチモトに編みつけして補強したほうが良い。
【まるかつの仕掛け】
ハリス14号1.5m、ハリはヒラマサ15号の1本バリ。(アジ・カマス)
ハリス14号1.5m、ハリはムツ19号(親孫共)の2本バリ(イカ)
【エサ】
ヤリイカ、スルメイカ、アジ、小サバ、アカカマスを活き餌で使用する。活きイカが釣れない場合に死にエサを使用する場合もあり。
【釣り方】
まずはエサ釣りからスタートというスタイルが一般的。一部船でエサが準備されている場合もあるが、それを買うスタイルになる。従ってエサ釣り用のタックルも用意しなければならない。(イカ・アジ・カマス)
船長指示によるが、底まで落としてから3〜5m巻き上げてアタリを待つ。
食い気があって魚がいればタナを取った直後に餌を加える前アタリが訪れ、しばし待つと竿先がズドンと海中に突っ込むはずだ。前アタリがあって1〜2分待って食わなければ、エサを取られたと判断し入れ替えを行うように手返しを心がける。
同船者や隣の船で食った時はチャンスなのでタナをしっかり確認する。
魚が掛かったら、強く引き込む時はリールを巻かず竿の弾力とドラグで凌ぎ、重く感じるだけの時はどんどんリールを巻く。魚はあがってくると船影に逃げようと船下に入ることがよくあるので、そんな時は糸を手繰らずテンションだけかけていると自分から円を描くように泳いで出てくる。この直後にスパッとタモ取りするのがコツである。
タモ入れは必ず頭から、タモに入った瞬間にハリスを緩めればブリはあなたの物だ。ハリスを緩めないと飛び出してしまうことがあるので注意しよう。
1本獲れれば大満足の獲物、食いの立った時に集中することが何より大切だ。