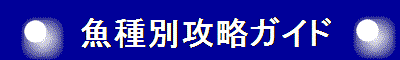 |
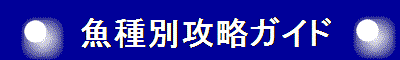 |
魚種別攻略ガイドは2016年11月末まで@Niftyつりに掲載されていた物を再掲したものです。
アカムツ(スズキ目ホタルジャコ科)
本州中部以南の水深100〜300mに生息していて、日本海側ではノドグロと呼ばれ珍重されている。ムツと名前についているがムツ科ではなく、ホタルジャコ科に属しています。(以前はスズキ科に分類されていました)
関東ではあまり生息数が多いので、なかなか狙って釣ることができませんので年に1〜2回お目にかかれば良い方です。最近は秋から冬にかけて鹿島、波崎エリアで乗合船が出ていて人気のターゲットになってきました。味は根魚の中でも最高で、刺身、煮付け、鍋とどんな料理でも美味しく、全長最大50cm、2kgほどまでに成長します。
【タックル】
中深場(150m前後)で120〜150号オモリ、深場(300m前後)で200〜250号オモリを潮の速さに応じて使います。
アタリが取りやすく魚が掛かってから胴に乗るような2m前後の竿が適しています。 アジビシ竿やイカ竿、中深場竿の中から調子を見て選びます。
リールは中深場ではPE3〜4号が300m巻ける電動リール、深場ではPE6〜8号が500m以上巻ける物が良いでしょう。
【仕掛け】
胴突2〜3本バリ仕掛け、又は中〜大型片天びん使用の2〜3本バリ吹流し仕掛けを使用します。
胴突は幹糸8〜10号ハリス6〜8号で枝間1〜1.5m、ムツバリ16〜18号、枝スは40〜60cmで親子サルカン・クロスビーズなどを使用して接続します。
吹流し仕掛けはオニカサゴの仕掛けに準じた物を使用します。
ビーズ類などのデコレーションは効果がある場合があります。水中ライトは胴突仕掛けの場合は効果があると思います。
デコレーション、水中ランプなどの光物はサメや外道が多い時などは外して対応する事が重要です。
【まるかつの仕掛け】
中深場では幹糸7号で上糸100cm、枝間は130cm、捨糸は5号100〜150cm。ハリスは6号60cm、ハリはホタ16号で中位の大きさの親子サルカン接続した2本バリ仕様。
デコレーションはソフトタイプの夜光玉3.5号グリーン、ピンク、水中ランプは小型の赤色点滅を使います。
深場では幹糸10〜12号で上糸100cm、枝間は150cm、捨糸は8号100〜150cm。ハリスは8号60cm、ハリはホタ16号、ムツ17〜18号で大き目の親子サルカン接続した4本バリ仕様。
デコレーションや水中ランプはサメ等の状況を見てから使う場合もあります。
【エサ】
代表的な餌は、サバ、シャケハラスの短冊で、幅1.5cm長さ10〜12cmにカットして使います。
この短冊にホタルイカのゲソを付けるのがポイント。ホタルイカを丁寧に胴体部分からゲソ部分を抜き出します。この時目玉とキモを潰さずに抜き出す事がポイント、針には目玉と目玉の間を刺す様に付けます。
シャケハラスは白い皮の部分が重要で、硬いためエサ持ちも良く食いも最高です。
【釣り方】
アカムツの泳層は底から4〜5mと言われています。底をキープし道糸のテンションを常に維持する事が重要ですが、底を狙いすぎるとドンコやユメカサゴなどの外道軍団ばかりを釣る事になってしまいます。そこで、捨て糸を長めにしている事が肝なのです。
上記2本バリの胴付仕掛けの全長が5.5m、泳層をカバーしていますが、上から落ちてくるエサを捕食する根魚の特性を利用し、竿をシャクリ上げてゆっくり落とし込む誘いが極めて有効です。早合わせは禁物、アタリがあったら一呼吸置いてゆっくり聞き上げましょう。大きな引き込みがあったら手巻きで5m位巻き上げるとアワセになりますので、後は電動(スロー)でドラグを効かせて巻き上げます。ドラグは強い引きで巻上げがストップする程度にし逆転するほど緩めてはいけません。
巻上げ時は手持ちで波による上下動や強い引き込みに常に対応できるようにします。ハリ穴が拡がる事も良くあり、水面まで来ても暴れますのでタモの中に入るまでハリスを緩めない事が大切です。
サバの短冊は白っぽくなったら交換しますが、シャケハラスは丈夫ですので何回でも使用できます。ホタルイカは目玉やキモがなくなったら効果が無くなりますのでマメに交換するようにしましょう。