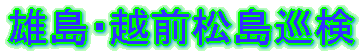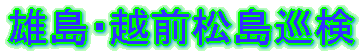|
| 雄島 柱状節理、板状節理や照葉樹林の観察 2021.4.20 (大湊神社例大祭) |
雄島で柱状節理と板状節理を調べてみよう。
新生代第3紀中新世 約1200万年~1300万年前にマグマが流れて地表近くで冷え固まった火山岩を観察しましょう。雄島は流紋岩でできています。流紋岩はマグマが地表近くで冷えて固まる時にできた流れ模様を観察することができます。流理構造と言われています。雄島の狛犬の土台の石や階段を作っている敷石はほぼ雄島の流紋岩が利用されています。また、橋を渡った左側の切り立った崖は柱が並べたように見ることができます。これは柱状節理といい、マグマが固まるときに上下方向に節理が発達したものです。また、西海岸から北海岸にかけては板を重ねたように見える節理を観察することができます。これは流紋岩の特徴から流理構造にそう板状節理ができたと考えられます。
雄島北東側の磁石岩をみてみよう。
雄島の北東海岸には方位磁石を狂わす石があります。方位磁針は通常北の方向をさしていますが、一部の岩に方位磁針を近づけると北の方向を指しません。これは岩に落雷があり、強い電流がながれたことにより、岩が磁石化したと考えられています。方位磁針を持っていき磁石岩を探してみましょう。
天気が良ければ白山を見ることができます。
瓜割の水
雄島西側海岸に地下水を観察することができます。流紋岩の柱状節理、板状節理の割れ目を流れてきたもので年中一定の水温を維持しています。
照葉樹林の森の観察
温帯地方の鎮守の森は常緑広葉樹林でタブノキやスダジイを観察することができます。葉が重ならず空が割れているように見える現象クラウン・シャイネス(樹冠の遠慮)もみることができます。
二の浜の岩脈を観察して、溶結凝灰岩(火砕流堆積物)をさがしてみよう。
雄島から越前松島方向に移動すると二の浜という海岸があります。よく見ると大トラ・小トラと呼ばれる柱状節理の発達した岩脈です。東の岩脈は薄い紫色をしています。浜辺の紫色の石をよく見ると、ガラスがレンズ状に薄くのび平行に並んでいるひとがわかります。この構造は陸上で火山が噴火して大量の火砕流ができる岩石で溶結凝灰岩と言われています。
越前松島の材木石や海食洞を見てみよう。
新生代第3紀中新世 約1200万年~1300万年前にマグマが地表近くで固まった玄武岩質安山岩からできていて、柱状節理がよく発達している。材木岩と呼ばれている。越前松島の下部の地層は水深1~2mの水中で急に冷やされバラバラに砕けながら固まり、角レキ状の水中自破砕状溶岩からできている。よく観察すると水中で固まったため、ガスがぬけた穴を見ることができます。
海食洞を見てみよう。
越前松島にはいくつかの海食洞があり、縄文、弥生時代と人々に利用されてきたことが分かっています。縄文時代の海面は現在の海面より数m高く波によって削られたことが想像できます。放射状柱状節理の中央部は風化に弱いようで海食洞になっています。
参考文献
福井市自然史博物館 自然史講座 ジオツアー② 東尋坊・雄島・越前松島の生い立ちを探る
北陸の自然を訪ねて 北陸の自然を訪ねて編小委員会 築地書館 |
 |
| 島には流紋岩があちらこちらに利用されていて、マグマが流れた流離構造を観察できます。 |
 |
| 流紋岩は石英分が多く白く粘性がある。流れたあとを観察てきる。 雄島南海岸 2021.4.20 |
 |
雄島 南海岸 柱状節理の断面 通称 猫の小判 2021.4.20
陸地側から沖に向けてマグマが流れ、30度ぐらいの傾向いているが海岸線では80度ぐらいの傾斜で海に落ち込んでいる。 |
 |
| 瓜割の水 2021.4.20 |
 |
| 雄島北東海岸 磁石岩 方位磁針が北の方向と違った向きを指しています。 |
|
 |
| 海越しの白山が見えました。 2019年3月9日 |
 |
| スダジイやタブノキからなる照葉樹林 各地の鎮守の森を作っている。 |
 |
 |
| スダジイ ブナ科シイ属 |
タブノキ クスノキ科タブノキ属 |
 |
| 雄島の照葉樹林 ダブノキ 木々の葉が重ならず空が割れているように見える現象クラウン・シャイネス(樹冠の遠慮)というらしいです。 |
 |
| 岩脈 小トラ と溶結凝灰岩 ガラスがレンズ状に薄くのび平行に並んでいる。火砕流堆積物 |
 |
| 小トラ 二の浜岩脈 硬い岩質の岩脈が残っている。柱状節理が発達している。 |
 |
| 越前松島 放射状柱状節理 |
 |
| 越前松島の柱状節理 |
 |
 |
| 水深1~2mの水中で急に冷やされバラバラに砕けながら固まり、角レキ状の水中自破砕状溶岩 (上) |
 |
| 海食洞 (観音洞) 2017.10.14 |