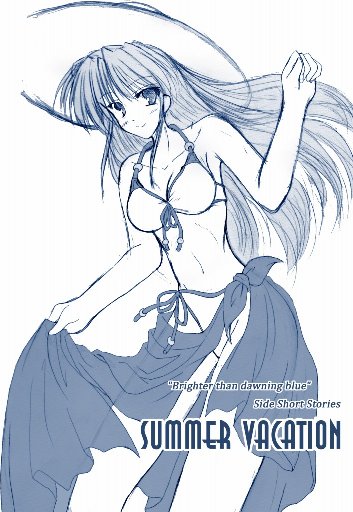 ・夜明け前より瑠璃色なMoonlight Cradle sideshortstory 「Summer Vacation」
「暑いわね」
駅を降りた俺達に夏の日差しは遠慮なくそそぐ。
「左門さん、最初に宿に行った方がいいのかしら?」
「あぁ、チェックインはまだ出来ないが荷物は預けられるだろう」
「そうね、それなら軽装で海水浴に行けるわね」
「そうと決まったら宿に行こう!」
菜月は一人元気良く走り出そうとする。
「わ、菜月ちゃん。そっちは逆の方向だよ」
「・・わ、わかってるわよ。ちょっと失敗しただけよ」
「菜月、その言い訳無理ありすぎだよ・・・」
「では、左門さん。案内お願いします」
「よし、行くか。仁、タツ、準備は良いか?」
「うぃっす!」
「りょーかいっと」
俺は両肩に荷物を背負い直す。
「達哉、一人で大丈夫?」
「あぁ、これくらいなら大丈夫っと」
ちょっとよろけたけど問題はないだろう。
「お兄ちゃん、少し持とうか?」
「だいじょうぶだって、麻衣。ほら、行こう」
「・・・うん、でも無理だと思ったら遠慮なく言ってね」
「そうね、達哉。あまり格好つけようだなんて思わなくてもいいわよ?」
「そんなことは思ってないさ」
本当は少しだけ思ってたりもするけど。
「いいねぇ、あっちは。我が愛しの妹殿は・・・」
「ほら、兄さん早く持ってきてよ」
「ねぇ、いいの? 私の分まで持ってもらって」
「いいのいいの、兄さんはこう言うときしか役に立たないんだから」
「我が妹殿は僕の事をどう思ってるのかよーくわかったよ・・・」
「あの・・・仁さん、やっぱり私は自分の持ちます」
「とんでもない! 乙女に重い荷物を持たせるだなんて僕には出来ないさ」
「そ、そうですか、あはははは・・・」
「兄さん、相変わらずよね・・・」
「さやちゃん達は荷物いいのかい?」
「えぇ、私はそんなに無いですから」
「私も大丈夫です、人様に頼ら無くては行けないほど柔ではありませんから」
「カレン様がそう仰ってるのですもの、私たちの事は気になさらないでください」
「そうか、俺も格好つけようと思ったのだが、残念だな」
「親父殿、そう思われるなら僕の荷物を」
「よし、行くか」
「親父殿・・・しくしく」
みんなで荷物を宿に預けてから、俺は着替えの入った鞄を持って砂浜に出た。
先に着替えてから、砂浜にベースキャンプを作るためだ。
「・・・思ったより人が少ないな」
「ここは穴場だからな、海は綺麗で人が少ない、ゆっくりとするにはもってこいだ」
「そうですね、何もしないでゆっくりするのも良いかもしれないですね」
「何言ってるんだ、タツ。若いんだから思いっきり遊んでこい」
「それもそうですね」
「ゆっくりするのは後でも出来るんだからな。あぁ、でも先に・・・」
おやっさんは持ってきたパラソルを立てる。
「これ、立てちまうか。タツ、手伝ってくれ」
「はい」
「お待たせ」
「仁さん、遅いですよ」
「いやぁ、すまないね。これの準備してたんだよ」
そう言うと仁さんはクーラーボックスをパラソルの下に置く。
「わざわざ我が店から持ってきたんだ、後でみんなにごちそうしようとおもってね」
「きっとみんなも喜ぶと思います」
「そうだろう、仁さん素敵! 格好良い! つきあって! みたいになるだろうね」
さすがにそれはどうかと・・・
「仁、中にはあれも入ってるんだろうな?」
「もちろんです、親父殿。先ほど補充しておきました」
「あれ?」
「達哉君にはちょっとだけ早い、あれだよ」
あぁ、あれか。
「よし、先に一杯やっておくか」
「遅いな、みんな・・・」
「女の子は準備が長いものさ、それを待つのが男の甲斐性ってもんだよ、達哉君」
「そういうもんですか?」
「そういうもんさ」
「おやっさん?」
「まぁ、あわてるな。まだ夏は逃げないさ」
そういって缶ビールをあおる、おやっさん。
「そうそう、夏は今日が本番なのだよ、そして真の本番は夜に訪れるのさ」
仁さんの笑顔に何か嫌な予感を感じる。
「仁さん、なにかたくらんで・・・」
「おまたせー!」
俺が問いただそうとしたとき、更衣室の方からみんながやってきた。
「・・・」
思わず見とれてしまい、声が出なかった。
「さぁ、泳ぎましょう!」
・・・一緒に遊ぶ、貴方の隣の人は?
遠山 翠
エステル・フリージア
リースリット・ノエル
インターミッション・フィアッカ
ミア・クレメンティス遠山 翠
鷹見沢 菜月
インターミッション・カレン
穂積 さやか
朝霧 麻衣
インターミッション・フィーナ&???
フィーナ・ファム・アーシュライト
・夜明け前より瑠璃色なMoonlight Cradle sideshortstory 「Summer Vacation」
「暑いわね」
駅を降りた俺達に夏の日差しは遠慮なくそそぐ。
「左門さん、最初に宿に行った方がいいのかしら?」
「あぁ、チェックインはまだ出来ないが荷物は預けられるだろう」
「そうね、それなら軽装で海水浴に行けるわね」
「そうと決まったら宿に行こう!」
菜月は一人元気良く走り出そうとする。
「わ、菜月ちゃん。そっちは逆の方向だよ」
「・・わ、わかってるわよ。ちょっと失敗しただけよ」
「菜月、その言い訳無理ありすぎだよ・・・」
「では、左門さん。案内お願いします」
「よし、行くか。仁、タツ、準備は良いか?」
「うぃっす!」
「りょーかいっと」
俺は両肩に荷物を背負い直す。
「達哉、一人で大丈夫?」
「あぁ、これくらいなら大丈夫っと」
ちょっとよろけたけど問題はないだろう。
「お兄ちゃん、少し持とうか?」
「だいじょうぶだって、麻衣。ほら、行こう」
「・・・うん、でも無理だと思ったら遠慮なく言ってね」
「そうね、達哉。あまり格好つけようだなんて思わなくてもいいわよ?」
「そんなことは思ってないさ」
本当は少しだけ思ってたりもするけど。
「いいねぇ、あっちは。我が愛しの妹殿は・・・」
「ほら、兄さん早く持ってきてよ」
「ねぇ、いいの? 私の分まで持ってもらって」
「いいのいいの、兄さんはこう言うときしか役に立たないんだから」
「我が妹殿は僕の事をどう思ってるのかよーくわかったよ・・・」
「あの・・・仁さん、やっぱり私は自分の持ちます」
「とんでもない! 乙女に重い荷物を持たせるだなんて僕には出来ないさ」
「そ、そうですか、あはははは・・・」
「兄さん、相変わらずよね・・・」
「さやちゃん達は荷物いいのかい?」
「えぇ、私はそんなに無いですから」
「私も大丈夫です、人様に頼ら無くては行けないほど柔ではありませんから」
「カレン様がそう仰ってるのですもの、私たちの事は気になさらないでください」
「そうか、俺も格好つけようと思ったのだが、残念だな」
「親父殿、そう思われるなら僕の荷物を」
「よし、行くか」
「親父殿・・・しくしく」
みんなで荷物を宿に預けてから、俺は着替えの入った鞄を持って砂浜に出た。
先に着替えてから、砂浜にベースキャンプを作るためだ。
「・・・思ったより人が少ないな」
「ここは穴場だからな、海は綺麗で人が少ない、ゆっくりとするにはもってこいだ」
「そうですね、何もしないでゆっくりするのも良いかもしれないですね」
「何言ってるんだ、タツ。若いんだから思いっきり遊んでこい」
「それもそうですね」
「ゆっくりするのは後でも出来るんだからな。あぁ、でも先に・・・」
おやっさんは持ってきたパラソルを立てる。
「これ、立てちまうか。タツ、手伝ってくれ」
「はい」
「お待たせ」
「仁さん、遅いですよ」
「いやぁ、すまないね。これの準備してたんだよ」
そう言うと仁さんはクーラーボックスをパラソルの下に置く。
「わざわざ我が店から持ってきたんだ、後でみんなにごちそうしようとおもってね」
「きっとみんなも喜ぶと思います」
「そうだろう、仁さん素敵! 格好良い! つきあって! みたいになるだろうね」
さすがにそれはどうかと・・・
「仁、中にはあれも入ってるんだろうな?」
「もちろんです、親父殿。先ほど補充しておきました」
「あれ?」
「達哉君にはちょっとだけ早い、あれだよ」
あぁ、あれか。
「よし、先に一杯やっておくか」
「遅いな、みんな・・・」
「女の子は準備が長いものさ、それを待つのが男の甲斐性ってもんだよ、達哉君」
「そういうもんですか?」
「そういうもんさ」
「おやっさん?」
「まぁ、あわてるな。まだ夏は逃げないさ」
そういって缶ビールをあおる、おやっさん。
「そうそう、夏は今日が本番なのだよ、そして真の本番は夜に訪れるのさ」
仁さんの笑顔に何か嫌な予感を感じる。
「仁さん、なにかたくらんで・・・」
「おまたせー!」
俺が問いただそうとしたとき、更衣室の方からみんながやってきた。
「・・・」
思わず見とれてしまい、声が出なかった。
「さぁ、泳ぎましょう!」
・・・一緒に遊ぶ、貴方の隣の人は?
遠山 翠
エステル・フリージア
リースリット・ノエル
インターミッション・フィアッカ
ミア・クレメンティス遠山 翠
鷹見沢 菜月
インターミッション・カレン
穂積 さやか
朝霧 麻衣
インターミッション・フィーナ&???
フィーナ・ファム・アーシュライト
case of 翠 「あっさぎっりくーん!、これ見て!」 そう言うと翠は両手で抱えないといけないほど大きないるかの浮き輪を 持ってきた。 「海で乗ろうと思って持ってきたの」 よく見るといるかに取っ手がついている。 「ボートに引っ張ってもらえるように出来てるんだよ」 「でもさ、俺達ボート持ってないよ?」 「あ゛・・・」 考えてなかったのか・・・ 「朝霧君、ふぁいとっ!」 「俺が引くのか!」 「まぁ、それは冗談として、泳ぎに行こう!」 そういって俺の手をとって海に誘う翠。 「おい、ひっぱるなって、海は逃げないよ」 「海は逃げないけど、時間は逃げていくんだよ!」 腕を引っ張られながら、今までいるかの浮き輪で隠れてた翠の水着姿を 見る事ができた。 前の部分だけが布であとはひもだけのブラは翠の大きい胸をきつそうに 覆っている。 下はパレオに隠れてて見えないけど、きっとブラと同じようなつくり なんだろうな。 ・・・いけないいけない、二人だけならともかく今はみんながいるんだ。 ここは我慢しないと・・・ 「朝霧君?」 「み、翠?」 「どうしたの? あー、もしかして私の水着姿に見とれちゃった?」 そういって頭の後ろで両腕を組んで、ポーズを取る翠。 「・・・」 「あ・・・ねぇ、朝霧君、何か言ってくれないと、その・・」 「・・・ごめん、見とれてた」 「っ! も、もぅ・・・恥ずかしい事言わないでよ」 「ご、ごめん」 二人で赤くなってしまった・・・ 「この辺でいいかな?」 浮き輪につかまりながら少し沖合まで俺達は来た。 「よし、とりあえず乗ってみよう!」 そう言うと翠はいるかに乗ろうとして・・・ 「ん・・・意外に難しいかも・・・んしょっ」 やっといるかに上半身をのせた翠を見た俺は 「!」 声にならない悲鳴をあげた。 ちょうど翠の可愛いお尻が突き出された形になっていたからだ。 「ねぇ、朝霧君。ちょっと押してくれる?」 「そ、それはちょっと・・・」 いろんな意味でそれはまずい。 「ん、じゃぁ反対側からいるかを押さえてて」 「わかった、それなら」 俺は泳いで翠のお尻の反対側に行く。 そこでいるかを押さえると、目の前に翠の大きな胸が・・・ 「んしょっと」 翠は俺の視線に気付かないようで、いるかに乗ることに集中している。 こ・・・これは天国なのか地獄なのか・・・ 「よし、何とか乗れたぁ!」 気付くと翠はいるかにまたがっていた。 「それじゃぁ朝霧君、ふぁいとっ!」 「わかった」 俺が引くのか、という問題よりも翠から目が離せるのなら それに越したことはない。 いるかの頭の所にあるとってをもって泳ぎ出す。 「おっ・・・これはバランスが難しい・・・きゃっ」 大きな水しぶきをあげて、翠は海に落ちていた。 「翠?」 「ぷはっ、これって思ったより難しいね〜、もう一回チャレンジだ!」 そう言ってまたいるかに乗ろうとする翠の胸にあるべき水着が無かった。 「み、翠・・・」 「え? きゃっ!」 両手で胸を隠して水の中に潜る翠。 俺は翠に背中を向けた。 「・・・見たでしょう?」 「・・・見ました」 嘘を言ってもしょうがないので本当のところを答える。 「ここは見てないって言う所じゃない?」 「でも見てしまったし、嘘は言いたくないから」 「そっか、その正直に免じて許してあげよう」 「ありがとう、翠」 「それに、朝霧君だったらかまわないし・・・」 「ん? 何かいった?」 「なな、なんでもないよ。それよりも水着を捜してよ。このままじゃ帰れないよ」 「わかった、その辺に沈んでると思うから」 俺は息を思いっきり吸ってから海に潜った。 潜った瞬間、翠の両腕だけで隠された胸を見てしまい、思わず息を 吐き出しそうになったことは言わないで置こう・・・ 「ふぅ、大災難だったね〜」 無事水着を見つけてから、砂浜へと帰ってきた。 「これも一夏の甘い思い出っていうもんだよね?」 「翠・・・俺は翠を尊敬するよ」 「そう? 今さら私の偉大さをわかったのかな?」 「はいはい」 アクシデントではあったけど、これも忘れられない夏の思い出になるのだろう。 「それじゃぁ、良い思いをした朝霧君は、海の家で焼きそばをかってきて もらおうかな。もちろん、朝霧君のおごりで」 「やっぱり?」 「あ、ラムネも一緒によろしくね」 「わかったよ、買ってくる」 俺は海の家へ行こうとかけだす。 「あ、朝霧君!」 「何?」 「・・・水着、捜してくれてありがとう、達哉」 翠のまぶしい笑顔は、何よりの思い出になりそうだった。 Next Episode
case of エステル 「どうしたんですか、こんなところで」 白いワンピースの水着に麦わら帽子をかぶっているエステルさん。 一人、砂浜から離れた岩場に腰掛けていた。 「達哉こそ、どうしたんですか?」 「エステルさんの姿が見えなかったので探しに来ました」 「そうですか・・・」 それだけを答えると、俺が来る前と同じように、海を眺めだした。 「・・・」 俺はそれ以上言葉が続かなかった。だから、エステルさんの横に同じように 座った。 そしてエステルさんが見ている景色を俺も見てみた。 「・・・」 静かな波の音と、視界一杯に広がる海と空。空には入道雲もある。 「・・・」 「・・・」 聞こえてくるのは自然の音だけだった。 「ふぅ・・・」 エステルさんが一息つくと同時に俺の方をむく。 「達哉、貴方は物好きです」 「え? いきなり何を言うんですか」 「だって、せっかくの家族旅行なのに、家族の所にいないんですもの。 家族旅行というのなら家族と一緒にいるのが普通じゃないんですか?」 「それはそうかもしれないけど、俺はエステルさんと一緒にいたかったから」 「っ!」 顔を真っ赤にするエステルさん。すぐこうして照れるのが可愛くて、いつも 照れさせるような言葉を言ってしまう。 まぁ、言う方も照れるんだけど。 「た、達哉はやっぱり物好きです」 そう言うとまた海の方に向いてしまった。 「・・・」 「・・・」 無言の時間が過ぎる、エステルさんは麦わら帽子をかぶってるので平気そうだけど 水着の上からパーカーしか羽織ってない俺は直射日光にあぶられている。 これは結構きついかもしれない。 それでもエステルさんがここにいるのなら、俺もここにいたい。 偽り無い俺の気持ちだから。 「・・・何か言いたいことがあるのでしょう?」 「え?」 「だから私の所にずっといるのでしょう」 どうもエステルさんの機嫌は良くないようだ。 俺は何もしてないと思うけど・・・何だろう? 「特に言いたいことは・・・」 無い、と言おうとしたとき、まだエステルさんに言ってない言葉があった 事に思いついた。 「エステルさん、水着似合ってます」 「っ! な、なにを言うんですか!」 「何って俺の思ったことですけど」 「・・・あ、ありがとうございます」 そう言うとうつむいてしまった。 そうして無言の時間がまた少し過ぎた頃にエステルさんが降参してきた。 「わかりました、白状します。でもこれはここだけの話ですからね?」 「えっと・・・」 特に何かを聞き出そうとした訳じゃないんだけど。 「わかりました、二人だけの秘密にしますね」 「・・・ふぅ、なんで私だけがどきどきさせられるのでしょうか」 「何か言いました?」 「何でもありません!」 「笑わないで聞いてくださいね」 約束ですよ! と念を押してからエステルさんは話し始めた。 「私は達哉の・・・その・・・彼女として自信が無いのです」 「え?」 「今日だって達哉の回りには私より魅力的で良い子ばかりが集まってます。 私は・・・その中に入っていける自信がありません」 「・・・」 「だから・・・」 「エステルさん」 俺はエステルさんの話を中断させる。そして思いを込めて伝える。 「馬鹿です」 「・・・は?」 「そんなこと考えるエステルさんは馬鹿だって言ったんです」 「な、なな・・・馬鹿とはなんですか!」 「当たり前です、俺は誰かと比べてエステルさんを選んだんじゃないんです! エステルさんだから、選んだんです!」 「達哉・・・」 「そりゃ確かに怒りっぽかったり潔癖性だったりするかもしれないです」 「・・・」 「でも、それを含めて全てがエステルさんなんです。 そしてそんなエステルさんだから、俺は好きになったんです」 「・・・」 「だから、そんなことで悩むのは」 「わかりました!」 今度は俺の話をエステルさんが中断した。 「私は馬鹿なら、その馬鹿を好きになった貴方は何なんですか?」 「えっと・・・」 「達哉は私以上の大馬鹿です、でもそんな達哉だから、好きです」 「俺も、エステルさんが大好きです」 「・・・ふふっ」 「ははっ!」 なんだかおかしくなって二人で笑いあった。 「エステルさん、せっかくだから海で泳ぎましょう。もう波は怖くないでしょう?」 「元から波は怖くありません! あの時は驚いただけです!」 「そう言うことにしておきますね、浮き輪は必要ですか?」 「失礼です! そんなもの必要ありません!」 そう言うと怒った顔をしたエステルさんが、ふっと表情を和らげる。そして 「・・・だって、達哉がいてくれるのですから」 「・・・降参」 エステルさんの笑顔とその言葉に、俺は白旗をあげるしかなかった。 「達哉が私に勝とうなんて、まだまだ早いですよ ふふっ、さぁ、泳ぎましょう!」 Next Episode
case of リース 「リース、何してるんだ?」 波打ち際に座り込んでるリース。 「・・・」 俺の言葉が聞こえてないほど集中してるのか、それとも無視して いるのか返事がない。 ・・・後者だったらいやだな。 そんなことを思いつつリースの正面に回る。 「・・・?」 「砂の城を作ってるのか?」 「そう・・・」 まだ作り始めたばかりなのか形にはなってないけど、しっかりとした 土台が出来ていた。 「よし、俺も手伝うよ」 「いらない」 即答だった。 仕方が無く、リースの横に少し離れて砂浜に座る。 「・・・」 リースは麻衣のお古の水着を借りて着ている。 学校指定の水着で、丁寧に胸のゼッケンの名前がりーすに書き換えられている。 これはきっと姉さんの仕業だな、俺はそう確信した。 「・・・」 ん? 今リースがこちらを見た気がした。 「リース、もしかして呼んだ?」 「呼んでない」 「そっか」 俺はそのままリースを見ている。 「・・・」 リースがちらりと俺の方を見た。 「何?」 「タツヤ、邪魔」 「・・・」 仕方がないので俺はリースの横に少し離れて座った。 ここならリースの気を散らすことはないだろう。 「・・・」 ぼーっとリースを眺めてるのも良いのだがどうも手持ちぶさただな。 「よし!」 俺も砂の城を造ってみるか。昔とった杵柄、今も腕は衰えていないはず。 回りの砂を集めて、土台を作り始める。 その上に砂をたくさん盛って、大きさを整える。 「・・・む」 「ん? 何?」 「・・・なんでもない」 「そっか・・・そうだな、せっかくだから勝負でもするか?」 「嫌」 「わかった、それじゃぁ競争だ」 「タツヤ、話聞いてない」 リースの反論を聞き流しつつ、俺は目の前の砂の城に集中する。 しばらくすると、俺の目の前に城らしき物が出来上がってきた。 まだ細部を整えてないが、たぶんリースの物より大きいだろう。 「よし、仕上げだ!」 俺は城の仕上げをしようと手を伸ばした瞬間、目の前を何かが遮った。 「・・・え?」 「ごめん達哉〜、ビーチボール取って〜!」 「・・・」 俺は無言でビーチボールを菜月達に投げて帰す。 「ふぅ」 俺は城があった場所に寝ころんだ。 もう作り直す気は無くなっていた。 「タツヤ・・・」 「リース、俺の負けだな」 「私は勝負を受けていない」 「そうだったな、でも俺の負けだ」 「タツヤ、勝手に勝負して勝手に負けた・・・無様」 そう言うリースは、笑顔だった。 確かにリースの言うとおり無様だが、リースの笑顔には俺は絶対勝てない。 「試合に負けて勝負に勝つってこう言うことなのかな」 「?」 「よし、せっかくだから泳ごうか、リース」 「わ、わっ!」 リースの手をとって海に向かって駆けだした。 Next Episode
インターミッション・フィアッカ このときに満弦ヶ崎に来たのは偶然だった。 いくら安全に使うとは言っても過去に破壊を引き起こした装置。 定期的に監視する必要はある。 作動や誤作動の場合、すぐに察知出来るように仕掛けてはあるが それでも定期検診をしておくにこしたことはない。 「あら、リースちゃんじゃない。久しぶりね」 「え? さ、さやか?」 なんでこんな所に? そういえばさやかのつとめている博物館は この近くだったな。 私が表に出ている状態ではまずい、リースと変わらなくては。 リースに話しかける。 「リース、頼むぞ」 「・・・」 「リース?」 ・・・寝ているのか。確かに今は夜遅い時間だ。 無理矢理起こして変わる事も出来るが・・・仕方がない。 なんとかごまかそう、と思った瞬間に 「えい、つっかまえた♪」 「わわっ」 後ろから抱きかかえられてしまった。 「ねぇ、リースちゃん。週末みんなで旅行に行くんだけど、一緒にこない?」 「旅行?」 そんな暇は無い、と即答したかったのだが、今の私はリースなのだ。 そう言うわけにはいかない。 「リースちゃん暇よね? うん、よかった。それじゃぁ家に帰りましょうか」 強引すぎないか? とは思ったが抵抗はやめておいた。 善意で行っていることはわかっているし、過去のあの風呂場の事件以来 私はさやかを苦手としてしまっている。 「それじゃぁ帰りましょう、達哉君も麻衣ちゃんもみんな驚くだろうな、ふふっ」 結局それから週末まで朝霧の家で過ごし、今こうして海に来ている。 途中で逃げ出す機会はいくらでもあったのだが、この旅行の意図を聞いたとき それでも良いかな、と思ってしまった。 そう、この旅行はみんなの夏休みなのだから。 たまには良いかもしれないな。 せっかくだ、深夜にリースと変わってもらおう。 良い温泉だそうだし、たまには私も夏休みを取るとしよう。 Next Episode
case of ミア 「おやっさん、向こうのパラソル、あれで良いんですか?」 みんなが来る前に設営したパラソルは2カ所。 まずクーラーボックスや荷物とおやっさんが常駐するパラソル。 その後ろに、2基のパラソルで囲いを作ったような感じのパラソル。 ちょうど後ろと左右からは中が見えないような作りになっていた。 唯一、開いてる方におやっさんのパラソルがあるのでちょっとした 囲いになっている。 「あぁ、あっちは女性陣専用さ。そう希望があったからな」 「はぁ・・・」 別に休むだけならあんな形にする必要は無いと思うんだけどな。 そう思った俺だったが、みんなが海に出てきてから、あのパラソルの 意味を知った。今あのパラソルの中で日焼け止めをみんなで塗っている。 「なぁ、達哉君。物は相談なんだが」 「嫌です」 「僕はまだ何も言ってないよ?」 「どうせ、あのパラソルの中を覗こうとしているんでしょう?」 「そうか、達哉君もそう思ってたんだね、同士よ!」 手を握ろうとする仁さんから逃げる。 「やめておいた方がいいですよ、というかやめてください」 「そこに!!」 突然、仁さんが大声をあげる。 「美しい物があるのなら男として見ないわけには行かないだろう!」 「・・・」 「だからこそ、行くのだよ! 死を恐れてはいけな・・・」 その仁さんの声が途中で途切れる。 そして砂浜に倒れた。後頭部にしゃもじが刺さっている状態で・・・ 「あれだけ大きな声を出してればバレバレでしょうに・・・」 「・・・はぁ」 俺は素直にみんなが出てくるのを待った。 「ミア、もういいのかい?」 パラソルの中にはいるとミアは片づけ物をしていた。 ライムグリーン色のワンピースのミアは、何故かカチューシャだけは していたままだった。 「達哉さん、はい。お待たせしました。みなさんにはもうお塗りしました」 そう、このパラソルの中で日焼け止めを塗っていたのはミアだった。 もちろん、みんな自分で濡れるところは自分でしたそうだが、どうしても 手が届かない背中はミアが進んで塗ってくれたそうだ。 「ミアは偉いな」 「とんでもないです! 私にはこれくらいしかできないですから。 あ、達哉さんにも塗って差し上げないと」 「俺は別に良いよ」 「駄目です、日焼けは低温火傷なんですよ? あとで痛い思いをさせたく ありませんから。だからここに座ってください」 ミアに腕をひっぱられて、俺はパラソルの影の中に連れ込まれた。 「ちょっと冷たいかもしれないですけど、我慢してくださいね」 そういってミアは俺の背中に丁寧に日焼け止めを塗ってくれる。 「っ」 「あ、痛かったですか?」 「あ、いや、なんでもない」 「痛かったら言ってくださいね」 日焼け止めを塗られて痛いわけはない。ただ、あまりの優しさにくすぐったい だけだった。 「はい、これで背中は大丈夫です。それでは今度は胸の方を塗りますね」 「え? あ、いや、だいじょうぶだよ。前は自分で塗るから」 「駄目です、私が塗ります」 「いや、その・・・」 「私に塗らせてください・・・駄目ですか?」 いつも俺のことばかりを考えてくれてるミア。 そのミアが真剣に俺のことを思ってしてくれる行為を、俺が・・・ 「わかった、くすぐったくないようにお願いします」 「はい!」 断れるわけはなかった。だって、この後みれるミアの笑顔に、俺は弱いから。 「さすがだな・・・」 日焼け止めを塗ってもらった俺は自分の前身を見回す。 塗りすぎの場所はなく、身体がべたべたしてる感じもしない。 この加減具合は、俺には真似は出来ないだろう。 「ありがとう、ミア。助かったよ」 「いえ、どういたしまして」 「それじゃぁミア。せっかくだから海で遊ぼうか!」 「はい・・・あっ」 「どうした、ミア」 「あの・・・私がまだ日焼け止めを塗っていませんでした」 ミアらしかった。 「そうか、それじゃぁさっきのお礼に背中は俺が塗ってあげるよ」 「え? でも悪いです!」 「背中には上手く塗れないだろう? 俺じゃ上手くないと思うけど」 「とんでもないです! 達哉さんは上手いと思います。 ただ、塗ってもらうと悪いとおもいまして・・・」 「俺もミアに何かしてあげたいんだ。駄目かい?」 「・・・ずるいです、達哉さん。そう言われると断れないです・・・」 「よし、それじゃぁここにすわって。俺は背中だけだから後は ミアが自分で塗ってくれ」 「・・・はい、ではお願いします」 そういうとミアは水着の肩ひもをはずし、少しだけ水着をずらした。 「・・え?」 「あ、あの、肩ひものところが塗りづらいと思いまして・・・その」 「・・・あ、ごめん。それじゃぁ塗るよ」 自分の手に日焼け止めのクリームを塗る。 それをそっとミアの白い肩に塗る。 「ひゃぁ!」 「わ!」 ミアのあげた声に思わず手を離す。 「あ、すみません。ちょっと驚いてしまって」 「ごめんごめん、俺も何も言わなかったからな。それじゃぁ、塗るよ?」 「はい、お願いします」 ・・・自分の手が震えてるのがわかる。 ただクリームを塗るだけなのに、なんでこんなに緊張してるんだ。 ミアに気付かれないように、そっと深呼吸してからミアの肩に、そっと ふれる。 「・・・」 傷つけないよう、そっとミアの肩から背中にかけてクリームを塗りつける。 肩ひもははずされていて、ほんの少しだけはだけた水着。 それが否応なしに俺を緊張させていた。 「・・・んっ」 ミアが甘い息を吐く。 俺はそれが気のせいだと、自分に言い聞かせながらミアの背中にクリームを 塗り続けた。 それはほんの数分の事だったはず。 なのにすごく長い時間緊張してたような気がした。 「あ、ありがとうございます、達哉さん」 「ごめん、ほとんど役に立てなかった」 「そんなことはありません! とても気持ちよかったです・・・あっ」 「そ、そっか。それは良かった」 ・・・のだろうか? 「は、はい。良かったです」 「・・・」 「・・・あの、達哉さん。海に行きましょう!」 「そ、そうだな。せっかくの夏休みだもんな。いっぱい楽しもう、ミア!」 「はい!」 Next Episode
case of 菜月 「ねぇ、達哉。ビーチバレーしない?」 パラソルの下で休んでた俺の所に菜月が誘いにきた。 青色の、というより海色というべきか。綺麗なマリンブルーのビキニ姿の 菜月。寝ている俺の視界には、そのビキニのトップが目に留まる。 「・・・」 「達哉?」 「あ、あぁ・・・ビーチバレー? いいぞ」 「ありがと、達哉。それじゃ行こう!」 菜月に連れられてきたビーチバレーのコートらしき所には・・・ 「仁さん?」 「おぉ、やっと来たか。こっちは準備万端OK!」 何故かネットを張っていた。 たくさんある荷物の中にネットは無かったと思ったんだけど。 「こんなこともあろうかと、手配はしておいたのだよ、達哉君!」 「俺、何も言ってないですよ?」 「聞きたそうな顔してたんだよ」 そうなのだろうか? 「兄さん、どうせその決め台詞言いたかっただけじゃないの?」 「そんなことはないぞ我が妹よ!」 額に汗を流してる仁さん、説得力ないですよ・・・ 「おー、準備出来たんだね」 「遠山?」 「そう、この遠山さんも助っ人に呼ばれたのですよ。私が来たからにはもう 勝ったも同然、かき氷に焼きそばは戴きよ!」 「何の話だ?」 「あれ? 朝霧君聞いてないの? 負けた方は勝った方におごるんだよ」 「それって翠が言いだした事じゃないの?」 「でも仁さんが良いって言ったよ?」 「その通り、敗者にはペナルティが付き物だよ! その方が試合に燃えれる じゃないか!」 「兄さんは無駄に燃えすぎだとおもうんだけど」 「萌えでもかまわないぞ? まぁ、我が妹には無理だろうが」 そういって歯をきらっと輝かせる仁さん。 「なぁ、菜月。燃えてさらに燃えてどうするんだ?」 「達哉、兄さんの話をいちいち気にしちゃ駄目よ」 「それではチーム分けだけど」 「私は菜月とだね! 息の合ったコンビを見せてあげるね!」 「え? あ、そうだよね・・・」 「それとも〜、菜月は旦那と一緒の方が良かった?」 「「まだ夫婦じゃない!」」 「・・・聞きました、遠山さん?」 「えぇ、聞きましたよ、まだ、だそうですよ?」 「いやぁ、熱いですね〜」 「ほんと、海に来てるのに熱いよね〜」 「・・・」 「ほ、ほら、早くビーチバレー始めましょう、ね?」 菜月のせかす声でビーチバレーは始まった。 「はぁはぁ・・・兄さんも達哉も大人げないわよ」 「そ、そうだよ朝霧君、本気・・・だすなんて」 「はっはっはっ、勝負の世界は厳しいのだよ、我が妹よ」 「・・・」 俺は仁さんほど余裕はないのでしゃべらず呼吸を整える。 砂浜に足を取られるビーチバレーは思った以上に体力を使う。 その上負けにはペナルティがあるので手は抜けない。 全力で戦えば俺と仁さんのコンビの方が有利になるわけだ。 ・・・でも、そうとわかっていて遠山は何で菜月と組んだんだろう? 「こうなったら、奥の手を使うしかないわね」 「奥の手?」 「菜月、菜月の協力があれば朝霧君は無力化出来るの。手伝って!」 「え? あ、うん、わかったけど、何をすればいいの?」 「簡単だよ、私の前に立ってくれればいいの」 「わ、わかったわ」 「作戦会議はもういいのかい?」 「えぇ、必勝の策有り! 勝ちは戴くわよ!」 「・・・」 翠の顔を見て何故か嫌な予感がした。 翠のサーブを仁さんが受ける。 「ほら、達哉君!」 「はい!」 俺は相手のコートめがけてボールを打とうとジャンプした。その瞬間。 「えぃ!」 「きゃぁ!」 そのコートで突然菜月が悲鳴をあげる。 思わず悲鳴の方を見ると・・・ 「菜月、また大きくなったね〜」 「や、やぁん、翠、もまないで!」 「達哉君!」 「え?」 気付くとボールは俺の目の前を通り過ぎ、自分のコートに落ちた。 「み、翠。作戦ってこれだったの?」 「そう、菜月の可愛い悲鳴は朝霧君を無力化するんだよ」 「恐ろしい作戦だね、確かに今の達哉君を見る限りものすごく有効だね。 でも、僕には効かないよ。どうするんだい?」 「だいじょうぶですよ、朝霧君だけ無力化できれば勝ったも同然ですから」 「ね、ねぇ翠。こんな事やめない?」 「駄目よ、勝負の世界は厳しいんだから!」 「そんな〜」 「ほら、菜月♪」 「だからぁ、もまないで〜あん」 「・・・」 「ふっ、我が妹のあえぎ声程度なぞ問題ないさ、だっていつもきうごぉぉ!」 「兄さん、何かしら?」 いつの間にかしゃもじが仁さんの後頭部に直撃していた。 ・・・本当に、いつ放ったんだ? 「っていうか、俺の方一人だけじゃないか?」 「・・・達哉、勝負の世界は厳しいんだよ」 「おまえが言うか!」 1対2の変則ビーチバレーは、続けてみたもののどうしようもなく 棄権という事で俺達の負けになった。 「大丈夫、兄さんのお財布からごちそうになるから。達哉も一緒にいかない?」 「あ、あぁ・・・先に行っててくれないか・・・少し休まないと動けそうにない」 「まったく、だらしないな朝霧君は。菜月、先に行ってよう!」 「う、うん・・・」 菜月と遠山が去っていくのを見送ってから俺は海に入る。 「・・・」 さっきの遠山の秘策のせいもあってか、あれから揺れる菜月の胸にどうしても 目が行ってしまう。 このままだと我慢できなくなりそうだった。 「ねぇ、達哉」 「っ! 菜月?」 「ごめんね、達哉。なんだか楽しくなさそうだったし」 「そんなことはない、楽しかったよ。これも良い思い出になると思う」 「でも・・・私の事、さけてない?」 「・・・」 「ねぇ、悪いところあったら言って。私、治すから」 「・・・」 「達哉・・・」 俺は覚悟を決めた。 「あ、あのさ・・・そのな」 「うん」 「遠山のせいで、その、菜月の胸から目が離せなくなった」 「あ・・・」 「・・・」 この無言の時間が恥ずかしかった。 「菜月〜!」 砂浜から遠山の声が聞こえる。 「・・・ほら、菜月。俺は少し頭を冷やすから先に行っててくれ」 「うん・・・その・・・達哉。夜まで我慢してね」 そういって菜月は離れていった。 「おまたせ、翠」 砂浜で遠山と合流した菜月は海の家の方へと向かっていった。 「菜月、余計に収まらなくなるだろうが・・・」 最後の一言のせいで、俺はしばらく海から出ることが出来なかった。 Next Episode
インターミッション・カレン 「なぁ、カレンさんは遊んでこないで良いのか?」 「はい、私はお目付役ですから」 「でも楽しまないと損だぞ?」 「私は仕事でもありますから」 「・・・なぁ、仕事の時でも休憩時間はあるよな?」 「はい」 「なら、俺につきあってくれないか?」 「・・・これは」 「缶ビールしかないけど、少しくらいなら大丈夫だろう?」 「しかし・・・」 「さやちゃんはすぐに酔うけど、カレンさんは大丈夫なんだろう?」 「え、えぇ・・・」 「それにな、実はつまみを作ってきてあるんだよ」 「たくさんありますね、おつまみが」 「だから、俺につきあってくれないか? なぁに、休憩時間の間だけで いいから」 「・・・ありがとうございます、鷹見沢さん」 「上手くいったみたいね、達哉」 「あぁ、フィーナのシナリオ通りだな」 「なんだかその言い方だと私はどこかの策略家みたいな言い方ね」 「気にするなって」 フィーナの案にのって俺はおやっさんに事前にカレンさんを誘うよう 頼んでおいた。 おそらく遊びにでないだろうカレンさんにも楽しんでもらいたい。 そんなフィーナの願いの為に。 「達哉、フィーナ! ビーチバレーしよう!」 「菜月、今行く! 行こう、フィーナ!」 「えぇ」 Next Episode
case of さやか パラソルに戻った俺は姉さんを捜してしまう。 「あれ? 姉さんは?」 「さっき飲み物買いに行くって言ってたから海の家じゃないかな?」 「そっか」 おやっさんが用意した飲み物がもう無くなったのか。 ビールはまだあるようだけど、これは飲む人数の差だろう。 「一言言ってくれれば俺が買ってきたのにな」 そう思いながら海の家の方をみると、遠くに姉さんがいるのが見えた。 遠目でもわかる、白いワンピースの水着姿。 そのまぶしい姿に思わず見とれそうになる。 「・・・あれ?」 そこに後から追いかけてきたのか、男の人が姉さんに話しかける。 「・・・」 俺はすぐに姉さんの元に走る。 いくら人が少ないとはいえ、観光客がいないわけではない。 姉さんほどの美人ならナンパもつきものだと思う、だからって黙って 見ていられるほど俺は大人じゃない。 「どうだい、僕と一緒にビールでも飲まないかい?」 「駄目よ、ビール飲んだら泳げなくなっちゃうわ」 「ならつきあうだけでもいいからさ、ねぇ、さやちゃん」 「・・・」 またか、またなのか。あの時の繰り返しなのか・・・ そして同じ手に引っかかる俺は成長していないのか・・・ 成長していない自分に思わず落ち込んでしまう。 「おや、どうしたんだい? 達哉君」 「姉さんが買い出しに行ったって聞いたから荷物持ちに来ただけです」 「その割には全力疾走だったね?」 「・・・」 上手くごまかそうとしたが、しっかり見られていたようだ。 「それじゃぁ荷物持ちは達哉君に任せるとして、僕は野暮用だ。アディオス!」 さわやかに去っていく仁さん。 「仁君、なんだったのかしらね?」 「・・・それよりも姉さん、買い出し一人じゃ辛いだろう? 声かけてくれれば良かったのに」 「大丈夫よ、達哉君。ちょっと重たいけどもてないわけじゃないし」 心配なのは姉さんの方だ、とは言えなかった。 「俺が持つよ、姉さん」 「そう? それじゃぁ半分持ってね」 ジュースのペットボトルが入ったビニール袋を一つ持つ。 そんなに入ってないけど、やはり重い。 「だいじょうぶ? 達哉君」 「これくらい大丈夫だよ、なんならそっちも持とうか?」 「ううん、一つなら私でもだいじょうぶよ」 「それじゃぁ戻ろう」 「えぇ」 並んで砂浜を歩く。 俺はなるべく姉さんを見ないように、でも歩幅をあわせて歩く。 俺より少し背が低い姉さんをこの角度からみると、どうしてもその 大きな胸に目がいってしまうからだ。 「ふふっ、やっぱり達哉君は頼れる男の子よね」 「・・・どうして?」 「だって、私のことをちゃんと見てくれてるんだもの」 いや、今はちゃんとみれないんですけど・・・ 「そ、そうなのかな?」 「走ってきてくれたんでしょう? ありがとう、達哉君」 姉さんにもばれていたようだ。 なんだか砂浜に埋まりたくなってきた気分だ。 「おまたせ〜」 「おつかれさまです、さやか」 パラソルの下からカレンさんが出迎えてくれた。 「カレンはビールなのね、飲み過ぎちゃだめよ?」 「さやかほどじゃないですから大丈夫です」 「それってどういう意味よ〜」 二人のやりとりを聞きながら俺は機械的にクーラーボックスに ジュースを移す。 全部終ってから、俺は一息つく。 「あ、お兄ちゃんここにいたんだ。ねぇ、向こうでビーチバレーしようよ。 フィーナさんとミアちゃんが待ってるの、ね?」 「えっと・・・」 姉さんを誘おうと思っているのだけどどうするか? 断るか? 「達哉君、せっかくだから行って来たら?」 「姉さんは?」 「私はここで少し休んでるから」 「それじゃぁ決まりだね、行こう、お兄ちゃん!」 麻衣に手を引かれてパラソルからでる。 振り返ると姉さんは笑顔で手を振っている。 「・・・」 後ろ髪引かれる思いで、俺はパラソルを後にした。 「・・・私って素直じゃないわね」 姉さんのつぶやきは聞こえなかった。 「達哉、調子が悪いの?」 「大丈夫だけど、どうして?」 「なんだか動きが鈍いみたいだから」 「そりゃ砂浜の上だからね、普通と同じようには動けないよ」 「・・・そう、達哉が言うのならそうかしらね」 フィーナに指摘されなくてもわかってる。 姉さんを誘えなかった事が、俺の動きを鈍らせている。 姉さんは今パラソルの下で留守番をしてるのだろうか? 「姫様」 「あら、カレン。どうしたの?」 「いえ、私も身体を動かそうと思いまして、せっかくなので参加させて いただきたいと思います」 「いいわよ、受けて立つわ」 「久しぶりに姫様の腕前、見せていただきます」 「ねぇ、お兄ちゃん。フィーナさんって月でもバレーしてたのかな?」 「さすがにそれはないと思うけど・・・」 カレンさんの意図がわからない、単純にフィーナと戦いたい、とは思えない。 「達哉さん、お願いします」 「あ、はい」 カレンさんと組んでコートに入る、向こうはフィーナとミアが組んでいる。 「では、参ります」 カレンさんのサーブは鋭くフィーナに向かう。 「はっ!」 フィーナは見事に受ける。 「わ、わ・・・はい、姫様!」 ミアがボールと取るとフィーナはしなやかにジャンプしてボールを打つ。 「っ!」 俺はそのボールを拾おうとして、足をもつれさせ転んでしまった。 「達哉さん、大丈夫ですか?」 「えぇ、なんとか・・・」 「では、コートから出てください、麻衣さんと交代です」 「え、私?」 麻衣が驚いた声をあげる。 「姫様との戦いに、集中力がない人は邪魔になります」 確かに集中力は無いかもしれないけど、言い方ってものが・・・ 「だから、パラソルに戻ってください」 「そうね、達哉は少し休んだ方が良いわね」 「・・・ありがとう、カレンさん、フィーナ。少し休んでくるよ」 俺はその場から駆け出す、一刻も早くパラソルに戻るために。 「あら、達哉は元気そうね」 「そのようですね」 「それではカレン、続きはどうするのかしら?」 「お手柔らかに」 「あら、達哉君。どうしたの?」 「姉さん、勝負しよう!」 「え?」 「この前のリベンジしたいんだ」 さっき姉さんをどうやって誘おうかと悩んでたことをすっかり 忘れて、俺は思ったことをそのまま伝えた。 「ふふっ」 驚いてた姉さんの顔がまぶしい笑顔になる。 「私は強いわよ?」 「大丈夫、今度こそ買って姉さんに焼きそばおごってもらうんだから」 勝てるかどうかはわからない、正直言えば勝負なんて関係ない。 姉さんと二人でいたいだけなんだから。 「それじゃぁ私が勝ったら私の言うこと一つきいてもらおうかしら」 「わかった」 「あら、いいの? そんな約束して」 「俺が勝つから大丈夫だよ」 「ふふっ、頼もしいわね」 そう言うと姉さんはパラソルから出てきた。 「それじゃぁ、あのブイまで競争よ。負けないから!」 「俺だって!」 Next Episode
case of 麻衣 「つきあってくれてありがとう、お兄ちゃん」 麻衣が海の家でみんなの分のアイスを買いに行くことになり、俺はその つきそいで一緒に行くことにした。 「麻衣一人で行かせると、たくさん買ってきそうだからな」 「もぅ、ちゃんと人数分しか買わないよ?」 「そうか? 買った数は人数分より多かったぞ」 「私、一人一本だなんていってないもん」 確かにそうは言ってなかった。 「物は言い様だな」 「うん♪」 そういって麻衣は笑った。 「それとね、もう一つ」 「何?」 「つきあってくれてありがとう、お兄ちゃん」 「それはさっき聞いたぞ?」 「今度のはさっきのとは違うの。お兄ちゃん、心配してくれたんでしょう?」 「・・・」 人が少ないとはいえ、ここは海水浴場。 麻衣を一人で行かせるのは心配だった。麻衣は可愛いからナンパされるんじゃ ないだろうかと。 「俺はアイスの買い出しにつきあっただけだよ」 「うん、そう言うことにしておくね、お兄ちゃん♪」 そう言いながら腕を組んでくる麻衣。 ピンク色のワンピースの水着にTシャツ姿の麻衣、ぱっと見た目ではわからない かもしれないけど、そのボリュームと柔らかさは組んでいる俺の腕に伝わってくる。 冷静に、冷静に・・・ 心の中でそう唱える。 普段ならともかく、ここは夏の海。麻衣は水着姿で、二の腕に柔らかい感覚。 と、とりあえず腕を放して欲しい。今はまずい。 直球で言うと麻衣に悲しい思いをさせてしまう。だから 「麻衣、熱いぞ」 よし、これで完璧だ。 「そうだね、熱いね・・・だからアイス食べよう?」 完璧ではなく完敗だった。 麻衣はビニールから2本アイスキャンデーを取り出した。 腕を組みながら器用に包装されてるビニール袋からアイスを取り出し渡してくれた。 「はい、お兄ちゃん」 「ありがと、麻衣」 俺のは白いアイスキャンデー、麻衣は赤かった。 「いっただきまーす」 こうなったらアイスを食べるのに集中するしかない。 一口かじる、口の中に冷たいアイスが広がって熱が引いていく気がした。 これなら大丈夫だな。 「ん・・・んちゅ」 俺のすぐ横から艶めかしい音が聞こえた。 思わずそちらに視線を向けると、確認するまでもなく、そこにいるのは麻衣。 赤いアイスキャンデーを口いっぱいにほおばって食べている。 「ぴちゃ・・・うん、イチゴ味だね、美味しいよ♪」 食べているのではなくアイスキャンデーをなめていた。 「お兄ちゃんどうしたの?」 俺が見ていたのに気付いたのか、麻衣が不思議そうな顔で見上げてくる。 「もしかしてこっちの方が良かった? 味見してみる?」 そう言ってアイスキャンデーを俺に差し出してくる。 一度麻衣の口に入ってなめられたアイスキャンデー・・・ 「いや、いいよ。俺のも美味しいから」 麻衣のキャンデーをかじったら戻ってこれなくなりそうで、やめておいた。 「お兄ちゃんの美味しいの? ねぇねぇ、味見していい?」 「・・・俺かじっちゃったぞ?」 「大丈夫だよ、だってお兄ちゃんのだもん、だからちょっとだけ、ね♪」 「仕方がないな」 麻衣のおねだりにかなわない俺はアイスキャンデーを差し出した。 「あむっ」 さっきと同じように口に含む麻衣。そして 「ん・・・お兄ちゃんの白いの美味しいね。ありがとう、お兄ちゃん」 ・・・そんな麻衣の仕草に変な想像をしてしまうのは俺がいやらしいから だろうか。 「お兄ちゃん?」 「いや、なんでもない。戻ろうか」 「うん」 麻衣はまたイチゴ味のアイスキャンデーをなめ始めた。 俺も自分のを食べようとして。 あ゛・・・ これって麻衣がさっきなめた事に気付いた。 っていうか、なんでこうなることに気付かなかったんだ? 「・・・」 間接キスは偶然にも必然にも何度も行ったことはあったけど、やっぱり 恥ずかしい。こうなったら。 「わ、お兄ちゃん?」 俺はアイスを一気にかじって口の中に放り込む。 キーン! という音が聞こえた気がした瞬間に頭痛が走る。 「っ!」 「お兄ちゃん!?」 俺はその場でかがみ込んで頭を押さえる。 「だいじょうぶ?」 麻衣もかがみ込んで俺の顔を心配そうに見てくれる。 「あ、あぁ、ちょっと頭に来ただけだよ」 「もぅ、そんなに急いで食べるからだよ?」 「ごめん、ちょっとそんな気だったんだよ。もうだいじょうぶさ」 「そう? 無茶な食べ方は駄目だよ?」 全く、俺は何をやってるんだよな。 「あっ!」 「麻衣?」 今度は麻衣が悲鳴を上げた。 「アイス落としちゃったんだ・・・」 麻衣の視線を追うと砂浜に落ちたアイスキャンデーがあった。 どうやら俺の心配をしてくれたとき手を離してしまったようだ。 「ごめん、麻衣。俺のせいで」 「ううん、いいの。お兄ちゃんが無事なら。そ・れ・に!」 袋の中から別のアイスキャンデーを取り出す。 「こんなこともあろうかと、たくさん買っておいたんだよ」 「それは後付だろう?」 「えへ、ばれちゃった。でも結果良しだよ」 そういって食べ始めたアイスは、今度は白かった。 「お兄ちゃんが食べてたの、美味しかったから私も白いの食べるね」 「あのさ、麻衣。みんな待ってるから続きは帰ってからにしないか?」 「うん、そうだね。きっとみんなも食べたいんだよね」 ちょっと残念そうに袋にアイスキャンデーを戻す。 「また落とすと勿体ないし、続きは帰ってからにするね」 「よし、パラソルへ戻ろう」 「うん!」 Next Episode
インターミッション・フィーナ&??? 「やっと私の出番が来たようね。いつもは一番最初で緊張してしまうのだけど 一番最後も緊張するものなのね」 「姫様?」 「順番が最後だからって今回はオチになるわけではないようだし、安心だわ」 「あの、姫様?」 「私は最後だからって別に心配はしてないし、誰かみたいに順番を取られて 文句を言うつもりもないわ。だって真打ちは最後に登場するものですもの」 another view 「っくちゅん!」 「お姉ちゃん、だいじょうぶ?」 「だいじょーぶだよ、きっと誰かが美しい私に嫉妬して噂してるんだよ。 うん、そーだ、きっとそーにちがいない! 美しいって罪なんだね・・・」 「それはないと思うけどな・・・」 another view end 「姫様、どうかなされたんですか?」 「なんでもないわ、ミア。それよりもせっかくの夏休みですもの。 思う存分楽しみましょう」 「はい、姫様」 Next Episode
case of フィーナ 「熱い・・・」 俺はパラソルから離れた波打ち際の所に座って海を眺めていた。 荷物置き場の所に設置されたもう一つのパラソルの下では、今頃みんな日焼け止めを 塗っている。 「達哉は少し離れていてちょうだい」 そう言われて俺はここまで離れてフィーナ達を待っていた。 「おまたせ、達哉」 振り返るとそこには水着姿のフィーナがいた。 さっき一度見てはいるけど、こうしてゆっくりと見るのは今日初めてだ。 縁取りが青くあしらわれてる白いビキニに柄模様のパレオ。そして麦わら帽子。 「どうしたの、達哉?」 「似合ってるよ、フィーナ」 俺は正直に感想を口にした。 「あ、ありがとう、達哉」 顔を赤くしながらフィーナはお礼を口にする。 「でも、本当は新しいの欲しかったの」 「新作?」 「えぇ、でも水着を選びに行く時間がなかったの。それにこの水着はホームスティの 時の留学費用で買った物だから、ちゃんと使ってあげたかったの」 「月じゃ着る機会なんてないものな」 「えぇ、だから今日で2度目よ」 「その2度ともフィーナのその姿を見れて光栄だよ」 「ありがとう、達哉。さぁ、行きましょう!」 そう言うと俺の手を取って波打ち際を走り出す。 「み、みんなは?」 「あら、私と二人っきりじゃ駄目かしら?」 そう言ってすねた顔をする。俺は慌てて首をふる。 「嫌なわけないじゃないか」 「くすっ、冗談よ。みんなは順番に日焼け止めを塗ってるからまだ来るまでに 時間がかかるわ。それまで一緒に遊びましょう」 そう言うと今度は一人で波打ち際を走り出す。 「フィーナ?」 「達哉、早く早く!」 逃げるフィーナ、追いかける俺。 もう少しでフィーナに追いつく、その時に俺は砂に足を取られた。 「え、きゃっ!」 フィーナの背中にぶつかってしまい、そのまま倒れ込む。 「くっ!」 俺はなんとか身体を入れ替えフィーナを抱きかかえる。 「達哉?」 「フィーナ、だいじょうぶか?」 「え、えぇ・・・ありがとう」 「お礼を言う事じゃないさ、倒れてぶつかったのは俺の方だ、すまない」 「・・・」 「フィーナ?」 「達哉・・・いつまで私を抱きしめてるつもり?」 「え? あ!」 俺は慌ててフィーナから離れる。 「ご、ごめん!」 「私は嫌だって言ってないわよ?」 「え?」 「ふふっ、そろそろ戻りましょうか、達哉」 フィーナは悪戯が成功したような笑顔をしていた。 この後俺とフィーナ達は思う存分夏休みを楽しんだ。 「えぃっ!」 「はっ!」 ビーチバレーではフィーナと菜月の壮絶なラリー。 「負けないわよ、フィーナ!」 「私もよ、菜月!」 「ねぇ、お兄ちゃん。私は何をすればいいのかなぁ」 「俺もそれを聞こうとおもってたんだよ、麻衣」 「こんなこともあろうかと、用意しておいたんだよ」 といって取り出した西瓜を使った西瓜割り。 「ここね!」 えぃっと、可愛い気合いを入れて振り下ろした棒は、西瓜には当たらなかった。 「はははっ、残念だったね、フィーナ」 目隠しを取ったフィーナは俺の方をにらむように見つめてきた。 でも頬が真っ赤になってるから、ただの照れ隠しなのがばればれである。 「達哉の誘導が正確じゃなかったのが原因よ?」 「はいはい」 「もぅ、なら達哉もやってみて」 「俺か? おっけー、まかせろ!」 「達哉、何か言い訳はあるかしら?」 「・・・すみませんでした」 俺はふらつきながら尻餅をついたりと、フィーナより悪い成績だった。 「空が広いわね」 少しだけ沖にある遊泳地区を表すブイの所までフィーナと一緒に泳いできた。 フィーナはそのまま仰向けに水に浮かぶと、空を眺めている。 「とても青いわ・・・」 俺も同じように仰向けに浮かぶ。 視界に広がるのは一面の青空、入道雲も見える。 「こんなに綺麗な景色、私は一生忘れないわ」 「そうだな、俺も夏休みの思い出として一生残るな」 「夏休み・・・もう終わってしまうのね。楽しい時間ってあっという間よね」 「フィーナ、今日という時間がずっと続けば良いと思う?」 俺の問いに、フィーナは少し考えて、こう答えた。 「それは駄目ね。こんな日が続くと私は私じゃなくなってしまうわ。 それに、今日が続くと、この先の楽しい時が迎えられなくなってしまうわ」 俺は思ってたとおりの、それ以上の答えに満足した。 「そうだな、明日を迎えられないとフィーナと一緒になれないものな」 「そうね」 いつか絶対俺はフィーナと添い遂げる。 その時を迎えるには今日が続いてはだめなんだから。 「そろそろ戻るか?」 「そうね」 俺は泳ぎだそうとして、ふと思いついた。 「なぁ、フィーナ。夏休みの思い出、一つだけ増やしていいか?」 「私はかまわないけど、何をするの?」 俺は答えずフィーナを抱きしめる。 そして唇をそっと重ねる。 「もぅ・・・達哉ったら」 「それじゃぁ戻ろうか、フィーナ。短い夏休みはまだこれからだ!」 「えぇ!」 Next Episode
「よいしょっと」 クーラーボックスを肩にかつぐ。 これで荷物は最後だった。 軽い荷物は女性陣に手伝ってもらい、重い物を中心に男性陣が持つ。 そうして片づけ終わった砂浜には、何も残っていなかった。 俺は海の方を振り返る。 まだ夕暮れというには早すぎる時間だが、宿にチェックインする関係上 あまり遅くまでいられない。 「達哉、重くない?」 「これくらいだいじょうぶだよ」 水着の上からパーカーを羽織ったフィーナ。 俺に話しかけながらも、目線はおれと同じく海を見ている。 「終わっちゃったわね」 「あぁ、そうだな。でもまだ今日という時間はあるさ」 「そうね、まだ夏休み、ですものね」 「そうだよ、だから行こうか、この先に」 「えぇ、行きましょう」 海岸からちょっとだけ山に入った場所に今日の宿はあった。 小さな旅館で、部屋数も少なく今日は貸し切りの状態だった。 「いらっしゃいませ、お疲れさまでした」 「お世話になります」 「それではお部屋までご案内致します」 そうして連れてこられた俺の部屋は海が見える和室だった。 中に荷物を置く。まずは水着を着替えないとな。 その前に風呂入ろうかな。まだ夕食の時間まで少しあるからだいじょうぶ だろう。 「俺、風呂行って来ますね。おやっさんはどうします?」 「あぁ、俺は後でいい」 「仁さんは?」 「僕も後でいいよ」 「それじゃぁ行って来ます」 そうして部屋の扉を出たとき、目の前にフィーナ達が居た。 「あら、達哉も温泉に行くのかしら?」 「あぁ、着替えるついでに一汗流しておこうかと思ってね」 「入り口まで一緒に行きましょう」 大浴場の入り口は残念ながら二つあった。 もちろん、男湯と女湯。 「それじゃぁ達哉。また後でね」 「あぁ、ゆっくり暖まってくるといいよ」 「えぇ、それじゃぁ」 「達哉、女風呂覗かないでよ?」 「仁さんじゃあるまいし・・・」 菜月は注意しながら女湯に入っていった。 他のみんなも女湯に入っていくのを横目に、俺は一人で男湯ののれんを くぐった。 「へぇ、露天風呂なんだ」 山の斜面を利用して作られた露天風呂は、海が一望できた。 ちょうど日が沈む、少し前の夕焼けが綺麗だった。 俺は温泉に浸かりながらその景色を眺める。 「わぁ、夕日が綺麗」 俺の頭の上の方から麻衣の声が聞こえた。 思わず上を向くけど、もちろん麻衣の姿は見えない。 「・・・あれか?」 斜面の少し上に見えるのは、おそらく女湯の露天風呂の端だろう。 そういえば、男湯はのれんをくぐってから少し階段を下りたっけ。 おそらく女湯は階段を上ったのだろう。 上の階に作られた女湯は、ここよりもっと良い景色が見えるのだろうな。 「本当に綺麗ね」 「私たち、さっきまであの砂浜にいたんですよね?」 「そのようですね」 どうやらみんなそろっているようだ。 「というわけで達哉君、僕と一緒にエクソダス、するかい?」 「仁さん? いきなりなんですか? っていうか、いつからここに?」 「いやぁ、細かいことは気にしない。せっかく麗しき女性達が居るのだから 男としては見ないわけには行かないだろう?」 「そういうことはやめてください」 「堅いねぇ、達哉君。硬くするのはあれだけでよいのにね」 そう言うときらっと歯を輝かせる仁さん。 「・・・俺は止めましたからね?」 「わかった、おーらい。僕は行くよ、桃源郷が僕を待っている!!」 そう言うと仁さんは斜面を登り始める。 本当なら身体を張って止めるべきなのだろう。 だが、俺の予想が当たっているのなら・・・ 「ぷぎゃっ!」 仁さんは斜面から転がり落ちてきた。 その頭にはしゃもじがささっていた。 「・・・お約束だな」 「達哉、そこに居るんでしょ?」 「あぁ、居るぞ?」 「そこに落ちた生もの、処理しておいてよね」 「な、生ものって・・・」 仁さんの扱いが酷い気もしないでもない。 「この下って男湯なの?」 そんな声が聞こえたと思ったら・・・ 「あ、お兄ちゃん発見!」 「ま、麻衣?」 上の浴槽の端からだろう、麻衣が顔を覗かせていた。 「麻衣、危ないから戻りなさい」 「はぁい!」 そう言うと麻衣の顔が引っ込む。 「ふぅ・・・万が一落ちたら大変だぞ?」 そう簡単に落ちることはないと思うけど、心配してしまう。 まぁ、でももうだいじょうぶだろう。 「どうしたの? 麻衣」 上の階からフィーナの声が聞こえてくる。 「あ・・えと・・その」 「?」 「フィーナさんって綺麗だなって思って。・・・胸もおっきいし」 「・・・」 思わずフィーナの胸を想像してしまいそうになった。 「そうですよね、姫様の肌は綺麗ですよね。最近少し大きくなられた ようですし」 「ミア?」 「フィーナ様は大きいだけじゃなく形も良いですよね」 「さやか!」 「いいなぁ、出るところは出ていて引っ込むところは引っ込んでいて」 「菜月まで」 「大丈夫だよ、菜月。菜月だっておっきいから」 「翠・・・自分の見たことある?」 「え? 私? 私は、ほら、平均だし・・・」 「じぃ・・・」 「ま、麻衣。そんなに見ないでよ」 「遠山さんもおっきぃです。それに比べて私は・・・あぅ」 「大丈夫だって、麻衣は成長期なんだから、ね?」 「成長期をすぎても、カレンは大きくない」 「り、リース!」 「私とサイズ、かわらない」 「こら、リース。そんなこと言っちゃだめでしょう? すみません、カレン様」 「いえ、エステルが悪いわけじゃないです」 「私は成長すればエステルと同じくらいにはなる。カレンとは違う」 「・・・」 「・・・もう出よう」 いろんな意味でのぼせそうだったので温泉を出ることにした。
インターミッション・楽屋裏編 菜月「みんな、グラスは行き渡った? それじゃぁ乾杯!」 一同「かんぱーいっ!」 菜月「と、いうわけで本編中ですが夕食の時間なので座談会に入ります」 ミア「いいんですか? 本編中なのに」 翠「いいんじゃない? 楽しければおっけーだよ♪」 さやか「この方が作者さんらしいですからね」 フィーナ「今日は達哉もいるのね」 達哉「あぁ、でも俺はおやっさんと見てるだけにしておくよ」 左門「そうだな、俺達が出る幕じゃないな」 麻衣「どうして?」 達哉「・・・大人の事情かな」 麻衣「あは、あははは・・・」 エステル「どうもこの浴衣という物が気になります。なんだか足下がすーすーと しすぎる気がしますし、すぐ脱げてしまいそうで・・・」 翠「それは伝統芸能なんですよ!」 エステル「伝統芸能?」 翠「そう、こうやって帯を手にとって思いっきりひっぱ」 菜月「はいはい、そこまでにしておいてね、翠。ここで脱線したらページ数が かさみ過ぎちゃうでしょう?」 翠「残念」 エステル「?」 菜月「ここにある進行台本の通りだと・・・まずはコンセプトの説明ね 長編が書けないのであれば短編を組み合わせてごまかせばいい、以上!」 翠「おぉ、理にかなってるね」 ミア「姫様、そうなんですか?」 フィーナ「ノーコメントにしておくわ」 さやか「同じ手法ですと、去年の今頃にふくびきを題材にして発表されたわね」 翠「あの時の順番の最後はオチだったんだよね、エステルさん」 エステル「・・・」 菜月「まぁまぁ。それじゃぁ次の進行に行くよ! それでは各ヒロインのみなさんにインタビューです。」 case of 翠 菜月「いきなりサービスシーン担当です」 翠「担当言うな! 私は本編だってそう言うシーンないんだぞ?」 リース「そのうち当番が回ってくる」 翠「うっ・・・」 菜月「モーターボートがないのにバナナの浮き輪を持ってくるなんて翠らしいよね」 翠「いいじゃん、乗りたかったんだもん」 リース「バナナにまたがる、サービスシーン担当」 翠「担当言うな!」 case of エステル 菜月「前回オチだったエステルさんです」 エステル「なっ」 菜月「今回は2番手に大幅出世したのですが、その辺はどう思われますか?」 エステル「こほんっ、やっと正当な評価を得られたのだと思っています」 菜月「でも最後は真打ちだったという話しもありますね。 だとすると今回はずいぶん早い出番、ということは?」 エステル「・・・」 カレン「メインで出番があるだけましなのよ、エステル・・・」 case of リース さやか「リースちゃんって器用よね。達哉君に匹敵するくらいのお城を 造ったのですもの」 リース「別に・・・」 麻衣「でも砂のお城凄かったよ? 壊れちゃうのもったいないくらいだったもん」 リース「かまわない」 カレン「勝負に勝って試合に負けた、リースらしいというか、それとも達哉さんが そう・・・なのかしら」 達哉「その、なんだか気になる言い方なんですけど・・・」 インターミッション フィアッカ フィアッカ「別に私の出番なぞ無くても良かったのだがな」 達哉「そう言うなよ、フィアッカだって家族なんだし、夏休みは必要だろう?」 フィアッカ「た、達哉がそこまで言うのなら、その、少しくらいはつきあっても やらないでもない。達哉がそこまで言うからだぞ?」 達哉「はいはい」 case of ミア 菜月「サービスシーン、その2!」 ミア「ひゃぁ!」 翠「実際あのパラソルの下では酒池肉林だったんだよね」 ミア「そんなことはありません、私はみなさんに日焼け止めを塗っただけです」 リース「フィーナ、上半身裸だった」 フィーナ「リ、リース!」 達哉「・・・」 case of 菜月 翠「実は菜月はサービスシーン担当じゃなくてお色気シーン担当だったんだよね」 菜月「えぇ! 嘘っ! 私お色気担当じゃないよ?」 翠「この胸を温泉で見せつけておいて何を言う?」 菜月「やんっ!」 翠「このたゆんたゆんは同じ女から見ても羨ましい! ねぇ、カ・・・」 カレン「・・・」 翠「・・・いえ、何でもありません」 インターミッション カレン カレン「フィーナ様にはめられてしまいましたわ」 フィーナ「人聞きの悪い言い方しないでちょうだい」 カレン「ですが、私はフィーナ様のシナリオ通りに動かされてしまいました。 さすがは我が主君です」 フィーナ「誉められてるのかけなされてるのかわからないわ・・・」 カレン「ふふっ」 case of さやか エステル「さやかさんはいつもみなさんのことを考えてらっしゃってるのですね」 さやか「そんなことはないわよ。ただみんな楽しく過ごせればいいなぁって 思ってるだけですよ」 カレン「それがなかなか出来ない事なんですよ、さやか」 さやか「そう?」 エステル「でも、あまりご自身を犠牲にされては駄目ですよ? 相手を幸せにするためには、自分自身も幸せにならないといけないのですから」 さやか「ありがとう、エステルさん」 case of 麻衣 菜月「ねぇ、翠。私がお色気担当って言ってたけど、麻衣はどうなるの?」 翠「麻衣にお色気っていうには無理があるとおもうの、だから八月の最強の義妹担当! そして真のエロイン!」 麻衣「えぇ!?」 翠「受け継がれる義妹の中で最強のスペックを誇る麻衣、 今回もしゃぶっちゃってます!」 麻衣「と、遠山さん、その言い方は恥ずかしいよぉ」 リース「シルフィー、茉理も凄かったけど麻衣を越えた義妹は八月に居ない」 麻衣「リースちゃんまで・・・あ、でも陽菜さんだって妹だって話しだし」 菜月「麻衣、陽菜さんは同級生で妹じゃないよ」 麻衣「えぅ」 インターミッション フィーナ ???「納得いかなーい! なんで私の話が本にならないのよ!」 ??「お姉ちゃん、お邪魔しちゃだめだよ!」 ???「だって、私の話は中篇として連載されたんだよ? 加筆修正されて デビューだと思ったのに! 何故!」 ??「だから、今回はお話の世界が違うんだから無理だったんだよ。ね?」 ???「むむむっ、こうなったら風紀シールで下克上!」 ??「お姉ちゃん!」 フィーナ「私の話じゃなかったのかしら?」 ミア「さぁ・・・でもなんだか声が姫様と似てらっしゃいますね」 フィーナ「それは他人のそら似よ」 ミア「はぁ・・・」 case of フィーナ さやか「真打ち登場ですね、フィーナ様」 フィーナ「いつも一番最初だったけど、一番最後もどきどきするわね」 エステル「私の時は出番が来なくてどきどきしてました」 リース「器の違い」 エステル「・・・」 フィーナ「何はともあれ、みんなで過ごせた夏休みは良い思い出になりました」 達哉「この刺身美味しいな・・・あれ? これは・・・台本じゃないか。 おーい、菜月。台本ここにおきっぱなしだぞ?」 菜月「あぁ、もうほとんど終わってるからいいのー」 達哉「そっか。あ、でも最後まで進行してないぞ?」 フィーナ「そうなの?」 達哉「あぁ、今回の絵師さんからのメッセージを紹介していない」 ミア「今回の絵師様というと・・・ブタベスト様ですね」 フィーナ「私の絵を描いてくださった方ですね。ありがとうございます」 達哉「それじゃぁあとがきを読むね」 『こんにちは、絵を描かせていただきましたブタベストです。 早坂さんの同人誌、ということで、(かなり)無理を言って参加 させていただきました。 『夜明け前より瑠璃色な』のヒロインを描いたのもかなり久しぶりでしたが、 オーガスト作品で一番はまったゲームの女の子たち、ということもあり とても楽しかったです。 早坂さんの書く"女の子たちそれぞれの夏の海"、皆様にも楽しんでいただけたら 幸いです。』 麻衣「私の絵は裏表紙に使われたんだよね」 その他一同「・・・」 達哉「みんな、どうしたの?」 その他一同「私たちの絵は?」 達哉「・・・えっと、だそうですよ、ブタベストさん?」 菜月「そろそろ食事も終わりだし、お開きにしよっか」 フィーナ「そうね」 ミア「もう終わってしまうんですね」 麻衣「そうだね」 ミア「姫様。私、伝統の枕投げという物もやってみたいです!」 菜月「翠・・・」 翠「わ、私じゃないよ?」 フィーナ「そうね、何事も経験よね。ミア、あとでやりましょう」 ミア「はい、姫様!」 エステル「カレン様、枕投げとは、あの枕投げのことでしょうか?」 カレン「たぶんそうです・・・」 エステル「止めなくて良いのですか?」 カレン「止める必要なんでありますか?」 エステル「・・・そうですね、私も参加させていただきましょう」 麻衣「なんだか凄い展開になってるような気が・・・」 さやか「良いんじゃない? なんだか学生時代を思い出すわ」 達哉「ふぅ、何事もなく終わったようだな」 フィアッカ「そう行くと思うか?」 達哉「リース・・・じゃない、フィアッカ?」 フィアッカ「せっかくの夏休み、もう少し私を楽しませてもらおう」 達哉「あの、なんだか発言がどこかの金髪吸血鬼の母親っぽいんですけど」 フィアッカ「まぁ、気にするな」 達哉「はぁ・・・」 フィアッカ「それで、達哉。誰が本命なのだ?」 一同「・・・」 達哉「な、何かな、この緊迫した空気は・・・」 フィーナ「達哉、この後時間あるわよね? 一緒に温泉入らない?」 麻衣「あっ、私もお兄ちゃんと一緒がいいなぁ。出来ればふたりっきりで」 ミア「達哉さん、あの・・・私と枕投げしませんか?」 エステル「達哉、達哉がどうしてもって言うのなら夜の散歩に行っても良いですわ」 菜月「やっぱり温泉旅館の夜は卓球よ、ね、達哉?」 翠「卓球ではだける浴衣って良いと思わない? ね、朝霧君」 さやか「そうね、せっかくですもの、一緒に寝るのも良いわね」 達哉「ちょっと待って・・・ってか、また後で!」 フィーナ「あ、達哉!」 リース「逃げた」 さやか「ふぅ、とりあえず座談会は終わりにしましょう。この後のことは後で みんなでゆっくり、達哉君に問いつめましょう♪」 麻衣「お姉ちゃん・・・笑ってるのになんだか怖い」 一方、その頃・・・ 仁「あれ・・・なんで僕は温泉で寝ているんだろう? はっ、あそこに見えるのは桃源郷への入り口、エクソダスっ!」
インターミッション・Moonlight Cradle 翠「もぅ、菜月ったら台本置きっぱなしなんだから・・・ あれ、なんだろう? このちらしは。 ・・・夜明け前より瑠璃色な Moonlight Cradle !?」 エステル「どうしたんですか?」 翠「エステルさん、これ見て!」 エステル「これは・・・」 翠「そうだよ、とうとう出るんだよ、私たちが主役のお話がみんなと 同じ舞台の上で!」 エステル「真打ちは最後に来るのは本当だったのですね」 翠「あ、まだこだわってたのね」 エステル「これでもう誰にも何も言わせないわ」 リース「二人とも、当番の回が来る事になる」 翠「あ゛・・・」 エステル「当番?」 翠「エステルさん、あのね・・・」 エステル「っ!」 リース「嫌なら辞退すればいい」 翠「嫌なわけないよ! やっと朝霧君と結ばれるんだから」 エステル「そうです、嫌なわけ無いです! むしろ待っていた・・・あ」 翠「ほほぉ、エステルさんもやりますね」 エステル「今のは無し、収録カットしてください!」 翠「無かったことにしていいの?」 エステル「・・・貴方は意地悪です」 翠「そうかな?」 エステル「貴方はどうなんですの?」 翠「私? 私は朝霧君が望むなら、ブルマでもスクール水着でもオッケーだよ」 エステル「ブルマ?」 翠「んふふ、世の男性が望む地球の伝統的な体操着なのですよ。 アンケートの結果でも相当強いらしいし、絶滅させてはいけない物なんですよ!」 エステル「達哉も望むのでしょうか?」 フィアッカ「この先は聞かない方が良さそうだな。全く、編集後記のスペースを とってまで続けた座談会がブルマで締めとなるとはな」 リース「らしい対談」 フィアッカ「そうだな、本当にらしい対談だったな」 リース「それよりも、達哉が隠れたまま」 フィアッカ「見つけた方が良いな、その方がおもしろそうだし」 リース「フィアッカ様、ノリノリ」 フィアッカ「せっかくの夏休みだからな。では、捜すとしようか」
・ ・ ・ 「ふぅ」 俺は海岸線の土手に座って一息つく。 ついさっきまでみんなで砂浜に出てきて花火をしていた。 それも終わり、後かたづけをした後、俺はすぐに旅館に帰る気にはならなかった。 「名残惜しいんだろうな、きっと」 海岸は月明かりに照らされて、砂浜が淡い光を放っている。 そして静かな波の音が聞こえてくる。 「・・・」 その時、俺の背後から誰かが近づいてくるのに気付いた。 俺は振り返らず、ただ彼女が来るのを待つことにした。 ここにいたのね、と彼女は微笑みながら俺の横に並んで座る。 「なんとなく」 そう、と頷く彼女は俺と同じく海の方に視線を移す。 「・・・」 そっと彼女は俺に身体を寄り添って来る。 俺も彼女の肩に手を添えて、俺からも寄り添う。 楽しかったね、と彼女は言う。 「あぁ」 ・・・ ただ二人だけの時間。 星空と月明かりと波の音だけの時間。 くちゅんっ! 静かな雰囲気は彼女のくしゃみで終わりを告げた。 「そろそろ戻ろうか」 彼女は顔を真っ赤にして頷く。 「まだ夏休みは終わってないんだ、明日だってあるんだよな」 彼女は不思議そうな顔をする、けどそれは一瞬だった。 「今日より楽しい明日にするぞ!」 今日よりももっともっと楽しい思い出を作りましょう、という彼女の手の握る。 「でも、その前に今夜ももっと遊ばないとな。今頃部屋で みんな待ってるだろうからな。行こう!」 手をつないだまま宿へと戻る。 そう、まだ夏休みは始まったばかりなのだから・・・
[ 元いたページへ ]
case of シンシア 「こんなところにいたんだ」 そこには蒼い縞模様のビキニ姿の、ポニーテールの少女が砂浜に座り込んでいる。 「タツヤ・・・いいの? こんな所に来て」 その少女、シンシアはそう訪ねる。 「なんで?」 「なんでって、私はここにはいていけない存在かもしれないのよ? またあの本の世界の中かもしれないのよ? 一度見てしまったら冷めたくない夢なのかもしれないのよ? それなのに・・・」 「シンシア、落ち着いて」 「私は・・・んっ・・・んん」 悲しい言葉が口から紡がれる前に、俺は口をふさいだ。 「タ、タツヤ・・・」 「良いじゃないか、シンシアは今ここにいる、俺の前にいる。これは真実だよ」 「でも・・・」 「シンシアは自分が信じられないのかい?」 「・・・」 「それじゃぁ、俺は信じられるかい?」 「そうね・・・私自身よりタツヤの方が信じられるかもしれないわ」 「ならそれでいいじゃないか」 「・・・でも」 「まだ気になることがあるのか?」 シンシアは何かを言いにくそうにしている。 「まだ、この世界が確定した訳じゃないの・・・不安定なのよ。 このまま私がいればどうなるか」 「シンシア、大丈夫だ。俺を信じてくれるんだろう?」 「・・・科学者としては根拠を知りたいわ」 「無い」 「え゛?」 「だけど大丈夫だ、だって俺とシンシアがいるんだから」 「・・・ぷっ」 シンシアが吹き出した、と思ったらお腹を抱えて笑い出した。 「な、なによそれ・・・おっかしぃ・・あははっ!」 「そんなに笑うことじゃないだろう?」 「いいじゃない、楽しいんだから」 「・・・」 なんだか納得行かない、けどシンシアが笑っているのならそれはそれで いいか。 「そうよね、未来なんてまだ確定したわけじゃないものね。 たくさんの分岐の先に何があるかなんて、ここからじゃわからないもの」 「シンシア?」 「よーし、決めた。今は夏休みを楽しむわ、ほら、タツヤ。海に入りましょう!」 「ちょ、ちょっと待てって」 「待たないわ! あの時は誰かさんのせいで海に入れなかったんだもの。 今日は跡はないしたくさん遊びましょう! ほら、えいっ!」 「冷たっ!」 シンシアは水をかけてきた。 「そっちがその気ならっ!」 「きゃー、タツヤが襲ってきたー!」 「待てっ!」 「嫌よ」 そう言って逃げるシンシア。 「そう、捕まえてくれないと嫌だからね!」 「なら逃げるなっ!」 「それが女の子なのよ! ほら、タツヤ。早く私を捕まえて! そしてずっとずーっと、離さないでねっ!」 「わかった、絶対捕まえてみせる、そして離さないで見せる!」 「うん、待ってるから!」