| 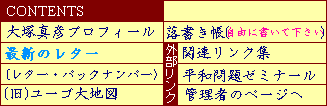 |
| 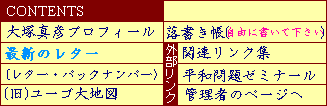 |
|
第57回配信
実は私がザグレブ入りした時は、クロアチアの2+3党連合政権が成立後最大の危機を乗り越えたばかりのところでした。第53回配信の後半でも触れたように、ラーチャン首相率いる社民党の連立パートナーである社会自由党(HSLS)は、昨年7月オランダ・ハーグの旧ユーゴ国際戦犯法廷から独立紛争当時の将軍が訴追され移送を求められた際に、引渡し反対の態度を取りました。しかしグラニッチ首席副首相ら同党出身の閣僚が党意に逆らって閣議で引渡しに賛成したことから、HSLSはブディシャ党首派とグラニッチ副首相派に分裂してしまいました。ブディシャ党首は2年前の選挙でHDZ政権打倒のため当時の野党が大同団結するために尽力、言わば現連立政権の生みの親でもあるのですが、自らは大統領選に立候補し大臣ポストには腹心のグラニッチらを送っていました。HDZ民族主義政権時代の最大野党ですから、HSLSは中道ないし中道左派というイメージで有権者には受け取られていました。しかしブディシャの大統領選期間中の発言や昨年の出来事などから、次第に同党の「右寄り」の姿勢が明らかになって来ました。今年初めの党大会で党内抗争に勝ったブディシャが党首にカムバック、党の非主流に転じたグラニッチ副首相を解任するようラーチャン首相に要求しました。しかし所属政党こそ異なれラーチャン首相の事実上の右腕として実績を上げているグラニッチの解任を、今度は社民党党首でもある首相が拒否。「連立解体、総選挙か?」とマスコミが騒ぐ事態に進展したのです。
しかし3月の世論調査の結果を見ると、2年前に較べHSLSが大幅に人気を落とした他は大した変化がありません。人気にはジリ貧傾向が見えるものの社民党がリード、同党とHDZのみが20%台の支持率で、あとは小党乱立です。HSLSは一時の5%割れ(選挙で5%の得票がないと議席はゼロになる)こそ免れたものの8%と低迷しました(英字月刊誌クロアチアタイムス3月号)。しかも党大会ではブディシャ派が数で勝って主流になりましたが、逆に現在の同党出身議員の多数はグラニッチを支持していることも明らかになりました。ブディシャ派としては、右派連合に加わることでグラニッチ派の大量離党を招き、小政党としてかつての仇敵HDZに飲み込まれるか、現連立政権を維持して実績を重ね再伸張への実力を養うか、の選択を迫られたわけです。 泰山鳴動ネズミ一匹。3月中旬、ブディシャ党首が首席副首相の座に就き、ヴォイコヴィッチ経済相らブディシャ派が新閣僚に就任。副首相ポストを従来の3人から一つ増やし、ラーチャン首相が支持するグラニッチは「首席」ではないもののこのポストにとどまる、という閣内妥協が成立しました。ブディシャは首席副首相に就任が決まるやいなや「クロアチア国民はハーグ戦犯法廷に従う義務がある」とまで発言(週刊グローブス誌3月22日付)、去年の移送反対騒動は何だったのか、と言いたくなるような笑劇に終わりました。現実主義的と言うべきか、無節操と言うべきか、まあバルカンの政治家だけの話ではありませんけれども・・・。 そんなザグレブで政変2年後のクロアチアの状況を見てみようと入った筆者ですが、中央バスターミナルに着いてまず新聞を買うと、いきなり「ザグレブにトゥジュマン広場が誕生か?」という見出しに出会ってしまいました。首都の中心部、ミマラ美術館があることで知られるルーズヴェルト広場を改称、前大統領トゥジュマンの名にするという提案が社民党のデンビッツ市議から出されたというのです。
ルーズヴェルト広場の斜め向かいの通称「劇場広場」の正式名称はティトー元帥広場です。良くも悪しくもクロアチアの歴史に君臨したティトー(J・ブロズ)とF・トゥジュマンは共にザゴリエ地方(ザグレブから北西の地域)の出身なので、一般市民の中には「斜め向かいの広場とくっ付けて、『ザゴリエの独裁者たち広場』にしたらどうか」などというユーモアのセンスを見せる人がいましたが、大半は「もうそんな政治の話はどうでもいい。それより政治家には経済状態をきちんとして欲しいんだ」という反応だったようです(日刊ユータルニ・リスト紙3月27日付、4月3日付)。 しかし経済問題こそ民族主義前政権の「負の遺産」が一番大きかったところです。この2年間のラーチャン首相の改革は順調と呼ぶには遠い状態です。
ご存知の通り、債務国に対する構造調整と発展はIMFの主要業務の一つです。基本方針は緊縮財政(公共支出・公務員削減など)で「小さな政府」による安定を実現することです。そのための条件を各国政府に要求しながらスタンドバイ(短期)融資、構造調整(中期)融資を行います。しかし政府がIMFに従順であろうとし、また企業が外資化・民営化して競争力を付けようとすれば、社会主義非能率体質を色濃く残す国営セクターや旧自主管理系大企業は余剰人員の削減という「痛み」を経験しなければなりません。失業が最大の課題なのに、受け皿としての中小企業などが十分育たない中でさらに失業者を増やさなければならないのです。社民党人気頭打ちの中、その先に見えてくる最悪のシナリオは民族主義勢力の再台頭です。 やはりクロアチアの経済改革にとって重要課題の一つは、IMFも要求する旧国営大企業の民営化・外資導入ではないかと思われます。国営石油公社INA、電気公団HEP、業界最大手クロアチア保険などの民営化は独立直後の93年頃から何度か話が持ち上がっては潰れて、の繰り返しで、現政権になってからも2年間ほとんど具体化していませんでした。INAの場合、帳簿上の資本13〜18億ドルの大企業民営化には大変な利権が絡み、HDZ前政権も現政権(現在のトップ人事はクロアチア民族党HNS寄り)もなかなか手放したくなかったことは誰の目にも明らかですが、遅まきながら25%プラス1株を民営化する法案が先頃議会を通過しました。
公務員も「親方何とか」で安心してはいられません。独立紛争での「需要」もあって、トゥジュマン政権時代に特に人数が膨れたのは警察と軍でした。現政権は警察官3000、軍人13500人の削減を発表、昨年以降警察のリストラが始まりました。第1次削減の対象となった162人のうち一部は「不当解雇である」として今年3月26日から首都中心部マルコ広場の政府庁舎前で座り込みを開始。一時は政府庁舎への強行突入を計画した容疑で逮捕者を出す騒動になりました。その後トーンダウンはしましたが、本稿執筆中の5月中旬も依然として座り込みは続いています。この状況を受けてラーチャン首相、ブディッシャ首席副首相は今夏に予定していた軍リストラ開始のタイミングを見直すことになりました。 今年のメーデーは、参加者こそザグレブで5000人程度(体制系メディア推計)と多くはありませんでしたが、「議会や政府で惰眠をむさぼる連中にこそ新しい職を捜してもらいたいものだ!次の選挙の後ではもう見つけられないだろうから」と、激しい調子での政府批判の場になりました。新労働関連法案で政府が打ち出している退職準備期間や退職金の削減に反対する、というのが表向きですが、実際は3年目にして曲がりなりにも動き出した「痛みを伴う改革」によるリストラ不安が危機感につながっているものと思われます。政府にとってショックだったことは、社民党の大票田として2001年政変の蔭の主役を務めたクロアチア独立労組連合(SSSH)がデモの中心になったことでした。同連合組合員はサッカーになぞらえ「イエローカード」を持って集合しました。「今回は警告だけにとどめておくが、今後も状況が改善されないようなら社民党を見離す」(ユリッチ委員長)という明白な意思表示でした。
スプリット銀行と業界第3位を争っていたリエーカ銀行は、独バイエルン州立銀行が60%の株を保有、前政権時代からスキャンダルにも無縁で現人事は社民党に近く、安定した銀行だと思われていました。3月9日、同銀のE・ノディロ筆頭ディーラーが、翌週にはポドブニク・ディーリング部ディーリング課長らが逮捕され、ノディロ容疑者が外貨ディーリングで作った損失をディーリング部全体が帳簿の不正操作によってごまかしていたことが明るみに出ました。当局の発表が遅れ、マスコミが「ディーリング部だけでなくトップ人事も承知していた可能性も」「損失額は1億ユーロに上るらしい」などと書き立てた(後の中銀調べでは0・9億〜1・3億ユーロ相当の損失)ため、3月中旬リエーカ銀行は解約を求める顧客で大行列になるという典型的な騒動に発展。バイエルン州立銀は保有していた60%の同銀株をわずか1ドルでクロアチア政府に売却しました(因みに同銀は先頃経営破綻で話題になった独キルヒグループの最大債権銀行です)。ロハティンスキ中銀総裁らが遅ればせながらパニック沈静化に努力し、トップ人事の更迭とオーストリア・エルステ銀行への株の再売却などで何とか最終的な破綻は免れました。しかし経済週刊誌「ポスロヴニ・ティエドニク」(3月25日号)などが騒動直後に実施したアンケートによれば、「今回のリエーカ銀騒動で銀行全体への信用は落ちたか」という問いに肯定の解答が49・3%。「民営化しても」「外資系でも」漠然とした不安は消えません。 トゥジュマン前政権の負の遺産の処理に苦しみ、また民営化・外資導入による将来に関してもバラ色のヴィジョンを提示出来ない。ラーチャン政権の改革路線は千鳥足、と言わざるを得ません。
サッカーW杯、我らがクロアチア代表は前回仏大会3位の頃に較べチーム力の低下が囁かれていましたが、新潟で6月3日に行われたメキシコとの緒戦は体格で劣る相手を攻めきれず0−1での敗戦でした。
。ヨジッチ代表監督は「決勝リーグ進出が最大の目標」と言っていますから、イタリア戦、エクアドル戦には頑張ってもらいたいものです。
ところが政変が起こって名前もディナモに戻されてからそのツケが一気に来ました。現政権は優遇策を取り消して大型の追加徴税に踏み切り、クラブは財政難に陥ってしまいました。市原に昨年移籍したムイチンの給料未払いは約1億円分、今年から清水でプレーするツヴィタノヴィッチにもほぼ同額、三浦には約6000万円分の未払いがあることが判明。クロアチア代表としてW杯を戦うプロシネチュキは未払い約9000万円分の支払いを求めて提訴、クラブの銀行口座が一部凍結される司法決定が下されました。有力選手を放出せざるを得なくなったディナモは当然のことながらチーム力も弱体化。今季国内リーグで3位の座に甘んじ、今までは無名に近い存在だったNKザグレブがリーグ初優勝をさらうという「波乱」が起こってしまいました。 ディナモ経営の救世主としてフロントが迎えたのは、クロアチア長者番付の50位には入っているというズドラフコ・マミッチ氏でした。
マミッチ氏は「クラブ立て直しのために頑張るつもりだ。今の収入源は入場券だけだが、テレビ放映権料や広告収入で経営出来るようにならないといけない。ディナモが引っ張れば国内リーグが活性化するはずだ」と語ります。が、今後も経営の「主流」は選手の売買であることは間違いありません。ただそれを、急場しのぎの大量売却を繰り返すことなくディナモの企業ビジネスとしてきちんと進めようということのようです。現在のディナモのレギュラー、D・ザホラ(FW)やJ・レコ(MF)はマミッチ氏が個人的に契約を結んでいる選手で、彼らが活躍してイタリアやドイツなどサッカー大国のクラブのスカウトの目にとまれば、ディナモもマミッチ氏も潤うというわけです。 こうしたクロアチアサッカーのビジネス化傾向に眉をひそめるサポーターも少なくはありませんし、ちょっと胡散臭い話ではあるわけですが、これもスポーツ界全体の傾向であるとともに、クロアチア脱社会主義・脱民族主義の方向を示している姿だと思います。何せ民主化と市場経済化の美名のもとに先進諸国が示しているヴィジョンは、何とも胡散臭いシホン主義なるものなのですから。そして地元の良質な「商品」を出来るだけ高く「輸出」するというマミッチ&ディナモ株式会社の方針は、資本主義ルールにのっとった健全な商行為なのですから。 (2002年6月上旬) 資料を提供して頂いた長束恭行氏(「クロアチアに行こう!!」)に謝意を表します。写真の一部は2002年3〜4月に日本の新聞社取材に同行した際筆者が撮影したものです。また本文もこの取材の通訳として業務上知り得た内容を含んでいます。これらの掲載に当たっては、私のクライアントから許諾を得ています。画像・本文の無断転載はかたくお断りいたします。 |
スロヴェニアサッカーを扱った前回第56回配信で、ルーマニア戦でのルドニャ選手のゴールの詳細を誤って記述してしまいました。うろ覚えで書いてはいけませんね。今後注意します。 配信では「ノヴァクが左サイドからセンタリングした」ように書きましたが、実際には中央やや左寄りをドリブルで持ち込もうとしたノヴァクが倒されながら左外(やや斜め前方向)にボールを流しました。明らかなルーマニア側の反則だったため、両チームの動きが一瞬止まったかのようにも思われましたが、次の瞬間には目の前に転がってきたボールにノーマークのルドニャが左サイドライン近くからクロスのミドルシュート。これがゴール右隅に見事に決まりました。もちろんスロヴェニアのアドヴァンテージというわけで得点が認められました。 |
<プロフィール> <最新レター> <バックナンバー> <(旧)ユーゴ大地図>
<落書き帳(掲示板)> <関連リンク集> <平和問題ゼミナール> <管理者のページ>
当サイトは、リンクフリーです(事後でもいいので連絡ください!→筆者メール)。
必ずカバーページ(http://www.pluto.dti.ne.jp/~katu-jun/yugo/)にリンクをはってください。
|
CopyRight(C)2002,Masahiko Otsuka. All rights reserved. Supported by Katsuyoshi Kawano & Kimura Peace Seminar |